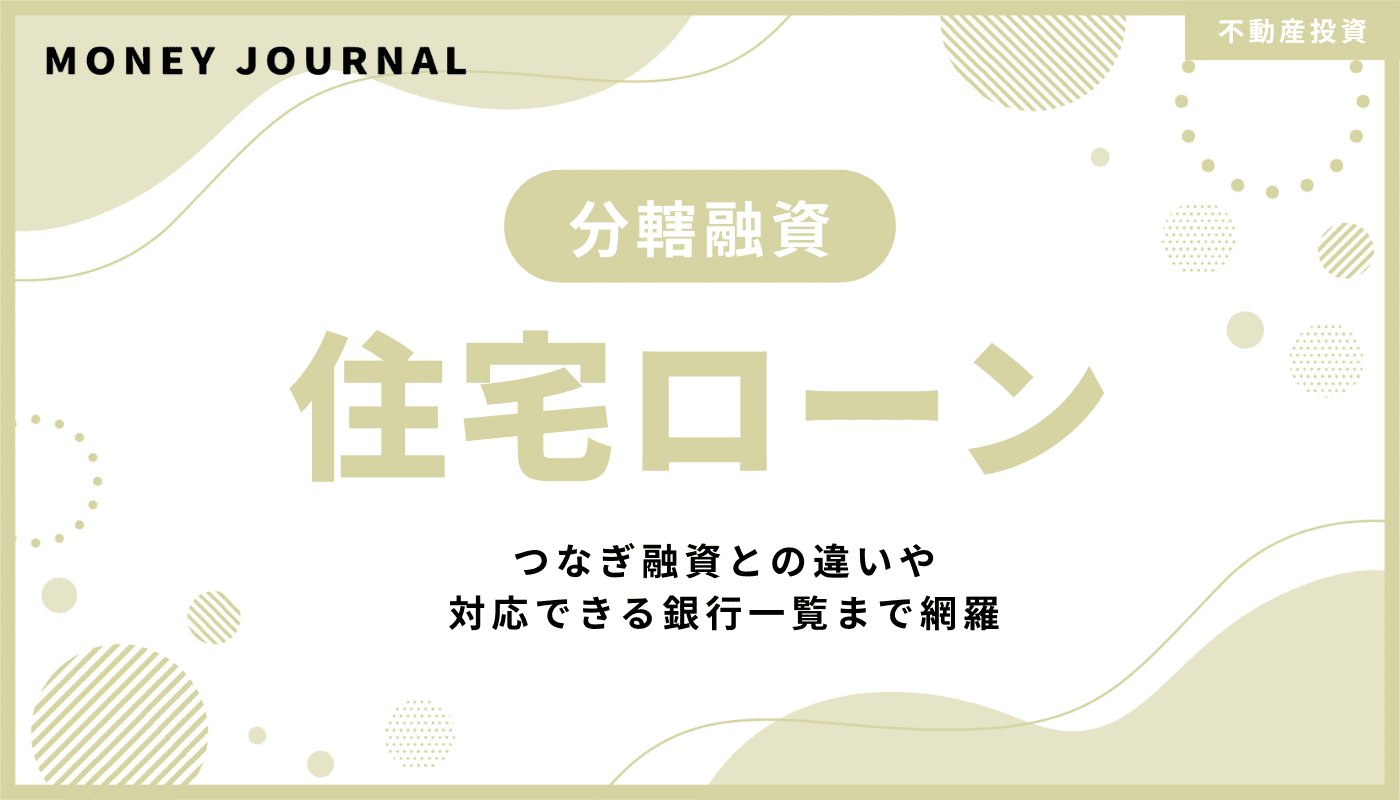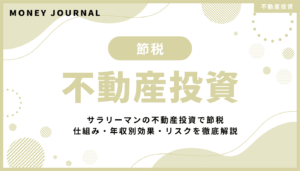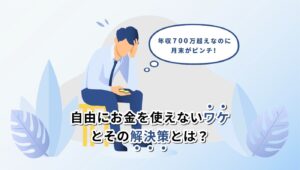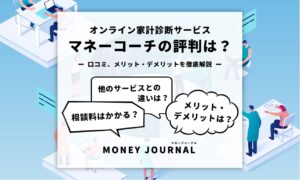- 「注文住宅を建てたいけど、土地代と建築費をまとめて払うのは難しい」
- 「つなぎ融資と分割融資の違いがよくわからない」
- 「どの銀行が分割融資に対応しているのか知りたい」
このように考えている方もいるでしょう。
本記事では、住宅ローン分割融資の仕組みからメリット・デメリット、つなぎ融資との違い、対応している銀行一覧まで徹底解説していきます。
住宅ローンの準備で迷っている方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
- 住宅ローン分割融資の仕組みと流れ
- 住宅ローン分割融資のメリットとデメリット
- つなぎ融資との違いと選び方の基準
- 住宅ローン分割融資に対応している銀行一覧
- 審査でチェックされるポイントと必要書類
住宅ローン分割融資とは?

注文住宅や土地購入では、家が完成するまでに土地代や着工金、中間金、残金など複数回の支払いが発生します。その都度まとまった自己資金を準備するのは難しく、ギャップを埋めるために利用されるのが「住宅ローン分割融資」です。
融資の内容は金融機関によって異なり、同じ金利を一括して適用するケースと、実行時ごとに金利を決め直すケースがあります。
契約が1回で済む銀行もあれば、毎回契約が必要な銀行もあるため、諸費用や手数料が変わる点に注意が必要です。

住宅ローン分割融資を活用する4つのメリット

住宅ローン分割融資には利息負担や税制面での優遇など、数多くのメリットがあります。ここでは代表的な利点を細かく見ていきます。
低金利で金利負担が軽減される
分割融資では、実行される融資すべてに住宅ローンと同じ低金利が適用されます。一般的な住宅ローンの変動金利が0.5%台〜1%台なのに対し、つなぎ融資は2〜4%の金利が必要です。
たとえば、5,000万円を30年返済で借り入れる場合、金利が1%違うだけで総返済額が数百万円変わるため、金利差は大きなメリットと言えます。
住宅ローン控除の対象になる
分割融資は土地と建物を一体の住宅ローンとして組むため、土地取得から2年以内に建物を完成させるなど条件を満たせば控除の対象です。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税などから控除する制度で、入居から最長13年間適用されます。
参考:国土交通省「住宅ローン減税」
つなぎ融資は短期融資で借入期間が10年未満のため住宅ローンの控除対象外です。
ほかにも以下のような注意点があります。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 入居時期の管理 | 住宅ローン控除は「入居した年」が起点。分割実行で工期が延び、入居が遅れると控除適用年や制度期限がずれるリスクあり |
| 年末残高の影響 | 控除額は「年末時点のローン残高」で決まる。分割実行のタイミング次第で残高が少なくなり、控除額を取りこぼす恐れあり |
| 証明書類の整備 | 分割実行住宅は途中で仕様変更しにくいため、省エネ基準・耐震基準などの性能要件を最初から満たす設計に。証明書も融資実行に合わせ早めに準備が必要 |
| 名義・登記の統一 | 土地と建物の名義が異なると控除対象外になることがある。分割実行時の抵当権設定や登記の整合性を事前に確認すべき |
| 手数料・コスト増 | 分割実行ごとに事務手数料や登記費用が発生するケースがある。結果的に控除メリットをコストが相殺してしまうリスク |
| 制度改正リスク | 制度期限直前の入居計画だと、制度変更で控除が受けられなくなる可能性あり。分割実行ではスケジュールに余裕を持たせることが重要 |
1回の契約で複数回の融資が受けられる
必要なときに必要な分だけ借りられるので、自己資金が少ない場合でも資金計画に柔軟性が生まれます。
さらに、つなぎ融資のように別契約を繰り返す必要がなく、金融機関とのやりとりも減るので、余計なストレスを抱えにくいのもメリットです。
資金計画が立てやすい
建築スケジュールに沿って必要な時期に資金を受け取れるため、あらかじめ支払い計画を立てやすくなります。
ただし、融資回数が増えるたびに費用や手続きが必要になり、思い描いた計画通りに進まないリスクもあります。

住宅ローン分割融資を活用する4つのデメリット
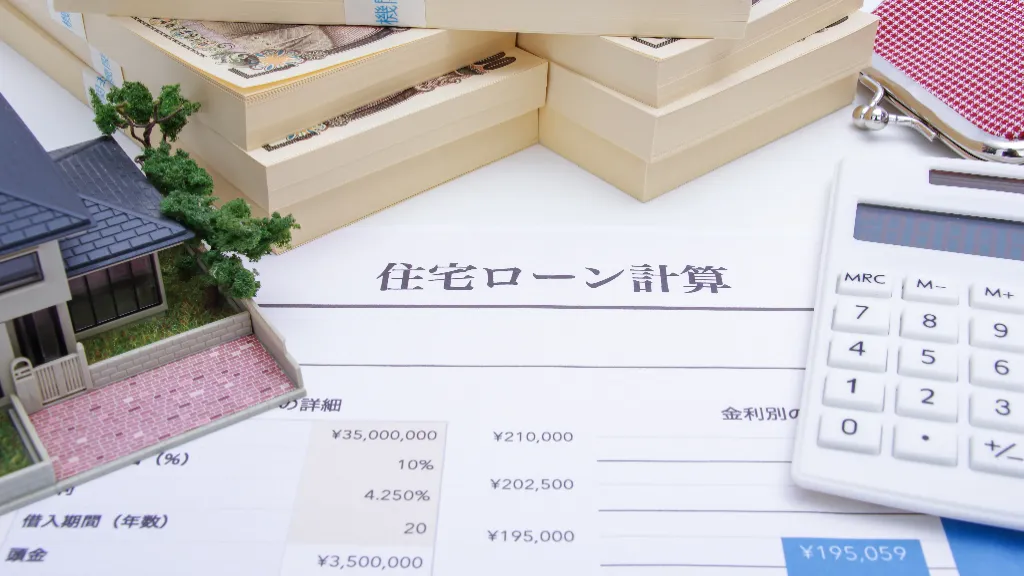
分割融資には資金繰りを安定させやすいなどのメリットがある反面、コストや手間が増えるといったデメリットもあります。
主な注意点としては、次の4つが挙げられます。
抵当権設定が複数回必要
土地分の融資を受けた際には土地に抵当権を設定し、建物が完成して最終金を借りる際には建物に抵当権を設定する必要があります。
抵当権設定には司法書士報酬や登録免許税が付きもののため、複数回設定すると費用が嵩みます。
また、土地と建物に別々の担保が設定されるため、将来の売却や借り換えの際に手続きが複雑になる可能性もあるでしょう。
登記費用や手数料が増える
登録免許税の税率は通常0.4%ですが、新築住宅に合わせて抵当権を設定する場合は0.1%に軽減されます。
ところが、土地のみに抵当権を設定する分割融資では優遇措置が適用されず、税率は0.4%となります。たとえば土地価格が3,000万円の場合、登録免許税は12万円が必要です。
さらに、契約を複数回に分けて行う金融機関では、融資実行のたびに事務手数料や印紙代がかかり、結果としてつなぎ融資よりも総費用が高額になる場合があります。
参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
分割融資に対応した銀行が少ない
分割融資を扱う銀行はごく一部で、住宅ローン全体から見ると少数派です。対応していても「融資回数に上限がある」「実行できる時期が限られている」など、自由度が低いのが実情です。
利用を検討する際には、自分が取引可能な銀行で分割実行が可能かどうかを早めに確認しておくことが大切です。
金利決定や返済開始時期の管理が複雑
分割融資では、各回の融資実行時点の金利が適用されるため、実行のタイミングによって返済条件が異なる場合があります。変動金利型を選ぶ場合、金利上昇リスクをどうコントロールするかがポイントです。
また、元金返済の開始時期も複雑になりやすく、一部融資分については「利息のみ支払い期間」が設けられ、元利返済の開始が遅れることがあります。このずれを考慮した返済シミュレーションを行わなければ、想定以上の返済負担を招く恐れがあります。
しかし「自分でシミュレーションしてもうまく比較できない…」という方も多いのではないでしょうか。そうした場合は、専門家に家計全体を見直してもらうのも有効です。
マネーコーチのオンライン家計診断なら、住宅ローン返済だけでなく、保険や教育資金、老後資金まで含めてトータルで改善ポイントを提案してくれます。
無料で受けられるので、まずはお気軽にご相談ください。
住宅ローン分割融資とつなぎ融資の違い

注文住宅で利用できる主な資金調達方法は分割融資とつなぎ融資の2つです。ここでは両者の違いを比較し、どのようなケースでどちらを選ぶべきかを整理します。
金利と費用の違い
つなぎ融資は建物が完成するまでの短期融資であるため、金利が年2〜3.5%と住宅ローンより高く設定されています。一方、分割融資は住宅ローンと同じ金利が適用されるので、支払う利息が少なく済みます。
手数料については、つなぎ融資は1本の契約で済むため事務手数料や登記費用が一度で済むのに対し、分割融資は融資のたびに登記費用や印紙代が発生し、総費用が高くなる傾向があります。
控除制度と税制の違い
住宅ローン控除の適用条件には「借入期間が10年以上」「取得から6か月以内に入居し、借入残高がある」といった要件があります。
つなぎ融資は借入期間が1年以内の短期融資であるため控除対象外ですが、分割融資は1本の住宅ローンとして組むため条件を満たせば控除を受けられます。
土地購入から2年以内に建物を完成させ居住するなどの制限はあるものの、税制メリットを受けたい人にとって大きな違いです。
契約手続きと手間の違い
つなぎ融資は1本の短期ローンを組み、住宅ローン実行時に一括返済するため手続きが比較的簡単です。融資実行時の審査は住宅ローンの審査と同時に行われることが多く、必要書類も少なく済みます。
分割融資は融資を受けるたびに銀行が工事の進捗を確認し、必要書類を提出して審査を行うため手間がかかります。
加えて、抵当権設定のために司法書士との日程調整が必要になるなど、工事期間中の作業が増える点はデメリットです。
どちらを選ぶべきかの判断基準
分割融資とつなぎ融資のどちらを選ぶかは、自己資金の有無、建築会社の対応可否、支払い回数、返済開始時期への希望などを踏まえて総合的に判断しましょう。
自己資金が少なく、手続きをシンプルに済ませたいならつなぎ融資が向いています。金利負担を少しでも抑えたい、住宅ローン控除を受けたい場合は分割融資が有利です。
ただし、分割融資は取り扱い銀行が限られ、融資実行のたびに手数料が必要となるため、事前にシミュレーションを行い、トータルコストを比較しましょう。住宅会社によってはつなぎ融資のみ対応というケースもあるので、契約前に確認が欠かせません。
住宅ローン分割融資の流れとタイミング

分割融資を利用する際は、工事の進行に合わせて融資が実行されるため全体の流れを理解しておくことが重要です。ここでは一般的な流れと確認すべきポイントを解説します。
融資実行のタイミング(土地・着工・上棟・引き渡し)
注文住宅では土地契約から引き渡しまでに複数回支払いが発生します。一般的には以下の4回のタイミングが代表的です。
- 土地の購入時
土地代金や手付金を支払います。手付金は自己資金で賄うケースが多く、残額を分割融資で用意します。 - 着工時
工事が始まる際に建築費の約3分の1を着手金(着工金)として支払います。 - 中間金(上棟時)
工事が進んだ段階で2回目の支払いが発生し、中間金として建築費の1/3程度を支払います。 - 引き渡し時
工事完成時に残金を支払い、建物の引き渡しと登記を行います。
金融機関によっては着工時と引き渡し時の2回のみ融資可能なところや、土地購入・着工・中間・引き渡しと4回まで融資可能なところがあります。自分の資金調達計画と合うように、融資可能回数とタイミングを確認しましょう。
契約回数・金利適用・返済開始時期の確認
分割融資を利用する際は、以下の点を必ず確認しておきましょう。
- 契約の回数
金融機関によっては1回の契約で複数回融資が実行できるところもありますが、毎回契約が必要な銀行もあります。 - 適用金利の決定時期
1回目の融資時の金利をその後も適用する銀行もあれば、毎回実行時点の金利が適用される銀行もあります。 - 返済開始のタイミング
融資を受けた翌月から元利返済が始まる場合と、建物の引き渡し後にまとめて元金返済を始める場合があります。
これらの条件によって毎月の返済額や総返済額が変わるため、建築会社の支払スケジュールと合わせてシミュレーションすることが大切です。変動金利の場合は金利上昇リスクも踏まえて余裕を持った計画を立てましょう。
住宅ローン分割融資に向いている人・向いていない人

分割融資は万能な商品ではありません。自己資金の有無や返済計画、建築会社の支払い方法によって向き不向きがあります。
向いている人の特徴
分割融資が向いているのは、以下のような人です。
向いていない人の特徴
一方、分割融資が向いていないのは次のようなケースです。
住宅ローン分割融資に対応している銀行一覧

分割融資を検討する際は、どの銀行が対応しているか、どのような特徴があるかを理解することが大切です。以下では主な金融機関を取り上げ、金利や融資回数、特徴を比較します。
| 銀行名 | 主な金利・融資回数 | 特徴 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 変動金利年0.525%程度〜、融資回数は複数回(一般に最大3回) | ネット住宅ローンで分割融資に対応し、つなぎ融資なしで土地代や建築費を支払える。契約は1回で追加手数料がかからない | ・電話番号: 0120-3242-86 ・受付時間:平日9:00~17:00 |
| 三菱UFJ銀行 | ・変動金利:0.595%~/年 ・固定10年:1.92%~/年 | 店頭申し込みが必要だが、低金利が魅力。公式に分割融資という商品はないものの、個別相談で対応。金利重視の人に向く | ・電話番号:0120-860-777 ・受付時間:毎日9:00~17:00 |
| 三井住友銀行 | 【バランスパック】 ・変動金利型:0.595%~/年 ・固定金利特約型(固定10年):2.10%~/年 【変動金利型】 0.925%~/年 ※物件価格の80%以内で借り入れる場合の金利 土地先行融資と併用で最大4回まで融資可能 | 土地代・着工金・中間金・残代金に細かく対応。土地先行融資併用時は、土地融資の実行から12ヶ月以内に着工、24ヶ月以内に完成する必要がある | ・電話番号:0120-338-555 ・受付時間:平日9:00~19:00 |
| 住信SBIネット銀行 | 変動金利年0.698%程度、土地先行プランを用意 | ネット銀行としては珍しく土地先行プランがあり、土地購入費を分割融資で借りられる。1回目融資後の変更には再審査が必要 | ・電話番号:0120-974-646 ・受付時間:平日9:00~18:00 |
| りそな銀行 | 変動金利:0.640%~/年 | 条件を満たせば土地資金も住宅ローン控除の対象となる。土地と建物で個別に申し込む必要があり、契約ごとに手数料が発生する | Webで来店予約のみ |
| イオン銀行 | 固定金利 ※貸出日当日の店頭表示の住宅ローン変動金利の基準金利が適用 | 建物の着工金・中間金に利用できるつなぎローンを提供。土地購入には利用できない。取扱手数料0円だが金利が上乗せされる | 電話番号:0120-48-1258 |
出典:三菱UFJ銀行「住宅ローン」
出典:三井住友銀行「住宅ローン金利」
出典:住信SBIネット銀行「土地先行プラン(2回に分けて融資)」
出典:りそな銀行「住宅ローン(新規)」
出典:イオン銀行「イオン銀行つなぎローン」
このほか、地方銀行や信用金庫でも分割融資に対応しているところがありますが、取扱件数は多くありません。各銀行の条件は変更されることがあるため、最新の金利や融資条件は公式サイトで確認しましょう。
住宅ローン分割融資の審査で重視されるポイント

分割融資を利用する場合でも、基本的な審査基準は通常の住宅ローンと大きく変わりません。銀行は「確実に返済できるかどうか」を軸に審査を行うため、年収や返済負担率といった数字面だけでなく、職業の安定性や建築計画の妥当性なども細かく確認されます。
以下の6つが代表的な審査ポイントです。
年収
住宅ローン審査で最も基本となるのが「年収」です。年収が高いほど借入可能額は増えやすく、返済余力があると判断されます。ただし、単純な額面年収だけでなく、実際の手取りや税引後所得、各種控除を差し引いた金額を基準に評価されることもあります。
また、年収の高さよりも「安定して同じ収入を得ているか」が重視される傾向が強く、継続的に同程度の収入を得ていることが望ましいです。
注意すべき点は、年収が高くても他の借入や生活費が多ければ返済余力は小さいと判断されることです。さらに、自営業やフリーランスのように収入が変動しやすい職業の場合、複数年分の確定申告書の提出を求められることがあります。
なお、配偶者の収入を合算できる仕組みもあるため、不足を補う方法として検討してみるとよいでしょう。
返済負担率
返済負担率とは、年収に対して年間返済額がどのくらいの割合を占めるかを示す数値です。住宅ローンだけでなく、自動車ローンやカードローンなど他の借入も含めて計算されます。
一般的に、多くの銀行は30〜35%を上限の目安としています。返済負担率が低ければ「無理なく返せる」と判断され、審査において有利になります。分割融資では、融資ごとに金利や返済開始時期が異なるため、少し余裕をもった返済負担率でシミュレーションしておくことが大切です。
ただし、上限の数値は銀行やローン商品によって異なります。将来の教育費や老後資金といった支出も考慮され、過度に返済負担率が高くならないよう調整される場合もあるので確認しましょう。
職業
職業や雇用形態は、収入の安定性を見極めるための大きなポイントです。正社員や公務員は安定していると判断されやすい一方で、自営業やフリーランスは収入に波があるため、数年分の確定申告書や決算書を提出する必要があります。契約社員や派遣社員であっても、勤務年数が長ければ審査に通過する可能性はあります。
転職直後は収入実績が乏しいため融資に不利となる場合がありますが、同業種への転職や収入増加を伴う場合には、マイナス評価が軽減される傾向があります。自営業者においては、安定した売上を数年間継続しているかどうかが審査の大きな分かれ目となります。
勤続年数
勤続年数は収入の継続性を判断するうえで欠かせない基準です。多くの銀行では1年以上を最低ラインとしていますが、3年以上の実績があれば審査上有利になることが多いです。
転職直後で勤続年数が短い場合は、以前の勤務先の経歴や収入実績を提出するよう求められることもあります。ただし、グループ内の異動や同業種への転職で収入が安定していれば、影響は小さいと判断される場合もあります。
自己資金
自己資金は、借入額を抑える効果に加え、銀行からの信用度を高める役割もあります。一般的には物件価格の1割程度を自己資金として用意することが望ましいとされています。
一方、自己資金ゼロでも借入可能な商品は存在しますが、その場合は金利優遇を受けにくくなったり審査が厳格化されたりします。分割融資を利用する場合、各支払い時点で自己資金を求められることもあるため、諸費用を含めて余裕を持った資金準備をしましょう。
建築計画と工事契約書
注文住宅や建築中の物件で分割融資を利用する際は、建築計画や工事請負契約書の提出が必要です。契約書には工事費用や支払いスケジュール、工期、引渡し条件が記載されており、それをもとに銀行は融資回収の可能性を判断します。
このほか、建築確認申請書や確認済証、設計図面、配置図などの書類を求められるケースもあります。工事の進捗と支払いスケジュールが対応しているか、融資実行のタイミングに矛盾がないかもチェックされます。
住宅ローン分割融資の必要書類

分割融資を利用する際には、通常の住宅ローンと同じく多くの書類を用意する必要があります。住宅を建てる流れは土地購入、建築契約、着工、引き渡しと段階的に進むため、書類も複数にわたります。準備が遅れると融資実行の時期がずれ、支払いに間に合わないリスクがあるため、早めにそろえておくことが大切です。
一般的に求められる書類は以下のとおりです。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 住民票・印鑑証明書
- 所得証明書(会社員なら源泉徴収票、自営業なら確定申告書など直近2〜3年分)
- 勤務先の在職証明書
- 建築請負契約書、設計図書、見積書
- 土地の売買契約書または登記簿謄本
- 資金計画表(自己資金と融資の割合を示したもの)
これらは銀行が「返済能力」と「建築計画の確実性」を確認するために必要となります。本人確認や所得証明は返済力の裏付けに、建築契約書や設計図は建築が確実に進むかどうかを判断する材料です。
金融機関によっては、追加で印鑑カード、健康保険証、納税証明書などを求められる場合もあります。事前に銀行からチェックリストを入手し、漏れがないよう準備を進めましょう。
住宅ローン分割融資を利用する際のポイント

後から「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、以下の4つは特に注意しておきましょう。
建築会社やハウスメーカーの対応可否を確認する
分割融資を使うには、建築会社やハウスメーカーが対応可能であることが前提です。支払いが着工金・中間金・上棟金・引渡し時に分かれている会社なら分割融資に対応しやすいですが、完成後一括払いが基本の会社では利用が難しくなります。
また、工事請負契約書や支払スケジュールを金融機関に提出する必要があるため、建築会社が書類対応に協力的かどうかも大切です。過去に分割融資を扱った実績がある会社なら手続きもスムーズに進みやすいでしょう。
トータルコストの比較をシミュレーションする
分割融資は通常の住宅ローン金利が適用されるため金利面で有利ですが、融資のたびに登記費用や手数料が発生する場合があります。そのため「つなぎ融資」と比べてどちらが総額で有利かを必ずシミュレーションしましょう。
費用としては登録免許税、司法書士報酬、印紙代や書類取得代などの実費に加え、追加抵当権設定や担保調整の手続き費用もかかることがあります。さらに、金利変動リスクを想定し、低金利・中金利・高金利と複数パターンで返済額を確認しておくと安心です。
金利変動リスクを踏まえ返済計画を立てる
分割融資では、融資を実行する時期ごとに金利が変わる可能性があります。途中で金利が上がれば、返済額が想定より増えることもあるため、変動を前提に計画しておく必要があります。
また、一部の融資分については「利息のみ支払い期間」が発生し、元金返済の開始が遅れる場合もあります。
住宅ローン分割融資に関するよくある質問
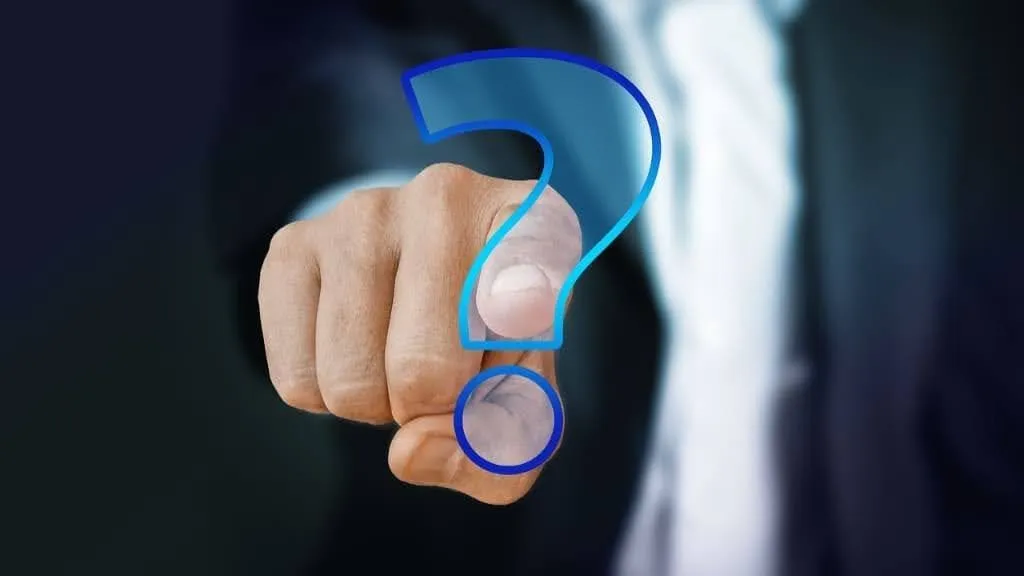
住宅ローン分割融資に関するよくある質問は以下のとおりです。
分割融資は注文住宅でない場合も使える?
分割融資は主に注文住宅や土地付き建物の購入に利用されますが、マンション購入など支払いが一括のケースでは必要ありません。建売住宅や中古住宅の場合は、引き渡し時に一括で支払うのが一般的なため、分割融資は利用できないか、必要ありません。住宅会社や金融機関に確認しましょう。
土地だけの購入でも利用できる?
土地代のみを先行して借りる場合は、分割融資の一種である土地先行融資が利用できます。ただし、土地購入から一定期間内に住宅を建てる計画が必要で、土地を購入したまま長期間建てない場合は利用できません。抵当権設定や返済開始が早まるといったデメリットも考慮しましょう。
借入回数は何回まで可能?
金融機関によって融資実行回数は異なります。一般的には2回までの銀行が多い一方、みずほ銀行や三井住友銀行では土地購入、着工金、中間金、引き渡し金の4回程度まで対応しています。回数が多くなるほど手数料や登記費用が増えるため、建築会社の支払いスケジュールと照らし合わせ、必要最低限の回数に抑えるとよいでしょう。
分割融資の期間中に転職した場合はどうなる?
融資実行の途中で転職すると、金融機関が融資条件を再確認する場合があります。収入が大きく変動したり勤続年数が短くなったりすると、追加融資の審査に影響を与えかねません。転職を予定している場合は、融資の実行後まで待つか、事前に金融機関へ相談してリスクを減らしましょう。
転職先の年収や雇用形態によっては審査に影響しないケースもありますが、返済計画に余裕を持たせることが大切です。
住宅ローン分割融資のまとめ
この記事では、住宅ローン分割融資の仕組みやつなぎ融資との違い、利用する際の注意点まで解説しました。
土地代や建築費を段階的に支払えるため、まとまった自己資金が少なくても安心して家づくりを進められます。一方で手数料や登記費用が増えるため、トータルでどちらが有利かを確認することが大切です。
将来の家計を考えるうえで、ローンの仕組みを正しく理解することは大切です。まずは本記事で学んだポイントを踏まえ、シミュレーションを行い、自分に合った融資方法を選んでください。