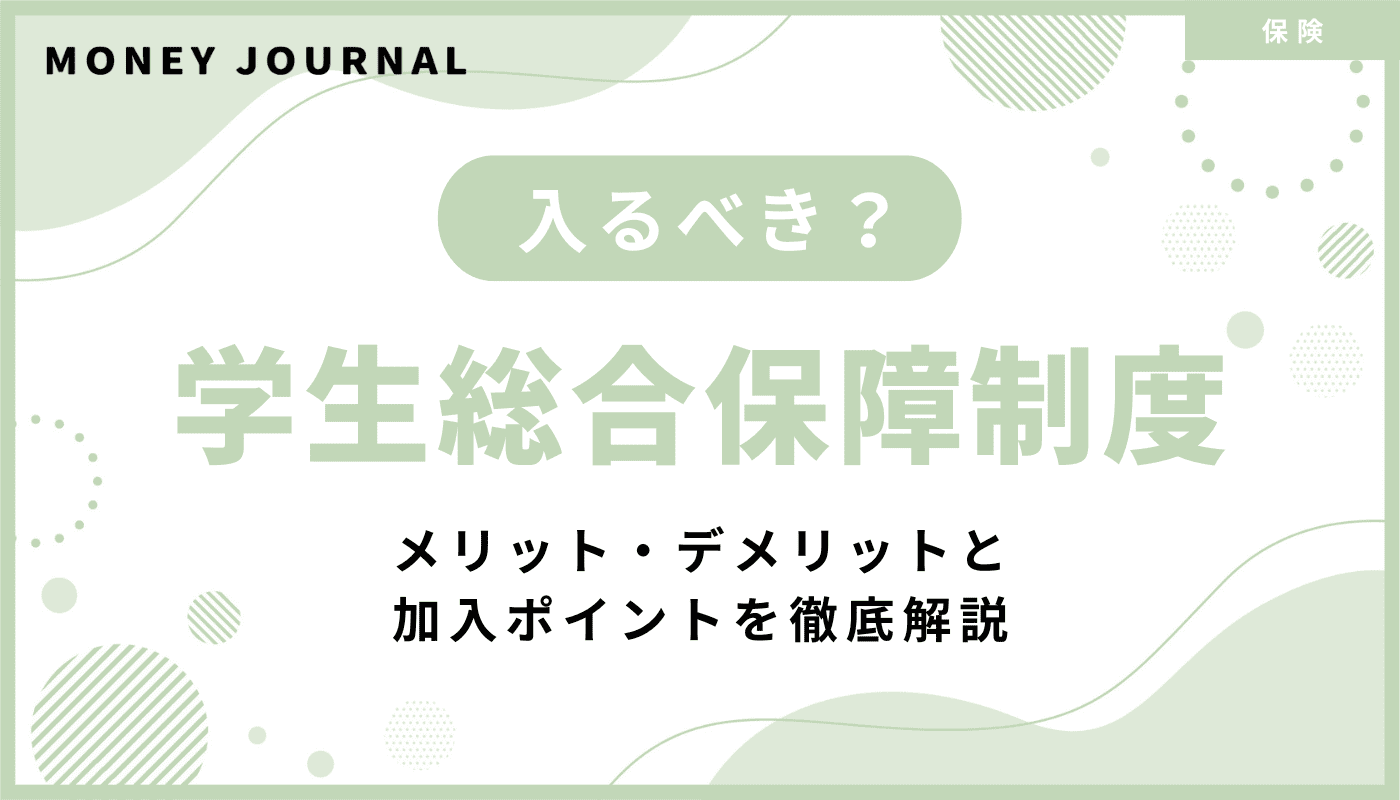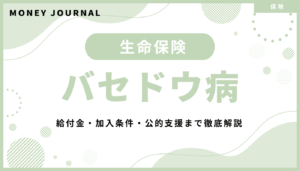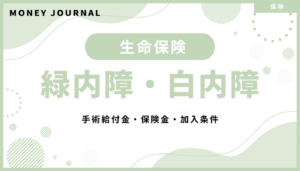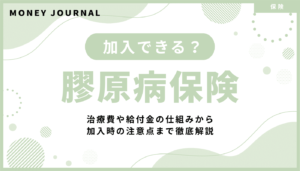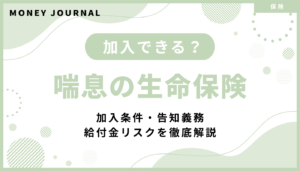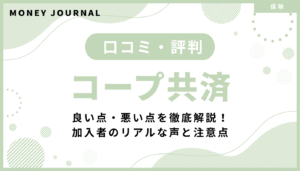- 「学生総合保障制度って入った方がいいの?」
- 「親の保険で足りているのか不安」
- 「大学生協の窓口で勧められたけど本当に必要?」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、学生総合保障制度は一人暮らしを始める学生やスポーツ・アルバイトをする学生には入っておく価値が高い保険制度です。
以下のような点がポイントです。
- ケガ・病気から賠償トラブルまで1つの契約で対応
- 団体割引があるので一般の保険よりも保険料が安い
- 海外留学やアルバイト中のトラブルも対象
本記事では、学生総合保障制度の仕組みから補償内容、メリット・デメリット、そして入るべき人と入らなくてもよい人の違いまで解説します。
学生生活を安心して送りたい方は、ぜひ参考にしてください。
- 学生総合保障制度の仕組みと加入条件
- 実際の補償内容(賠償・医療・持ち物など)
- 他の学生向け保険との違い
- メリットとデメリットを整理した具体例
- 入るべき人・不要な人の特徴
学生総合保障制度に入るべき?加入率を調査

学生総合保障制度と呼ばれるものは、コープ共済が提供する「学生総合共済」や一般財団法人未来サポートの「学生安心サポート」などを指します。名前に「制度」とあるため国の仕組みと誤解されがちですが、あくまで民間の共済・保険商品です。そのため、制度全体としての加入率や加入者数は把握できません。
参考になるのは一部の商品に限られます。たとえばコープ共済の「学生総合共済」は2024年度の加入者数が818,732人*で、前年の721,138人から大きく増加しました。もっともこの共済は対象年齢が満18歳から34歳までのため、小中高生や園児を含めた学生全体の加入状況とは異なります。一方で未来サポートの「学生安心サポート」は幼稚園児から加入可能であり、比較対象にはなりません。
*参考:co-op共済「コープ共済の加入状況」

学生総合保障制度とは?

まずは、学生総合保障制度の仕組みや対象となる学齢、加入条件、さらに運営する保険会社について整理していきます。
学生総合保障制度の概要
学生総合保障制度は、一般財団法人未来サポートや大学などが保険契約者となり、学生や園児とその家族が加入者になる団体保険です。制度のペットネームとして「学生あんしんパスポート」があり、損保ジャパンが引受保険会社として運営しています。
学生本人の急激で偶然な事故によるケガに対しては死亡・後遺障害・手術・入院・通院まで幅広く補償され、細菌性食中毒やウイルス性食中毒も対象となります。
学生総合保障制度の対象学齢
幼稚園児から大学生・専門学生まで加入でき、大学・短大・専門学校、医歯薬学部用など年齢や学部によってプランが分かれています。
契約者は一般財団法人未来サポートの会員である保護者が多く、インターネットからクレジットカード決済で申し込みできます。
学生総合保障制度の加入条件
学生総合保障制度は任意加入であり、一般的な任意保険と同じく強制ではありません。ただし、一部の学部では事情が異なります。
東京海上日動が取り扱う「学研災付帯学生生活総合保険(付帯学総)」は、学研災への加入が前提条件となっており、さらに実習や留学に参加するためには制度加入が必須となる場合があります。
学生総合保障制度の引受保険会社
学生総合保障制度は一般財団法人未来サポートが保険契約者、損害保険ジャパン株式会社が引受保険会社です。大学別の団体契約では東京海上日動火災保険など複数の損害保険会社が共同で引き受けることもあります。
保険料は団体割引や長期割引が適用され、卒業まで一括で契約すると割安になるのが特徴です。契約更新時に料率改定があっても保険料の追加・返戻がないのも特徴です。

学生総合保障制度の補償内容

学生総合保障制度の補償は多岐にわたります。以下では主な補償を具体的に紹介します。
個人賠償責任補償
学生や同居の家族が他人にケガをさせたり、他人の物を壊した場合、国内は無制限、海外は1億円を限度に保険金が支払われます。
自転車保険の義務化に対応した賠償責任補償である点も特徴で、学生本人だけでなく同居家族の事故も対象です。インターンシップやアルバイト中の賠償事故も補償され、示談交渉サービスが付いているので事故後の対応も任せられます。
ケガ・病気・特定感染症補償
急激かつ偶然な外来の事故によるケガで、死亡・後遺障害・手術・入院・通院まで補償され、学校の授業中や運動中だけでなく交通事故やレジャー中も対象です。
病気による入院・手術・通院も補償され、O‑157など特定の感染症を発症した場合の入院や通院、後遺障害もカバーします。
育英費用・学資費用補償
扶養者が事故で死亡したり重度後遺障害となり扶養不能になった場合、育英保険と同様に育英費用として一時金が支払われます。
付帯学総ではさらに、学資費用を実費で支払年度ごとに保障するプランがあり、扶養者の病気による死亡時にも学資費用保険金が支払われます。交通事故の場合は育英費用が倍額になるプランもあります。
住まいと持ち物の補償
一人暮らしの学生がアパートやマンションの部屋で火災・爆発を起こし家主に損害賠償責任を負った場合、借家人賠償責任保険が適用されます。
学生の生活用動産(家財)が火災や盗難で損害を受けた場合の補償や、身の回り品が住宅外で盗難・破損した場合の携行品損害補償も含まれます。
天災・熱中症・救援者費用など
地震・噴火や津波によるケガに対し、入院・通院・死亡・後遺障害・手術・育英費用まで補償する天災補償があります。日射や熱射による熱中症で入院・通院・死亡・後遺障害・手術の保険金を支払う特約も含まれているのが特徴です。
さらに、急激な事故や病気で学生本人の捜索や保護者の駆け付けが必要になった場合の交通費・宿泊費などを補償する救援者費用補償が設けられています。
サポートサービス
契約者や被保険者、その家族を対象に健康・医療・法律相談を受け付ける無料電話サービス「学校生活安心ダイヤル」が提供されています。東京海上日動の「メディカルアシスト」では救急科専門医や看護師が24時間対応する緊急医療相談や医療機関案内を行っています。
学生生活では、SNS上の誹謗中傷やいじめへの法的トラブルに対応する弁護士費用サポートもオプションで付けられるため、現代的なリスクにも備えられるでしょう。

学生総合保障制度に入るべき?5つのメリット

学生総合保障制度の利点は単なる怪我の保険に留まらず、学生生活を包括的に守れる点にあります。
ここでは、学生総合保障制度のメリットを紹介します。
幅広いリスクを1契約でカバー
賠償責任補償やケガ・病気補償、育英費用、家財保険までひとつの契約でまとめて備えられることが最大のメリットです。自転車事故で他人をケガさせた場合の損害賠償や、アルバイト中の賠償事故も対象です。
災害や熱中症など自然災害に伴うリスクも含まれるため、複数の保険に分けて加入する手間を省けます。さらに、扶養者が亡くなった際には育英費用が支払われるため、学業継続に必要な学費を確保できるのも特徴です。
団体割引で保険料が割安
学生総合保障制度は団体契約として設計されており、未来サポートの会員として加入することで保険料が割引になります。
大学ごとの団体契約では長期割引も適用され、卒業までの契約を一度に行うと毎年申し込む手間が省けるだけでなく保険料が割安になります。学生の限られた予算でも手厚い保障を得やすい点は大きな魅力です。
SNS・いじめ・法的トラブルに対応
学生総合保障制度には法的トラブルに遭った場合に弁護士費用をサポートする特約があります。
SNSの誹謗中傷やいじめによる精神的被害、ストーカー被害などの社会問題にも保障されるのが特徴です。
24時間365日、国内外で補償
補償は学校内外・国内外を問わず24時間適用されます。授業中だけでなく通学中や課外活動、旅行や海外留学中の事故も対象になるため、ライフスタイルが多様な現代の学生に合致しています。
東京海上日動の付帯学総では、アルバイトやインターン中の事故も補償の対象と明記されているため、働きながら学ぶ学生にも適しているでしょう。
フレキシブルな特約とオプション
学生総合保障制度には、標準補償に加えてさまざまな特約が付けられます。
一人暮らしを始める学生には家財やパソコン、タブレット、ゲーム機などの高額な機器を補償する「携行品損害補償」があり、登校中・課外活動中の盗難や破損に備えられます。
園児や小学生向けプランでは、メンタルサポートや電話相談サービスが重視されており、保護者が安心して子どもを見守れる仕組みになっています。
必要な補償だけを選べる柔軟性は、学生総合保障制度ならではの強みです。

学生総合保障制度に入るべき?3つのデメリット

メリットが多い反面、加入にあたっては注意点も存在します。ここでは学生総合保障制度のデメリットを整理します。
補償の重複・家族保険との被り
すでに親の火災保険や個人賠償責任保険、医療保険に加入している場合は補償が重複することがあります。
クレジットカードに付帯する賠償責任保険や自動車保険の個人賠償特約があれば、学生総合保障制度の賠償補償部分と重なる可能性があるのです。また、自治体によっては子どもの医療費助成制度が整備されており、医療費の自己負担がほとんどない地域では医療補償の必要性が下がります。
医療補償に制限がある
付帯学総では、歯科疾病や精神障害、痔核・裂肛など一部の疾病に対する治療費用は支払い対象外です。
学生総合保障制度のケガや病気補償も、病気が原因の場合は限度額が低めだったり補償日数が短かったりするプランがあるため、パンフレットで詳しい支払条件を確認する必要があります。
申請手続きの煩雑さ
保険金請求の際は、保険会社から請求書類を取り寄せ、領収書など必要書類を添えて返送する必要があります。ネット申し込みができる反面、事故発生後の手続きや書類準備には手間がかかり、連絡を怠ると支払いが遅れることもあります。
学生総合保障制度に入るべき?必要な人・不要な人

学生総合保障制度への加入は義務ではなく、状況に応じて必要性が変わります。ここでは加入を検討すべき人と不要な場合を整理します。
必要な人|一人暮らし・スポーツ・アルバイトなど
学生生活のなかでリスクに直面する可能性が高い人は加入を検討した方が安心です。具体的には以下のような学生です。
- 一人暮らしをしている人
- 自転車通学やアルバイト・インターンをしている人
- 扶養者の収入に不安がある人
- スポーツやアウトドア活動をする人
- SNSやいじめのトラブルが心配な人
幅広い生活リスクを1つの制度でカバーできるため、行動範囲が広い学生におすすめできる実用性が高い制度だと言えるでしょう。
不要な人|親の保険でカバーされる場合など
一方で、すでに十分な補償を受けられている学生は入らない選択をしても大きな問題はない場合があります。代表的なのは次のようなケースです。
- 親の保険や共済で補償が十分な場合
- 医療費助成が充実している地域に住んでいる場合
- 生活スタイルにリスクが少ない場合
このように、加入すべきかどうかは自分や家族の補償内容を確認しながら判断することが大切です。
学生総合保障制度と他の学生向け保険の違い

学生が加入できる保険は複数あり、制度ごとに目的や補償が異なります。代表的な保険との違いを整理します。
学研災・学研賠・付帯学総との違い
多くの大学で全員加入が推奨される「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」は授業や学校行事中のケガを補償する制度で、個人賠償責任は含まれません。
学研災に付帯する「学研災付帯学生生活総合保険(付帯学総)」は東京海上日動が提供しており、賠償責任や病気による治療費、育英費用、生活用動産補償などをセットにした保険です。
PTA保険やスポーツ保険との違い
小中学校で案内される「児童・生徒総合補償制度」や「PTA保険」は、学校管理下のケガと賠償責任に限定された補償が中心で、SNSトラブルや育英費用の特約はありません。
また、スポーツ安全保険は部活動やクラブ活動中のケガを補償する安価な保険ですが、個人賠償責任や生活用動産補償は対象外です。
学生総合保障制度に関するよくある質問

制度について調べると「生命保険や医療保険とはどう違うの?」「一人暮らしの火災保険と重複しないの?」など、細かな疑問が湧いてくるはずです。ここでは特に多い質問に答えます。
学生総合保障制度と生命保険・医療保険はどちらが必要?
学生総合保障制度は、学生生活で起こりやすいリスクを幅広くカバーします。病気やケガの治療費、通学中の事故による賠償、スマートフォンやパソコンの損害、扶養者の万一まで対象です。
一方で生命保険や医療保険は、本人の死亡や長期入院を大きな保障額で支える商品で、保険料も高めに設定されています。
既に親の生命保険があるなら、学生総合保障制度で不足分を補う形が現実的です。
一人暮らしの火災保険との重複は?
大学進学を機に一人暮らしを始める新生活では、賃貸契約に火災保険がセットで付く場合が多いです。火災保険は建物や家財を補償しますが、借家人賠償責任や学生生活用動産の補償は特約を付けないと含まれないことがあります。
学生総合保障制度には、次のような補償が標準で含まれています。
- 借家人賠償責任補償:借りている部屋で火災や爆発を起こし家主に損害を与えた場合に対応
- 動産補償:家具やパソコン、タブレット、電動自転車などが壊れた場合に補償
自宅通学の学生には不要でも、一人暮らしで高価な電子機器を持つ方には安心材料になります。現在加入している火災保険の内容を確認し、不足している部分を学生総合保障制度で補うと無駄がありません。
付帯学総と学生総合保障制度、どっちを選ぶべき?
東京海上日動の付帯学総は、学研災に加入する学生を対象とした補償で、病気やケガ、賠償責任まで幅広くカバーします。医療系学部向けには針刺し事故や感染症補償など独自の特約があり、24時間医療相談サービスも利用できます。
一方で損保ジャパンなどが提供する学生総合保障制度は、賠償責任補償が国内無制限・海外1億円と手厚く、SNSいじめやストーカー被害時の弁護士費用も対象に含まれています。
中学生・高校生も入るべきか?
学生総合保障制度は大学生だけでなく、園児から高校生まで対象とするプランがあります。多くの自治体で自転車保険の加入が義務化されており、学生総合保障制度に含まれる賠償責任補償はその要件を満たせる点が強みです。部活動専用のスポーツ保険に加入することもできますが、対象は活動中のみであり、学校外での事故には対応できません。
学生総合保障制度のまとめ
この記事では、学生総合保障制度の仕組みや補償内容、メリットとデメリット、さらに加入すべき人と不要な人の特徴まで解説しました。
親の保険で十分に補償される場合や医療費助成が充実している地域では不要となるケースもありますが、行動範囲が広い学生には制度が大きな支えになります。
加入するか迷うときは、家族の保険内容と照らし合わせ、不足している部分を補う形で検討するとよいでしょう。将来の安心を手に入れるために、今の生活に合った補償を選んでください。