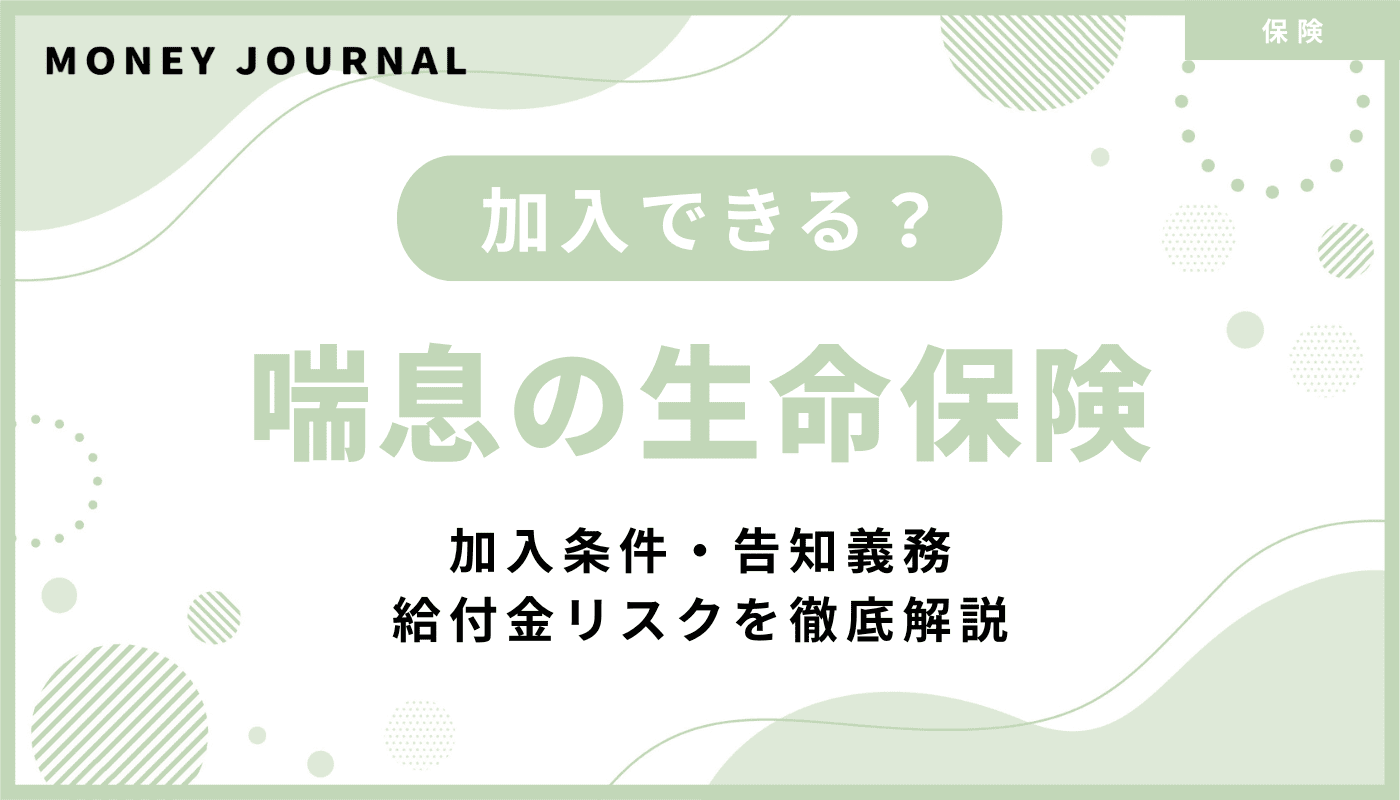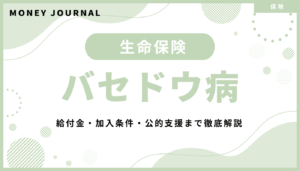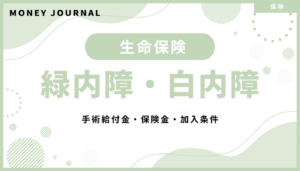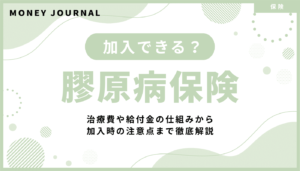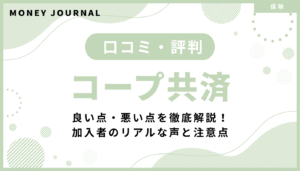- 「喘息を持っていても生命保険に入れるのだろうか」
- 「過去に入院したことがあるけど審査に通るのか心配」
- 「告知義務でどこまで正直に伝えるべきか迷っている」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、喘息を持っていても加入できる生命保険は存在します。条件や保険の種類を整理すると以下のように分かれます。
- 軽症かつ入院歴がなければ、通常の医療保険に加入できる可能性がある
- 症状が安定していない場合でも、引受基準緩和型や無選択型なら加入できるケースがある
本記事では、喘息患者が安心して保険を選び加入するために必要な情報をまとめました。
「喘息があっても将来の安心を得たい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
- 喘息生命保険の基本的な仕組みと対象疾患
- 症状別に加入できる医療保険の種類
- 告知義務違反がもたらすリスクと回避方法
- 保険に入れない場合に利用できる公的制度
- 保険を選ぶ際のチェックポイント
喘息生命保険とは?

ここでは「喘息生命保険」という言葉の意味を明確にし、一般的な医療保険やがん保険と比較しながら、なぜ喘息患者が特定の保険選びを意識する必要があるのかを解説します。
喘息生命保険の基本的な仕組み
喘息生命保険とは、呼吸器疾患や喘息の症状を抱える人でも加入しやすい生命保険の総称です。
保険会社は加入希望者の健康状態や体況を審査してリスクに見合った保険料を設定しますが、喘息の場合は症状の程度や治療歴によって条件が変わります。
喘息生命保険の対象となる疾患
喘息に関連する病気は、生命保険の審査で「特定疾患」や「呼吸器疾患」としてひとまとめに扱われることが多いです。そのため、加入を検討する際にはどの病気が対象になるのかを正しく知っておく必要があります。
代表的なものは以下の3つです。
| 疾患名 | 主な症状 | 特徴・原因 |
|---|---|---|
| 気管支喘息 | 息苦しさ、喘鳴(ゼーゼー音)、発作的な呼吸困難 | 気道の慢性的炎症で過敏な状態。ハウスダストや花粉などアレルギー反応が引き金になることが多い |
| 咳喘息 | 数週間以上続く咳のみ(喘鳴はなし) | 軽度の炎症でも気道が敏感に反応。放置すると気管支喘息に進行する可能性がある |
| 慢性気管支炎 | 咳や痰が3か月以上続き、年に2回以上繰り返す | 喫煙や大気汚染が主な原因。喘息と区別されるが生命保険では呼吸器疾患として扱われやすい |
このように病名ごとに症状や原因は異なりますが、いずれも呼吸のしづらさや長引く咳など日常生活に大きく関わる病気です。

喘息持ちで通常の医療保険に加入できる条件

医療保険は健康体であることを前提に作られているため、持病があると加入が難しくなります。喘息も例外ではなく、発作の有無や治療の内容によって審査の可否が大きく変わります。
注意したいのは、加入できても「部位不担保(肺や気管支を保障対象外とする)」や「特定疾病不担保(喘息悪化に伴う入院を対象外とする)」といった制限が付くことが多い点です。
さらに保障除外の期間は2〜5年程度に限られるのが一般的です。その間に呼吸器疾患で入院しても給付金を受け取れないため、条件をきちんと理解してから加入を検討することが大切です。
では、どのような状態であれば通常の医療保険に入れる可能性があるのでしょうか。主な条件は以下の3つです。
軽症で入院歴がない
現在の喘息治療は吸入ステロイド薬の普及により大きく改善されており、以前よりも入院に至る患者は減っています。
特に過去5年間で入院歴がなく、発作も適切にコントロールされている場合は、保険会社から「軽症」と判断されることが多いです。
軽症とみなされると、通常の医療保険に加入できる可能性が高まります。
経口ステロイドの処方歴がない
喘息治療では吸入薬が基本とされます。一方、経口ステロイドは重度の症状を抑える目的で用いられるため、処方歴があると「症状が重い」と判断されやすいです。
そのため、経口ステロイドを使ったことがなければ、保険に加入できる可能性が高くなります。
治療を継続し症状が安定している
喘息は慢性的な病気のため、通院と治療を続けることがとても大切です。お薬手帳に処方の記録が残っていれば、きちんと治療を受けている証拠となり、保険の審査でもプラスに働きます。
症状が安定していれば、保険料の割増や部位不担保といった制限が緩和されることもあります。つまり、治療を続けて体調を安定させることが、保険加入のポイントになるのです。

喘息でも入れる生命保険の種類
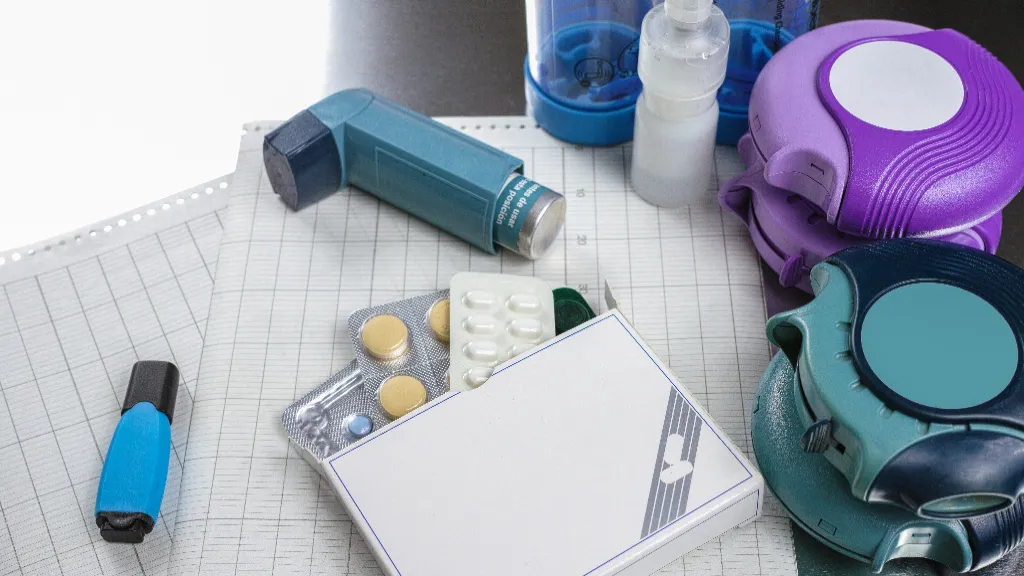
保険に加入したい喘息患者が最初に直面するのは、「どの種類の保険に加入できるのか」という問題です。ここでは、喘息のある方が検討しやすい代表的な保険の種類を紹介します。
引受基準緩和型医療保険
引受基準緩和型医療保険は、持病や既往症がある人でも加入しやすいよう健康告知の項目を減らした保険です。
健康状態に関する質問が3~5項目程度と少なく、直近2年以内の入院や手術の有無など簡単な告知だけで加入できる商品が多くあります。そのため、経口ステロイドを使用している人や過去に入院歴がある人でも、条件次第で給付金がおりる可能性が高いです。
- 持病の悪化も保障対象:喘息悪化で入院した場合も給付金が支払われる
- 告知が簡単:詳細な病歴や服薬内容を細かく書く必要がない
- 死亡保障付き商品もある:終身型なら万一のとき遺族への備えも可能
一方で、引受基準緩和型医療保険には注意点もあります。
- 保険料が通常の医療保険より高めに設定されている
- 加入後1〜2年は給付金が半額となる削減期間がある
- 契約時によっては特定の病気が保障対象外となる場合がある
喘息で通常の医療保険が難しい方でも、条件付きで加入できる可能性が高いのが緩和型です。
無選択型保険
無選択型保険は、健康状態に関する告知や医師の診査が一切不要な保険です。加入審査がほとんどないため、重度の喘息や他の慢性疾患がある人でも申し込むことができます。
しかし、無選択型保険には以下のようなデメリットがあります。
- 保険料がかなり高い
- 加入から1〜2年は給付金が出ない「免責期間」がある
- 免責期間終了後も保障内容が限定されることが多い
つまり、誰でも入れる代わりに保障面の制限が厳しい商品です。そのため、無選択型保険は最後の手段と考えるのが妥当です。
実際の流れとしては、まず通常の医療保険や緩和型医療保険を申し込み、それでも入れない場合に検討するのが望ましいでしょう。
がん保険・死亡保険・団体信用生命保険
喘息はがんのリスクと直接関係ないため、がん保険に加入する際の影響はほとんどありません。経口ステロイドを使用していても加入を断られることはほとんどありません。
一方、死亡保険では、過去5年以内に喘息で入院したかどうかが審査の分かれ目になります。
- 入院歴がない、または症状が安定している→通常の死亡保険に加入できる可能性が高い
- 入院歴がある→保険料が割増になったり、特定条件付きになることがある
また、住宅ローンを組む際に必須の団体信用生命保険(団信)も、喘息の有無が審査対象です。軽症なら加入できる場合がありますが、症状によっては断られることもあります。
その場合は「ワイド団信」と呼ばれる緩和型商品を検討することになります。団信に加入できなかったときは、民間の死亡保険で住宅ローンの残債をカバーする方法もあるため、住宅ローンの契約先や金融機関と相談してみましょう。

喘息生命保険加入時の告知義務について

保険に加入する際は、現在の健康状態や過去の病歴を正直に申告する「告知義務」があります。
喘息患者は日常的に薬を使用しながら症状を管理しているため、どこまで告知すべきか迷うこともあるでしょう。ここからは、告知義務を怠った場合のリスクと、正しく準備する方法を解説します。
告知義務違反がもたらすリスク
告知義務違反とは、健康状態や既往症について事実と異なる内容を申告したり、申告すべき情報を省略することです。
告知義務に違反すると、以下のようなリスクがあります。
契約解除や保険金不払いにつながる
告知内容は、保険料や保障内容を決定する基準となるため、虚偽の申告や申告漏れがあれば契約が無効となるのが一般的です。
わずかな見落としでも大きな不利益につながるため、正直に申告することがとても重要です。
契約期間中でも解除される場合がある
違反が見つかると、契約から2年以内ならさかのぼって契約が解除される場合があります。その際には、入院や手術をしても保険金は支払われず、既に納付した保険料も返還されません。
さらに、2年を経過していても重大な事実の隠蔽が認められれば、契約が取り消される可能性があります。つまり、契約が続いていても安心できるとは限らない、という点を理解しておくことが大切です。
他の保険会社での加入を拒否される可能性がある
告知義務違反により契約が解除された経歴は、保険会社間で共有される場合があります。その結果、新しく申し込んでも「違反歴あり」と見なされ、加入を断られるリスクが高くなります。
たった一度の違反が将来の保険選びに響くので、告知内容は正確に伝えることが大切です。
告知内容を正しく準備する方法
告知義務を守るためには、事前準備が大切です。記憶のみに頼ると漏れが生じやすく、うっかり「告知しない」状態になる恐れがあるため、次の情報を整理しておくとよいでしょう。
- 初診日と診断名:喘息と診断された日付と診断名を正確に記録する
- 入院歴や手術歴:入院時期・医療機関名・入院期間を時系列で整理する
- 薬剤名と用量:お薬手帳を確認し、使用中の薬剤とその用量を控えておく
- 現在の症状や治療状況:発作の頻度、症状の安定度、日常生活への影響を具体的にまとめる
保険会社は給付金請求時に医療機関へ照会を行い、診療記録や処方履歴を確認します。したがって「申告しなくても問題ない」と考えた内容でも、後に判明すれば違反と見なされることがあります。

喘息生命保険の審査基準

喘息を持っている人が生命保険に申し込むと、保険会社は「リスクをどの程度と判断するか」を審査します。審査で見られるポイントは主に以下のとおりです。
| 判断要因 | 内容 | 保険会社が重視する点 |
|---|---|---|
| 発症時期・年齢 | 何歳で発症したか、発症からの経過年数 | 若年発症は慢性化の可能性を疑われやすい |
| 症状の重症度・頻度 | 発作の頻度、夜間発作、救急搬送歴 | 発作が重い・頻繁な場合はリスクが高いと評価される |
| 入院歴 | 入院経験の有無、直近の時期 | 2〜5年以内に入院歴があると加入が難しい傾向がある |
| 最終発作からの経過期間 | 最後の発作からの経過時間 | 発作が長期間起きていない場合は有利に働く可能性がある |
| 治療内容・薬剤使用状況 | 吸入薬、経口ステロイドの使用状況 | 経口ステロイドを常用していると重症と見なされやすい |
| 定期通院・検査データ | 呼吸機能検査や通院記録 | 安定したデータがあれば評価が改善する |
| 合併疾患・生活習慣 | アレルギー性鼻炎、心肺疾患、喫煙歴 | 他のリスク要因があると審査は厳しくなる |
| 年齢・性別・保険種類 | 加入希望年齢や商品タイプ | 年齢が高いほどリスク評価は厳格化する |
| 告知内容・医療記録 | 申告内容や過去の診療記録 | 虚偽や申告漏れは保険金不払いの原因となる |
喘息だからといって必ずしも加入を断られるわけではありません。むしろ「症状がどの程度安定しているか」「治療を継続しているか」が大きな判断要素です。

喘息生命保険に加入できない場合の代替策

喘息の治療費や入院費は長期的にかかることが多いため、公的な補助制度を上手く利用することが大切です。ここでは高額療養費制度、自治体の助成制度、医療費控除など、公的制度の概要と活用方法を解説します。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
たとえば、70歳未満で年収370〜770万円の方の場合、自己負担の上限は「8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%」となります。限度額を超えた金額は後日払い戻されるため、高額な治療費が発生しても安心です。
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、国が定める特定の疾病を有する児童を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。重症の小児喘息が認定されれば、公費により治療費の大部分を賄うことが可能となります。
ただし、制度の対象範囲や利用条件は自治体によって異なるため、居住地の市区町村役場や保健所で確認する必要があります。小児喘息や慢性気管支炎のように長期的な治療が欠かせない疾患では、本制度を活用することで家計への負担を大幅に軽減できます。
参考:小児慢性特定疾病情報センター「医療費助成」
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が「10万円」または「所得の5%」を超えた場合に、その超過分を所得から差し引ける制度です。喘息では薬代、通院交通費、差額ベッド代などがかさみやすく、控除の対象となるケースも少なくありません。
制度を利用するには、領収書や明細を必ず保管し、確定申告の際に提出する必要があります。また、医療保険から給付金を受け取った場合には、その分を差し引いた自己負担額のみが控除対象となります。

喘息生命保険を選ぶ際のポイント

数多くの保険会社がさまざまな商品を提供しているため、どの商品が自分に適しているのか判断するのは簡単ではありません。ここでは保険を選ぶ際の基本的なポイントや比較方法を紹介します。
保険会社の比較とシミュレーションをする
保険を選ぶ際には、一社のみで決定するのではなく、複数社を比較検討することが重要です。ネットのシミュレーションや保険ショップの無料相談を利用して、見積もりを集めてみましょう。
比較の際に注目すべき主な項目は以下のとおりです。
- 月額保険料:長期的に支払いを継続できる金額か
- 保障内容:入院給付金の日額、手術給付金の条件、通院保障の有無
- 不担保期間・削減期間:喘息に関する保障が除外されていないか、その期間の長さ
- 保険会社の信頼性:保険金支払い実績や顧客対応の評価
たとえば、30代の喘息既往歴がある方が緩和型保険で試算した場合、同額の保障であってもA社とB社とでは月額保険料に2,000円以上の差が出ることがあります。条件を入力して比べるだけで、自分に合った有利な契約先が見えてくるでしょう。
専門家に相談する
ファイナンシャルプランナー(FP)や保険ショップの専門家に相談するのも1つの方法です。
専門家に相談するメリットは次のとおりです。
- 商品を横断的に比較できる:多数の保険を扱っているため、中立的な意見が得られる
- 家計への影響を考慮できる:毎月の負担と将来の生活設計を総合的に検討できる
- 公的制度との併用を提案してもらえる:高額療養費制度や医療費控除などを踏まえたアドバイスが受けられる
また、オンライン相談サービスならスマホやパソコンから気軽に利用でき、カメラをオフにして音声だけで相談することも可能です。
既に保険に加入している人が喘息になった場合

保険契約後に喘息を発症した場合でも、契約時に告知義務を果たしていれば、入院や通院の際に給付金を受け取ることができます。
給付金請求には、医師の診断書、治療内容をまとめた書類、領収書などが必要となるため、申請前に保険会社へ必要書類を確認し、あらかじめ揃えておくと手続きが円滑に進むでしょう。
ただし、給付金の支払い条件は保険商品によって異なります。特定部位不担保や削減期間が設定されている場合、その期間中は給付金が支払われないのが一般的です。契約書を熟読し、保障内容を理解したうえで請求することが大切です。
また、入院給付金に加え、通院給付金を受け取れる保険もあるため、通院治療であっても申請を忘れないようにしましょう。

喘息生命保険に関するよくある質問

最後に、喘息生命保険に関するよくある質問と回答をまとめます。
喘息が軽度でも保険料は割増されますか?
軽度の喘息で入院歴がなく、経口ステロイドの処方歴がない場合は、保険料が標準に近い形で設定されることが多いです。
しかし、肺や気管支の病気に対する不担保期間(2~5年)が付く可能性があるため、その期間の保障が限定される点に注意しましょう。複数の保険会社を比較し、最も条件が良い会社を選ぶことをおすすめします。
告知義務ではどこまで伝えるべきですか?
告知義務では、喘息に関する初診日や診断名、入院歴や手術歴、現在使用している薬剤名を正確に伝える必要があります。些細な内容でも隠さず申告し、保険会社から追加書類の提出を求められた場合は迅速に対応しましょう。過去に治療したアレルギー疾患や既往症があれば、それも忘れずに伝えてください。
喘息と慢性気管支炎は別の病気ですか?
喘息と慢性気管支炎はどちらも呼吸器の炎症が関係しますが、原因や症状が異なります。喘息は気道の過敏性が高まって発作的に呼吸困難になる病気で、アレルギー反応が主な原因です。一方、慢性気管支炎は咳や痰が長期間続く病気で、喫煙や大気汚染が原因となることが多いです。
保険審査では別の疾患として扱われますが、併発している場合はリスクが高まるため審査が厳しくなる傾向があります。
保険加入後に喘息が悪化した場合、追加の保険に入れますか?
既に保険に加入している場合でも、症状が悪化した後に新たな保険に加入することは可能ですが、通常よりも審査が厳しくなります。特に経口ステロイドの使用や入院歴があると加入できないことが多いため、緩和型医療保険や無選択型保険を検討する必要があります。
また、既存の保険で喘息の悪化による入院が保障されているか契約内容を確認し、保障が不十分な場合は保障の上乗せや保険の見直しを検討しましょう。
喘息患者が県民共済と民間保険を両方利用するメリットは?
県民共済は掛金が低く手軽に加入できる点が魅力ですが、喘息など慢性疾患があると加入できない場合や保障が限定される場合があります。民間の医療保険や緩和型保険と組み合わせることで、県民共済でカバーできない部分を補い、総合的な保障を確保できます。
喘息生命保険のまとめ
この記事では、通常の医療保険、引受基準緩和型医療保険、無選択型保険の違いと加入条件を解説し、告知義務や審査基準、公的制度などの周辺知識も詳しく紹介しました。
軽症で入院歴がない場合は通常の医療保険に加入できることが多いものの、重度の喘息や経口ステロイドを使用している人は緩和型や無選択型の保険が検討対象となります。
喘息生命保険について正しい知識を持ち、喘息と付き合いながらも安心して生活できる未来を手に入れましょう。