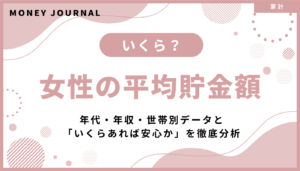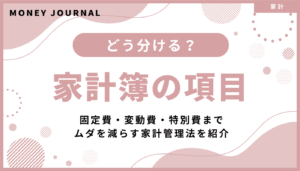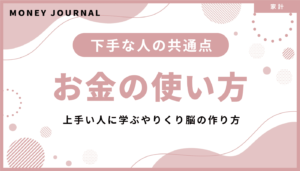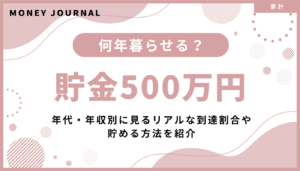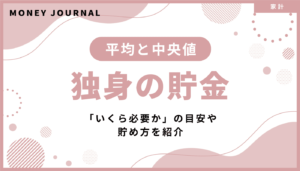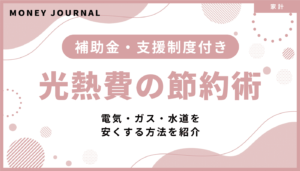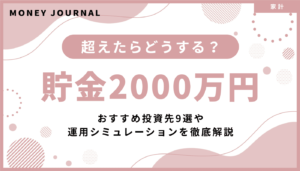養う家族がいる場合、税金や社会保険料の負担を減らせる扶養制度。共働きの場合には、子供をどちらの扶養に入れるほうがお得なのか迷うかもしれません。
今回は、扶養について基礎から徹底解説します。夫婦どちらの扶養に子供を入れたほうが良いのか判断する基準やシミュレーションのほか、制度を使うときの注意点も紹介していきます。
この記事を読めば、あなたのご家庭では夫と妻どちらの扶養に入れるべきなのか分かるようになるでしょう。
扶養控除とは?

年末調整の時期になるとよく耳にする扶養控除。「なんとなくは知っているけれど、説明はできない」という人も多いでしょう。実は、一般的に使われる扶養控除と本来の扶養控除の意味が異なっていることを知っていますか。
この章では、扶養控除について解説していきます。
扶養控除とは、子供など扶養している家族がいる場合に受けられる所得控除のひとつです。扶養している家族がいる場合は、生活費が多くかかるため、税金が免除される仕組みになっています。
一般的に言われる「扶養内で働く」というのは、所得控除である「配偶者控除」や「扶養控除」で控除される金額以内に収入を抑えることを指します。そのため、「扶養控除」と「配偶者控除」をまとめて「扶養控除」と考えている方が多いです。
しかし、扶養控除と配偶者控除はそれぞれ別の所得控除です。この記事では、扶養控除と配偶者控除を合わせて「扶養制度」と呼ぶこととします。
扶養は2種類ある

扶養控除は所得控除のひとつで、一般的に使われる言葉の意味と異なっていることを説明しました。扶養について正しく理解するために詳しく見ていきましょう。 実は、扶養は以下の2種類に分けられます。
- 税法上の扶養
- 健康保険上の扶養
適用条件が異なるので、ひとつずつ解説します。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、所得税や住民税に関する扶養のこと。税法上の被扶養者は、扶養親族と呼ばれます。扶養する人は、所得控除を受けられ、所得税や住民税の負担が減ります。 税法上の扶養に該当する所得控除の代表例は、以下の3つです。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
基礎控除は、一定額以下の収入がある人全員が対象になる所得控除です。控除の額は、住民税と所得税で異なるので間違えないようにしましょう。
納税者の所得と基礎控除額を表にまとめます。
| 納税者の合計所得 | 住民税の基礎控除 | 所得税の基礎控除 |
|---|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
扶養控除とは、扶養親族がいる場合に扶養者が受けられる所得控除です。扶養控除は、基本的に以下の扶養親族の条件を満たすときに適用され、生計を共にしていれば同居の必要はありません。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。引用元:扶養控除の対象
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
人によっては分かりにくいと感じるかもしれません。簡単に言い換えると以下のようになります。ひとつずつ当てはまるかどうか確認してみましょう。
- 配偶者以外の近い親族。または、里親として引き取った子供、または市町村長から養護するように依頼された高齢者。
- 生活費を負担している。
- 年間の所得が年間48万円以下であること。給与(会社に勤めの収入)のみの場合は年間103万円以下。
- 事業所得を得ていないこと。(自営業や個人事業主としての収入がないこと。)
なお、扶養控除額は被扶養者の年齢によって異なります。被扶養者の年齢と扶養控除額の対応は以下の通りです。