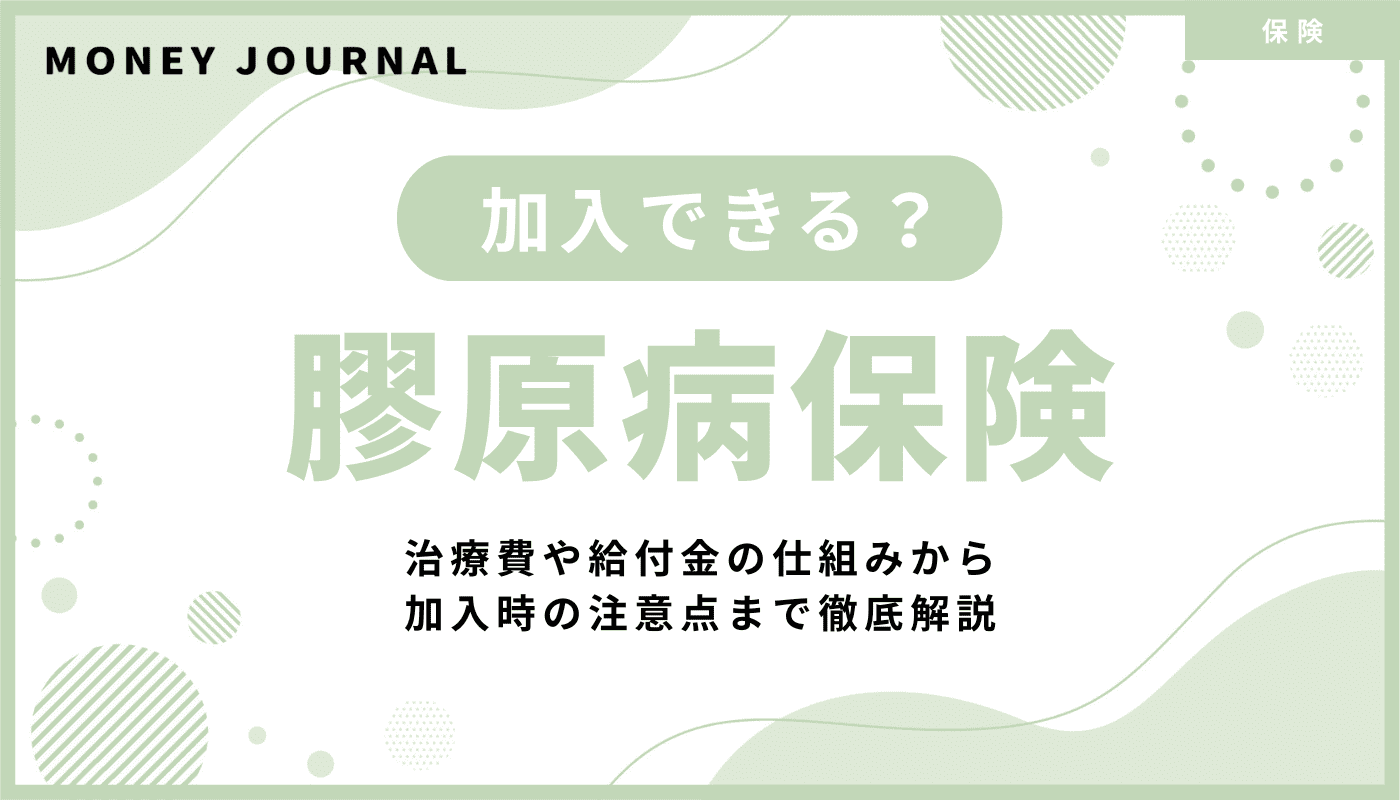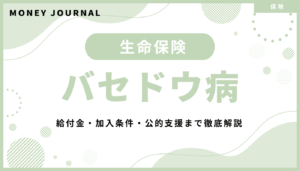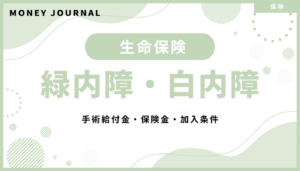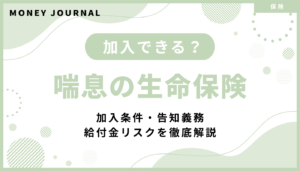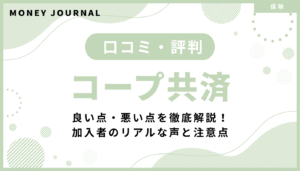- 「膠原病になったら保険に入れないんじゃないか…」
- 「もし治療費が高額になったら、どうすればいい?」
- 「膠原病でも入れる保険や、給付金ってあるの?」
このように考えている方もいるでしょう。
本記事では、膠原病に関連する医療費支援制度をはじめ、比較的加入しやすい保険の種類や、申し込み手順までを徹底解説します。
膠原病で保険に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
- 膠原病保険が存在しない理由
- 治療費をカバーできる医療費支援制度の詳細
- 膠原病でも給付金がもらえるケース
- 加入しやすい生命保険の種類(緩和型・無選択型)
- 保険会社を選ぶ際に見るべき審査基準や条件
- 申し込みから契約成立までの流れ
- 膠原病の主な種類と特徴
膠原病保険とは?

「膠原病保険」という名称の専用商品が存在するわけではなく、膠原病を抱える方でも加入可能な民間保険を指す通称です。
公的医療保険や高額療養費制度によって自己負担額は一定に抑えられるものの、入院や長期の通院が続けば、経済的な負担は決して軽くはありません。そのため、民間保険での備えを検討する方が少なくないのです。
しかし、膠原病の既往がある場合、一般的な医療保険や生命保険の審査に通過することは容易ではありません。健康状態の告知項目を減らした「引受基準緩和型保険」や、告知が不要な「無選択型保険」が、現実的な選択肢となります。

膠原病保険が存在しない理由

膠原病に特化した専用保険がほとんど見られないのは、将来の医療費を正確に予測しにくい病気だからです。
症状の出方や進行スピードが人によって大きく異なり、合併症も起こりやすいため、専用商品を設計すると収支が不安定になりやすいのです。

膠原病の治療費・検査費用に使える医療費支援制度

この章では、膠原病の患者さんが利用できる代表的な制度を整理して紹介します。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。対象となるのは保険診療による自己負担分であり、自由診療や差額ベッド代などは含まれません。
自己負担の上限額は、被保険者の所得(年収)や年齢によって異なり、同月内に複数の医療機関や薬局を利用した費用も合算して判定されます。
指定難病医療費助成制度と特定医療費受給者証
膠原病の中には、指定難病として公的医療費助成の対象となる疾患があります。
制度を利用するには、都道府県または指定都市に申請し、審査を経たうえで「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受ける必要があります。
ただし、申請から実際の交付までには数か月かかるのが一般的なので、早めの手続きが大切です。
その他の支援制度や税控除
膠原病の患者およびその家族は、前述の制度以外にも医療費控除や障害者控除といった税制上の支援を受けられる可能性があります。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の負担を軽減できる制度です。また、症状に応じて障害者手帳の交付を受けた場合には、所得税や住民税の控除や医療費の一部免除を受けられるほか、一部自治体では障害者医療費助成制度を利用できることもあります。
加えて、難病支援団体や自治体が独自に実施している補助金制度なども存在します。こうした制度の詳細は地域や団体によって異なるため、気になる方は各種相談窓口で早めに情報を集めておくことをおすすめします。
膠原病で保険金はおりる?医療保険の給付内容

医療保険では、膠原病による入院や手術が給付金の支払い対象となることが一般的です。ここでは入院給付金や手術給付金の仕組み、がん保険や特約の活用方法について解説します。
入院給付金
入院給付金は、病気やケガで入院したときに日額×入院日数で支払われるお金です。入院中は差額ベッド代や食事代、交通費などの負担が増えるため、給付金は生活費や雑費の補填に役立ちます。ただし支払いには条件があります。
代表的な制約は以下のとおりです。
- 治療目的の入院が対象
- 支払限度日数がある
- 再入院の通算規定
- 責任開始日前の発病は対象外
膠原病を既往症として告知している場合は「不担保」とされ、入院給付金が支払われないことがあります。ただし契約後に新たに膠原病を発症した場合は給付対象になることもあります。
手術給付金
手術給付金は、病気やケガで所定の手術を受けたときに支払われるお金です。入院を伴う手術はもちろん、日帰りの外来手術でも対象となる商品があります。
給付形式は「入院給付金日額×倍率(10倍・20倍など)」か「一律定額」が一般的です。
膠原病でも加入しやすい生命保険

「膠原病がある(あるいは既往歴がある)状態でも比較的加入しやすい保険」のタイプには主に以下の2つがあります。
引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険は、通常の生命保険に比べて告知の内容を減らし、基準を緩めている商品です。
告知では「過去数年以内の入院・手術歴」や「現在の通院・投薬状況」など、限定的な質問に答える形が一般的です。保障の対象は医療保険・終身保険・定期保険など幅広く、死亡保障にも対応している商品があります。
ただし保険会社は高リスクを織り込んでいるため、保険料は通常の保険より高めに設定されています。契約から一定期間は給付金が減額される「支払削減期間」があるのも特徴です。
代表的な商品には以下のようなものがあります。
- かんぽ生命「引受基準緩和型普通終身保険」
- SBIいきいき少短「持病がある人の医療保険」
- 全国労働者共済(全労済)や県民共済の緩和型共済
無選択型保険
無選択型保険は、健康状態に関する告知や医師の診査が不要な保険です。持病や既往症の有無に関わらず申込できるため、膠原病を持つ方でも加入しやすいのが特徴です。
代表例として、SOMPOひまわり生命の「新・誰でも終身」があり、医師の診査なしで死亡保障を持てる設計です。
無選択型保険は「どうしても保険に入りたいけれど他では断られた」という場合の最終的な選択肢となります。

膠原病の方における保険会社の選び方ポイント

保険会社によって審査基準や不担保の扱い、保険料の設定、付けられる特約などに差があります。ここからは保険会社を選ぶ際に確認しておきたい視点を紹介します。
審査基準の柔軟さ
告知項目が少なく、医師の診査を求めない設計の会社は加入しやすい傾向があります。たとえば緩和型保険では、入院歴や投薬状況など3項目程度の質問に答えるだけで済む商品もあります。
膠原病のように経過が人によって異なる病気では、柔軟な審査基準を採っている会社を選ぶことが大切です。
特定部位・疾病不担保の条件
契約時に「この部位や病気は保障対象外」とされる不担保条件が付くことがあります。たとえば「関節に関する病気は全期間対象外」とされると、実際に使える場面が大きく制限されてしまいます。
保険料水準と割増率
割増が契約期間を通じて固定なのか、ある時点で見直されるのかもチェックが必要です。緩和型や無選択型保険では、通常の保険より保険料が高めに設定されているからです。
また、詳細な告知をすれば割増なしで加入できる商品を提供している会社もあります。将来長く払い続ける費用だからこそ、保険料の水準と割増率をしっかり比較することが大切です。
保障内容の広さと特約の可否
入院や手術だけでなく、通院保障や先進医療の給付があるかどうかも確認したいところです。
保険会社によっては「がん特約」「三大疾病特約」「難病特約」などを追加できる場合もありますが、緩和型や無選択型では特約の幅が限られることもあります。
給付制限(免責・支払削減期間)
多くの緩和型保険では契約から1年間は「支払削減期間」とされ、その間は給付金が半額になるといった制限が設けられています。免責期間中は給付なしになる商品もあるため注意が必要です。
制限がどのくらい続くのか、削減率はどの程度かを事前に確認し、万一のときに想定外の負担が発生しないように備えましょう。
膠原病とはどのような病気?主な種類と特徴

ここでは代表的な膠原病について概要を紹介します。
関節リウマチ
関節リウマチは免疫の異常により関節に炎症が生じ、痛みや腫れが出る病気です。進行すると関節が変形し、機能障害を引き起こすことがあります。
日本では人口の0.4~0.5%、30歳以上の人口の平均1%にあたる人がこの病気にかかるといわれています。悪性関節リウマチは難病指定の対象であり、重症度が一定以上の場合は医療費助成を受けられます。
参考:公益財団法人「日本リウマチ財団」
全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス(SLE)は免疫が自分の体を攻撃することで、肺や心臓、消化管、腎臓など全身に炎症を起こす疾患で、頬に蝶形の赤い発疹が現れることもあります。
症状が悪化すると入院が必要で、副腎皮質ステロイドなどの薬による治療の副作用も問題になります。完治は難しく再発と寛解を繰り返すため、長期的な治療費の負担が大きい病気です。
全身性強皮症
全身性強皮症は皮膚や内臓の結合組織が硬くなる病気で、皮膚が硬く厚くなったり手指が冷たくなるレイノー症状が起こります。
皮膚の変化だけでなく、肺や心臓、腎臓の線維化を引き起こすこともあり、長期的な臓器障害に注意が必要です。
多発性筋炎・皮膚筋炎
多発性筋炎は筋肉に炎症が起こり、筋力の低下や倦怠感、食欲不振などが生じます。皮膚に特徴的な発疹が出る場合は皮膚筋炎と呼ばれます。
進行すると歩行や階段昇降が困難になり、ステロイド療法が必要です。多くの症例でステロイドが有効とされていますが、長期治療に伴う副作用の管理が欠かせません。
結節性多発動脈炎
結節性多発動脈炎(結節性動脈周囲炎)は中型の動脈の壁に炎症や壊死を引き起こす病気で、高熱や高血圧、関節痛、腹痛などさまざまな症状が現れます。
顕微鏡的多発血管炎
顕微鏡的多発血管炎は小血管に炎症が起こる病気で、急速に進行する腎障害や肺病変が特徴です。
ベーチェット病
ベーチェット病は慢性再発性の全身性炎症性疾患で、口腔粘膜や外陰部に潰瘍ができ、皮膚や眼にも症状が出ます。
最近は女性患者が増えていますが、症状が重いのは男性に多いとされています。免疫抑制薬や生物学的製剤で症状を抑えながら経過を見守る治療が行われます。
シェーグレン症候群
シェーグレン症候群は涙腺や唾液腺などの外分泌腺が破壊されることで目や口が乾き、関節や筋肉に痛みやだるさが出る病気です。
点眼や唾液分泌を促す薬、漢方薬で症状の改善を図ります。外観では分かりにくい病気のため、周囲の理解が得にくいという悩みもあります。
膠原病保険に関するよくある質問

膠原病保険に関するよくある質問は以下のとおりです。
難病になったら医療保険の保険金はもらえますか?
いいえ。保険金が支払われるかどうかは、あくまで保険契約で定められた給付条件に合致するかどうかによります。難病での入院・手術であっても、既往症不担保や責任開始日前の発病、給付制限期間などが適用されれば給付対象外になることがあります。
入院費用が払えない場合はどうすれば良いですか?
まずは公的制度を最大限利用することが重要です。高額療養費制度や指定難病医療費助成(医療受給者証を使った負担軽減)などが使えないか確認しましょう。
膠原病治療中でも生命保険の給付金はもらえますか?
治療中であっても、生命保険の死亡保険金や高度障害保険金は、契約で定められた保障対象(死亡・高度障害)が発生すれば支払われる可能性があります。
膠原病保険のまとめ
この記事では、膠原病に関連する医療費支援制度や加入しやすい保険の種類、さらに契約時に注意すべき条件について解説しました。
膠原病専用の商品は存在しませんが、公的制度と民間保険をうまく組み合わせれば経済的な負担を減らすことができます。
膠原病の治療を続けながら安心した生活を送りたい方は、公的制度を調べつつ、条件に合う保険を比較検討してください。