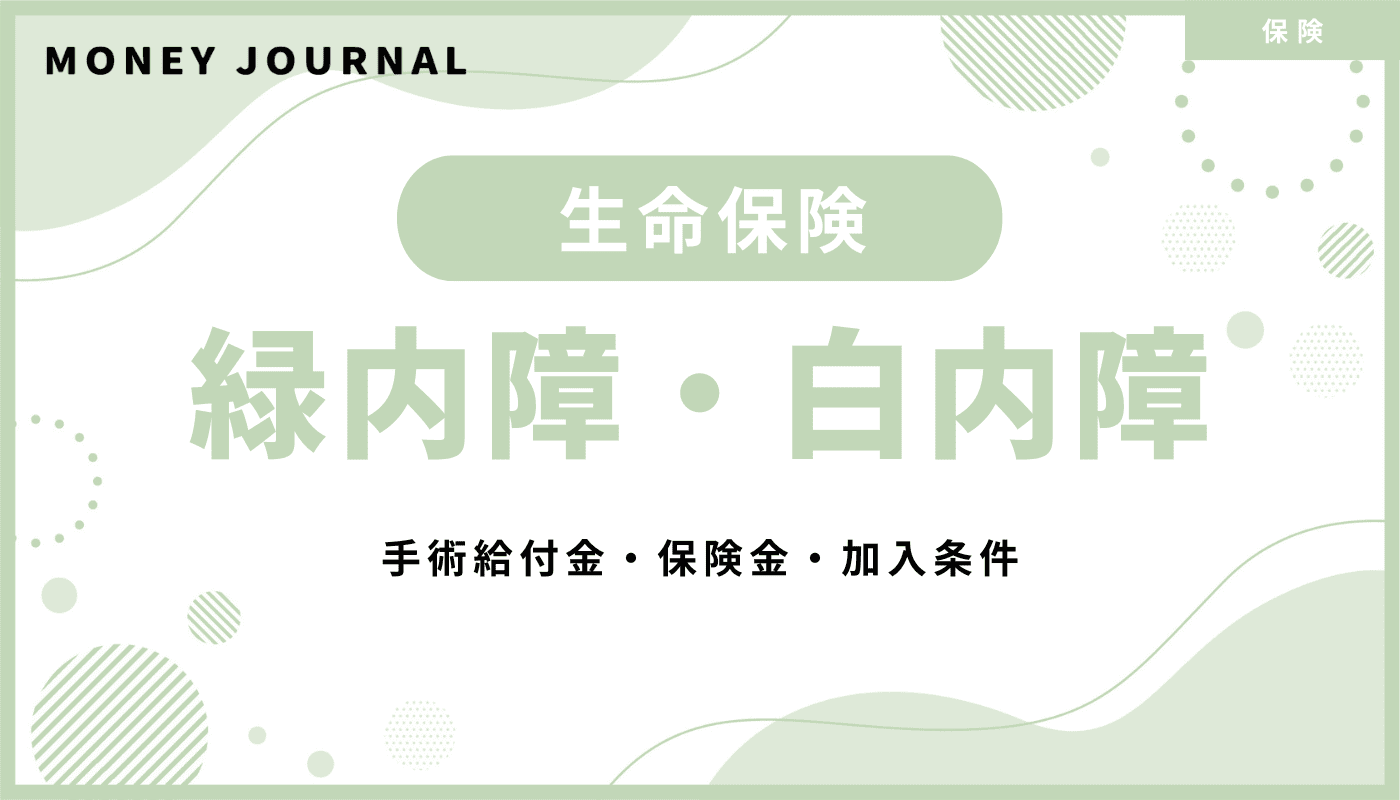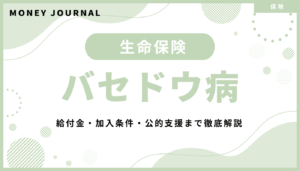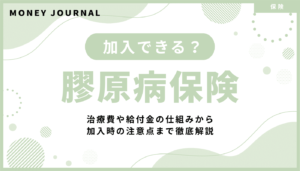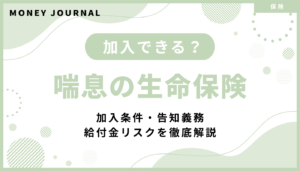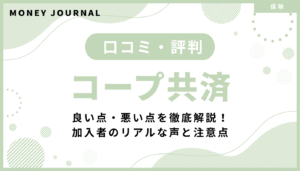- 「緑内障や白内障でも生命保険に入れるの?」
- 「治療中だけど、手術給付金は受け取れるの?」
- 「過去に手術をしたけど、加入を断られないか不安…」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、緑内障・白内障の方でも加入できる保険はあります。症状の進行度や手術歴によって加入条件は異なりますが、以下のような選択肢があります。
| 病状の状態 | 加入できる可能性のある保険 |
|---|---|
| 軽度・経過観察中 | 通常の医療保険 |
| 手術歴あり・症状安定 | 引受基準緩和型医療保険 |
| 他の病気もあり断られた場合 | 無選択型保険 |
本記事では、緑内障・白内障の基礎知識と治療費の実態や手術給付金・保険金の支払い条件、病気があっても加入できる保険の種類と選び方などを解説します。
「どの保険なら加入できるのか」「手術給付金はいつ受け取れるのか」など、保険加入前の不安を解消したい方はぜひ参考にしてください。
- 緑内障・白内障の症状と治療内容の基本
- 公的保険や医療費控除などのサポート制度
- 加入しやすい医療保険・生命保険の種類
- 手術給付金・高度障害保険金の受け取り条件
- 保険加入が難しい場合の具体的な対応策
緑内障・白内障とは?症状と治療の基礎知識

緑内障と白内障は、年齢を重ねるにつれて発症しやすい目の代表的な病気です。
まず、緑内障は「眼圧(がんあつ)」が上がり、視神経が圧迫されることで徐々に視野が欠けていく病気です。目の中を流れる「房水(ぼうすい)」という液体の通り道が詰まり、圧力が高くなるのが主な原因です。自覚症状が出にくく、気づかないうちに進行するのが特徴で、日本では40歳以上の約20人に1人が発症しています。
一方、白内障は目の中の「水晶体(レンズ)」が濁ることで視界がかすむ病気です。加齢や紫外線、糖尿病などが原因とされ、進行するとまぶしさや二重に見えるなどの不調が現れます。手術で濁った水晶体を取り除き、人工レンズを入れることで視力を回復できるのが特徴です。現在は日帰り手術が一般的で、身体への負担も少なくなっています。

緑内障・白内障の治療費・手術費用は保険適用?自己負担と補助制度

緑内障や白内障の治療(目の治療)は、基本的に公的医療保険の対象です。ただし、治療内容や使用する医療機器によって自己負担額が変わります。
ここでは、緑内障と白内障それぞれの保険適用範囲と自己負担額の目安を整理します。
緑内障:検査・治療は公的保険が適用される
緑内障の治療は、検査から手術まで公的医療保険の対象です。初期段階では、まず眼圧の上昇を防ぐための検査と点眼治療から始まります。
検査には以下のようなものがあります。
- 眼圧測定
- 視野検査
- 眼底検査
自己負担3割の場合、1回あたり1,500〜4,000円前後が目安です(初診料や検査内容によって変動)。
薬で十分な効果が得られない場合は、レーザー治療や外科手術が行われます。代表的な治療内容と費用の目安は以下のとおりです。
| 治療内容 | 自己負担3割時の費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| レーザー治療(SLTなど) | 約3万円 | 通院・日帰り可能 |
| 流出路再建術(眼内法) | 約4~5万円 | 数日間の入院あり |
| iStent併用手術(白内障と同時手術可) | 約9万円 | 保険適用・先進医療対象外 |
緑内障は進行がゆるやかで自覚しにくいため、治療を中断せず、定期検診を続けることが費用を抑える最大のポイントです。
白内障:単焦点レンズは保険診療、多焦点レンズは自由診療
白内障の治療では、濁った水晶体を取り除き人工の眼内レンズを入れる水晶体再建術が行われます。費用は選ぶレンズの種類によって保険が使えるかどうかが決まります。
主なレンズの特徴を整理すると次のとおりです。
| レンズの種類 | 保険適用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単焦点眼内レンズ | 適用あり(公的保険) | ピントが合う距離が1つ。遠距離または近距離のどちらかを選択。メガネ併用が必要。 |
| 多焦点眼内レンズ | 適用なし(自由診療) | 複数の距離に焦点を合わせられるが、公的保険の対象外。 |
| 選定療養(多焦点+一部保険) | 一部適用 | 追加費用を負担することで多焦点レンズを選べる制度。 |
単焦点レンズを使用した場合、片眼あたり約5万円前後(自己負担3割)が目安です。多焦点レンズを選ぶと自由診療となり、片眼で20万~50万円程度の自己負担が発生します。
ただし「選定療養制度」を使えば、多焦点レンズでも一部に保険を適用できます。

緑内障・白内障でも加入できる生命保険・医療保険の種類

緑内障や白内障があっても、加入できる保険は複数存在します。ただし、治療中か完治後か、症状が進行しているかどうかによって審査の通りやすさは変わります。
一般的には、以下の3種類の医療保険が検討対象になります。
| 保険の種類 | 加入しやすさ | 保険料 | 審査の特徴 |
|---|---|---|---|
| 通常の医療保険 | やや厳しい | 標準的 | 健康状態に応じて条件付き加入が可能 |
| 引受基準緩和型医療保険 | 通りやすい | やや高い | 告知項目が少なく、持病があっても加入可能 |
| 無選択型保険 | 最も通りやすい | 高い | 告知・診査なしで加入できるが保障は限定的 |
ここからは、それぞれの特徴と加入時の注意点を詳しく見ていきましょう。
通常の医療保険
緑内障や白内障があっても、症状が軽く安定していれば通常の医療保険に加入できる可能性があります。
ただし保険会社は、将来的に入院や手術が必要になるリスクを考慮するため、「特定部位不担保(目の病気を保障対象外にする)」という条件が付く場合があります。
加入できる主な条件は次のとおりです。
- 手術や入院治療がすでに完了しており、再発のリスクが低いと判断される
- 経過観察中で、定期通院のみを行っている状態
このような場合、眼疾患を除いた他の病気(がん・脳疾患・心疾患など)については、健康な人と同じ保障を受けられます。一方で、緑内障や白内障が進行中だったり治療中であったりする場合には、加入を断られるか、保障範囲が限定されます。
引受基準緩和型医療保険
通常の医療保険で加入を断られた方には、引受基準緩和型医療保険が現実的な選択肢となります。このタイプは、健康状態の告知項目が少なく、持病や既往症があっても加入しやすいとされています。
- 過去3ヶ月以内に入院や手術を受けていないか
- 過去1年以内に医師から入院・手術をすすめられていないか
- 現在、がん・肝硬変・透析治療など重い病気がないか
緑内障や白内障の治療中でも、状態が安定していると判断されれば審査に通る場合があります。
無選択型保険
無選択型保険は、健康状態に関係なく加入できる医療保険です。告知や健康診断が不要なため、緑内障や白内障が進行していても加入可能です。
主な特徴をまとめると以下のとおりです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 告知・診査 | 一切不要 |
| 免責期間 | 加入から1〜2年は病気による給付金が支払われないことがある |
| 給付金の上限 | 入院日額3,000〜5,000円程度とやや低め |
| 保険料 | 通常より高額 |
無選択型保険は「他の保険に入れなかった人の最後の受け皿」といえる存在です。緑内障や白内障の症状が進み、緩和型でも加入できなかった場合の最終手段として検討します。
そのため、高額療養費制度や医療費控除と併用することで、負担を抑えるのが一般的です。
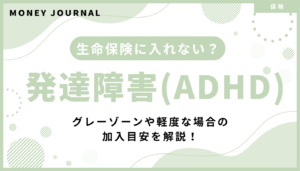
緑内障・白内障の方におすすめの保険プラン

緑内障や白内障の方が医療保険を検討する際は、今後の治療の見通しを踏まえて選ぶことが大切です。どの程度の治療が必要になるのか、日帰り・入院・手術のどこまでを想定するのかを明確にすると、自分に合った保障内容が見えてきます。
以下に、症状ごとにおすすめの保険プランを整理しました。
緑内障の方におすすめの保険プラン
緑内障は進行に伴い入院治療が必要になることも多く、入院保障の充実度が保険選びのポイントになります。
一例として、以下のような保障内容があると安心です。
| 保障内容 | 給付額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 入院給付金 | 日額5,000円 | 入院1日あたり支給 |
| 入院一時金 | 5万円 | 入院時に一括支給 |
| 手術給付金 | 5万円 | 手術実施時に支給 |
入院6泊7日の手術を受けた場合、合計約13.5万円の給付が受け取れます。
もし加入中の保険で緑内障が保障対象外になっている場合は、内容を見直し補償範囲を広げることをおすすめします。
白内障の方におすすめの保険プラン
白内障の治療は、日帰り手術(外来手術)が中心です。約7割の患者が通院当日に手術を受けており、入院を伴わないケースが多数を占めます。そのため、外来手術にも対応する手術給付金が充実した保険を選ぶと安心です。
代表的な保障内容を例に挙げると次のとおりです。
| 保障内容 | 給付額の目安 | 手術が日帰りの場合 |
|---|---|---|
| 入院給付金 | 日額5,000円 | 対象外(入院時のみ) |
| 入院一時金 | 5万円 | 入院時に一括支給 |
| 手術給付金 | 5万円 | 外来手術でも2.5万円支給 |
外来手術の場合でも2.5万円程度の手術給付金が受け取れます。入院を伴う場合は一時金が加算され、さらに手厚いサポートを受けられます。
多焦点レンズ手術は公的保険の対象外ですが、自己負担分は医療費控除の対象になるため、確定申告で一部還付を受けられます。日帰りでも手厚い給付金を受け取りたい方、視界の質にこだわりたい方には、外来・先進医療の両方をカバーできるプランが最適です。

緑内障・白内障の保険金請求の流れ

ここでは、実際に給付金を受け取るまでの流れを4つのステップで整理します。
①加入している保険会社へ連絡する
治療や手術が決まった段階で、まず加入している保険会社のカスタマーセンターや代理店へ連絡します。連絡時には、以下の内容を伝えると手続きが早く進みます。
- 証券番号(契約番号)
- 病名(緑内障または白内障)と治療内容(レーザー治療・日帰り手術など)
- 入院・手術の予定日
- 治療を受ける医療機関名
多くの保険会社では、「給付金請求書」や「診断書フォーマットを郵送またはWEB上で案内してくれます。
②医療機関で必要書類を発行してもらう
次に、治療を受けた病院で診断書や領収書を発行してもらいます。書類の種類や提出先は保険会社ごとに異なりますが、一般的には以下のとおりです。
| 書類名 | 発行元 | 内容 |
|---|---|---|
| 給付金請求書 | 保険会社 | 契約者情報や請求金額を記入する書類 |
| 診断書 | 医療機関 | 病名・手術名・入院日数・術式などを記載 |
| 領収書 | 医療機関 | 治療日・支払金額・診療科名を記載 |
| 身分証明書 | 本人 | 本人確認用(求められる場合あり) |
特に注意したいのは「手術名(術式)」の記載です。給付金の支払い可否は手術名で判断されるため、次のような正式な術式名が記載されているかを必ず確認してください。
③保険会社へ書類を提出する
必要書類がそろったら、保険会社に郵送またはオンラインで提出します。最近は、スマートフォンで診断書や領収書を撮影してアップロードするだけで申請できるサービスも増えています。
なお、追加資料の提出を求められることもあるため、原本はすぐに処分せず保管しておきましょう。
④請求期限・時効に注意する
保険金の請求には時効(消滅時効)があります。多くの保険会社では「給付事由が発生した日から3年以内」と定めており、手術や治療から3年以上経過すると、給付金を受け取れなくなる場合があります。
また、再手術や通院治療で追加の請求を行う際も、それぞれの治療日から時効がカウントされるので注意が必要です。
「今は忙しくて申請できない」という方も、まずは保険会社へ連絡だけでもしておくことが大切です。申請意思を伝えておけば、後日の手続きが円滑になります。
緑内障・白内障で保険に入れない場合に活用したい制度

緑内障や白内障の治療は長期にわたることも多く、進行度によっては手術や入院でまとまった費用が必要になります。もし持病などの理由で生命保険や医療保険に加入できなくても、公的な医療費支援制度を使えば自己負担を大きく減らすことが可能です。
ここでは、医療費を抑えるうえで頼りになる代表的な4つの制度を紹介します。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1ヶ月あたりの医療費が上限を超えた分を払い戻してもらえる制度です。日本の公的医療保険に加入していれば、誰でも利用できます。
年齢や所得によって上限額は異なります。
| 年収区分 | 自己負担上限(月) |
|---|---|
| 約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% |
| 年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% |
| 年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
| 年収156万円~約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
さらに、事前に「限度額適用認定証」を取得して病院窓口で提示すれば、退院時の支払い自体を上限額に抑えることができます。
選定療養制度
白内障治療で多焦点眼内レンズを使う場合は、原則として自由診療(全額自己負担)となります。ただし、選定療養制度を利用すれば、レンズの差額だけを自己負担すればよい場合があります。
たとえば単焦点レンズ(保険適用)と比べて多焦点レンズを選んだ場合、費用の内訳は次のようになります。
- 手術・入院費:保険診療(3割負担)
- 多焦点レンズ費用:自己負担(10万〜30万円前後)
このように、公的保険と自費を併用できるのが選定療養制度の特徴です。
医療費控除
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円を超えた場合に所得税が戻る制度です。緑内障・白内障の治療費や手術費に加え、通院時の公共交通機関の運賃も対象となります。
控除を受けるには、確定申告で次の書類を提出します。
- 医療費の領収書または医療費控除の明細書
- 給与所得の源泉徴収票
- 確定申告書(AまたはB様式)
医療費控除の対象は、給付金等を差し引いた実際の自己負担額のみです。
自治体の補助金制度
一部の自治体では、高齢者や障がい者を対象に医療費助成や補助金制度を設けています。
代表的な制度を以下にまとめました。
| 自治体 | 制度名 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 高齢者医療費助成制度 | 70歳以上 | 医療費の自己負担を1割に軽減 |
| 神奈川県 | 福祉医療費助成(重度障害者) | 視覚障害などがある方 | 自己負担分を全額助成 |
| 大阪府 | 高齢者医療費助成制度 | 75歳以上 | 所得に応じた助成上限あり |
緑内障や白内障によって視覚障害認定(身体障害者手帳)を受けた場合は、障害年金や医療費助成を併用できることもあります。

緑内障・白内障に関するよくある質問

ここでは、実際の加入相談でよく聞かれる質問をQ&A形式で解説します。
緑内障・白内障でもがん保険や死亡保険に入れる?
入れる可能性はあります。緑内障や白内障は、がんや循環器疾患のような生命に直接関わる病気ではないため、がん保険・死亡保険の加入に制限がかかるケースは比較的少ないです。
ただし、加入審査では「他に重大な持病があるか」「視力低下の進行度合い」「日常生活への支障度」が確認されます。
緑内障が治った後でも保険加入に制限はある?
白内障は手術で完治することが多く、緑内障は安定状態になれば加入可能な場合があるのが一般的です。
生命保険・医療保険の審査では、次の点が確認されます。
- 白内障手術からの経過期間(3か月〜1年)
- 緑内障の治療継続状況(点眼薬・経過観察のみか)
- 医師から「再発の可能性が低い」と診断されているか
白内障は手術後の視力が安定していれば、ほとんどの保険で加入可能です。
日帰りレーザー治療でも給付金はおりる?
はい。保険会社が手術と認める治療内容であれば、日帰りでも給付金は支払われます。
レーザー治療(SLT・YAGレーザーなど)は、緑内障や白内障の標準的な治療として位置づけられています。
生命保険の「高度障害保険金」は視力障害でも対象になる?
視力障害が一定基準を超える場合は、高度障害保険金の支給対象になります。生命保険の高度障害とは、身体の機能が永久的に失われ、今後回復が見込めない状態を指します。
治療後に再加入できる条件はある?
はい。完治または経過観察期間を経ていれば、再加入できる可能性があります。
まとめ
この記事では、緑内障・白内障でも加入できる生命保険や医療保険、そして手術給付金の受け取り条件について解説しました。
病気の進行度や手術歴によって加入できる保険は異なりますが、状況に応じて選べる保険があります。緑内障・白内障の方は、「自分の症状に合う保障」と「公的支援の併用」を意識することが大切です。