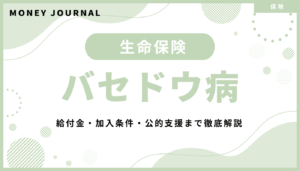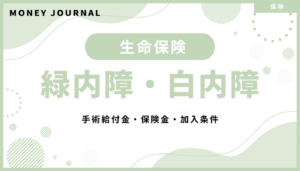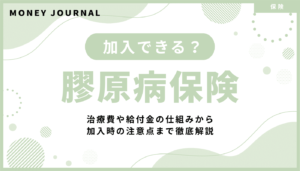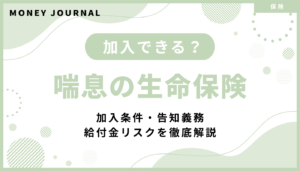- 「働けなくなったときの収入が不安」
- 「会社の福利厚生としてGLTDを入れるべきか悩んでいる」
- 「他の所得補償保険とどう違うのか分からない」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、GLTD(団体長期障害所得補償保険)は、長期の就業不能リスクに備えたい方に最適です。ただし、加入前にメリット・デメリットの両面を把握することが必須です。
| メリット | ・働けない間も給与の50~60%以上が補償される ・福利厚生として導入すると採用 ・定着率が上がる ・補償内容や免責期間を柔軟にカスタマイズできる |
|---|---|
| デメリット | ・従業員数が少ないと保険料が高くなる傾向 ・免責期間が長いため短期の体調不良は対象外 ・掛け捨て型で、税制面での恩恵が少ないケースも |
本記事では、GLTDの基本事項から加入すべきかどうかの判断基準、他の所得補償保険との違い、保険料相場や企業の導入事例まで網羅的に解説していきます。
あなたや社員のいざというときに備えるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
GLTDとは?団体長期障害所得補償保険の基本

公的制度では生活費のすべてをカバーできない、貯蓄を切り崩す生活に追い込まれるなどのリスクに備える手段として注目されているのがGLTD(団体長期障害所得補償保険)です。
企業単位で契約する団体保険の一種で、働けない状態が長引いた場合でも安定した収入補償が受けられる仕組みとなっています。
以下では、GLTDの仕組み・補償条件・対象範囲について詳しく解説していきます。
働けない期間の収入を補償する団体保険
GLTDは、長期間働けない状態が続いた場合に給与の一部を補償してくれる制度です。収入が止まることで生じる家計の崩壊を防ぐために、あらかじめ企業が保険料を支払い従業員を支える役割を果たします。
GLTDの基本情報は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称(正式名) | 団体長期障害所得補償保険(Group Long Term Disability Insurance) |
| 加入形態 | 企業・団体が契約者となり従業員に付保する |
| 補償対象期間 | 免責期間経過後~定年や就業可能になるまで(最長60歳・65歳まで設定可) |
| 補償金額の目安 | 月収の50%〜70%(上限あり) |
| 支給の条件 | 医師の診断による「就業不能状態」の認定 |
補償内容は企業ごとにカスタマイズできるため、社員の職種や就業環境に合わせて柔軟に設計できます。
医師の診断+免責期間後に補償開始
GLTDでは、補償を受けるには2つの条件を満たす必要があります。
- 医師による就業不能の診断
- 免責期間(待機期間)の経過
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1.医師の診断が必須
補償開始には「主観的に働けない」だけでは足りません。医師が「業務の継続が医学的に困難である」と診断しなければ補償対象になりません。
診断書が提出され、それに基づいて保険会社が就業不能かどうかを判断します。
2.免責期間の経過が必要
免責期間とは、働けなくなってから実際に補償が始まるまでの待機期間です。多くの場合、90日・120日・180日などから選択され、長いほど保険料が安くなります。
たとえば、「うつ病」で4月1日に診断され、免責期間が90日の契約なら、補償開始は7月1日からとなります。
補償対象はけが・病気・精神疾患など幅広い
GLTDが対象とする就業不能の原因は幅広いのが特徴です。一般的な所得補償保険では対象外になりやすい精神疾患なども含まれる場合があります。
補償対象の具体例は以下のとおりです。
| 補償対象の例 | 状態や条件 |
|---|---|
| 骨折・事故によるけが | 日常生活や業務に支障が出る場合に対象 |
| がん・脳卒中・心筋梗塞等 | 長期療養が必要で業務復帰が見込めない場合に補償対象 |
| うつ病・適応障害・躁うつ | 精神疾患特約がついていれば対象になる場合が多い |
| 妊娠関連疾患 | 条件付きで補償対象となることも(例:重度の切迫早産) |
補償対象となるかどうかは加入プランの設計次第で変わるため、以下の点を事前に確認しておくことが大切です。
- 精神疾患の補償が特約扱いか否か
- 妊娠・出産・産後うつなどが補償対象になるか
- 天災や障害(特定の身体部位喪失など)への備えがあるか

GLTDの必要性は?加入すべき人の特徴と判断基準

ここからは、GLTDが必要な人の特徴や、他の保険との違い、貯蓄状況に応じた判断ポイントを解説していきます。
長期の就業不能に備えたい人には必須の選択肢
GLTDは、半年以上働けない状態が続くリスクに備えたい方に最適です。働けない期間が短ければ有給休暇や傷病手当金でしのげますが、長期化すると生活資金が尽きてしまう可能性があるからです。
具体的にGLTDが必要な状況は以下が考えられます。
- がんや脳卒中で1年以上の治療が必要
- うつ病など精神疾患で復職が困難
- 難病や交通事故で長期療養が必要
補償金は毎月支給されるため、家賃・食費・通信費・教育費などの支出に充てられます。長期の収入ダウンに備えるなら、GLTDは「あると安心」ではなく「ないと困る」保険といえるでしょう。
就業不能保険・収入保障保険より補償期間が長い
GLTDが他の所得補償系保険と異なるのは補償の長さです。定年退職までカバーできる制度はGLTD以外にはほとんどありません。
以下に主な違いを比較表でまとめました。
| 保険種類 | 補償期間の目安 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| GLTD | 定年まで(60~65歳) | 団体型で長期補償、法人加入が前提 |
| 就業不能保険(個人) | 最長2年程度 | 契約しやすいが、補償が短期 |
| 収入保障保険 | 被保険者の死亡時のみ | 就業不能時は対象外、死亡時のみ支給 |
長期間の離脱リスクに備えたい場合、GLTDは他の保険より現実的だといえるでしょう。
貯蓄が少なく、公的給付だけでは不安な人に向く
GLTDは「いざというときに頼れる貯蓄が少ない方」にこそ必要な保険といえます。理由は公的制度だけでは生活を支えきれないからです。
公的な給付制度としては「傷病手当金」や「障害年金」がありますが、それぞれ以下のような制約があります。
| 制度名 | 補償内容 | 限界・注意点 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 給与の約67%を最長1年6ヶ月 | 退職後は打ち切り。フル補償ではない |
| 障害年金 | 障害等級に応じて支給 | 軽度な精神疾患や慢性病は対象外の場合も |
こうした公的制度だけでは生活水準の維持が難しく、補助的にGLTDを活用することで生活費・住宅ローン・教育費などを確保できます。

GLTDのメリット4選|福利厚生・信頼性・柔軟性など

GLTDの代表的な4つの利点について具体的に解説していきます。
給与の50〜60%以上が補償され生活を守れる
1つ目のメリットは、働けなくなったときにも生活費に充てられる収入が確保されることです。補償金は「標準報酬月額」に対して50〜60%を目安に設定されるのが一般的です。
たとえば、月給30万円の方が病気で長期休職した場合、補償内容が60%であれば以下のような支給イメージとなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月給(標準報酬) | 30万円 |
| 補償割合 | 60% |
| 月額補償金 | 18万円 |
さらに、GLTDの補償金は用途が限定されないため、医療費・教育費・食費など、家庭の事情に合わせて自由に使えるのも安心できるポイントです。
福利厚生としての導入で採用・定着率が上がる
GLTDは従業員の備えになるだけでなく、企業の魅力向上にも貢献する制度です。
福利厚生が充実している会社は、求職者から「安心して働ける」と受け取られやすくなります。実際にGLTDを導入している企業では、制度内容の精度が高く評価されており、以下のような声が採用現場で聞かれています。
- 「福利厚生が手厚くて安心できた」
- 「家族に何かあっても会社が支えてくれると感じた」
- 「長く働くイメージが持てた」
さらに、導入形態の柔軟さも企業にとっての魅力です。
| 設計例 | 内容 |
|---|---|
| 会社全額負担型 | 企業が全従業員の保険料を負担 |
| 基本補償は会社+任意追加 | 基本は会社負担で、希望者は補償上乗せも可能 |
| 管理職・専門職限定型 | ハイリスク職種を対象に選定導入 |
社員の定着に悩んでいる企業にとって、企業の信頼性を高める施策として活用できるでしょう。
保険制度が企業の信頼性につながる
GLTDの導入は、社内外に対して「従業員を大切にしている企業」という印象を与える効果があります。
たとえば、以下のような文脈でGLTDは評価されています。
| 評価対象 | GLTDが与える影響 |
|---|---|
| 求人票・採用サイトの印象 | 社員想いな企業という安心感を与える |
| 健康経営優良法人の認定要件 | 従業員支援制度の充実として評価される |
| ESG・CSR報告書での記載内容 | 社会的責任への対応として外部ステークホルダーに訴求可能 |
大手企業の中にはGLTDの導入を「福利厚生の柱」として紹介し、エンゲージメントスコア(会社への信頼度)の上昇につなげている事例もあります。
免責期間や補償条件を柔軟にカスタマイズ可能
GLTDのもうひとつの強みは、制度設計の柔軟性が高いことです。企業ごとの人員構成や財務状況に応じて、以下のような項目を自由に調整できます。
| カスタマイズ項目 | 選択肢例 |
|---|---|
| 免責期間(補償開始まで) | 60日・90日・180日など |
| 補償割合(給与に対する) | 40%・50%・60%・70%など |
| 加入形態 | 全員加入/任意加入/併用(2階建て) |
| 特約 | 精神疾患特約・妊娠特約・天災特約など |
短期の欠勤には傷病手当金で対応し、長期の離脱に絞ってGLTDを発動するように設計すれば、企業側の保険料を抑えつつ社員の安心感を確保できます。

GLTDのデメリット3選|保険料負担・免責期間・補償制限

導入前に知っておきたいGLTDの代表的なデメリット3つを具体的に解説していきます。
従業員数が少ないと保険料が割高になる
GLTDは「団体保険」であるため、加入人数が多いほど保険料が安くなる傾向があります。そのため、中小企業や社員数が20名以下の事業所では、1人あたりの保険料負担が割高になるというデメリットがあります。
また、加入者の年齢や職種構成によっても保険料は変動します。
ただし、以下のような工夫により負担を抑えることも可能です。
- 補償割合を60%→50%に調整
- 免責期間を90日→180日に延長
- 任意加入制にし、希望者のみでスタート
GLTDは一律の料金制度ではなく、企業規模や目的に合わせて調整できる制度です。見積もり段階で代理店や保険会社に複数パターンを依頼すると、費用と効果のバランスが見えてきます。
免責期間が長く短期離脱では補償されない
GLTDでは、「免責期間」と呼ばれる補償が始まるまでの待機期間が設定されており、90日~180日が一般的です。つまり、働けなくなっても3ヶ月以上経たないと保険金の支給は始まりません。
以下は免責期間の影響を示した一例です。
| 就業不能期間 | GLTD補償の有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 骨折で2ヶ月休職 | 補償なし | 免責期間未満 |
| インフルエンザで1ヶ月入院 | 補償なし | 短期間の就業不能は対象外 |
| がん治療で半年治療 | 補償あり(4ヶ月目から) | 免責期間を超えて就業不能が継続したため |
GLTDは最後のセーフティネットとして位置づけ、短期〜中期の離脱は別の制度でカバーする運用が現実的です。
掛け捨て型で節税効果が限定的な場合もある
GLTDは基本的に掛け捨て型の保険です。そのため、補償を受けなければ保険料は戻ってこないという点に不満を感じる方もいるかもしれません。
また、節税効果についても加入形態によって違いがあります。
| 加入形態 | 節税メリット |
|---|---|
| 法人契約(全従業員対象) | 福利厚生費として全額損金処理が可能 |
| 個人契約 | 介護医療保険料控除の対象(他の保険料と合算。所得税4万円・住民税2.8万円まで) |
GLTDは万一に備えるための保険という性格が強いため、掛け捨てであることや控除額の上限を踏まえても、必要な安心を得られる制度と考えると納得しやすいでしょう。
ただし、節税効果を主目的に保険を選びたい方にはやや不向きな面があることも理解しておくべきです。

GLTDと他の所得補償保険の違いは?

GLTDと混同されやすい2つの保険との違いを明確にしながら、GLTDがどのような立ち位置にある制度なのかを解説していきます。
個人型就業不能保険との違いは「補償期間と対象」
GLTDと個人型就業不能保険はどちらも「働けなくなったときの収入を補う保険」ですが、補償の範囲が大きく異なります。
以下に両者の違いをまとめました。
| 比較項目 | GLTD(団体型) | 就業不能保険(個人型) |
|---|---|---|
| 補償期間 | 定年(60〜65歳)まで設計可能 | 最長2年程度が一般的 |
| 補償開始までの免責期間 | 90〜180日 | 30〜60日 |
| 精神疾患への対応 | 特約付きで補償されることが多い | 補償対象外の商品が多い |
| 加入方法 | 企業を通じた団体契約 | 個人で保険会社と直接契約 |
収入保障保険との違いは「死亡補償か就業不能補償か」
名前が似ているため混同されやすいのが、GLTDと収入保障保険の違いです。どちらも月額で保険金が支払われますが、カバーするリスクと支払対象がまったく異なります。
違いを整理すると以下のようになります。
| 比較項目 | GLTD | 収入保障保険 |
|---|---|---|
| 対象リスク | 就業不能(病気・ケガ・精神疾患) | 死亡(病死・事故死) |
| 補償対象 | 被保険者本人 | 被保険者の遺族 |
| 補償開始条件 | 医師の診断+免責期間経過 | 死亡または高度障害 |
| 保険金の支給形態 | 月額で所得補償 | 月額で死亡保険金を支給 |
死亡と就業不能はどちらも深刻なリスクであり、両方をカバーするには両保険の併用が現実的です。

GLTDの保険料相場・月額シミュレーション

GLTDの保険料は、全額会社負担とする企業もあれば、基本部分のみを会社が負担し、補償の上乗せを希望者に任意加入で提供するケースもあります。
支給される補償金は、主に定額型または定率型のいずれかで設計します。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 設計方式 | 内容 |
|---|---|
| 定額型 | 全従業員が毎月同じ額(例:月10万円)を受け取る |
| 定率型 | 標準報酬月額に対する一定割合(例:60%)を受け取る |
具体的なシミュレーションとして、年収別に想定される月額保険料を以下にまとめました(補償割合60%、免責期間90日、会社負担の場合の概算)。
| 年収(想定月収) | 月額補償額(60%) | 月額保険料の目安 | 年間保険料の概算 |
|---|---|---|---|
| 300万円(25万円) | 約15万円 | 約1,500円 | 約18,000円 |
| 500万円(42万円) | 約25万円 | 約2,500円 | 約30,000円 |
| 700万円(58万円) | 約35万円 | 約3,500円 | 約42,000円 |
導入前には、必ず複数社に見積もりを依頼し、年収・従業員数・業種ごとの試算を比較することをおすすめします。

GLTDの導入事例|企業が選んだ理由と導入後の効果

実際にGLTDを導入した企業の具体的な事例をご紹介します。
全額会社負担で高満足度を実現|情報通信サービス企業
長野県に本社を構える東証プライム上場の情報通信サービス企業・株式会社電算では、「社員と家族を大切にする」という経営理念のもと、GLTDを全額会社負担で導入しました。
導入にあたっては、従業員への説明会やアンケートを実施し、制度の内容や必要性を丁寧に共有。その結果、任意加入でありながら加入率は65%を超え、福利厚生制度として高い浸透率を誇るまでになりました。
参考:株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント「GLTD(団体長期障害所得補償保険) 導入事例インタビュー 株式会社電算」
補償×コスト削減を両立|服飾資材商社・清原株式会社
大阪府の老舗専門商社・清原株式会社では、GLTDを福利厚生の一環として導入し、補償と運用コストの最適バランスを実現しています。同社は「健康経営優良法人2020」にも認定されており、従業員を大切にする文化が根づいた企業です。
制度設計は、全員加入の基本補償と、任意加入による上乗せ補償の2階建て構造。年間約400万円の保険料は会社が全額負担しており、従業員には自己負担なしでベースの補償が提供されています。
導入後は、採用時の福利厚生アピール材料としても効果を発揮しており、若手人材の定着にも好影響を与えています。
参考:厚生労働省「両立支援の取組事例」
70%補償で安心感アップ|電子機器メーカー
ある大手電子機器メーカーでは、従業員の長期休職リスクを重く見て、GLTD制度を最大70%の補償設計で導入しました。制度の目的は、休職時の収入減少を補うことに加え、従業員が安心して治療に専念できるよう経済的サポートを行うことです。
導入後には「経済的な不安がなくなり、復職に前向きになれた」という声が現場から上がり、企業全体としても福利厚生の質が向上。さらに、GLTDを福利厚生として明示することで、採用活動や企業ブランディングにもプラス効果が出ているとのことです。
参考:キャピタル損害保険「導入プラン例(1)のご紹介」

GLTDに関するよくある質問

最後に、GLTDに関するよくある質問と回答を紹介します。
GLTDは退職後も継続できる?
GLTDは基本的に企業や団体を通じた団体保険のため、退職すると自動的に契約は終了します。ただし、保険会社によっては、「個人転換制度」や「任意継続」プランが用意されていることもあり、一定の条件を満たせば個人で継続加入できる場合があります。
退職予定がある場合は、事前に保険会社または福利厚生担当者へ確認しておくとよいでしょう。
妊娠・うつ病・精神疾患は補償対象になる?
GLTDでは、妊娠・うつ病・適応障害などの精神疾患も補償対象となることがありますが、基本契約だけでは対象外の場合も多いです。その場合は「精神疾患特約」「妊娠関連特約」などの追加オプションを付けることでカバーできます。
法人の福利厚生費として経費計上できる?
はい、法人がGLTDに加入し、全従業員を対象とした制度として導入する場合、その保険料は福利厚生費として全額損金算入(経費処理)できます。
ただし、一部の従業員だけが対象となる場合や、加入が任意制で企業が一部費用を負担する場合などは、会計処理上の取り扱いが異なる場合があります。詳細は税理士や保険会社に相談するのが確実です。
GLTDと他保険の併用はできる?
はい、GLTDは長期就業不能所得補償保険のため、他の保険(医療保険、就業不能保険、収入保障保険、がん保険など)との併用が可能です。
精神障害・天災・身体障害特約の使いどころは?
特約は補償範囲を広げるための追加オプションです。以下のような場面で役立ちます。
- 精神障害保障特約:うつ病・統合失調症・適応障害などによる長期離脱に対応したいとき
- 天災危険補償特約:地震・津波・台風など自然災害に伴う就業不能に備えたいとき
- 身体障碍補償特約:事故や疾病による高度障害が残った場合の補償を充実させたいとき
GLTDの保険料は控除対象になる?
個人がGLTDに任意加入し自身で保険料を負担する場合は、生命保険料控除のうち「介護医療保険料控除」の対象になることがあります。
この場合、他の医療系保険と合算して以下の金額が控除可能です。
- 所得税:最大4万円/年
- 住民税:最大2.8万円/年
ただし、法人が全額負担する場合は従業員の課税対象にはならず、個人控除も適用されません。
どの保険会社がGLTDを扱っている?
GLTDを取り扱っている保険会社は複数ありますが、代表的な例として以下が挙げられます。
- 損保ジャパン(団体所得補償保険)
- 東京海上日動火災保険
- 三井住友海上火災保険
- アドバンテッジリスクマネジメント(制度運営支援・販売代理)
- AIG損害保険・メットライフ生命など(提携型GLTDあり)
- あいおいニッセイ同和損保
- 日本生命保険相互会社
各社で補償内容・料率・特約の有無が異なるため、複数社からの見積もり取得が大切です。
まとめ:GLTDは「備えたい期間」と「負担」に応じて取捨選択を
この記事では、GLTDの補償内容や他保険との違い、導入メリット・デメリットまで詳しく解説しました。
働けない期間が長引いたとき、家計を守れる制度があるかどうかで安心感はまったく違います。とくに備えておきたい方の特徴は以下のとおりです。
- 精神疾患やがんなどで復職の目途が立たない場合に備えたい
- 採用や定着率を高めたい企業の経営層
- 福利厚生費として損金処理できる保険を探している
補償割合・免責期間・加入形態などを柔軟に設計できる点はGLTDならではです。
まずは、補償したい期間と会社の負担額を整理し、見積もりを複数社から取って比較してみてください。