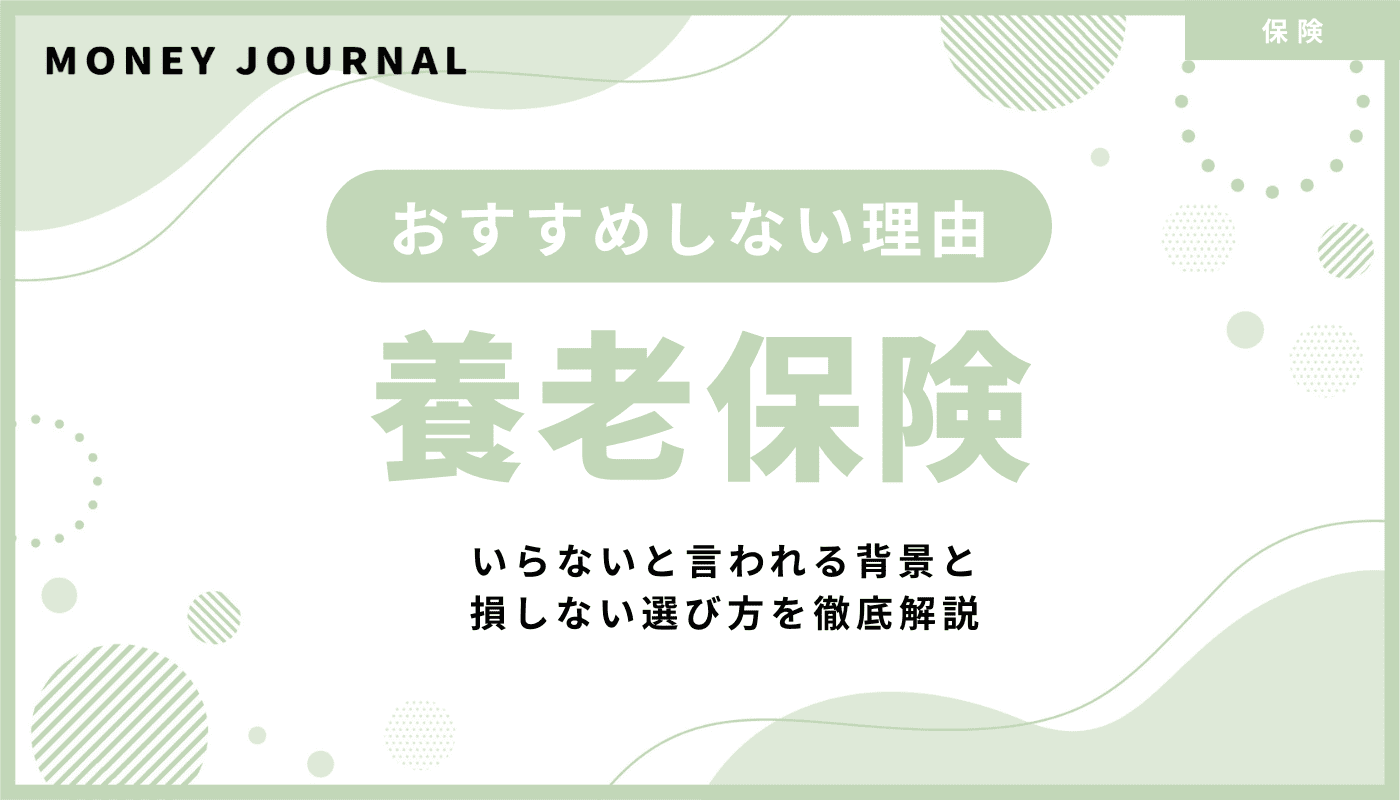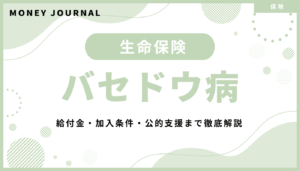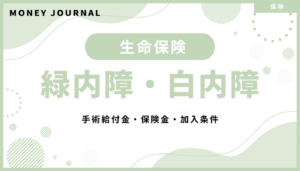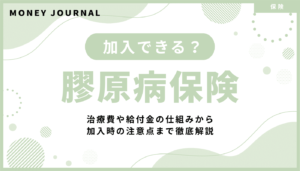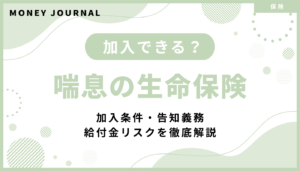- 「老後のために保険に入っておいた方がいいのでは?」
- 「とりあえず満期金が戻ってくるなら損はしないはず」
- 「営業担当に『元本保証』って言われて何となく契約した」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、養老保険がおすすめしないと言われる理由は主に次の3つです。
- 構造的に増えにくい
- 時代に合っていない
- 他の商品が優秀
本記事では、養老保険の仕組みから、なぜ今おすすめしないと言われているのか、それでも向いている人がいるとしたらどんなケースかまで、実例と数値を用いて解説していきます。
損を防ぎたい方、将来への備えを自分で選び取りたい方は、ぜひ参考にしてください。
養老保険の仕組み・基本的な特徴

養老保険は「満期まで生きていればお金が戻る」「万が一亡くなっても保険金が支払われる」という2つの顔を持つ保険です。保険と貯蓄がセットになっているように見えるため、「損しにくい商品」として紹介されることもあります。
ここでは、養老保険の基本構造をわかりやすく整理するために、3つのポイントに分けて解説していきます。
満期金と死亡保険金は基本的に同額
養老保険は、「満期金」と「死亡保険金」が原則同額です。一見シンプルですが、勘違いされやすいポイントでもあります。
たとえば、保険金額が300万円の契約の場合は以下のとおりです。
| 状況 | 受け取れる金額 | 名称 |
|---|---|---|
| 契約者が満期まで生存 | 300万円 | 満期保険金 |
| 保険期間中に死亡 | 300万円 | 死亡保険金 |
どちらも同じ金額(300万円)が支払われますが、受け取れるのはどちらか一方のみです。つまり、「貯金もできて死亡保障も手厚い」と思って契約すると、実際には貯蓄性も保障機能も弱く、「どちらも中途半端」になってしまいます。
保険期間が終了すると保障も消える
養老保険は保険期間が明確に設定されています。そして、保険期間を過ぎると保障は完全に消滅します。
たとえば以下のような契約を想定してください。
| 契約内容 | 保険期間 | 満期到達後 |
|---|---|---|
| 10年満期の養老保険 | 契約から10年間のみ死亡保障 | 満期金を受け取って契約終了・保障も終了 |
| 60歳満期の養老保険 | 加入年齢から60歳まで死亡保障 | 以降の死亡保障は一切なし |
つまり、満期を迎えたら保障が終わるため、そのまま延長したり自動更新したりはできません。よくある誤解は、「老後のために入っておけば安心」というものです。
「掛け捨てでないからお得」とは限らない構造
現在の養老保険は、以下のような背景により「貯蓄としては物足りない」と感じる方も少なくありません。
予定利率が低下している
昔は予定利率が3~5%台の商品も存在していましたが、現在は0.2〜0.5%程度が主流です。満期金が微増しても、利息はほぼ実感できません。
インフレに対応できない
物価が上がるとお金の価値が目減りします。10年後に同じ金額が戻ってきても、買えるものは減っている可能性があります。
途中解約は元本割れのリスクがある
契約から数年以内の解約では、払い込んだ保険料の半額程度しか戻らない可能性があります。
養老保険は「確実に一定額が戻る安心感」はありますが、配当金が出ない(またはごくわずか)設計が主流のため、「増やす目的」には適していません。
満期金を保証してくれる代わりに、運用効率は犠牲になっているというのが養老保険の本質といえるでしょう。

養老保険が「おすすめしない」と言われる背景とは?

養老保険が「おすすめしない」とされる根本的な理由を、経済環境・保険の構造・他商品との比較という3つの視点から解説していきます。
バブル期設計の保険が令和の時代に合っていない
養老保険の構造自体は昔からほとんど変わっていません。問題は、その設計思想がバブル期の金融常識に基づいている点です。
かつての金利水準を見てみましょう。
| 時代 | 預金金利 | 養老保険の予定利率(例) |
|---|---|---|
| 1980~90年代 | 年利6%前後 | 年利5~5.5% |
| 現在(令和) | 年利0.002~0.2% | 年利0.3~1.0% |
当時は「銀行に預けるだけでお金が増える」時代でした。養老保険も例外ではなく、10年で1.6倍になるような高利率プランが実際に存在していました。
- 昔:保障+高利率の運用が両立できた
- 今:保障はあるが運用益は微々たるもの
今の養老保険は仕組みだけが過去から残っており、現代の資産形成や保障ニーズには合っていないのが実情です。
低金利・インフレ環境では資産が目減りする
養老保険の満期金は確かに戻ってきますが、お金の価値は戻ってきません。インフレによって物価は年々上昇しています。
以下は、年2%のインフレが10年間続いた場合の実質価値のシミュレーションです。
| 満期金 | 300万円 |
|---|---|
| インフレ率 | 2%/年 |
| 実質的な価値(10年後) | 約246万円相当の購買力 |
つまり、表面上は300万円が戻ってきても、実際に買えるモノは減っているのです。満期金が据え置きなら、インフレが進むほど損をしたような状態になります。
掛け捨てでないことばかりが強調されがちですが、保険料・運用効率・将来価値のどれを取っても、現代の経済環境では不利になりやすいのが養老保険です。
同じ金額で他にもっと増やせる商品がある
今の時代、資産を効率的に増やす手段は他にもあります。養老保険を選ばないほうがいい最大の理由は、「同じお金でもっと増やせる手段が普通に存在するから」です。
たとえば、毎月2万円を10年間積み立てるケースで比較してみましょう。
| 商品 | 想定利回り | 10年後の資産 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 養老保険 | 約0.3% | 247.3万円 | 7.3万円 |
| つみたてNISA | 5% | 390.93万円 | 150.93万円 |
しかも、つみたてNISAは運用益が非課税で、自由に引き出せる柔軟さもあります。一方、養老保険は途中解約で元本割れのリスクがあり、満期までは資金が固定されます。
また、保障の必要性がある場合でも、保険と運用を一緒にしないほうが効率的です。
- 死亡保障→掛け捨て定期保険(月々1,000円程度)
- 資産形成→つみたてNISA、iDeCo、国債など
このように目的別にお金を分けたほうが、費用も少なくリターンも大きくなります。養老保険はどちらも中途半端であり、貯蓄性の弱さや解約リスクといったデメリットが目立つ商品です。

養老保険を選んで後悔した人に共通する3つのパターン

養老保険は仕組みそのものが分かりづらく、メリットばかりを強調された営業トークをうのみにすると、本来の目的とズレたまま高額な保険料を払い続けることになりかねません。
ここでは、実際に後悔した方々の典型的な3パターンを紹介しながら、なぜ失敗につながったのかを具体的に解説します。
「とにかく元本割れが不安」という人には不向き
養老保険は「満期まで解約しなければ元本が戻る」と紹介されがちですが、元本保証の商品ではありません。途中で解約すれば、支払った保険料を下回る「元本割れ」が発生することが一般的です。
以下は、契約5年で解約した場合のシミュレーションです。
| 総支払額 | 300万円 |
|---|---|
| 解約時期 | 5年後 |
| 返戻率(目安) | 約60~80% |
| 返戻金 | 180~240万円 |
解約タイミングが早いほど返戻率は低下し、2年以内に解約すれば半分も戻らないこともしばしば。
また、以下のような心理的ストレスを感じる人も多くいます。
- 途中解約できないプレッシャーが重い
- 資金が固定されて身動きがとれない
- 長年払っても「増えてないこと」にがっかりする
「満期金が戻る=安心と思ってたが、貯金と違って流動性が低い」と感じる方にとっては、養老保険は不要といえるでしょう。いつでも自由に引き出せて、元本割れのない資産管理を好む人には不向きな商品です。
「節税になる」と言われて加入したが効果が薄かった
「生命保険料控除が使えて節税になりますよ」と勧められて養老保険に加入したものの、思ったほど得にならなかったという声も非常に多く聞かれます。
たしかに、養老保険は「一般生命保険料控除」の対象であり、年12万円の支払に対して最大4万円(所得控除)までが適用される制度があります。
しかし、実際に減る税金額は多くても年間1万円前後が一般的です。にもかかわらず、月2〜3万円の高額な保険料を10年以上も払い続ける必要があり、「節税額<払込負担」という本末転倒な構図になってしまうのです。
節税が目的であれば、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済のほうがはるかに控除効果が高いうえ資産形成にも向いています。
養老保険に期待されがちな節税メリットは、額も範囲も限定的で、加入の決め手にはなりません。
「保険のプロに任せれば安心」と思って盲信していた
「よくわからないから、保険のプロにお任せで…」という姿勢で加入した結果、後になって内容を見返して愕然とする人も少なくありません。
営業担当者の中には、自社商品を販売することでインセンティブを得られる立場の人も多く、本当に加入者のライフプランに合った提案になっていない場合もあります。
養老保険のように見た目がシンプルで中身が複雑な商品は、契約者自身が内容を理解して判断することが大切です。

【例外あり】養老保険が向いている人の3パターン

ここまで養老保険が「おすすめしない」と言われる理由を解説してきましたが、すべての人に不向きとは限りません。以下では、養老保険が適している具体的な3パターンについて詳しく解説します。
保険料と満期金をシミュレーションし納得できる人
養老保険は、あらかじめいくら払って、いくら戻るかがシミュレーションできます。納得したうえで契約する人であれば満期時に不満を感じにくい商品です。
実際に下記のように判断できる人には向いているといえるでしょう。
- 「満期金は減るけど、死亡保障もあるからOK」
- 「利回りは低いが、元本がほぼ戻るなら問題ない」
- 「資産運用ではなく確保目的だから割り切れる」
また、保険と資産形成は本来別物であることを理解し、あくまで保障付きの貯蓄商品と位置付けている方も失敗しにくいです。
貯金が苦手で、目的別資金を強制的に積み立てたい人
養老保険は強制貯蓄の仕組みとして機能します。
理由は以下のとおりです。
- 保険料は自動引き落としのため、手元に残らず使えない
- 中途解約すると元本割れがあるため、無駄遣いを防げる
- 満期まで続ければ、目的金額が確実に貯まる
ただし、途中で解約すると返戻金が減るため、「いつ使うのか」「本当に必要か」を自分の中で言語化できない場合は避けたほうがよいでしょう。
法人の福利厚生・節税目的で活用するケースも存在
個人ではなく法人契約として導入する場合の主な活用目的は以下の3点です。
- 役員退職金の積立
- 福利厚生としての死亡保障の提供
- 法人税の繰延べ(※一部損金計上可能な契約形態)
半損タイプの養老保険では以下のような会計処理になります。
| 項目 | 処理方法 |
|---|---|
| 保険料の50% | 損金処理(法人税軽減効果) |
| 保険料の残り50% | 資産計上(将来の満期金原資) |
さらに、満期時に役員退職金として受け取ることで、個人側の退職所得控除を使って節税効果を得ることも可能です。
ただし、以下のような注意点もあります。
- 2020年代以降の税制改正で制限が厳しくなっている
- 設計次第では節税にならずコストだけが残る事例もある
- 利用には専門家(税理士・FP等)の関与が必須
法人契約での養老保険活用は、税金・経理・資金計画を含めた総合的な判断が必要です。

【数値比較】養老保険のシミュレーション|満期時に損する具体例

養老保険と他の資産形成手段のシミュレーションを比較しながら、なぜ損をしている構造になるのかを解説していきます。
10年満期で30万円損?払込総額vs満期金を徹底比較
養老保険は「お金が戻るから安心」と思われがちですが、戻ってくる金額と支払った金額を数値で比較すると、実際には損失が出ている構造です。
たとえば、かんぽ生命による養老保険加入例を見てみましょう。
| 加入年齢 | 30歳 |
|---|---|
| 基準保険金額 | 100万円 |
| 保険期間 | 15年 |
| 保険料払込期間 | 15年 |
| 死亡保険金額 | 100万円 |
| 満期保険金額 | 100万円 |
| 保険料 | ・男性:6,040円/月 ・女性:6,030円/月 |
男性の場合、保険料の総払込額は1,087,200円に対し、満満期100万円の固定型設計では実質的に損失が生じる場合があります。
一方、養老保険は途中解約すると以下のように元本割れします。
| 解約時期 | 返戻率(目安) | 解約返戻金 |
|---|---|---|
| 2年後 | 約50% | 50万円 |
| 5年後 | 約70% | 70万円 |
途中で解約すれば損が膨らみ、最後まで続けても増えず、使い勝手も悪い資金拘束型の商品だという現実が浮き彫りになります。
同額をつみたてNISAで運用していた場合との損益差
同じ1,087,200円を使っても、別の方法で積み立てれば結果は大きく変わります。ここでは「つみたてNISA」を例にシミュレーションしてみましょう。
想定条件は以下の通りです。
- 月額積立:9,060円
- 積立期間:10年
- 想定利回り:年5%(長期・分散・積立を前提)
- 税制:運用益非課税(NISA制度)
この条件で積み立てを行った場合、次のような結果になります。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 総拠出額 | 1,087,200円 |
| 運用益 | 約299,000円 |
| 最終資産 | 約1,386,000円 |
| 差額(vs養老保険) | 約341,000円 |
養老保険と比べると、約34万円近い差が生まれています。しかもつみたてNISAは以下の点でも有利です。
- 運用益が非課税(通常の金融商品より手取りが増える)
- 途中引き出しが自由(教育費や急な支出にも対応可能)
- 積立対象が分散投資のため、長期でリスクが抑えられる
もちろん投資商品である以上、元本保証はありません。ただし、つみたてNISAは「長期×分散×積立」という安定的な運用を前提とした制度です。10年〜20年というスパンで見れば、大きく損をする可能性はかなり低く抑えられます。
保険と投資はそもそも目的が異なるため一概には比べられませんが、「お金を増やす」目的なら養老保険は非効率です。

【目的別】養老保険より合理的な代替手段とは?
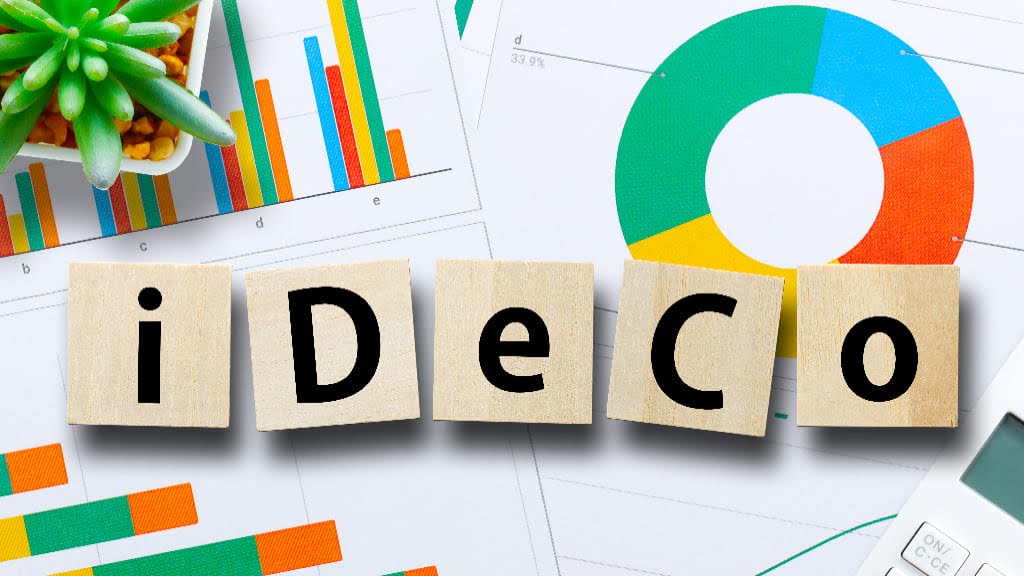
目的別に養老保険より合理的な代替手段を紹介します。
死亡保障を重視するなら「掛け捨て定期保険」
万が一のときに家族にお金を残したいと考えているなら、掛け捨て定期保険がよいでしょう。
理由は以下のとおりです。
- 死亡時のみ保険金が出るシンプルな仕組み
- 満期金がない代わりに保険料が格段に安い
- 同じ保障額でも支払い負担を大幅に抑えられる
掛け捨て保険は返戻がありませんが、補償の手厚さに焦点を当てるのであれば養老保険よりも掛け捨て型のほうが合理的です。
老後資金を貯めるなら「つみたてNISA・iDeCo」
老後資金を目的に養老保険を選ぶ方もいますが、資産形成に向いた制度はほかに存在します。代表的なのが「つみたてNISA」と「iDeCo」です。
どちらも税制優遇を受けながら長期で資産を増やせる制度で、金融庁が推奨しています。
制度の比較は以下のとおりです。
| 制度 | 年間上限 | 税制メリット | 引き出し制限 |
|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 年360万円 | 運用益が非課税 | いつでもOK |
| iDeCo | 職業により異なる(例:自営業者 81.6万円) | 掛金が全額所得控除・運用益も非課税 | 60歳まで不可 |
養老保険との違いは以下の2点です。
- 運用によって資産が増える可能性がある
- 税制優遇が強く、老後の生活資金づくりに直結する
老後の準備を始めたい方にとっては、養老保険よりも積み立てながら増やせる制度のほうが現実的です。
学費目的なら「学資保険」
子どもの教育費を目的に養老保険を契約する方もいますが、その用途であれば設計が明確な学資保険のほうが扱いやすいです。
学資保険は以下の特徴があります。
- 子どもの進学タイミングに合わせて給付金を設定できる
- 親が万が一死亡した場合も保険料が免除される
- 満額の給付が保障されるため、教育費の確保がしやすい
設計イメージを比較すると次のようになります。
| 商品 | 給付タイミング | 万が一の契約者死亡時 |
|---|---|---|
| 養老保険 | 満期時、もしくは契約者死亡時に一括 | 保険金支払いで終了 |
| 学資保険 | 18歳、21歳など分割受取 | 満期時まで保険料の支払い免除 |
ただし運用効率は高くないため、「利回りを求める」というより「確実に教育費を確保したい」という目的に沿った使い方がおすすめです。
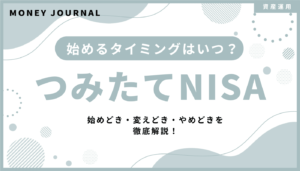
養老保険はおすすめしないに関するよくある質問

養老保険はおすすめしないに関するよくある質問と回答は以下のとおりです。
養老保険の満期金は本当に戻ってくるだけ?
はい、基本的には「払った保険料の総額」とほぼ同額の満期金が戻ってくるだけです。たとえば月3万円×10年=360万円支払い、満期金が300万円なら、実質的には60万円の損です。
利息や運用益はほとんど発生せず、10年間お金が拘束された割には増えません。「貯金の延長」と捉えると期待外れに感じる場合が多いでしょう。
「解約すると損」と言われるのはなぜ?
養老保険は、契約から数年以内に解約すると返戻率(戻ってくるお金の割合)が低く、元本割れするからです。
たとえば5年目で解約した場合、払込総額250万円に対し、返戻金が180万円程度の場合もあります。長期前提の商品なので、途中解約すると損をするよう設計されており、「貯金代わり」の感覚で加入すると後悔しやすくなります。
養老保険は法人契約でも意味ない?
法人契約で活用するケースはありますが、税制改正により以前よりメリットは薄れています。昔は損金計上と退職金準備の両立が可能でしたが、現在は経理処理が厳格化され契約内容によっては全額損金は不可です。
一定の節税効果は残りますが、設計ミスで法人の負担が重くなることもあります。活用するなら税理士と連携し、契約内容を精査することが必須です。
営業マンに勧められたらどう断るのが正解?
「検討はしますが、今は契約しません」と即決を避けるのがよいでしょう。無理に内容を否定する必要はなく、「他の商品と比較してから判断したい」「家族と話し合いたい」と伝えれば角が立ちません。また、資料をもらったうえで後日メールなどで断るのもおすすめです。
養老保険は親が入れと言ってくる…どうする?
親世代は「保障+貯蓄」が常識だった時代の価値観を持っており、養老保険を良いものと信じていることが多いです。
正面から否定せず、「今は別の制度(NISAなど)があって、効率が良い選択肢もあるんだよ」と情報を共有する形で会話を進めるとよいでしょう。最終的に加入するのは自分自身なので、自分のライフプランを優先してください。
養老保険は一生涯の保障が受けられる保険なの?
いいえ、養老保険は「一定期間のみ保障が続く期間限定の保険」であり、終身保険のように一生涯の保障は受けられません。たとえば15年満期の契約なら16年目以降、20年満期なら21年以降は保障がなくなります。満期金を受け取ると同時に契約も終了するため、老後まで保障を続けたい方には向いていない保険です。
養老保険は全期前納できる?
はい、養老保険は「全期前納(契約時に保険料を一括払い)」が可能な商品もあります。前納することで保険料の総額が割引される場合もあります。
養老保険は円建てと外貨建て、どちらがいい?
一般的に初心者には円建てが無難です。外貨建て養老保険は、為替差益によるリターンの可能性がある一方、為替リスクも高く、元本割れの可能性があります。
養老保険は年末調整で控除対象?
はい、養老保険は「一般生命保険料控除」の対象になります。年末調整や確定申告で申請すれば、年間最大4万円まで所得控除が受けられ、結果的に1万円前後の税金が軽減される場合もあります。
養老保険は何歳から入れる?
多くの保険会社では、養老保険は満15歳~満60歳または70歳前後まで加入可能です。ただし、年齢が高いほど保険料が割高になり、利回りも悪くなる傾向があります。
養老保険の被保険者は誰に設定すべき?子どもでも可能?
被保険者は基本的に万が一のときに備えたい人(=保障を受ける人)に設定するのが原則です。子どもを被保険者にすることも可能ですが、一般的には親や世帯主が被保険者になり、家計を支える人の万が一に備える場合が多いです。
まとめ:養老保険は中途半端な商品|代替策と比較してから判断を
この記事では、養老保険はおすすめしないとされる理由と、より納得できる代替手段について解説しました。
養老保険は「貯蓄」と「保障」を一つにまとめたように見えて、どちらも中途半端になりやすい商品です。
たとえば、以下のような構造に陥ります。
- 【保障面】満期で契約終了→その後の備えが不十分に
- 【貯蓄面】利回りがほぼゼロ→インフレで実質目減り
- 【柔軟性】途中解約で元本割れ→自由に使えない資金
同じお金を使うなら、目的ごとに分けて管理したほうがはるかに効率的です。
納得できる保障と資産づくりのために、自分の目的に合った制度を選びましょう。そして、将来の不安に備えるなら、まずは「増やせる仕組み」を選んでください。