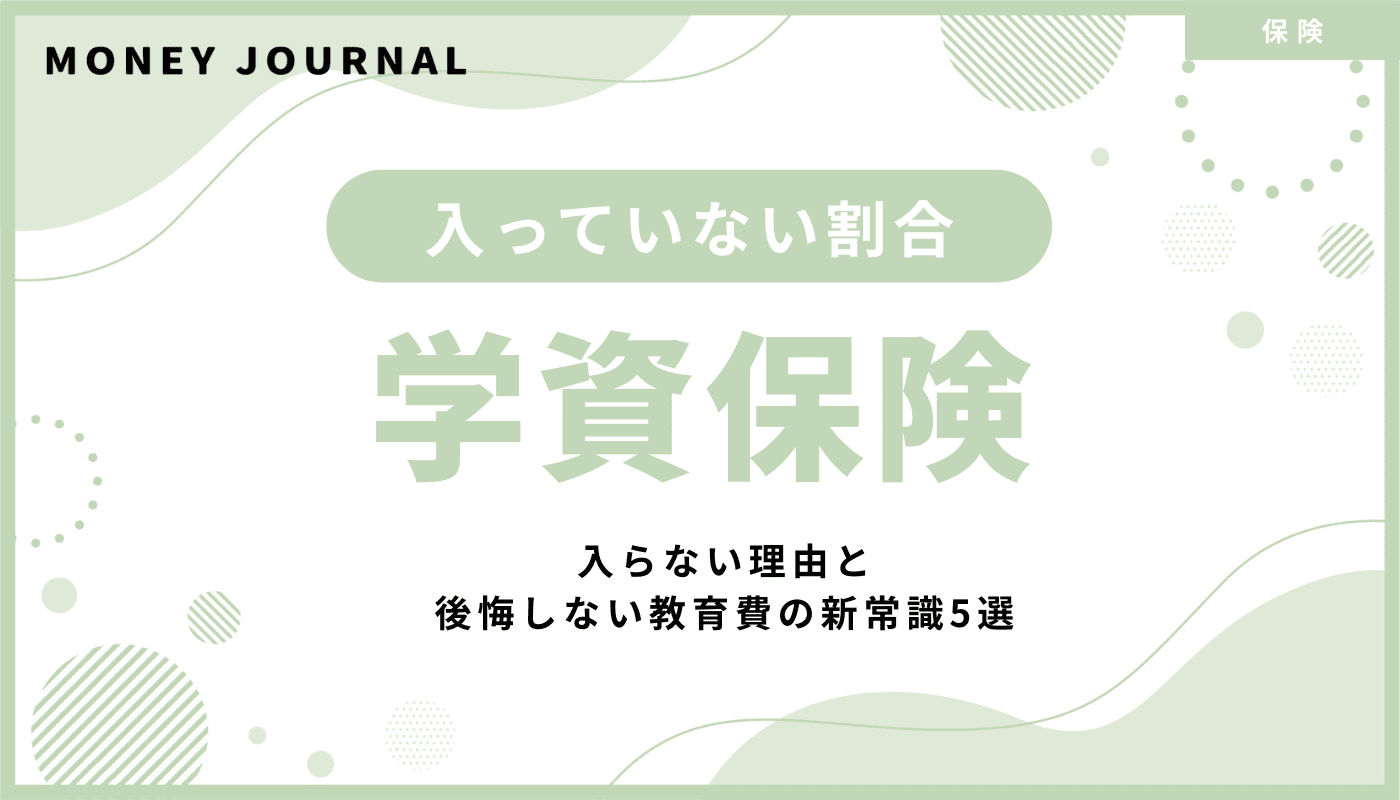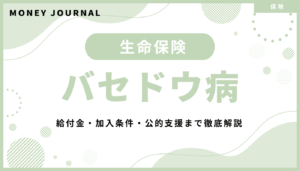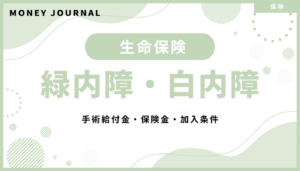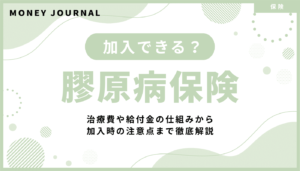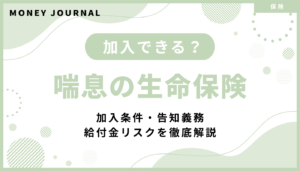- 「学資保険かけてないけど本当に必要なの?」
- 「うちは入ってないけど、みんな入ってるのかな?」
- 「学費ってどうやって準備するのが正解なんだろう」
このように考えている方もいるでしょう。
本記事では、学資保険の最新の加入率データを始め、学資保険に入らない理由や「じゃあどうやって教育費を用意すればいいの?」という方に向けて、実践的な5つの備え方も具体的に紹介しています。
教育費への不安を安心に変えたい方は、ぜひ参考にしてください。
学資保険に入っていない割合は6割超!加入率の最新データ

結論から言うと、学資保険に入っていない家庭のほうが多く、むしろ入らないという判断がスタンダードになりつつあるのが今の現実です。
まずは、実際の加入率データを見てみましょう。
▼学資保険の加入率(2025年調査)
| 対象家庭 | 加入率 | 未加入率 |
|---|---|---|
| 0歳〜高校生の子どもを持つ家庭 | 38.4% | 61.6% |
| 大学生の子どもを持つ家庭 | 38.5% | 61.5% |
では、未加入の家庭はどのように教育費を準備しているのでしょうか。
▼教育資金の準備手段ランキング(複数回答)
| 教育費の準備方法 | 割合 |
|---|---|
| 銀行預金 | 54.3% |
| 学資保険 | 38.4% |
| 投資信託・NISAなどの資産運用 | 24.1% |
| 定期預金 | 21.7% |
| 財形貯蓄 | 7.2% |
最も多かったのは銀行預貯金で過半数を占めており、学資保険を上回っています。また、新NISAなどの資産運用も活用され始めており、保険のデメリットを踏まえ、自分でコントロールできる方法を選ぶ家庭が増えています。

学資保険に入っていない人のリアルな理由とは?

学資保険に加入していない家庭が6割を超えている背景には、明確な理由があります。単なる無関心ではなく、現代の家計事情や金融知識の変化を受けた結果なのです。
ここでは、実際に加入を見送った家庭が抱えていたリアルな不安と判断理由をテーマごとに解説していきます。
返戻率が低く、インフレに弱いと感じている
学資保険の返戻率は、ここ数年で減少の推移にあり、元本とほぼ変わらない水準の商品が多く、将来の物価上昇に負けてしまうと感じる家庭が増えています。
たとえば、よくある商品では以下のような返戻率となっています。
| 契約内容例 | 総支払額 | 満期受取額 | 返戻率 | 年利換算(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 月1万円×15年(180万円) | 180万円 | 189万円 | 105.0% | 約0.55% |
| 月1.2万円×18年(259万円) | 259万円 | 270万円 | 104.2% | 約0.36% |
一方、新NISAや投資信託を活用した積立投資では、年3〜5%の利回りが想定されており、リスクはあるものの成長余地が大きいと評価されています。
下記は簡易的な比較シミュレーションです。
| 方法 | 年利想定 | 18年間の運用益(元本250万円) |
|---|---|---|
| 学資保険 | 0.4% | 約+10万円 |
| つみたてNISA | 4.0% | 約+130万円 |
インフレが進行すれば資産価値は目減りします。返戻率がインフレに追いつかない商品では、実質的に損をしている感覚になるのも無理はないといえるでしょう。
途中解約リスクと資金拘束が不安
学資保険は満期まで続けてこそ意味がある商品であり、途中での解約は原則損失が発生します。
そのため、途中で「子どもの塾代」や「家の修理費」にあてるために解約するのであれば、そもそも銀行預金でよかったよね、となってしまうのです。
iDeCo・NISAなど自分で増やす時代になった
最近は「保険で守る」よりも「運用で増やす」時代になっています。なかでもNISAやiDeCoは税制面での優遇があるため、教育費準備にも有効だと評価されています。
以下は各制度の特徴です。
| 制度名 | 利回り想定 | 税制優遇 | 途中引き出し |
|---|---|---|---|
| 新NISA | 3~5% | 運用益が非課税 | いつでも可能 |
| iDeCo | 3~5% | 掛金・運用益が非課税 | 不可 |
自分で増やすことがリスクに感じる方もいますが、今や20代・30代の多くが積立投資を生活に取り入れています。
学資保険では物足りないと感じる家庭が、新NISAを選ぶのも自然な流れといえるでしょう。
児童手当・貯蓄でなんとかなるという意識
毎月もらえる児童手当をそのまま貯金しておけば、ある程度の教育費は準備できると考える家庭も存在します。
実際に支給される総額を確認すると、一定の教育費をまかなえることがわかります。
▼児童手当を全額貯金した場合の想定額(子ども1人)
| 年齢帯 | 月額手当 | 支給年数 | 累計額 |
|---|---|---|---|
| 0~2歳 | 15,000円 | 3年 | 540,000円 |
| 3歳~中学卒業(15歳) | 10,000円 | 12年 | 1,440,000円 |
| 高校生相当(~18歳年度末) | 10,000円 | 3年 | 360,000円 |
| 合計 | ー | ー | 2,340,000円 |
このように、1人あたり約234万円の貯蓄が可能です。
保険に頼ることをおすすめしない家庭も多く、「手数料がかからず自由に使える」「途中で引き出せる」というメリットから学資保険より魅力を感じる人が増えています。
とはいえ、「本当にこのままで足りるのか?」「児童手当だけで将来の教育資金はまかなえるのか?」と、不安を感じている方も少なくありません。
そんなときは、お金のプロによる無料の家計診断を活用してみてはいかがでしょうか。
保険や貯蓄のバランス、無理のない資金計画まで丁寧にアドバイスしてくれます。
もちろん診断は何度でも無料・カメラオフもOK。まずは気軽に、今の家計が本当に最適かどうかをチェックしてみてください。
入りたいが、月々の保険料を捻出できない
年収が限られた子育て世帯では、学資保険に入りたくても入る余裕がないのが現実です。
とくに月の手取りが25万円前後のご家庭では、保育料や住宅ローンなどの固定費で大半が消えてしまいます。
「保険に入っても、もし途中で支払えなくなったらどうしよう」というリスクを踏まえ、最初から加入を見送るという選択をせざるを得ないのでしょう。
さらに昨今は、物価上昇や住宅費の高騰もあり、「固定支出を増やさない」という考え方が主流になりつつあります。

【体験談で検証】未加入家庭の後悔と納得の分かれ道

学資保険に入らなかった家庭は、本当に後悔しているのでしょうか。よくある2パターンの声から、後悔の分岐点について整理していきます。
後悔した人の声:「大学進学時に一気にお金が足りず焦った」
「毎月の生活費は何とかなるけれど、将来の教育費は後回しになってしまっていた」家庭では、大学進学のタイミングで資金不足に陥ることが考えられます。
というのも、大学入学時には以下のような支出が集中するからです。
| 項目 | 支出目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 入学金 | 約20~30万円 | 初年度に一括請求 |
| 授業料(前期分) | 約30~40万円 | 国公立でも納入期限は短い |
| 引っ越し費用 | 約10万円 | 一人暮らしを始める場合 |
| 家具・家電購入 | 約15万円 | ベッド・冷蔵庫・洗濯機などの初期費用 |
| 仕送り準備 | 約20万円 | 最初の1~2ヶ月分の生活費 |
合計で100万円以上が一気に必要になる場合があります。このとき、「児童手当は生活費で使ってしまった」「貯金もあまり残っていない」という状態では対応が難しくなります。
結果として、「学資保険に入りそびれたせいで、もっと早くから積み立てておけばよかった」と後悔することに。計画的な準備を怠ったという後悔は、教育費という逃げられない出費のタイミングで表面化しやすいです。
後悔しなかった人の声:「預金で対応できた」
学資保険に入らず、自分たちで資金管理を行ってきた家庭では、むしろ保険に頼らなかったことをプラスに捉える声もあります。
実際に以下のような積立スタイルを実践していた場合、教育費にも対応しやすくなります。
- 毎月1万円を自動で目的別口座に積立
- 児童手当を一切使わずに貯金
- ボーナス時に年間10万円を追加積立
- 貯めたお金は使わないと家族でルール化し死守
上記をすべて実践していた場合、18年間で400万円以上の貯蓄が可能です。しかも、学資保険と違って途中での引き出しが可能で流動性が高く、手数料もかからないというメリットがあります。

子どもの教育費はいくらかかる?公立・私立別の必要額

学資保険を検討するにあたり、押さえておきたいのが子ども1人あたりに必要な教育費の全体像です。
ここでは、進学パターン別の総額から、出費が集中する時期、年収ごとの負担感までを整理します。
幼稚園〜大学までの総額は約1,000万〜2,500万円
子ども1人にかかる教育費は進学先が公立か私立かで大きく変わります。
文部科学省や日本政策金融公庫の調査をもとに、代表的な進学ルートごとの総額を表にまとめました。
▼進学パターン別 教育費の総額目安(幼稚園〜大学まで)
| 教育ルート | 総額の目安 |
|---|---|
| 幼~大すべて公立 | 約1,000万円 |
| 小中高公立・大学私立(文系) | 約1,300万円 |
| 小中公立・高校私立・大学私立(理系) | 約1,800万円 |
| 幼〜大すべて私立(理系) | 約2,500万円超 |
参考:文部科学省「調査結果の概要」
学費だけでなく制服・部活動・交通費なども含めると、実質的な負担はさらに大きくなる点にご注意ください。
世帯年収ごとの教育費負担感目安一覧
教育費を考えるうえで大切なのは、「いくらかかるか」よりも「どれだけ負担に感じるか」です。同じ年間100万円でも、家計への響き方は年収によって大きく変わります。
以下は、年収別に教育費100万円を支出した場合の家計への圧迫度の目安と、対策の方向性をまとめた一覧です。
▼世帯年収別 教育費100万円の負担感と備え方
| 年収(税込) | 月手取り目安 | 年間教育費100万円の負担率 | 家計の特徴・対策の目安 |
|---|---|---|---|
| 約300万円 | 約20万円 | 約33% | 支出と貯蓄の両立が難しい水準。無理な保険加入は慎重に |
| 約500万円 | 約30万円 | 約20% | 児童手当やボーナスで積立すれば対応可能。先取り貯蓄が効果的 |
| 約700万円 | 約40万円 | 約14% | 私立進学を視野に入れた計画も立てやすい |
| 約1,000万円 | 約60万円 | 約10%未満 | 新NISAなどで長期的に分散して備える余力がある |
年収300万円の家庭が月1万円の保険料を払うと、年間で40万円以上を使えないお金として拘束されることになります。
学資保険を検討する際には保険料の負担率だけでなく、固定費として継続できるかどうかも見極めておくことが大切です。

学資保険に入らなくても教育費は準備できる?実践的な代替手段5選

学資保険に加入しなくても、教育費を確実に準備している家庭はたくさんあります。
ポイントは「無理なく続けられて、必要なときに使える仕組みを持っているかどうか」です。
この章では、学資保険に頼らず教育資金を備えるための実践的な5つの方法を紹介します。
児童手当を全額貯金して教育費に充てる
もっともシンプルかつ確実な方法が、児童手当の全額貯金です。
支給総額は第1子でも200万円以上にのぼるため、それだけで大学入学金や初年度学費の一部をまかなえます。
▼児童手当の累計支給額(子ども1人・第1子想定)
| 年齢帯 | 月額手当 | 支給年数 | 累計額 |
|---|---|---|---|
| 0~2歳 | 15,000円 | 3年 | 540,000円 |
| 3歳~高校卒業相当 | 10,000円 | 15年 | 1,800,000円 |
| 合計 | ー | ー | 2,340,000円 |
受取口座を「教育費専用口座」に設定しておけば、毎月自動的に積立が完了します。元本割れの心配がなく、使いたいときに自由に引き出せるのも大きなメリットです。
生活費とは完全に分け、「手をつけない」と決めておくことが教育資金準備のコツです。
新NISAで月1万円から資産運用を始める
新NISAは、教育資金の長期積立にも相性がよい制度です。運用益が非課税なうえ、いつでも引き出せる柔軟さがあり、学資保険よりも自由度が高いのが魅力です。
▼シミュレーション:月1万円×15年、年利5%の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 元本 | 180万円 |
| 運用益 | 87万円 |
| 合計資産 | 267万円 |
「将来の教育費を、自分の手で増やす力を身につけたい」という方には最適な方法だといえるでしょう。
iDeCoで老後と教育費を分けて管理する
教育費と老後資金を一緒に考えると、どちらも中途半端になりやすいです。
iDeCoを活用すれば、老後用の使えない資産を別枠で積み立てられます。
▼iDeCoの特徴まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 掛金 | 全額所得控除で節税効果あり |
| 引き出し時期 | 原則60歳以降 |
| 投資運用の利益 | 非課税で再投資可能 |
| 教育費との関係 | 引き出せない分を老後用と割り切れる |
教育費は児童手当やNISAで備え、iDeCoには手をつけない資産を確保しておけば目的が混在せず管理できます。
定期預金+財形で堅実に積み立てる
元本割れがどうしても不安な方には、定期預金や財形貯蓄がおすすめです。
会社に財形制度があれば、給与天引きで半強制的に積立できるのが魅力です。
▼積立方法の比較表
| 方法 | 特徴 | 利率目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 定期預金 | 自由に積立、引き出しも可能 | 0.275~1.00% | 使い勝手重視の方 |
| 財形貯蓄 | 会社で管理、強制力が高い | 0.280~0.400% | 仕組みで貯めたい方 |
参考:ゆうちょ銀行「定期預金」
参考:三菱UFJ信託銀行「財形貯蓄のご案内」
利回りは低いですが、減らさずに貯めたい方にとっては精神的にも安心でしょう。
金融機関によっては金利優遇キャンペーンを行っている場合もあるため、積極的に活用してみてください。
学資保険より柔軟に使える終身保険を活用
学資保険ではなく、貯蓄型の終身保険を“教育資金用の資産”として使う方法もあります。
▼活用パターンの例
| 契約条件 | 活用イメージ |
|---|---|
| 終身保険10年払い | 払込満了後から15年目に解約して教育費に充当 |
| 解約返戻金設計型 | 満期前でも一定額まで戻るタイプを選ぶ |
| 死亡保障付き | 万が一の備えにもなり、精神的安心感も得られる |
学資保険よりも用途に柔軟性があるうえ、死亡保障も確保できます。ただし、返戻率は商品によって差が大きいため、事前比較は必須です。

【診断】あなたは学資保険に向いてる?5つのチェックポイント

5つのチェックポイントをもとに、学資保険との相性を診断します。自分に当てはまる項目が多ければ、学資保険を前向きに検討してみてください。
定額で積み立てるのが得意
毎月決まった金額をコツコツ貯めるのが得意な方には学資保険が向いています。契約時に金額と期間を決めて、そのまま長く積み立てていくスタイルだからです。
以下のような特徴があれば、支払いを無理なく続けやすいでしょう。
- 家計の波が少なく、月ごとの収支が安定している
- 生活費と貯金を分けて管理する習慣がある
- 一定額を先取りしてから残りで生活している
反対に、月によって収入が上下する方や、自営業で支出が不規則な方は慎重に判断した方が良いかもしれません。
途中解約せず長期間続けられる
学資保険は契約してすぐ解約すると損をします。返戻金が少なく、元本を割り込むことがあるためです。
下記は、契約からの経過年数ごとの返戻率の一例です。
| 解約時期 | 戻ってくる割合の目安 | 180万円の契約時の想定損失 |
|---|---|---|
| 5年以内 | 80~90%程度 | 18万〜36万円程度 |
| 10年以降 | 95~100%前後 | 少額〜±0程度 |
| 満期(18年) | 105〜110%前後 | 10万〜20万円程度の上乗せ |
途中でやめる予定がないなら、計画的に満期まで続けられます。「教育費以外に使うつもりはない」「転職や収入減の予定もない」という方は、安心して契約できるでしょう。
貯金が苦手で強制力がほしい
お金があるとつい使ってしまう方にとって、学資保険は使わずに残す仕組みとして機能するでしょう。
いったん契約すると、毎月決まった日に口座から引かれるため、自分の意思で止めることができないからです。
たとえば以下のような方におすすめです。
- 児童手当を気づいたら使ってしまっていた
- 目的別の貯金がうまく分けられない
- 先取り貯金がなかなか続かない
貯金を意思だけで管理するのが難しい場合には、保険のようにルールが決まっている方法が合いやすくなります。
大きな医療保障はすでに備えている
学資保険は、基本的に教育資金を積み立てるための保険です。医療費への備えはオプションとして付けられるものの、保険料が高くなりますし保障内容はそこまで手厚くありません。
そのため、子どもの病気に備えた保険がすでにある家庭なら、学資保険は教育費の準備に特化しやすく、相性がよいでしょう。
- 子どもの医療保障は共済や医療保険で確保している
- 入院や手術の備えは他の保険に任せている
- 教育資金の準備だけに集中したい
子どもの医療費にも不安があり「一つの保険で全部カバーしたい」と思っている方には、学資保険だけでは物足りなく感じるかもしれません。
収入に対して保険料負担が重すぎない
毎月の保険料が家計を圧迫しないかどうかは、契約前に必ず確認しておきたいポイントです。
手取り収入の5〜10%程度に収まっていれば、長期でも継続しやすくなります。
以下は、目安としての金額表です。
| 手取り月収 | 無理のない保険料目安 |
|---|---|
| 20万円 | 月10,000円~20,000円以内 |
| 25万円 | 月12,000円~25,000円以内 |
| 30万円 | 月15,000円~30,000円以内 |
「教育資金を早めに確保しておきたい」「生活にゆとりがあり、毎月の保険料も無理なく払えそう」と感じる方なら、保険を利用した積立も前向きに考えて良いでしょう。

学資保険に関するよくある質問

ここでは、学資保険初心者の方から寄せられる質問の中でも、とくに多い項目をわかりやすく整理しました。加入を検討するうえでの判断材料としてご活用ください。
学資保険は必要?それとも不要?
学資保険は教育費を計画的に積み立てたい方におすすめです。ただし、途中で解約すると損をする構造になっており、使い勝手がよいとは言いづらい面もあります。
強制的に貯めたい方や貯金が苦手な方には向いていますが、資産運用や自由度を重視する家庭には合わない場合もあることを踏まえ検討してください。
学資保険の月々の保険料は平均いくら?
学資保険の保険料が月いくらかといいうと、1万円〜2万円程度が一般的です。子どもが0歳での加入が多く、「大学入学時に200万円前後を受け取る」ことを目安に設計されています。
保障金額が高いほど月額も増えるため、無理なく続けられる水準で設計することが大切です。なお、15歳から入れる学資保険も一部存在しますが、基本的には早期加入が有利です。加入前に家計への影響を見ておきましょう。
学資保険に入らないのは非常識?みんな入ってる?
まったく非常識ではありません。実際には学資保険に入っていない家庭のほうが多く、加入率は4割未満にとどまります。
最近は児童手当やNISAを活用し、保険に頼らず教育費を貯めるスタイルも一般的になってきました。収支管理ができる家庭なら、学資保険をやってない状態でも十分に教育費は準備できます。
シングルマザーでも入れる学資保険はある?
はい、あります。母子家庭や父子家庭でも、安定した収入があれば多くの学資保険に申し込むことが可能です。ただし、契約者の年齢や雇用形態によっては、引き受け条件が設けられている場合もあるため、いくつかの保険会社を比較して相談することが大切です。月々の保険料が家計を圧迫しないかも事前に確認しておきましょう。
学資保険は本当に増えないの?利率の目安は?
昔に比べて増えにくくなっているのは事実です。現在の学資保険は、返戻率100〜110%前後が目安で、年利に直すと0.2〜0.6%ほどにとどまります。貯金よりは若干増えますが、インフレを考慮すると実質価値が減る可能性もあり、メリットないと感じる人もいます。「大きく増やす目的」というよりは、「確実に使う時期に受け取れる安心感」を重視したい方向けです。
学資保険は年末調整・確定申告で控除できる?
はい、できます。学資保険は「生命保険料控除」の対象に該当するため、年末調整や確定申告を通じて一部の所得控除を受けられます。控除額は保険料の支払額や他の契約の有無によって異なりますが、毎年秋頃に届く控除証明書を提出すれば手続きできます。所得税・住民税が軽減されるため、提出を忘れないようにしましょう。
返戻率が良いのはどの会社?明治安田・ソニー生命はどう?
明治安田生命やソニー生命は、返戻率が高めの商品を扱っていることで知られています。加入年齢が若く、短期払い(10年払込など)にするほど返戻率が上がる傾向があり、110%を超える商品も存在します。ただし、特約の有無や契約条件によって数値は大きく変わるため、資料を取り寄せて細かく比較することが大切です。
途中で崩すとどうなる?元本割れのリスクは?
途中で解約すると、多くの場合で元本割れします。とくに契約から数年以内は解約返戻金が支払った保険料を大きく下回ることが多く、損失が出るリスクが高いです。
教育費以外にも急な出費に備えるなら、保険とは別に扱いやすい資産を持っておくことが望ましいです。学資保険だけで対応しようとするのは避けた方が安全です。
まとめ:学資保険に入らない選択でも後悔しない備えはできる
この記事では、学資保険の加入率や未加入理由、保険に頼らず教育費を準備する具体策を解説しました。
返戻率の低下やインフレへの懸念から、今は加入しない選択が珍しくありません。
最新の現状として教育費の備え方はさまざまです。代表的な例を整理すると以下のとおりです。
- 児童手当を毎月コツコツ貯金
- 新NISAで運用益を非課税で積立
- 定期預金や財形で元本確保を優先
- 終身保険で柔軟に対応
たとえば「児童手当を使わず別口座で管理し続けた」だけで、高校卒業までに約234万円を準備できます。小学生のうちから始めても100万円以上は貯まります。
家計がきついときでも続けられる備えを見つけて、将来の学費にあわてない仕組みを今日からつくってください。