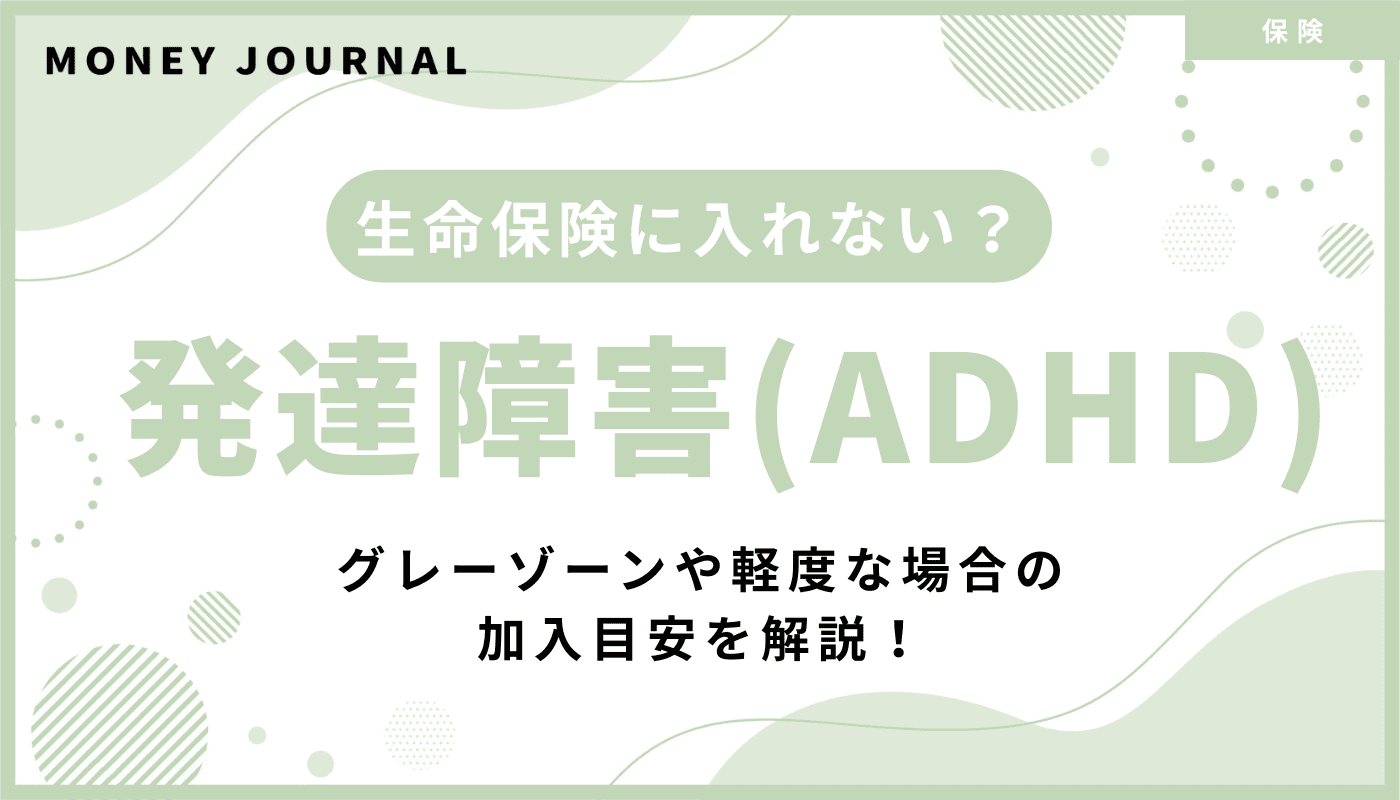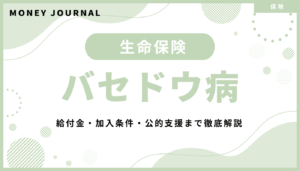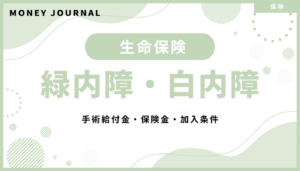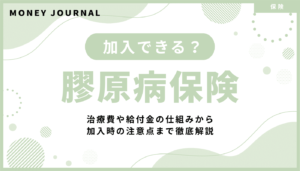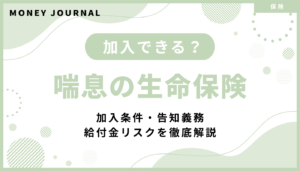- 「ADHDや発達障害があると生命保険に入れないと言われて不安」
- 「どの程度の症状なら加入できるのか判断できない」
- 「保険には入っておきたいけど選び方がわからない」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、ADHDや軽度の発達障害でも条件を満たせば生命保険に加入できる場合があります。
代表的な可否の目安は以下のとおりです。
| 状況 | 加入できる可能性 | ポイント |
|---|---|---|
| ADHDで症状が安定している | 高い | 服薬状況や通院歴を正確に告知 |
| グレーゾーンや軽度 | 高い | 生活自立度が重視される |
| 重度で日常生活に介助が必要 | 低い | 引受基準緩和型保険を検討 |
| 学資保険(親契約) | ほぼ加入可能 | 子の障害有無は原則不問 |
本記事では、発達障害(ADHD)のある方が生命保険へ加入する際の加入しやすい条件や注意点を解説します。さらに、保険の種類別の可否や、加入しやすい共済・民間保険の一覧、加入が難しい場合の代替策まで網羅しています。
保険選びに迷って時間を無駄にしたくない方は、ぜひ参考にしてください。
発達障害(ADHD)は生命保険に入れないと言われる理由

ADHDを含む発達障害があると、生命保険の加入が難しくなると耳にする方は多いでしょう。背景には、契約や保険金請求を正しく行えるかどうか、病歴や症状の安定度など、保険会社が重視する複数の審査基準があります。
ここでは、加入を断られる要因や審査のポイントを順に解説します。
知的障害や重度症状があると契約拒否されやすい
生命保険は、契約内容を理解し同意できる意思表示能力があることが前提です。
知的障害を伴う発達障害や、ADHDでも重度で判断力や意思疎通に大きな支障がある場合は、多くの保険会社で契約を断られる傾向があります。
理由は次のとおりです。
- 契約内容を正確に理解できないと判断される
- 保険金や給付金の請求手続きが適切に行えない可能性がある
例として、療育手帳B1やA判定、IQが著しく低い場合は加入が見送られやすいです。ただし、成年後見人を立てる、契約者を親にするなど条件を付ければ加入できる場合もあります。
判断能力の有無や病歴・服薬状況が審査で重視される
契約時には診断歴・通院歴・服薬状況が詳しく確認されるため、以下のような状況ではリスクが高いと判断されやすくなります。
- 長期間の精神科通院歴がある
- 向精神薬や抗不安薬を複数継続して服用している
- 入院歴がある
病歴や服薬内容は、発作・事故・就業不能リスクを推測する材料になります。
ストラテラやコンサータを長期間服用していても症状が安定していれば加入できる場合もありますが、直近で薬の量が増えている場合は慎重に審査されます。
告知義務違反防止のため保険会社が審査を厳格化する
生命保険契約では告知義務があり、過去の診断や治療、服薬について正確に申告する必要があります。
発達障害(ADHD)の場合、診断名や診断時期、通院歴を「軽いから申告不要」と誤解して告知しなかった事例が過去にあり、保険金不払いトラブルの原因となったことがあります。
障害手帳の有無で加入条件が設定されている保険がある
一部の保険商品は、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・療育手帳など)の所持を条件に加入可否や保障内容を決定しています。
具体的には、以下のような内容です。
- 手帳所持者は契約不可
- 契約できても保障額や給付条件が制限される
手帳の等級は障害の程度を示す指標として使われます。一方で、ぜんち共済のように手帳所持を条件に加入できる障害者向け保険もあるため、さまざまな生命保険商品を比較することが大切です。
ただ、数多くの保険商品から自分に合うものを選ぶのは簡単ではありません。
そこで活用したいのが、オンラインでプロに相談できるマネーコーチの無料家計診断です。
スマホやPCから30秒で予約できるため、まずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

【発達障害(ADHD)の種類別】生命保険加入の目安

発達障害と一口にいっても、症状の程度や日常生活への影響は人によって異なります。そのため、生命保険の加入可否も一律ではありません。
ここからは、ADHDを含む発達障害の種類ごとに加入の目安について解説します。
ADHD(注意欠陥障害)は症状コントロールできていれば加入できる
ADHDでも、薬や療育で症状が安定し、日常生活や仕事・学校に大きな支障がない場合は一般の生命保険に加入できる可能性があります。
審査で好印象となる条件は次のとおりです。
- 服薬が安定しており、過去1年以上大きな症状変化がない
- 就職・就学が継続しており、欠勤・休学が少ない
- 入院歴や事故歴がない
一方、最近になって薬が増えた、医師の受診頻度が上がったなど症状の変化が見られる場合は、慎重な審査となりやすいです。
グレーゾーンや軽度は生活自立度が高ければ加入できる
ADHDの「グレーゾーン」や「軽度」の診断を受けている場合でも、生活面での自立度が高ければ加入できる可能性はあります。
具体的な目安は以下のとおりです。
- 一般学級を卒業している
- 一人暮らしや安定した就業ができている
- 日常生活で介助を必要としていない
ただし、告知書には「診断歴の有無」や「発達特性の指摘を受けたか」などの項目があるため、診断がなくても指摘を受けたことがあれば申告が必要です。
学習障害やアスペルガー症候群も症状安定なら加入例がある
学習障害(LD)やアスペルガー症候群は、症状が生活に与える影響が限定的であれば加入できる可能性があります。
具体的には以下のとおりです。
- 読み書きの特性はあるが就業や日常生活に支障がない
- 社会生活に適応しており、事故や入院歴がない
反対に、転職や休職を繰り返している、対人トラブルが頻発しているなど社会生活に不安がある場合は、就業不能リスクが高いと判断され加入が難しくなることがあります。
自閉症スペクトラム障害は生活自立度が判断基準になる
自閉症スペクトラム障害(ASD)は症状の幅が広く、加入可否は生活自立度に左右されます。
保険会社が好意的に判断しやすい条件は次のとおりです。
- 自立して通勤・通学ができる
- 金銭管理や契約内容の理解ができる
- 他者とのトラブルや事故が少ない
一方、日常生活全般に支援が必要な場合は一般の生命保険は難しく、障害者向け保険や共済のほうが現実的です。
ダウン症や先天性難聴は加入できる保険が限られる
ダウン症や先天性難聴は、生まれつきの状態として告知が必要であり、一般的な生命保険では加入が難しい傾向にあります。
加入が見込める商品には以下があります。
- 引受基準緩和型保険
- 無選択型保険
- 障害者向け共済(障害者扶養共済など)
学資保険や、契約者を親に設定できる保険であれば、被保険者が障害を持っていても加入できる場合があります。
てんかんや精神障害者保健福祉手帳保有者は条件付きで加入可能
てんかんや精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は、加入できる保険が限定されるものの、条件付きで契約できる可能性があります。
加入しやすい条件は以下のとおりです。
- 発作が一定期間(例:2年以上)起きていない
- 服薬が安定している
- 直近5年以内に入院歴がない
ただし、手帳の等級や発作頻度によっては、保険金額や保障内容に制限が設けられる場合があります。

【保険の種類別】発達障害(ADHD)の加入可否

発達障害の種類だけでなく、保険の種類によっても審査基準が異なります。
ここからは、主要な保険ごとの加入可否の目安を解説します。
医療保険は入院や手術リスクが高いと加入できない
医療保険は、入院や手術に伴う給付金支払いのリスクが高いと判断されると契約できません。
発達障害(ADHD)の場合、審査で不利になりやすい条件は以下のとおりです。
- 過去に精神科や心療内科で入院歴がある
- 事故やケガによる通院・入院が複数回ある
- てんかんやパニック発作の既往歴がある
告知書では診断名や治療内容、服薬期間、日常生活の制限まで詳しく記載します。ここから入院リスクが高いと判断されれば、契約不可や条件付き契約になることがあります。

がん保険は発達障害と直接関係がないため加入しやすい
がん保険は、発達障害の有無が直接的な加入可否に影響することはほとんどありません。
主な告知内容は以下のようにがんに関する既往歴や検査結果に限られるためです。
- 過去にがんと診断されたことがあるか
- 最近3か月以内に診察・検査・治療を受けたか
- 健診や人間ドックで異常を指摘されたか
そのため、ADHDやASD、学習障害などの発達障害があっても、がん保険に加入できる可能性は高いです。ただし、がん以外の重大疾患(心疾患や脳疾患など)の既往がある場合は別途審査が行われます。

学資保険は親が契約者なら子供の障害有無は問われない
学資保険は、契約者である親の健康状態や告知内容が審査の対象です。
子供が被保険者であっても、以下のような形であれば、子供の発達障害や障害手帳の有無は審査に含まれないことが多いです。
- 親が契約者になる
- 親が保険料を支払う
ただし、商品によっては子供の加入年齢や健康条件が設定されている場合があるため、事前確認が必要です。
学資保険の必要性が気になる方は以下の記事も参考にしてください。

死亡保険は事故リスクや症状安定性が審査に関わる
死亡保険は、被保険者の死亡リスクが高いと判断されると加入が難しくなります。
ADHDの場合、以下の点が審査で考慮されます。
- 衝動性や不注意による事故リスク
- 精神的な不安定さによる自傷や自殺のリスク
- 医療歴や服薬の安定度
一方、症状が安定し、就業や生活が自立していれば死亡保険に加入できる場合もあります。
死亡保険や生命保険の必要性が気になる方は以下の記事も参考にしてください。

所得保障保険は就業不能条件を満たせば加入できる可能性あり
所得保障保険は、病気やケガで働けなくなった場合の収入減少を補う保険です。
発達障害があっても、次の条件を満たせば加入できることがあります。
- 正社員や契約社員として継続的に就業している
- 過去数年間に就業不能状態がない
- 症状が安定し、職場での勤務継続が可能
ただし、精神疾患や神経系疾患を支払い対象外とする商品もあるため、約款を必ず確認しましょう。
団体長期障害所得保障保険について気になる方は、以下の記事も参考にしてください。
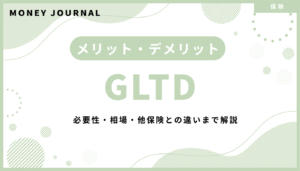
特定疾病一時金保険は加入条件が保険会社ごとに異なる
特定疾病一時金保険は、がん・心疾患・脳疾患などの重大疾病にかかったときに一時金が支払われる保険です。
発達障害自体が加入制限になることは少ないですが、健康状態や既往歴によって判断が分かれます。
- 発達障害以外に持病がない→加入できる可能性が高い
- 重大疾病の診断や治療歴がある→加入不可の可能性が高い
対象疾病や告知項目は保険会社によって異なるため、複数社を比較して条件の合う商品を探すことが重要です。
生命保険の必要性について気になる方は、以下の記事も参考にしてください。

発達障害(ADHD)でも加入しやすい生命保険・共済一覧

発達障害や知的障害があっても、条件を満たせば加入できる保険や共済は存在します。
特徴としては、契約者を親に設定できる商品や、診査や告知が簡易なプラン、障害児向けに設計されたコースなどです。
ここからは、発達障害があっても比較的ハードルが低く、保障を確保しやすい保険・共済を紹介します。
低解約型終身保険は契約者が親なら障害児でも加入可能
低解約型終身保険は、払込期間中の解約返戻金を抑える代わりに保険料を割安にした終身型の生命保険です。
発達障害や知的障害がある子どもでも、契約者を親に設定すれば、被保険者である子どもの健康状態が審査対象外になる商品があります。
具体的には以下のとおりです。
- 将来の死亡保障や長期貯蓄に活用可能
- 払込期間終了後は解約返戻金が増加し、教育費・生活資金・結婚資金などに充当できる
- 子どもが社会参加を始める前に契約しておくと、後年の保険加入制限の影響を受けにくい
ただし、保険会社によっては子どもの健康告知を求めることもあるため、契約前に必ず確認しましょう。
終身保険については以下の記事で詳しく解説しています。

コープ共済は条件を満たせば障害児向けプランに入れる
コープ共済の「たすけあいジュニアコース」は、障害児でも加入できる可能性があります。加入を断られるのは、現在入院中、または直近1年以内に入院や手術予定がある場合などです。
- 障害の有無よりも現在の健康状態を重視
- 満期後は健康状態に関係なく一般コースへ移行可能
- 掛金が1,000円~と安く、入院・手術・通院をカバーできる
参考:co-op共済「《たすけあい》ジュニアコース」
条件を満たせば、発達障害や軽度の知的障害がある子どもでも、低負担で医療保障を確保できます。
こくみん共済保険は医師の診査不要で加入できる場合がある
こくみん共済(全労済)は、掛金が一定で分かりやすい保障が特徴です。医師の診査を不要とするプランもあり、発達障害や軽度の知的障害があっても加入できる可能性があります。
- 年齢と告知内容だけで加入可否を判断する商品がある
- シンプルな保障で低コスト
- 怪我・病気の入院保障に加え死亡保障もセット可能
ただし、障害の程度や他の病歴によっては加入が難しい場合もあるため、事前に共済組合へ確認することが大切です。
こくみん共済については以下の記事で詳しく解説しています。

都道府県民共済は掛金が安く障害児型保障がある
都道府県民共済は、各地域の生協が運営する非営利型共済で、掛金の安さとシンプルな保障内容が魅力です。
子ども向けプランの中には、発達障害や知的障害を持つ子どもでも加入できる障害児型保障が用意されている地域があります。
- 月1,000円程度から入院・死亡・賠償責任の保障が付く
- 割戻金制度により、実質負担額がさらに軽くなることもある
- 障害児でも加入可能なプランが存在
加入条件や保障内容は都道府県や共済組合ごとに異なるため、申し込み前に地域の共済窓口で条件を必ず確認しましょう。
障害者扶養共済は親亡き後の生活費を年金形式で支給
障害者扶養共済は自治体が運営する公的制度で、障害のある子を持つ親が掛金を払い続けることで、親が亡くなった後に子へ終身年金が支給されます。
民間保険ではカバーが難しい「親亡き後の生活費」を確保できるのが特徴です。
- 1口につき月額2万円の終身年金を支給
- 掛金は加入時年齢で決定(35歳未満なら月9,300円〜)
- 所得税や住民税の控除対象
参考:厚生労働省「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」
親の死亡や重度障害発生時から年金が支給されるため、長期的な生活基盤の確保に役立ちます。
かんぽ生命は健康状態によって加入できる場合がある
かんぽ生命には、健康告知型と引受基準緩和型の両方の商品があり、発達障害や持病があっても条件次第で加入できる可能性があります。
- 郵便局窓口で相談可能
- 学資保険・終身保険など幅広い商品を扱う
- 健康状態や病歴を踏まえて最適なプランを提案してもらえる
加入可否は面談や書類審査で判断されるため、障害の程度を正確に伝えることが大切です。

発達障害(ADHD)で生命保険に加入する際の注意点

発達障害がある方が生命保険へ加入する場合、審査~契約の過程で見落としがちなポイントがあります。
ここでは、加入前に必ず意識しておきたい3つの注意点を解説します。
健康状態・診断歴・服薬内容は正確に告知する
生命保険の加入時には、告知書に過去の診断名や通院歴、服薬状況などを正しく記載する義務があります。
発達障害に関する告知で必要な情報は以下のとおりです。
- 診断名(例:ADHD、注意欠陥障害、自閉症スペクトラム障害など)
- 診断日と診断を受けた医療機関名
- 現在の通院有無と頻度(例:月1回精神科通院)
- 服薬名と服薬期間(例:コンサータを1年間服用中)
- 過去5年間の入院や手術の有無
「軽度だから申告しなくていい」という自己判断は危険です。告知義務違反となれば契約解除や保険金不払いの恐れがあります。医師の診断書や薬手帳を用意し、事実に基づいて記入しましょう。
保険期間は将来の保障ニーズに合わせて設定する
発達障害のある方は、今後の就労状況や生活環境が変化する可能性があります。保険期間はライフステージに応じた保障ニーズに合わせて決めましょう。
- 子育て中→子どもが独立するまでの期間をカバーする定期保険
- 長期の生活保障→一生涯保障の終身保険
- 親亡き後の生活費→障害者扶養共済や終身型死亡保険
期間を長くすれば安心ですが保険料は増えます。短すぎると保障切れのリスクがあります。加入前に将来の生活設計や収入見込みを考え、無理のない期間設定を行いましょう。
保障金額は生活費や医療費を基準に決定する
生命保険の保障額は「万が一のとき、残された家族がどれくらいの期間生活できるか」を基準に決める必要があります。
発達障害のある方やその家族の場合、一般的な家庭よりも支援費用がかかりやすいため、金額設定は丁寧な試算が必要です。
- 生活費:毎月の生活費×保障したい年数
- 医療費・療育費:年間医療費×予想年数
- 教育費(子どもがいる場合):高校・大学進学費用の総額
- 住宅ローン残債(ある場合)
過大な保障額は保険料負担が大きく、生活を圧迫します。反対に不足すれば家計が破綻しかねません。将来の支出を具体的に試算してから決めましょう。

発達障害(ADHD)を抱える人の生命保険加入の流れ

発達障害があっても、条件次第では生命保険へ加入できる可能性は十分あります。
ただし、一般的な申込手順に加え、診断歴や健康状態に関する確認事項が多く、準備不足だと審査が長引いたり加入できない場合もあります。
ここでは、加入準備から契約後の管理までを4つのステップに分けて解説します。
加入しやすい保険を複数社から探す
発達障害(ADHD)の有無や症状の程度によって、加入できる保険は大きく変わります。
1社だけに絞るのではなく、複数の保険会社や共済を比較することが重要です。
保険商品を探す際の主な方法は以下のとおりです。
- 保険代理店やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談する
- 障害者向け・引受基準緩和型・無選択型保険を扱う会社を調べる
- コープ共済や都道府県民共済など、障害児向けプランを提供する共済を確認する
「告知不要」「医師の診査なし」といった条件の商品は、加入ハードルが低い傾向があります。
告知項目と必要書類を事前に確認する
申込書を書く前に、何を質問されるのか、どの書類が必要なのかを把握しておきましょう。
よく求められる告知内容は以下のとおりです。
- 診断名と診断日(例:ADHD、2019年4月診断)
- 現在の治療内容と通院頻度(例:月1回精神科)
- 服薬名と服薬開始日(例:コンサータ、2021年5月~)
- 過去5~10年の入院歴・手術歴
- 障害手帳や精神障害者保健福祉手帳の有無
また、必要書類としてよく求められるものは以下のとおりです。
- 医師の診断書
- 薬手帳や処方箋
- 療育手帳や障害者手帳のコピー
事前準備をしておくことで、告知漏れや記入ミスによる審査遅延を防げます。
契約手続きを完了させる
保険内容・保険料・告知内容に間違いがないかを確認したうえで、契約手続きを進めます。
- ネット申し込みの場合:入力内容をスクリーンショットで保存
- 対面申し込みの場合:営業担当者に控えをもらう
審査期間は数日~数週間が目安です。引受基準緩和型や無選択型は比較的早いですが、診断書提出が必要な場合は1か月以上かかることもあります。加入を急ぐ場合は余裕をもって申し込みましょう。
保険証券を安全な場所に保管する
契約成立後、保険証券は紛失や災害に備えて安全に保管します。
保険証券のおすすめの保管方法は以下のとおりです。
- 防火・防水対応の書類ケース
- 家族がわかる場所(重要書類フォルダ)
- デジタルコピーをクラウドに保存(紛失・災害時対策)
保険金請求は本人だけでなく家族が行う場合もあります。障害児や療育中の子どもが被保険者の場合は、将来の受取人となる家族が契約内容と保管場所を確実に把握しておくことが大切です。
4つの手順を紹介しましたが、「実際にどの保険が自分に合うのか」「告知内容をどうまとめればいいのか」に悩む方も多いはずです。
特に発達障害(ADHD)を抱える場合は要件が複雑になりやすく、個人での情報収集には時間も手間もかかります。
こうしたときは、オンラインで相談できるマネーコーチの無料家計診断を活用するのがおすすめです。
スマホやPCから30秒で予約でき、全国どこからでも相談可能なので、まずは気軽に利用してみてはいかがでしょうか。
発達障害(ADHD)で生命保険に入れない場合の代替策

発達障害(ADHD)で生命保険に入れない場合の代替策は以下のとおりです。
引受基準緩和型・無選択型保険で保障を確保する
引受基準緩和型保険は、告知項目が2~5項目程度と少なく、通院や服薬中でも加入できる可能性が高い商品です。
無選択型保険は告知や診査が不要で、健康状態に関係なく加入可能です。
ただし、以下のようなデメリットがあります。
- 保険料が割高
- 契約後90日程度の免責期間あり
利用する際は、死亡保険金や医療給付額を必要最低限に設定し、保険料負担を抑えることがポイントです。
健康保険証提示で診療費の自己負担割合を下げる
日本の公的医療保険に加入していれば、病院・薬局で健康保険証を提示することで医療費の自己負担は原則3割(6歳未満は2割)になります。
高額な検査や入院が必要な場合でも、この制度が基盤となり負担を軽減できます。まずは公的医療保険の適用範囲を正しく理解し、日常的な医療費を確実に抑えていきましょう。
自立支援医療制度で精神科・療育の通院費を軽減する
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患や発達障害のある人を対象に、通院医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です。
対象となる治療例は以下のとおりです。
- 精神科・心療内科の診療
- ADHD治療薬(コンサータ、ストラテラなど)の処方
- 療育機関での指導
自立支援医療制度を利用するには、市区町村の福祉窓口で申請し、医師の診断書を提出します。通院が長期化しやすい発達障害の方にとって負担軽減効果の大きい制度です。
高額療養費制度で月ごとの医療費上限を抑える
高額療養費制度は、1か月の医療費が高額になった場合に自己負担額を一定の上限まで抑え、超過分を払い戻す制度です。
上限額は所得によって異なります。
長期入院や高額手術では家計への負担を軽減できます。申請は加入している健康保険組合や協会けんぽに行います。
あらかじめ「限度額適用認定証」を取得しておくと、支払い時点から上限額での精算が可能です。
傷病手当金で就業不能時の収入を補う
会社員や公務員など健康保険に加入している人は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合、最長1年6か月間、標準報酬日額の約3分の2が支給されます。
申請には、医師の意見書と事業主の証明が必要です。収入減で生活が不安定になるのを防ぐため、勤務継続が難しいときは早めに申請準備を始めましょう。
子ども医療費助成制度で18歳までの医療費を軽減する
多くの自治体では、0歳〜18歳までの子どもを対象に、通院や入院の自己負担分を全額または一部助成しています。発達障害のある子どもも対象で、療育や通院費の軽減に役立ちます。
医療費が高額になりがちな家庭ほど、早めの申請がおすすめです。
就職時の団体保険・企業共済で保障を追加する
正社員や契約社員として就職すると、勤務先を通じて団体生命保険や企業共済に加入できる場合があります。
企業共済では、病気や障害に関係なく一定額の弔慰金や入院給付金を受け取れる制度も。就職時には福利厚生制度の内容を確認し、必要に応じて活用すると保障を手厚くできるでしょう。

発達障害(ADHD)の生命保険加入に関するよくある質問

発達障害(ADHD)の生命保険加入に関するよくある質問と回答は以下のとおりです。
- 自分をADHDと思い込んでいるだけでも告知は必要?
- ADHDの診断テストは何科に行けば受けられる?
- 発達障害があっても病院行くべきか迷った場合の判断基準は?
- 子供の症状を保険会社はどこまで見抜く?
- 障害手帳がないと入れない保険はある?
- 症状が軽度でも将来の加入制限はある?
- 保険加入の申請でよく聞かれる質問や答え方は?
- 大人になってからADHDと診断された場合の加入可否は?
- 知的障害者でも加入できる生命保険はある?
- 障害児でも入れる保険にはどんな種類がある?
自分をADHDと思い込んでいるだけでも告知は必要?
医師の診断を受けていない場合は、診断名そのものを告知する必要はありません。
ただし、保険会社の告知項目に「過去○年以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがあるか」という質問があれば、症状の有無に関係なく受診歴や服薬歴は正確に記載する必要があります。
未診断であっても、ADHD治療薬や精神科通院歴がある場合は、それらの事実を告知しないと告知義務違反となるリスクがあります。
ADHDの診断テストは何科に行けばいい?
ADHDの正式な診断は、精神科・心療内科・発達障害外来(小児科や児童精神科)で受けられます。
子どもの場合は児童発達支援センターや療育センターが入り口になることもあります。
- CAARS(Conners’ Adult ADHD Rating Scales)成人向け
- WISC-Ⅳ(知能検査、子ども向け)
- ADHD-RS(症状評価スケール)
診断には複数回の面談や行動観察、心理検査が必要です。
発達障害があっても病院行くべきか迷った場合の判断基準は?
以下のいずれかに該当する場合は受診を検討すべきです。
- 学校や職場での注意欠如や衝動性により生活に支障が出ている
- 集中力低下や衝動行動で人間関係トラブルが増えている
- 不眠や抑うつなど二次障害が出ている
受診によって、薬物療法やカウンセリング、療育支援が受けられるほか、診断書を取得することで保険や福祉制度の利用がスムーズに進みます。
子供の症状を保険会社はどこまで見抜く?
保険会社は診断書・通院歴・薬の処方歴をもとに審査します。医療機関名や診療科目が保険会社に通知されることはありませんが、告知書の記載内容や加入時の面談で確認されることがあります。
虚偽の申告が発覚すると、契約解除や保険金不払いのリスクがあるため、事実は正確に告知することが重要です。
障害手帳がないと入れない保険はある?
多くの一般的な生命保険や医療保険は、障害者手帳の有無ではなく健康状態や診断歴で審査します。
ただし、一部の障害者向け共済や公的制度型保険は、障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の所持を加入条件にしている場合があります。
症状が軽度でも将来の加入制限はある?
軽度でも診断や通院歴があれば、将来的に告知が必要な条件に該当する可能性があります。例えば、加入時に「過去5年以内の精神疾患の診断歴」を問う保険では、数年前の軽度ADHD診断も審査対象になります。
一方で、発症から長期間経過し、治療や通院が終了している場合は、条件付き承諾や通常加入が可能になることもあります。
保険加入の申請でよく聞かれる質問や答え方は?
よくある告知・質問項目と回答のポイントは以下のとおりです。
| 質問例 | 回答のポイント |
|---|---|
| 過去5年以内に医師から診断を受けましたか? | 診断名・診断日を正確に記載 |
| 現在治療・服薬中ですか? | 薬の名称・用量・開始時期を記載 |
| 日常生活に支障はありますか? | 就業・通学状況、生活支援の有無を事実に基づき記載 |
| 入院や手術歴はありますか? | 発達障害に関連する入院歴も含めて回答 |
ポイントは、医師の診断書や薬の処方記録など客観的資料を基に正確に記入することです。
大人になってからADHDと診断された場合の加入可否は?
大人になってからADHDと診断された場合でも、加入可能な保険はあります。告知義務はありますが、発症から時間が経ち症状が安定していれば、審査が通ることもあるでしょう。
加入を目指すなら、通院状況や服薬内容を正確に記録し、安定していることを証明できる状態で申し込むと有利です。
知的障害者でも加入できる生命保険はある?
知的障害者でも加入できる保険は存在します。たとえば、告知項目が限定されている「引受基準緩和型保険」や、一部の共済商品が該当します。
契約者を親にすることで被保険者の健康告知が不要になる場合もあり、条件次第では加入が可能です。各社の条件や告知範囲を比較して選ぶことをおすすめします。
障害児でも入れる保険にはどんな種類がある?
障害児でも入れる保険には、共済型保険や低解約返戻金型終身保険などがあります。共済は告知が簡易な場合が多く、終身型は契約者を親にすることで子どもの診断歴を問われない商品もあります。
教育費や将来の生活資金を備える手段として有効ですが、加入条件や補償内容は商品ごとに大きく異なるため、必ず複数社を比較しましょう。
まとめ:発達障害(ADHD)でも条件を満たせば生命保険加入は可能
この記事では、発達障害(ADHD)やグレーゾーンの方が生命保険に加入する際の条件や注意点、加入しやすい保険の種類を解説しました。
症状が安定していて生活自立度が高ければ、一般の生命保険に加入できる可能性は十分あります。逆に重度で日常生活に介助が必要な場合は、以下のような選択肢が現実的です。
- 引受基準緩和型や無選択型の保険
- 障害者扶養共済や障害児向け共済
- 契約者を親に設定する低解約型終身保険
万が一に備えた保障は、家族の安心にもつながります。条件に合う保険を複数比較し、迷ったら専門家に相談して、自分と家族の将来を守ってください。