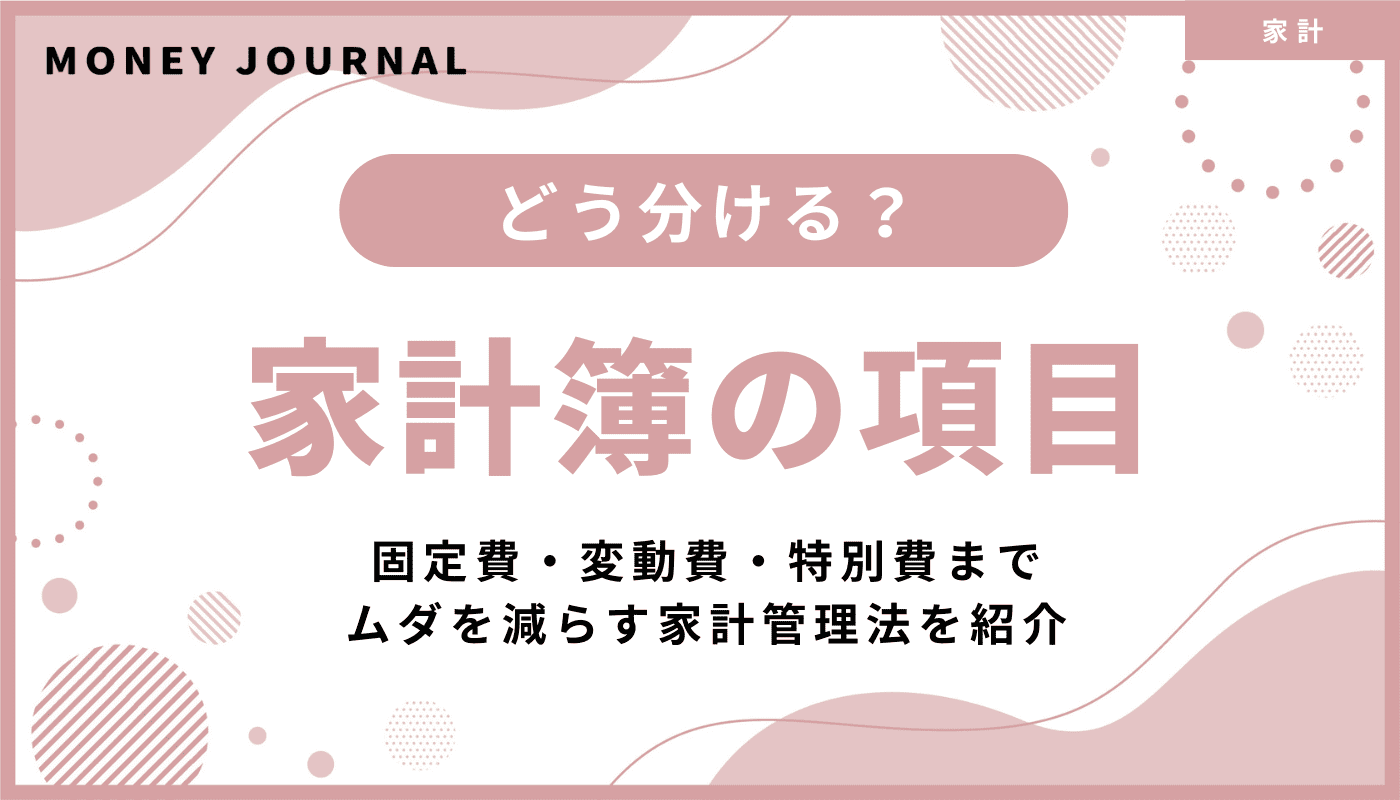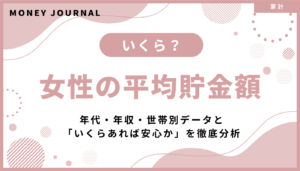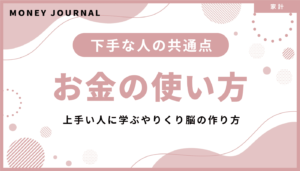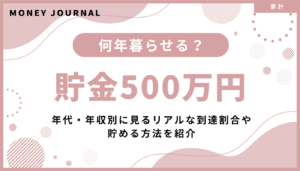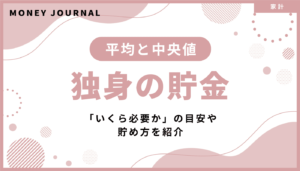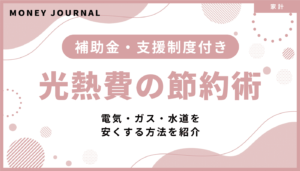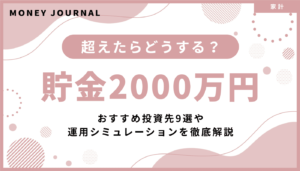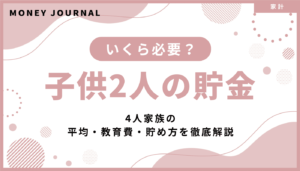- 「家計簿をつけても、どの項目に入れればいいかわからない」
- 「固定費と変動費の違いがあいまいで、毎月の整理がむずかしい」
- 「途中で面倒になって、家計簿を放置してしまった」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、家計簿の項目は 「固定費」「変動費」「特別費」 の3つに分けるだけで十分です。
| 分類 | 主な内容 | 管理のコツ |
|---|---|---|
| 固定費 | 家賃・通信費・保険料・サブスク(定額サービス)など | 一度見直すと効果が長く続く |
| 変動費 | 食費・日用品・交際費・交通費など | 週ごとの予算設定が効果的 |
| 特別費 | 冠婚葬祭・旅行・家電購入など | 年間計画に組み込んで準備する |
本記事では、家計簿の基本項目から目的別の分け方、続けるコツまでを解説します。
何に使ったかわからないお金を減らしたい方は、ぜひ参考にしてください。
- 自分に合った家計簿項目の決め方
- 固定費・変動費・特別費の上手な分類法
- 挫折しない家計簿の続け方
- 家計簿アプリ・ノート・Excelの使い分け
- 項目を整理して貯金を増やすコツ
家計簿の基本項目一覧|固定費・変動費・特別費の内訳

家計簿を正しくつけるために、支出の性質を理解することから始めましょう。お金の流れを3つに整理すると、どこにムダが潜んでいるかが自然と見えてきます。
家計管理で使われる主な区分は次の3つです。
| 分類 | 特徴 | 管理の目的 |
|---|---|---|
| 固定費 | 毎月ほぼ同じ金額で発生する支出 | 継続コストの見直し |
| 変動費 | 月ごとに金額が変わる支出 | 無駄遣いのコントロール |
| 特別費 | 不定期に発生する支出 | 年間予算の備え |
以下では、それぞれ詳しく解説します。
固定費:住居費/通信費/保険料/光熱費など
固定費とは、毎月またはほぼ毎月、決まった金額で発生する支出のことです。家計の土台となる部分であり、見直しを行うと大きな節約効果を得られます。
主な項目は次のとおりです。
| 費目 | 具体例 |
|---|---|
| 住居費 | 家賃・住宅ローン・駐車場代 |
| 通信費 | スマートフォン・インターネット・固定電話 |
| 保険料 | 生命保険・医療保険・介護保険など |
| 光熱費 | 電気・ガス・水道の基本料金や平均的な使用額 |
電気代やガス代のように月ごとに多少変動する支出でも、契約プランや平均額がほぼ一定なら固定費に含めて問題ありません。そのうえで、使っていないサブスク(定額サービス)や高すぎる通信プランを見直せば、生活の質を落とさずに家計を引き締められます。
変動費:食費/日用品費/交通費/美容費/交際費など
変動費とは、生活の仕方や使い方によって金額が毎月変わる支出のことです。家計の中でもコントロールしやすく、節約効果を実感しやすい部分です。
主な項目は次のとおりです。
| 費目 | 具体例 |
|---|---|
| 食費 | 自炊用の食材・外食・お酒・お菓子など |
| 日用品費 | ティッシュ・洗剤・シャンプーなどの消耗品 |
| 交通費 | 電車・バス・ガソリン・駐車場代など |
| 美容費 | 化粧品・美容院・服・アクセサリーなど |
| 交際費 | 飲み会・プレゼント・お祝いごとなど |
変動費は、使い方次第で結果が変わる支出です。ただし、項目を細かく分けすぎると記録が面倒になり、家計簿が続かなくなることがあります。
特別費:冠婚葬祭/旅行/家電購入/イベント費など
特別費とは、毎月は発生しないが、年に数回まとまって発生する支出のことです。冠婚葬祭や旅行、家電の買い替えなどが代表的で、想定外の出費として家計を圧迫しやすい項目です。
主な内容を整理すると次のとおりです。
| 費目 | 具体例 |
|---|---|
| 冠婚葬祭 | 結婚式のご祝儀・香典・法事・帰省費など |
| 旅行 | 家族旅行・帰省・レジャー費 |
| 家電購入・修繕 | 冷蔵庫・エアコン・テレビ・パソコンなど |
| イベント費 | 記念日・誕生日・趣味イベントなど |
特別費は金額の差が大きいため、年間でどのくらい発生するかをあらかじめ見積もることが大切です。たとえば、「冠婚葬祭10万円」「旅行15万円」などのように、年間の目安金額を出しておくと管理がしやすくなります。

家計簿をつけることでわかる2つのこと

家計簿をつけることで、家計の状況がわかり、自分がすべきことが理解できます。家計簿をつけることでわかることは主に以下の2つです。
それぞれ詳細に解説します。
①収支の状況
家計簿を使ってお金の管理をすることで、収支の状況がわかるようになります。まず、毎月どこからお金が入ってくるのかをはっきりさせられます。
お金が入ってくるところには会社の給料や副業収入、資産運用の利益などさまざまです。いろいろなところからお金が入ってくる場合でも、どこからいくら、何日に入っているのかをきちんと把握できます。
食費や光熱費、家賃などと項目にわけて書くと、より見やすくなります。家計簿をつけるとお金の出入りを明確にでき、無駄な出費を減らし、地道に貯金ができます。
②収支の改善点
家計簿をつけることで、収支の改善点を見抜けるようになります。たとえば、通信費が1万円を超えていて高すぎることや食費費がかさんでいるなどと、調整すべき項目がわかります。
各種保険にお金を支払いすぎている、支出に対する浪費の割合が高いなどの見直しポイントにも気づけるでしょう。見直すべきポイントがわかるとすぐに調整できるため、お金を貯める速度を上げられるのがメリットです。

お金が貯まる家計簿のつけ方とは

お金を貯められる家計簿の作り方の手順は、下記のとおりです。
3つの手順について、具体的にチェックしていきましょう。
①費目を3つに分けて予算を決める
貯蓄を意識した家計簿をつける際、まずは費目を決めましょう。費目とは使途で分類した費用の名目のことであり、ここでは貯蓄・固定費・変動費の3つに分けます。支出を内容に応じて分けることで、常に「ほかの費目と比較して多かったか」と支出の振り返りが可能になります。
貯蓄・固定費・変動費についてくわしく見ていきましょう。
貯蓄
家計簿をつける際、食費や水道光熱費といった費目を真っ先に思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、固定費や変動費を先に確保し、残ったお金を貯蓄に回すという方法ではなかなかお金は貯まりません。
そのため、まずは毎月どれくらい貯蓄するかを考え、残りの金額でやりくりする方法を取り入れることで貯蓄スピードをアップさせることが可能です。
固定費
固定費は、毎月同じ金額を支払う必要がある費用を指します。
一般的な固定費は以下の通りです。
- 住居費
- 保険料
- 給食費
- 新聞代
- 習い事の月謝
変動費
変動費に分類される費用は、固定費以外の支出です。
- 水道光熱費
- 通信費
- 食費
- 病院代
- 交際費
病院代や交際費のように、毎月必要でない費用であっても、あらかじめ月間予算として割り振っておくことで貯蓄を切り崩す必要がなくなります。
②家計簿をつける手段を選ぶ
家計簿の手段には、下記の3つがあります。
- 家計簿アプリ
- 家計簿ノート
- Excel
それぞれの手段について、具体的に解説します。
家計簿アプリ
手段の1つ目は、家計簿アプリを使って行う方法です。iPhoneとAndroidともに、さまざまな家計簿アプリが登場しています。
App StoreまたはGoogle Playで「家計簿」と検索すると、多数のアプリの検索が可能です。デザインや機能などアプリごとに特色があり、なかには家族や恋人と共有できる機能がついたものもあります。
家計簿ノート
家計簿の定番の手段は、普通のノートを活用する方法です。お店でお気に入りのノートを購入して、自分で自由にアレンジして家計簿を作ります。
家計簿アプリと異なり、項目やデザイン、表なども思い通りに作成できます。また、お気に入りのノートが見つかれば、モチベーションアップにつながり継続しやすいのがメリットです。
デメリットとしては、記入前までの下準備に時間がかかることです。項目や表を作るのが億劫な場合は、すでにある程度のデザインが記入されている家計簿ノートを購入するといいでしょう。
Excel(エクセル)
Excelは仕事の資料作りで使われるイメージがありますが、家計簿として使うこともできます。
Excelを使うメリットは、関数を使えるので、自分で細かい計算をする必要がなくなることです。一方で、Excelを使わない人にとっては操作がややこしく、Excelソフトは有料な点がデメリットでしょう。
③支出内容を改善する
実際に家計簿をつけると、記録したお金の流れが確認でき、支出内容の改善点が見つかります。お金の出入りを可視化しても、使い方を調整していかなければ何も変わりません。
固定費・変動費・貯蓄のそれぞれの項目ごとに、お金がどのように出ていったのかを振り返ってみてください。たとえば、予算を超えて使っている場合、予算を超えた原因を探って対策を考えたり、項目ごとの予算を変えたりするといいです。

【目的別】自分に合った家計簿項目の決め方

ここでは、目的別におすすめの家計簿の構成について紹介します。
お金の流れをざっくり把握したい人向けの項目
「細かくつけるのが苦手」「まずはお金の動きを見えるようにしたい」という人に向いているのが、シンプルな5項目構成です。
項目を少なくまとめると、お金の流れ全体を一目で把握できるのがメリットです。
たとえば、次のような構成がおすすめです。
| 項目名 | 内容の例 |
|---|---|
| 固定費 | 住居費・光熱費・通信費などをひとまとめ |
| 食費 | 自炊・外食・飲料など食に関する支出 |
| 日用品・雑費 | 洗剤・トイレットペーパーなどの消耗品 |
| 特別費 | 旅行・冠婚葬祭・家電購入など |
| その他 | 上記に当てはまらない支出 |
まずは家計簿を続けることに意識を向けましょう。慣れてきたら、食費を「自炊」と「外食」に分けるなど、少しずつ細分化して精度を高めるのがおすすめです。
節約・貯金をしたい人向けの項目
節約や貯金を目的にする場合は、支出の多い部分を細かく分けることが効果的です。どこにお金が流れているかを明確にすると、見直すべきポイントがすぐにわかります。
支出を細かく分類するときの基本構成は次のとおりです。
| 項目名 | 内容の例 |
|---|---|
| 固定費 | 住居費・通信費・保険料・光熱費など |
| 食費(自炊) | 食材・調味料など家庭での食事費用 |
| 食費(外食) | 外食・テイクアウト・カフェ代など |
| 日用品費 | 消耗品・生活雑貨など |
| 美容・被服費 | 美容院・化粧品・洋服・アクセサリーなど |
| 交際費 | 飲み会・プレゼント・お祝い関連 |
| 特別費 | 家電の買い替え・旅行などの大型支出 |
変動費は、何を減らすかよりもどのくらい使うかを意識して予算を立てることが大切です。記録が複雑になりすぎない範囲で、支出を細かく整理していきましょう。
夫婦・家族で共有したい人向けの項目
夫婦や家族で家計簿を共有する場合は、誰がどの支出を担当するかをはっきり決めることが大切です。共通費用と個人費用を分けて記録すると、トラブルを防ぎながら貯金計画を立てやすくなります。
代表的な項目と管理方法をまとめました。
| 分類 | 管理方法・内容の例 |
|---|---|
| 共有費用 | 住居費・光熱費・通信費などは共通口座から支払う |
| 担当別費用 | 食費・日用品費などを夫婦で分担して記録する |
| 個人費用 | 美容費・趣味費・交際費などはそれぞれが管理する |
| 口座構成 | 共通口座と個人口座を分ける、または費目ごとに担当口座を決める |
家計をオープンにすることで、お金に対する考え方の違いを減らし、無理のない貯蓄ペースを築けます。「2人で貯める」という意識が生まれれば、家計管理も自然と続けやすくなるでしょう。
一人暮らし・独身者向けの項目
一人暮らしの家計簿では、できるだけシンプルに続けることが大切です。家計調査によると、単身世帯で支出の多くを占めるのは食費・住居費・光熱費・通信費です。
そのため、生活に直結する支出を中心に、5〜6項目に整理すると無理なく管理できます。
おすすめの分類例は次のとおりです。
| 項目名 | 内容の例 |
|---|---|
| 住居費 | 家賃・管理費・駐車場代など |
| 光熱費 | 電気・ガス・水道など |
| 通信費 | スマートフォン・インターネットなど |
| 食費 | 自炊・外食・飲料など |
| 日用品費 | 消耗品・洗剤・衛生用品など |
| 娯楽・交際費 | 趣味・友人との食事・お小遣いなど |
収支が安定してきたら、食費を「自炊」と「外食」に分けるなど、細かく管理するステップアップも効果的です。少しずつ自分に合ったルールをつくり、無理のない家計管理を続けていきましょう。
夫婦二人・子どものいない家庭向けの項目
夫婦二人の家庭では、生活費を共有しながらも、価値観やお金の使い方に違いがあることが多いです。そのため、共通費と個人費を分けて管理する設計にすると、家計を整理しやすくなります。
共通費は生活を維持するための支出、個人費はそれぞれが自由に使うお金として区別します。
次の表は、具体的な構成例です。
| 分類 | 項目名 | 内容の例 |
|---|---|---|
| 共通費 | 住居費・光熱費・通信費・食費・日用品費 | 生活に必要な支出を共通口座で管理 |
| 個人費 | 交際費・美容費・趣味費など | 各自の財布で自由に管理 |
| 共有目標 | 貯蓄・旅行・特別費 | 二人で計画的に積み立てる費用 |
共働きの夫婦なら、共通口座をつくり「お互いが同額を入金し、その口座から共通費を支払う」仕組みにすると公平です。
お互いの支出を見える化して、納得できる分担ルールをつくることが大切です。
子どものいる家庭向けの項目
子どもがいる家庭では、教育費・習い事・学校行事など支出の種類が多くなるのが特徴です。そのため、家計簿に子ども費という項目を独立させると、支出の整理がしやすくなります。
全体の構成例は次のとおりです。
| 項目名 | 内容の例 |
|---|---|
| 住居費 | 家賃・住宅ローン・管理費など |
| 光熱費・通信費 | 電気・ガス・水道・スマートフォン・インターネットなど |
| 保険料 | 生命保険・医療保険など |
| 食費 | 家族全員の食費・外食・お弁当代など |
| 日用品費 | 生活雑貨・洗剤・衛生用品など |
| 子ども費 | 学費・習い事・教材・学校行事・衣服など |
| 美容・交際費 | 夫婦それぞれの支出 |
| 特別費 | 旅行・冠婚葬祭・大型家電など |
子ども費を明確に分けて管理すると、教育にどれだけお金を使っているかが一目でわかります。
大学生・若者向けの項目
大学生や若い世代は、収入の多くがアルバイトや仕送りに限られることが多く、出費も学費や教材費など独特の内容になります。そのため、勉強と生活の両方を整理できる家計簿の構成が向いています。
実践しやすい分類は次のとおりです。
| 項目名 | 内容の例 |
|---|---|
| 学費関連 | 授業料・教材費・検定料など |
| 交通費 | 通学・アルバイト・帰省の交通費 |
| 通信費 | スマートフォン・インターネット・アプリ課金など |
| 生活費 | 食費・日用品・家賃など |
| 交際・娯楽費 | 飲み会・映画・ライブ・旅行など |
| 学外活動費 | サークル費・資格講座・自己投資費など |
| 奨学金返済 | 借入額・返済予定額の記録 |
学生生活では、自由に使えるお金を「生活費」と「自己投資費」に分けて管理すると、使いすぎを防げます。

お金が貯まる家計簿をつけるための5つのポイント

お金を貯蓄していくのに家計簿を活用するポイントは以下の5つです。
目的を設定したり、自分に適した項目を作成したりするなどポイントを理解していると、お金が貯まる家計簿の作成ができます。
それぞれのポイントについて内容を見ていきましょう。
①家計簿をつける目的を決める
お金を貯めるためには、家計簿をつける目的を決めましょう。目的を決めるとモチベーションアップができ、家計簿をつけるのを継続しやすいです。
「友達と旅行するお金を10万円貯めるため」「両親の誕生日プレゼント費用に5万円貯めるため」などと目的を決めましょう。目的を決める際は、期限も合わせて定めておくといいです。
毎日の支出を記録しながら無駄な買い物をなくし、使い過ぎている項目を見直すなどして、貯金に回すお金を増やしていきましょう。
②家計簿をつけるタイミングを決定する
家計簿をつけるタイミングを決めておくのも大切で、つけ忘れを防いで習慣化しやすいです。
家計簿をつけるタイミングは、自分の生活スタイルに合わせて決めてみましょう。たとえば、朝起きてすぐにつけたり、仕事から帰ってきてからつけたりなどがあります。
毎日つけることが負担な方は、週末に1回、2週間に1回などにしてもいいです。重要なのは、長く続けることです。
家計簿をつけるタイミングを決めることは、お金を貯めるために欠かせない要素です。自分の生活スタイルや好みに合わせて、効果的なタイミングを見つけましょう。
③クレジットカードは使った月に記入する
家計簿をつける際に、クレジットカードの支払い記録を使った月に記入することが重要です。クレジットカードの支払いを使った月に記入することで、クレジットカードの請求がくる際に、利用を思い出せます。
クレジットカードの支払いは、買い物をしてから数カ月後に発生します。クレジットカードの支払いが発生する日のページに前もって、いくら請求があるか記入しておくのもおすすめです。
お金を増やすのに家計簿をうまく活用するためには、クレジットカードの記録タイミングも意識してみてください。
④自分の支出に合わせた項目を決める
家計簿をうまく活用するためには、自分の支出に合わせた項目を決めるのも大切です。自分の支出に合った項目を決めておくと、記入が楽になり続けやすくなります。
家計簿の項目にはルールはありません。自分の生活スタイルや好みに合わせた項目を考えることも1つの方法です。
たとえば、細かく記入したい場合は、家賃・通信費・保険料などと項目を細分化するのがおすすめです。細かくすると続かない気がする場合は、固定費・食費・医療費・その他生活費・雑費などと大まかに項目を決めましょう。家計簿の項目は、あとから少しずつ調整していくことも可能です。
⑤レシートを保管する
お金を貯めるために家計簿をうまく活用するためには、レシートを丁寧に保管することも大切です。レシートは、支出を記録する際に必要となるため必ず取っておきましょう。
レシートが1ヶ所にまとまっていないと、記録する準備だけで疲れてしまい、継続するのが難しいと感じる可能性があります。

家計簿を続けるコツ|挫折しない習慣化のポイント

家計簿は、完璧な記録を残すことよりも、支出の傾向を把握し、無駄を見つけることが目的です。ここでは、誰でも挫折せず続けられる3つのコツを紹介します。
完璧主義をやめる
家計簿を続けるいちばんのコツは、「完璧を目指さないこと」です。1円単位で正確に入力しようとすると、手間が増えて疲れてしまいます。最初のうちは「ざっくりでOK」と割り切ることが大切です。
実践しやすい考え方は次のとおりです。
- 記録漏れがあっても気にしない
- 数百円のズレは許容する
- 費目を細かく分けすぎない
- 思い出せない支出は「その他」にまとめる
大切なのは、お金の流れをおおまかに把握する習慣を続けることです。完璧さよりも、続けられる形を優先しましょう。
記録タイミングは週に1回で十分
「毎日つけないと意味がない」と思い込むと、家計簿は続きません。むしろ、週に1回まとめて入力する方が長く続けやすい方法です。自分の生活リズムに合わせて記録日を決めておくと、家計簿が自然に習慣になります。
たとえば、次のようなスケジュールがおすすめです。
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 日曜日の夜 | 1週間分のレシートをまとめて入力する |
| 平日夜 | 支出メモをスマートフォンに記録しておく |
| 月末 | 支出合計を確認し、来月の予算を決める |
週に1回でも続ければ、1年間で52回の振り返りができます。毎日入力するよりも現実的で、忙しい人でも無理なく続けられます。
可視化ツール(円グラフ・アプリ通知)でモチベーションを維持
家計簿を続けるために大切なのは、成果が見えることです。数字だけが並ぶ状態では達成感が得にくく、続ける意欲が下がってしまいます。
家計簿アプリやノートを使う場合は、次のような工夫がおすすめです。
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| アプリの円グラフ表示 | 支出の割合を一目で把握できる |
| 月ごとの比較グラフ | 節約の成果を数字で確認できる |
| 通知・目標達成率機能 | 継続するモチベーションを保てる |
| ノート+色ペンの可視化 | 手書きでも達成感を感じやすい |
アプリを使う場合は、「自動入力機能」や「家族との共有機能」が便利です。一方でノート派なら、支出ごとに色分けして簡単な円グラフを描く方法がおすすめです。
家計簿の項目に関するよくある質問
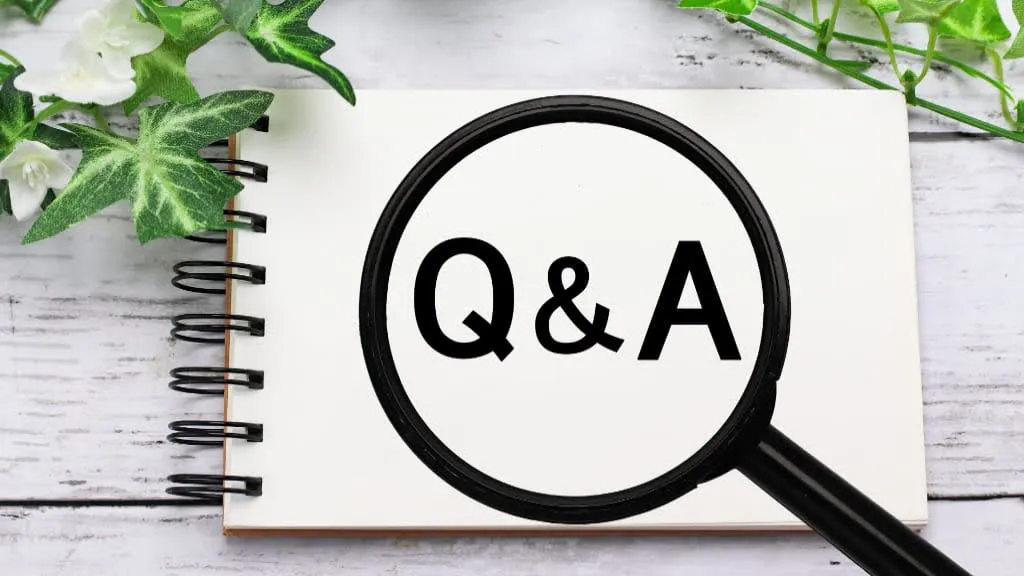
収支を把握するために始める家計簿は、利用しているとさまざまな疑問点が浮かんでくることがあるでしょう。ここでは代表的なの3つの疑問点をそれぞれ解説します。
- いつから始めると良い?
- 挫折しないためにどうすればいい?
- いつまで続けると良い?
- 家計簿の項目を細かくしすぎると続かない?
- 交際費はどう振り分ける?
- 美容費はどう振り分ける?
- 光熱費は固定費と変動費どちら?
- 特別費の予算はどう決める?
- 家計簿の分類はどうすればいい?
- 家計簿をシンプルにしたい場合のおすすめ項目は?
- 医療費や教育費はどのカテゴリに入れる?
- 生活費の中身はどこまで含めるべき?
- 家計簿の項目の分け方・付け方で迷ったときの考え方は?
- おすすめの家計簿項目の5項目構成は?
- 家計簿の科目(勘定科目)はどう決める?
- 家計簿のカテゴリ分けはどのくらい細かくすべき?
- 家計簿を手書きでつける場合のコツは?
- 家計簿を3つの項目でつけるならどうすればいい?
- 化粧品代は美容費に入れる?日用品費に入れる?
いつから始めると良い?
家計簿はいつ始めるべきかと悩む人がいますが、家計簿はいつ始めても良いと言われています。1月1日といったキリの良い日付を選ぶよりも、できるだけ早く家計簿をつけ始めて収支を把握するほうが良いでしょう。
なお、家計簿は12月31日もしくは年度末で一度締め、1年間の収支を確認する必要があります。年単位での収支を把握し、貯蓄スピードすることが大切です。
挫折しないためにどうすればいい?
家計簿をつけ始める場合、まずは続けることを意識して取り組むことが重要です。つい多くの項目を設定して細かく収支を把握しがちですが、支出内容の仕分けに手間がかかってしまいます。最初はできるだけ大まかに項目を設定し、慣れた段階で必要に応じて項目数を増やしましょう。
また、1円単位で収支を合わせようと追求することは、ストレスの原因になりかねません。1円単位の誤差を追うのではなく、大きなお金の流れを確認することで挫折を防ぐことができます。
いつまで続けると良い?
まずは家計簿を半年間つけることを意識しましょう。半年間の収支を把握すると、1年間のおおよその収支を計算することができます。
また、家計簿利用を半年間継続できれば、すでに家計簿をつけることは習慣化して挫折しにくくなっています。半年、1年と、徐々に長期的な目線を取り入れながら家計簿を付けると良いでしょう。
なお、家計簿をつけることで毎月の貯蓄額が増え、ある程度まとまった金額の貯蓄が出来た場合は、投資信託を利用するなど積極的な運用も検討しましょう。
家計簿の項目を細かくしすぎると続かない?
項目を細分化しすぎると、記録の負担が増えて長続きしません。まずは「固定費」「変動費」「特別費」など大まかに分け、慣れてきたら少しずつ細かくしましょう。
交際費はどう振り分ける?
交際費には、友人との飲み会やプレゼント代など人付き合いに関する支出をまとめます。外食も、家族となら食費、友人や仕事関係なら交際費と分けると後から見直しやすいです。
美容費はどう振り分ける?
美容費には、化粧品・美容院・衣類など身だしなみに関する支出を含めます。毎月衣類を購入する場合は美容費として独立させ、クリーニング代も忘れず記録しましょう。
水道光熱費は固定費と変動費どちら?
水道光熱費は月ごとに金額が変動しても、基本料金があるため固定費として扱います。
特別費の予算はどう決める?
特別費は冠婚葬祭や家電の買い替えなど年数回の高額支出を含みます。まず年間で想定できる出費をリスト化し、月ごとに積み立てて備えましょう。
家計簿の分類はどうすればいい?
支出の分類は「固定費」「変動費」「特別費」の3つに分けるのが基本です。固定費は生活を維持する支出、変動費は使い方で変わる支出、特別費は臨時支出です。
家計簿をシンプルにしたい場合のおすすめ項目は?
記録の負担を減らすなら、項目は3〜5個に絞りましょう。たとえば「固定費」「食費」「日用品費」「特別費」「その他」の構成が続けやすいです。
医療費や教育費はどのカテゴリに入れる?
医療費は通院や薬代など変動が大きいため変動費に分類します。一方、教育費は毎月の学費や月謝など定期的に発生するため固定費に入れると管理がしやすいです。
生活費の中身はどこまで含めるべき?
生活費には、住居・光熱・通信・食費・日用品など暮らしを維持する支出を含めます。趣味や美容・交際費は生活費とは分けておくと、節約の効果が確認しやすくなります。
家計簿の項目の分け方・付け方で迷ったときの考え方は?
迷ったときは「よく使う支出」または「見直したい支出」を基準に項目を作ると整理しやすいです。支出が大きい費用や頻度の高い費用は、専用の項目を設けるのが効果的です。
おすすめの家計簿項目の5項目構成は?
家計簿の初心者におすすめなのは、5項目前後のシンプルな構成です。「食費」「日用品費」「通信費」「水道光熱費」「保険料」などが一般的です。
家計簿の科目(勘定科目)はどう決める?
家計簿の科目は、企業会計のように厳密でなくて構いません。自分が振り返りやすい名称をつけ、ルールを一定に保つことが大切です。
家計簿のカテゴリ分けはどのくらい細かくすべき?
最初から細かく分けすぎると続きません。初期段階では大まかに、慣れてから必要に応じて細分化するのがおすすめです。
家計簿を手書きでつける場合のコツは?
手書きで続けるコツは、項目数を絞り、書く時間を決めておくことです。ノート形式ならレシートを貼る、色ペンで分類するなど工夫すると見やすくなります。
家計簿を3つの項目でつけるならどうすればいい?
初心者や忙しい人には、「生活費」「特別費」「貯蓄」の3項目で十分です。慣れたら生活費を細分化して、より精度を高めていきましょう。
化粧品代は美容費に入れる?日用品費に入れる?
化粧品代は、使い方と金額で判断しましょう。毎月の消耗品レベルなら日用品費、高額なコスメや美容目的の購入なら美容費に分類します。
まとめ
本記事では、お金が貯まる家計簿の作り方の手順や家計簿をつけることでわかることなどについても詳しく解説します。
家計簿をつけることで、収支の状況や改善点がわかりお金を貯蓄しやすくなります。家計簿の作り方の手順は項目ごとに予算を決める、手段を決める、支出内容を改善するの3ステップです。
家計簿の手段には、ノートを作る以外にも、アプリやExcelなどがあります。好みに合わせて、継続しやすそうな手段を選んでみましょう。