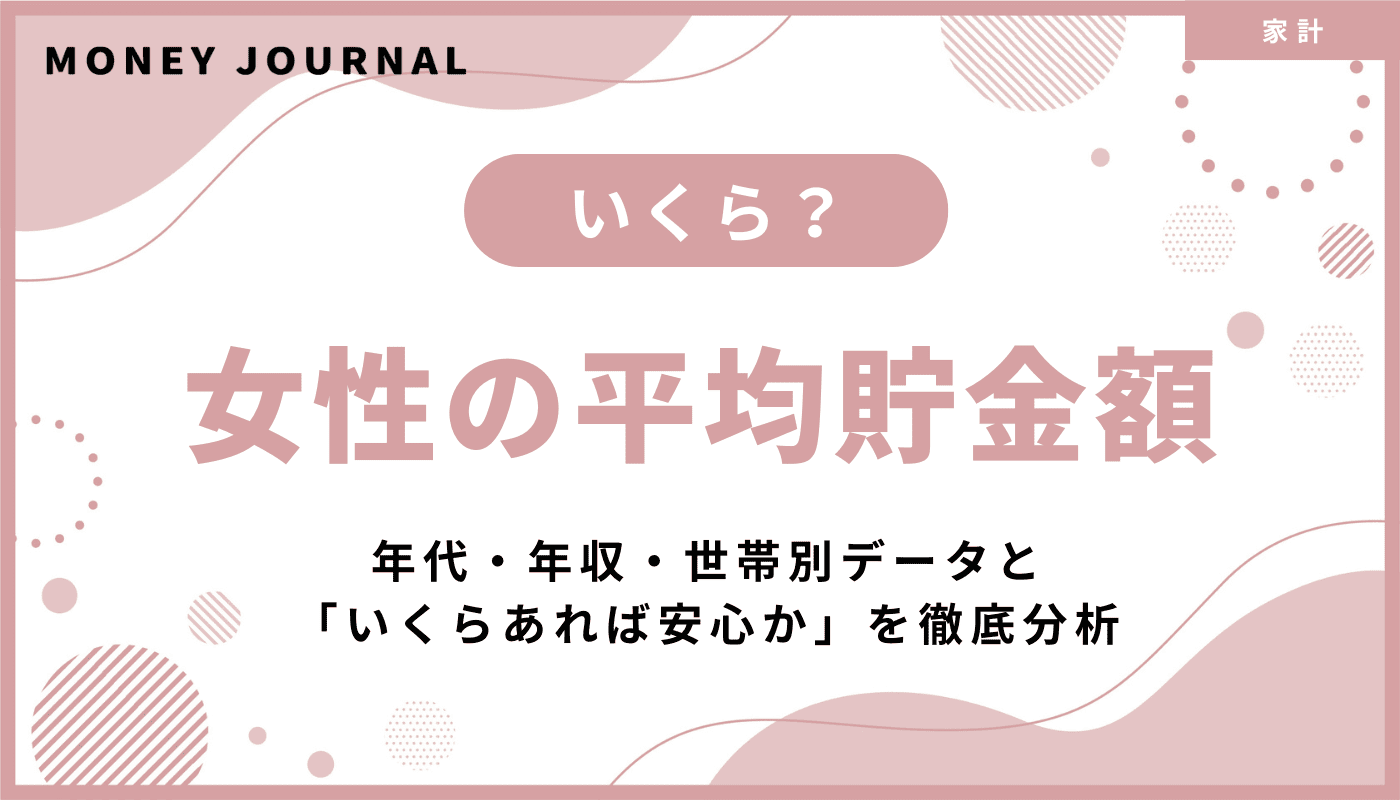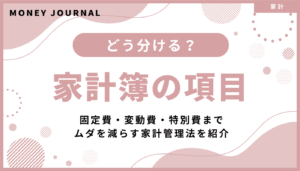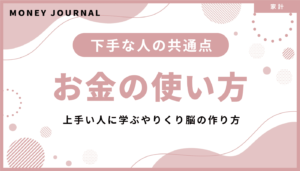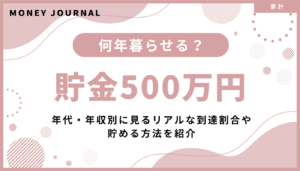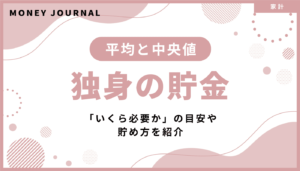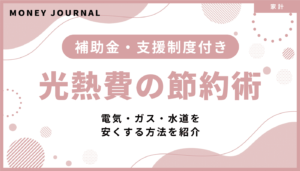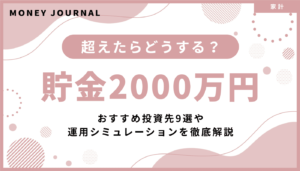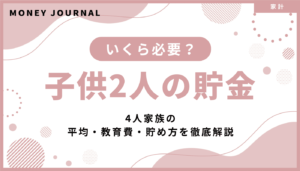- 「みんなはどれくらい貯金しているんだろう?」
- 「自分の貯金、少ないのかもしれない」
- 「将来のためには、どのくらいあれば安心なのかな…」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、女性の平均貯金額は以下のとおりです。
| 分類 | 平均貯金額の目安 |
|---|---|
| 30歳未満女性 | 約187万円 |
| 30代女性 | 約408万円 |
| 40代女性 | 約800万円 |
| 50代女性 | 約1,111万円 |
本記事では、女性の平均貯金額を年代別・世帯別・年収別にわかりやすく整理し、結婚・出産・教育費・老後資金など、ライフイベントごとに必要な金額の目安を解説します。
自分の年代・年収に対して平均的な貯金額を把握したい方は、ぜひ参考にしてください。
- 女性の平均貯金額(年代・年収・世帯別の最新データ)
- 結婚・出産・教育・老後などライフイベント別に必要な金額
- 貯金を増やすための具体的な行動ステップ
- 平均貯金額より少なくても安心できる「貯金+運用」の考え方
- 貯金ゼロからでも始められるシンプルな貯蓄習慣
女性の平均貯金額【項目別】

女性の貯金額は「年代」「世帯構成」「年収」などによって異なります。同じ女性でもライフステージが変わると、貯金の目的や貯め方が自然と変化するためです。
まずは、年代や世帯構成ごとの平均貯金額を見ていきましょう。
【年代・世帯別】女性の平均貯金額
女性の貯金額を年代別・世帯別で比較すると、年齢を重ねるごとに増える傾向が見られます。収入の安定、ボーナスや共働きなど複数の収入源が増えるため、30代〜40代で貯金額が大きく伸びるのが一般的です。
ただし、平均値だけを見ても実感がわきにくいため、ここではライフスタイル別に3つのタイプに分けて確認していきます。
独身・一人暮らし女性の平均貯金額
独身女性の平均貯金額は、年齢によって大きな差があります。
調査結果をまとめると次のとおりです。
| 年代 | 平均貯金額 |
|---|---|
| 30歳未満 | 約187万円 |
| 30代 | 約408万円 |
| 40代 | 約800万円 |
| 50代 | 約1,111万円 |
| 60代 | 約1,423万円 |
| 70代 | 約1,217万円 |
| 80代以上 | 約1,084万円 |
60代でピークを迎えた後は、退職や年金生活に入ることで貯金を取り崩す人が増えます。そのため、40代〜50代のうちに老後資金を積み立てておくことが現実的な目標といえるでしょう。
夫婦・二人暮らし以上世帯の平均貯金額
共働き夫婦の貯金額は、単身世帯に比べて大きく増える傾向にあります。
調査結果をまとめると次のとおりです。
| 指標 | 貯金額 |
|---|---|
| 平均値 | 約1,067万円 |
| 中央値 | 約300万円 |
一方で、収入源が2つあることから「毎月の先取り貯金」や「ボーナス時の一括積立」を続けやすいのが強みです。家計を分担しつつ、目的別に貯金口座を分けるなど工夫することで、より着実に資産を増やせます。
子どもあり・二人暮らし以上世帯の平均貯金額
子どもがいる家庭の平均貯金額は、次のようになっています。
| 指標 | 貯金額 |
|---|---|
| 平均値 | 約1,212万円 |
| 中央値 | 約400万円 |
一方で、支出の増加により貯金ペースが落ちることもあるため、固定費の見直しや新NISAなど長期運用を併用するのも効果的です。
【年収別】女性の平均貯金額
次のデータは、年収別の平均貯金額を示したものです。
| 年収帯 | 平均貯金額 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 約295万円 | 50.8歳 |
| 100〜150万円未満 | 約217万円 | 50.7歳 |
| 150〜200万円未満 | 約278万円 | 47.2歳 |
| 200〜250万円未満 | 約325万円 | 44.5歳 |
| 250〜300万円未満 | 約395万円 | 42.8歳 |
| 300〜350万円未満 | 約439万円 | 39.6歳 |
| 350〜400万円未満 | 約376万円 | 36.0歳 |
| 400〜450万円未満 | 約486万円 | 36.7歳 |
| 450〜500万円未満 | 約522万円 | 43.0歳 |
| 500〜550万円未満 | 約814万円 | 42.9歳 |
| 550〜600万円未満 | 約1,026万円 | 42.4歳 |
| 600~650万円未満 | 約731万円 | 46.9歳 |
| 650~700万円未満 | 約828万円 | 49.0歳 |
| 700~750万円未満 | 約411万円 | 46.3歳 |
| 750~800万円未満 | 約2,882万円 | 49.2歳 |
| 800~850万円未満 | 約3,001万円 | 51.0歳 |
| 850~900万円未満 | 約3,159万円 | 52.0歳 |
| 900~950万円未満 | 約1,423万円 | 50.3歳 |
※表示項目:単身世帯/勤労者世帯/女/全国/純金融資産(貯蓄-負債)
年収400万円を超える層では、収入の上昇に伴い貯金額も大きく伸びています。ただし、年収が上がっても支出が比例して増えることが多く、手元に残る額が思うように増えない人もいます。
一方で、年収400万円未満の層では年齢が上がるほど貯金額が増えている傾向があり、収入よりも「貯める習慣」や「支出管理力」が影響しているといえます。

女性のライフイベント別に必要なお金

女性にとって人生の大きなライフイベントには、結婚、出産、新生活、教育、住宅購入、老後介護などがあります。これらのイベントにはまとまった費用が必要となるため、事前に目安を把握しておきましょう。
結婚費用
結婚は人生の中でも大きな出費イベントで、婚約から入籍までにかかる費用の総額は約454.3万円と言われています。
主な内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 平均費用 |
|---|---|
| 結納 | 約43.9万円 |
| 両家顔合わせ | 約8.3万円 |
| 婚約指輪 | 約39.0万円 |
| 結婚指輪 | 約29.7万円 |
| 挙式・披露宴・パーティー | 約343.9万円 |
| 新婚旅行 | 約61.6万円 |
| 新婚旅行土産 | 約8.1万円 |
挙式スタイルや招待人数、海外ウェディングかどうかによって費用は変動します。少人数のレストランウェディングなら200万円台で収まることもありますが、ホテル挙式やリゾートウェディングでは600万円を超える場合もあります。
新生活スタート費用
結婚後に新しい生活を始める際には、住まいの契約、引っ越し、家具や家電の購入など、生活基盤を整えるための費用が必要です。
主な支出の目安をまとめると以下のとおりです。
| 項目 | 平均費用 |
|---|---|
| 住居契約費(敷金・礼金・仲介手数料など) | 家賃の4〜6ヶ月分 |
| 引っ越し費用(二人暮らし) | 約7〜10万円 |
| 家具購入費 | 約24.4万円 |
| 家電購入費 | 約28.8万円 |
家賃10万円の物件を借りる場合、契約時に20〜60万円前後が必要です。さらに家具・家電をすべて新調すると合計で100万円を超えることもあります。
妊娠・出産費用
妊娠から出産までは、定期健診や入院・分娩などでまとまったお金が必要になります。
主な費用を整理すると以下のようになります。
| 費用項目 | 平均金額 |
|---|---|
| 妊婦健診(約14回) | 約7万円 |
| 入院・分娩費用 | 約506,000円 |
| 出産一時金(支給) | −42万円 |
| 自己負担額 | 約16万円前後 |
出産一時金を活用しても自己負担は残るため、事前に出産専用の貯金口座をつくるのがおすすめです。
教育費
子どもを育てるうえで最も大きな負担になるのが教育費です。幼稚園から高校卒業までの15年間だけでも、すべて公立校に通った場合は約574万円、すべて私立校では約1,840万円がかかります。
さらに大学進学を希望する場合、教育費は一気に高額化します。大学4年間で必要な費用の目安は以下のとおりです。
| 大学区分 | 4年間の学費合計(入学料含む) |
|---|---|
| 国立大学 | 約242万円 |
| 公立大学 | 約252万円 |
| 私立文系大学 | 約411万円 |
| 私立理系大学 | 約542万円 |
| 私立医歯系大学(6年間) | 約2,354万円 |
出典:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」
出典:e-GOV 法令検索「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)」
教育費は短期間で用意できる金額ではないため、一般家庭でも無理なく積立できるよう早めの準備が大切です。児童手当を全額貯金すれば約200万円ほど確保できます。加えて、学資保険や教育資金専用の新NISAを併用し、将来の負担を分散しましょう。
住宅購入資金
住宅の購入費用は、エリアや建物の種類によって変わります。
住宅金融支援機構の調査による全国平均は以下のとおりです。
| 種類 | 平均購入額 |
|---|---|
| 注文住宅 | 約3,863万円 |
| 土地付き注文住宅 | 約4,903万円 |
| 建売住宅 | 約3,603万円 |
| 新築マンション | 約5,245万円 |
| 中古戸建 | 約2,536万円 |
| 中古マンション | 約3,037万円 |
首都圏では全国平均より約1,000万円高く、注文住宅では5,600万円超が目安です。住宅購入資金には、物件価格のほかにも頭金・諸費用・引っ越し費用などが必要になります。諸費用は物件価格の5〜10%程度かかるため、たとえば4,000万円の住宅を購入する場合、合計で4,200万円前後の資金を想定しておきたいところです。
家を購入するときは、「購入後に無理なく返済できるか」を最優先に考えることが大切です。住宅ローンの返済比率(年収に対する返済額)は25%以内が理想といわれています。また、老後資金や教育費とのバランスをとるために、頭金づくりや住宅購入時期のシミュレーションも必要です。
介護・疾病費用
病気やけがによる入院、家族の介護が必要になったときにも備えが必要です。
公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、直近の入院時にかかった自己負担額は平均19.8万円でした。また、入院によって得られなかった収入の平均は約30万円です。
こうした事態に備えるには、最低でも50万円程度の緊急資金を確保しておくのが安心とされています。
長期化する介護費に対応するには、公的介護保険制度を理解したうえで早めに備えることが大切です。
出典:公益財団法人 生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」
老後資金
総務省の家計調査によると、65歳以上の夫婦世帯では毎月の支出が約28万円、収入は約25万円となっており、毎月3万円前後の赤字が発生しています。単身世帯の場合も同様に、年金だけでは生活費をまかなえない人が多い状況です。
この赤字が25年間(65歳〜90歳)続くと、単純計算で約900万円の不足になります。つまり、最低でもこの金額を老後までに貯金しておくことが目安になります。
まとめると、老後資金の目安は次のようになります。
| 生活スタイル | 目安金額(25年間分) |
|---|---|
| 必要最低限の生活 | 約900万円 |
| ゆとりある暮らし | 約3,900万円 |
出典:厚生労働省「主な年齢の平均余命」
老後は「収入が減る時期」ではなく、「これまでの準備を形にする時期」です。現役のうちにコツコツと積立を進め、新NISAなどの非課税制度を活用して効率的に資産を育てていきましょう。
生活防衛資金
どのようなライフステージでも、予期せぬ出費に対応できる生活防衛資金は必要です。病気やケガによる休職、突然の転職、冠婚葬祭、家電の故障など、急な支出は誰にでも起こり得ます。
たとえば、生活費が月20万円の場合は120万円程度が目標になります。以下に目安をまとめます。
| 毎月の生活費 | 生活防衛資金の目安 |
|---|---|
| 15万円 | 約90万円 |
| 20万円 | 約120万円 |
| 25万円 | 約150万円 |
| 30万円 | 約180万円 |
生活防衛資金は、必要なときにすぐ引き出せる普通預金や定期預金で備えるのが基本です。一方で、長期的に使う予定のない資金は、新NISAなどで運用することで貯めながら増やす仕組みをつくれます。

理想はいくら?女性の貯金額シミュレーション

「平均より少ないかも…」「自分はいくらあれば安心なの?」と感じる方も多いでしょう。理想の貯金額は、年齢やライフスタイルによって変わります。
下記の表は、生活費3ヶ月分の緊急資金+将来のイベント費を加味した目安です。
| 年代 | 独身女性(1人暮らし) | 夫婦・共働き | 子どもあり世帯 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 約100〜200万円(生活基盤づくり) | 約150〜300万円(結婚準備含む) | ― |
| 30代 | 約300〜500万円(将来資金の積立) | 約500〜700万円(住宅・教育費準備) | 約400〜600万円 |
| 40代 | 約700〜1,000万円(老後資金の種) | 約1,000〜1,500万円(教育費ピーク期) | 約800〜1,200万円 |
| 50代 | 約1,000万円以上(退職後準備) | 約1,500〜2,000万円(老後生活費確保) | 約1,000万円以上 |
あくまで目安ですが、40代で1,000万円前後、50代で2,000万円近くを目指すと安心です。
今の生活を守りながら、10年先の自分を支える育てる貯金を意識していきましょう。

女性が貯金をしておく3つのメリット

ここでは、女性が貯金をしておくことで得られる3つのメリットを紹介します。
老後生活を安心して送れる
貯金があると、年金以外にも自由に使えるお金を確保できるため、生活水準を保ちやすくなります。総務省の家計調査では、老後の夫婦世帯では毎月3万円前後の赤字が発生しているとされています。年金だけに頼ると、医療費や介護費が増えたときに家計が厳しくなるのが現実です。
将来の自分の生活を守る意味でも、早めの準備が大切です。
緊急時の備えになる
予期せぬトラブルが起きたとき、手元にまとまったお金があれば冷静に対応できます。
人生では、思いもよらない出来事が起こるもの。突然の病気やケガ、勤め先の倒産、パートナーの収入減などは、誰にでも起こり得る現実です。
貯金がないとカードローンやリボ払いに頼ることになり、返済が重くのしかかって生活が苦しくなる可能性もあります。まずは、生活費の3〜6ヶ月分(例:月20万円なら60〜120万円)を目安に、緊急資金として確保しておきましょう。
夢や目標の資金を用意できる
貯金は万が一に備える守りだけでなく、夢を叶えるための力にもなります。マイホームの購入、子どもの教育費、趣味や自己成長への投資など、人生ではお金が必要な場面がたくさんあります。
たとえば、次のような夢も貯金があれば実現しやすくなります。
- マイホームやリフォームのための資金を準備する
- 留学や資格取得など、自分の成長に投資する
- 老後に趣味や旅行を楽しむための資金を確保する
目的ごとに貯金口座を分けておくと、進捗がわかりやすく、やる気を保ちやすくなります。夢を実現するための第一歩として、今日から少しずつ始めてみましょう。

女性が貯金をしないリスク

貯金を後回しにしてしまうと、将来の安心を失うリスクが高まります。お金がないことで選べる人生の幅が狭まり、老後・緊急時・ライフイベントのすべてに影響が出てしまうからです。
ここでは、女性が貯金をしないことで起こりやすい3つのリスクを見ていきましょう。
老後資金が不足して不安になる
貯金がないと、退職後の生活資金が不足するリスクが高まります。年金だけでは、ゆとりある生活どころか基本的な生活費さえ足りない可能性があります。
貯金がなければ、老後の暮らしを我慢しながら続ける状況になりかねません。安心して老後を迎えるためにも、現役時代から少しずつ積み立てておくことが大切です。
緊急時に対応できず借金が増える
病気やケガ、突然のリストラなど、予期せぬトラブルは誰にでも起こり得ます。貯金がないと、急な医療費や修繕費、冠婚葬祭の支出に対応できず、カード払いや借金に頼るしかなくなります。
安心して生活を続けるには、少なくとも生活費の3〜6か月分(例:月20万円なら60〜120万円)を緊急資金として確保しておくのが理想です。
目標やライフイベントが遠のく
貯金がないと、人生の節目で必要な資金を準備できず、夢や目標を先延ばしせざるを得なくなります。マイホーム購入、結婚、出産、子どもの教育費など、いずれもまとまったお金が必要です。
必要な資金を用意できなければ、住宅購入を諦めたり、教育環境を妥協したりといった選べない人生になってしまう可能性があります。
目標を叶えるには、まず小さな貯金から始めることが大切です。
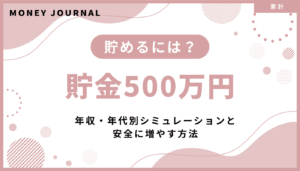
女性が平均貯金を増やす方法

貯金を増やすには、我慢ではなく仕組みづくりが大切です。支出の流れを整えれば、無理なく節約しながらお金を残せます。
ここでは、今から始められる2つのステップを紹介します。
毎月先取り貯金を習慣化する
貯金を続けるうえで最も効果的なのが、先取り貯金です。給料を受け取ったら、使う前に決まった金額を貯金用口座へ移す方法です。
先に貯金を済ませることで、残りのお金で生活する感覚が自然と身につき、使い過ぎを防げます。
先取り貯金をスムーズに続けるコツは以下のとおりです。
- 給与振込日と同日に自動振替を設定する
- 貯金用口座は引き出しにくい金融機関を選ぶ
- ボーナス時は通常月より多めに積み立てる
貯金を後回しではなく最優先にするだけで、お金の貯まり方が変わります。
キャッシュレス決済を活用する
キャッシュレス決済を上手に使うと、家計管理の効率が一気に上がります。支払い履歴が自動で記録され、家計簿アプリと連携すればどこにいくら使ったかがすぐにわかるからです。
キャッシュレス決済を効果的に活用するコツは以下のとおりです。
- 月ごとの利用上限を決めておく
- 1枚または1アプリに絞り、支出を一元管理する
- ポイントは生活費の一部として再利用する
貯まったポイントを日用品や食費にあてれば、現金を使わずに支出を抑えることも可能です。月の生活費を10万円と決めたら、上限を超えた時点でクレジット決済をストップするルールを設けましょう。
固定費・家計を見直す
貯金を増やす最初のステップは、使うお金を減らすことです。無理に節約するよりも、継続しやすいのが特徴です。
このような支出を正確に把握するには、家計簿アプリを活用するのが効果的です。
家計簿アプリを活用する
資産形成の基本は、「収支の見える化」です。家計簿アプリを使うと、銀行口座・クレジットカード・電子マネーの情報が自動で反映されます。アプリ内で支出がカテゴリー別に分類されるため、どこにお金を使いすぎているかが一目でわかるのが特徴です。
さらに、アプリによっては目標貯金額の設定機能や達成率グラフがあり、楽しみながら家計管理が続けられます。
主な利用手順は次のとおりです。
- 銀行口座・クレカ・電子マネーを連携する
- 支出を「食費」「固定費」「娯楽費」などに自動分類
- 目標貯金額を設定して進捗をグラフで確認
最初は1ヶ月分の支出を記録し、どの支出を減らせそうか分析してみましょう。
資産運用・投資を活用する
支出を整えたら、次はお金を育てるステージへ進みましょう。銀行預金だけでは金利が低く、長期的な資産形成は難しいため、投資による運用も取り入れるのがおすすめです。
とはいえ、リスクを抑えながら始めることが何よりも大切です。ここでは、投資初心者でも実践しやすい3つの方法を紹介します。
投資信託・株式投資・債券で資産運用
投資信託では、少額から複数の銘柄に分散投資できます。専門家が運用を行うため、知識が少なくても始めやすい点が特徴です。
株式投資は企業の成長に応じて値上がり益や配当金を得られますが、価格変動リスクがあります。債券は株式に比べてリスクが低く、定期的に利息収入が得られます。安定を重視するなら、国債・社債・投資信託をバランスよく組み合わせるのが理想です。
NISA・iDeCo(イデコ)を活用した節税と長期積立
NISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)は、税制優遇を受けながら資産を増やせる制度です。
2024年から始まった新NISAでは、年間360万円(積立120万円+成長投資240万円)まで非課税で投資でき、生涯上限額は1,800万円となっています。一方、iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税・住民税が軽減されます。
不動産・保険・財形貯蓄
貯金や投資信託だけでなく、勤務先の制度や保険商品を活用する方法もあります。
財形貯蓄は給与から自動で天引きされるので、確実に貯金を続けられます。勤務先によっては奨励金や利率上乗せがあり、長期の積立に向いています。
積立保険(終身・養老型)は、保障と貯蓄を兼ねた商品です。保険料を支払いながら解約返戻金を貯められるため、強制的に貯めたい人にもおすすめです。
収入アップも視野に入れる
支出を減らすだけでなく、収入を増やす努力も貯金を加速させます。副業やスキルアップを通じて、手取りを増やせば貯蓄や投資に回せる余裕が生まれるでしょう。
資格取得やオンライン講座、在宅ワークなど、女性が活躍できる働き方は増えています。たとえば、Webライティング・デザイン・データ入力などはスキルを磨けば在宅でも安定収入を得やすい分野です。

【知識】貯金額に含まれるものとは?

「貯金はいくらありますか?」と聞かれても、現金だけを思い浮かべる人もいれば、投資や保険を含めて考える人もいます。実際、金融の世界では「貯金」「金融資産」「総資産」は意味が異なります。
資産形成を進めるうえで、3つの違いを正しく理解しておくことが大切です。
まずは「預貯金」と「金融資産」の違いから整理していきましょう。
預貯金と金融資産の違い
一般的に「貯金額」とは、現金や銀行預金を指します。すぐに引き出せるお金が対象です。
以下の表に主な違いをまとめます。
| 項目 | 含まれる主な内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 貯金(預貯金) | 現金・銀行預金 | すぐに使える、元本が減らない |
| 金融資産 | 現金・預貯金・株式・投資信託・債券・保険など | 運用で増える可能性があるが、価格変動リスクもある |
貯金が100万円、投資信託が50万円あれば、金融資産は合計150万円です。現金だけでなく金融資産全体で考えることで、資産の全体像がより明確になります。
投資をしている方は、自分の金融資産総額を定期的にチェックすると良いでしょう。
総資産との違い
「総資産」は、金融資産に加えて不動産などの実物資産も含めた金額を指します。貯金が100万円、株式が50万円、自宅が3,000万円なら、総資産は3,150万円という考え方です。
つまり、総資産は家計全体の「持っている資産の総合評価」といえます。
次の表で違いを整理します。
| 分類 | 含まれるもの | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 貯金 | 現金・預貯金 | 即時に使えるお金 |
| 金融資産 | 貯金+株・債券・投資信託など | 運用で増える可能性あり |
| 総資産 | 金融資産+不動産・車などの実物資産 | 家計全体の資産規模を示す |
老後資金を考えるときは、貯金だけでなく総資産のバランスを見て判断してください。まずは手元に現金を十分に確保し、余裕が出てきたら投資や保険を活用して資産全体で増やす仕組みを作りましょう。

女性の貯金平均に関するよくある質問

ここでは、女性の貯金平均に関連するよくある質問と回答を紹介します。
- 女性の平均貯金額はいくら?
- いくら貯めれば安心?
- 20代女性は毎月いくら貯金すればいい?
- 貯金ゼロで不安です。どうしたらいいですか?
- 貯金と投資の優先順位は?
- 貯金額は手取りの何%が理想?
- 貯金に含める資産の範囲は?
- 女性の平均貯金額の「内訳」はどうなっている?
- 金融資産を持たない貯金ゼロ女性はどれくらい?
- 共働き世帯や2人以上世帯の平均貯金額は?
- 育児や教育資金に必要な貯金の目安は?
- 主婦やパート女性の平均貯金額は?
- ローンや住宅購入(マイホーム)を抱えていても貯金は可能?
- 積立保険や財形貯蓄も貯金額に含まれるものになる?
- 貯金を増やすためのライフプランニングの立て方は?
- 現金と預金、どちらを多く持つべき?
- 生活費が高くても貯金を続けるコツは?
- マイホームや車購入を考えるとき、どれくらいの貯金が必要?
女性の平均貯金額はいくら?
女性の平均貯金額は、年齢や世帯構成によって異なります。金融広報中央委員会の調査によると、独身女性では30歳未満で約187万円、30代の社会人女性では約408万円、40代で約800万円と年齢と比例して貯金額が上昇傾向にあります。
一方、年収別に見ると、年収100万円未満の平均貯金額は約295万円、年収100~150万円で約217万円と逆転するものの、それ以降は300~800万円と上昇傾向且つ幅広くなっていきます。
いくら貯めれば安心?
安心と感じる金額はライフスタイルによって違いますが、一般的な目安は以下のとおりです。
| 目的 | 安心ラインの目安 |
|---|---|
| 緊急時(生活費3〜6ヶ月分) | 約60〜120万円 |
| 結婚・出産・教育など将来イベント | 約300〜800万円 |
| 老後の生活費(65歳以降) | 約1,000〜2,000万円 |
まずは、生活費の半年分を現金で確保し、次に「将来のイベント資金」「老後資金」と段階的に積み上げましょう。お金が貯まってくると、将来の不安が減るだけでなく、選べる人生の幅も広がります。
20代女性は毎月いくら貯金すればいい?
20代のうちは収入もまだ安定していないため、月収の1割以上を目標に貯金するのが現実的です。手取り20万円なら、まずは毎月2万円を先取り貯金として給与日に自動で貯金口座へ移すようにしましょう。
継続すれば、以下の金額を継続的に貯められます。
- 1年で24万円
- 5年で120万円
貯金のコツは「残ったら貯金する」ではなく、「先に貯金して残りで生活する」こと。30代以降のライフイベント(結婚・出産・転居)に備え、20代のうちに貯金習慣を固めておくと楽になります。
貯金ゼロで不安です。どうしたらいいですか?
貯金がゼロでも大丈夫です。大切なのは「今すぐ行動を始めること」です。まずは生活費を見直し、毎月少額でも貯金を始めましょう。
- 月5,000円でも給与日に自動振替で貯金
- 使わなかった食費・交通費を翌月に繰り越さず貯金
- ボーナスや臨時収入は半分を貯蓄口座に入れる
これだけでも半年で数万円の貯金ができます。最初から完璧を目指すよりも、貯める習慣を作ることが大切です。貯金が1万円でも増えると、不安は確実に小さくなります。少しずつ前進していきましょう。
貯金と投資の優先順位は?
まずは生活を守るための生活防衛資金(生活費3〜6ヶ月分)を現金で確保してください。たとえば月20万円の生活費なら、最低でも60〜120万円を貯金として準備します。
そのうえで余裕資金を使い、NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用して投資を始めるのが理想です。投資は時間を味方につけることがリスクを抑えるコツだからです。
貯金額は手取りの何%が理想?
手取り額のうち貯金に回す理想の割合は年齢によって変わります。目安を以下にまとめました。
| 年代 | 理想の貯蓄率(手取りに対して) |
|---|---|
| 20代 | 10〜15% |
| 30代 | 15〜20% |
| 40代 | 約20% |
| 50代 | 20〜25% |
| 60代以上 | 10〜15% |
教育費や住宅ローンがある時期は一時的に貯蓄率が下がっても問題ありません。収入が上がったタイミングで増えた分をそのまま貯金や新NISAへ回す先取り貯蓄を習慣化すれば、無理なく貯蓄率を上げていけます。
貯金に含める資産の範囲は?
貯金と聞くと現金や銀行預金を思い浮かべる人が多いですが、実際はもっと広い意味で考える必要があります。資産形成を考える際は、以下のような金融資産・実物資産をすべて含めて把握することが大切です。
- 現金・銀行預金
- 投資信託・株式・債券
- iDeCoや企業型DCなどの年金積立
- 生命保険の解約返戻金
- 不動産(自宅や投資物件の評価額)
また、総資産からローンやクレジット残高などの負債を差し引いた「純資産」で管理すると、資産全体のバランスが明確になります。預貯金・投資・保険をそれぞれ偏りなく配分することが、安定した資産づくりの基本です。
女性の平均貯金額の「内訳」はどうなっている?
女性の貯金は現金・預貯金だけでなく、保険や投資信託なども含めた構成が増えています。金融広報中央委員会の調査によると、女性が保有する金融資産の内訳は以下のような傾向があります。
| 項目 | 単身世帯 | 二人以上世帯 |
|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 408万円 | 563万円 |
| 生命保険 | 72万円 | 153万円 |
| 損害保険 | 9万円 | 25万円 |
| 個人年金保険 | 48万円 | 79万円 |
| 債券 | 41万円 | 55万円 |
| 株式 | 225万円 | 253万円 |
| 投資信託 | 106万円 | 119万円 |
| 財形貯蓄 | 9万円 | 26万円 |
まだ現金比率が高い一方で、20代後半〜30代の女性を中心に投資信託の保有率が上昇しています。新NISAなどの非課税制度が普及したことで、資産運用を生活の一部に取り入れる人が確実に増えていることが分かります。
金融資産を持たない貯金ゼロ女性はどれくらい?
金融広報中央委員会の調査(令和5年)によると、単身女性の約36%が貯金ゼロ(金融資産非保有)という結果が出ています。特に20代では収入が安定しないことや支出の多さから、貯金を始められない人が目立ちます。
しかし、少額からでも習慣化すれば流れは変わります。月5,000円を給与日に自動で積み立てるだけでも、1年で6万円、5年で30万円になります。
育児や教育資金に必要な貯金の目安は?
子どもを育てるうえで最も大きな支出が教育費です。文部科学省のデータによると、幼稚園から高校まですべて公立校の場合は約574万円、すべて私立だと約1,840万円かかるといわれています。
さらに大学進学時には以下のような学費が必要です。
| 大学区分 | 4年間の学費合計(入学料含む) |
|---|---|
| 国立大学 | 約242万円 |
| 公立大学 | 約252万円 |
| 私立文系大学 | 約411万円 |
| 私立理系大学 | 約542万円 |
| 私立医歯系大学(6年間) | 約2,354万円 |
出典:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」
出典:e-GOV 法令検索「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)」
教育資金は子どもの成長とともに急増します。児童手当を全額貯金すれば、教育費の基礎資金を確保可能です。残りは学資保険や新NISAなどを活用して、「貯める・増やす・備える」を同時に進めるのがおすすめです。
ローンや住宅購入(マイホーム)を抱えていても貯金は可能?
住宅ローンを支払いながらでも貯金は十分に可能です。ポイントは「ローン返済」「生活費」「貯金」を明確に分け、毎月の固定費を抑えることです。
たとえば、次のような手順で家計を整えると効果的です。
- 毎月の返済額は手取り収入の25%以内に設定
- 光熱費・通信費・保険などの固定費を見直す
- ボーナスの一部を貯蓄口座に自動振替
住宅購入直後は出費が多く貯金が減りやすいですが、ローン完済までの長期戦を前提に少額でも続けることが大切です。また、繰上げ返済を焦るよりも、生活防衛資金(生活費6ヶ月分)を確保し、新NISAなどで将来の資産を育てていく方が安定した家計管理につながります。
積立保険や財形貯蓄も貯金額に含まれるものになる?
積立保険や財形貯蓄は、広い意味で貯金に含まれる資産です。どちらも強制的にお金を貯めるという点で、通常の預金と同じ役割を果たします。
たとえば次のようなものが対象です。
- 積立型の生命保険(終身保険・養老保険など)
- 社員の給与から天引きされる財形貯蓄(一般・住宅・年金)
これらは「解約返戻金」や「積立残高」として資産に計上できます。ただし、途中解約すると元本割れのリスクがあるため、短期的な引き出しには向きません。
貯金を増やすためのライフプランニングの立て方は?
効率的に貯金を増やすには、場当たり的な節約よりもライフプランを明確に立てることが必要です。ライフプランとは、将来の目標や必要資金を時系列で整理した人生のお金の設計図のようなものです。
以下の3ステップで進めると効果的です。
- 人生の節目(結婚・住宅購入・子どもの進学・老後)を洗い出す
- 各イベントにかかる費用を具体的に算出
- 逆算して「いつまでに・いくら貯めるか」を決める
目標が明確になると、無駄遣いが自然と減ります。ライフプランは年1回見直し、変化に合わせて柔軟に調整しましょう。
現金と預金、どちらを多く持つべき?
現金と預金はどちらも必要ですが、比率のバランスが大切です。目安として、生活費の1〜2ヶ月分は現金で持ち、残りは預金口座で管理すると効率的です。
| 資産の形 | 役割 | 目安額 |
|---|---|---|
| 現金 | 災害・急な出費への備え | 生活費1〜2か月分 |
| 普通預金 | すぐ使う生活費の保管 | 生活費3〜6か月分 |
| 定期預金・投資 | 将来のための貯蓄・運用 | 余裕資金 |
現金を多く持ちすぎると、盗難リスクやインフレで価値が目減りするおそれがあります。一方、預金は安全性が高く、管理もしやすいのがメリットです。
生活費が高くても貯金を続けるコツは?
生活費が高くても、やり方次第で確実に貯金を続けられます。大切なのは使う前に貯めてしまうことです。まずは給料日に自動で貯金用口座へ振り分ける先取り貯金を設定しましょう。
加えて、固定費を見直すだけでも月1〜2万円は節約できます。スマホの料金プラン、サブスク、保険などを整理し、不要な支出を削減すると貯金余力が生まれます。
マイホームや車購入を考えるとき、どれくらいの貯金が必要?
マイホームや車を購入する際は、購入費+初期費用+維持費を合計して考える必要があります。それぞれの目安は以下のとおりです。
| 項目 | マイホーム | 車 |
|---|---|---|
| 購入費 | 3,000万〜4,500万円(全国平均) | 200万〜350万円(新車) |
| 初期費用 | 購入価格の5〜10% | 税金・保険などで20万〜30万円 |
| 維持費 | 年間20万〜40万円(固定資産税・修繕など) | 年間10万〜15万円(ガソリン・保険・税金など) |
頭金として、住宅は購入額の10〜20%、車は総額の10〜30%を貯めておくと安心です。たとえば3,500万円の住宅なら350万〜700万円が目安になります。
まとめ
この記事では、女性の平均貯金額や年代・年収ごとの傾向、そしていくらあれば安心なのかという現実的な目安を整理しました。
貯金は目標が高ければいいというものではなく、「目的に沿って」「無理なく続ける」ことが大切です。
たとえば、以下を目安にすると、自分の立ち位置が見えやすくなります。
- 緊急時に備えるなら生活費の3〜6ヶ月分
- 結婚や出産など将来のイベント費に300〜800万円
- 老後資金は1,000〜2,000万円ほど
また、貯金を増やすには以下の流れが効果的です。
- 給与日に先取りで自動貯金
- 家計簿アプリで支出を見える化
- 新NISAなどの非課税制度で貯めながら増やす
今日の1,000円が、未来の安心につながります。まずは無理のない金額から始めて、10年後の自分を笑顔にできる貯金習慣を育ててください。