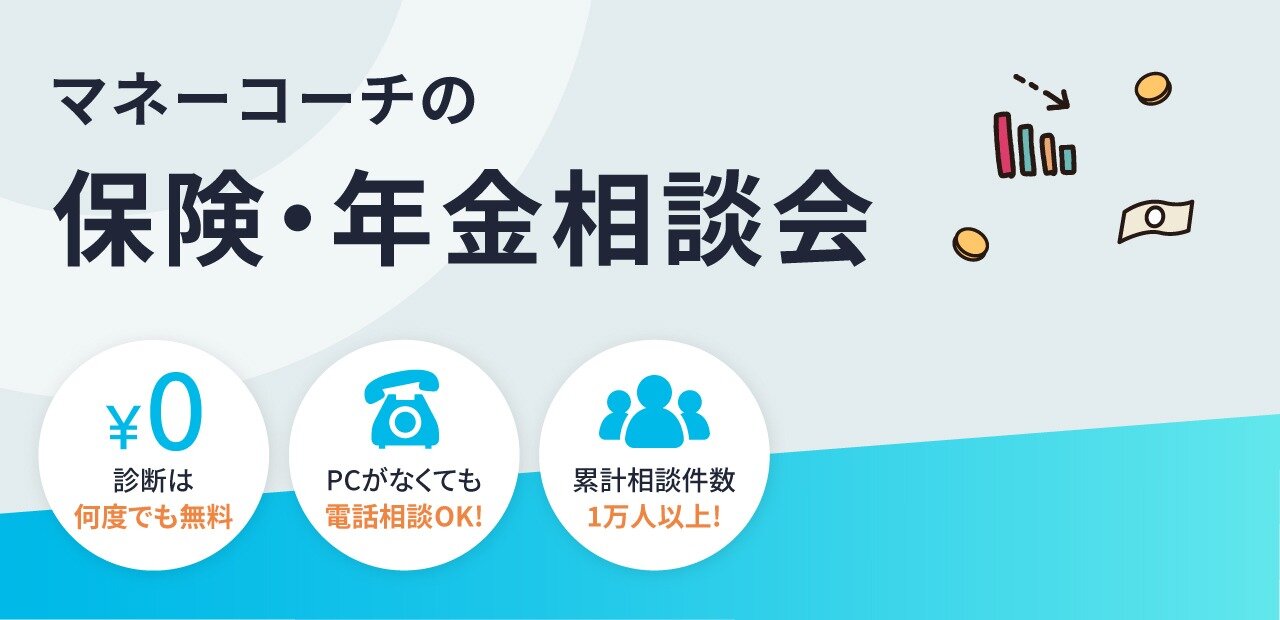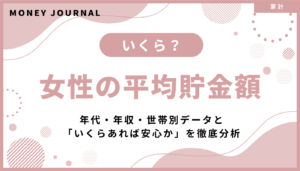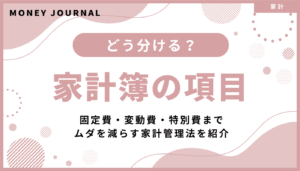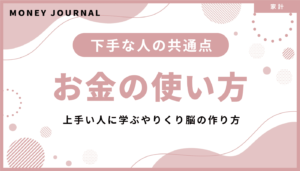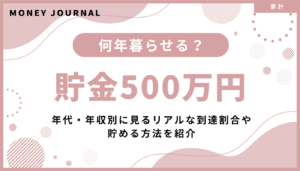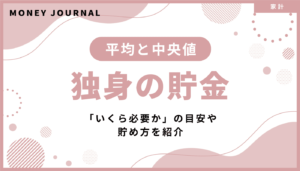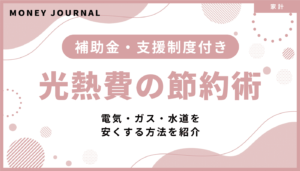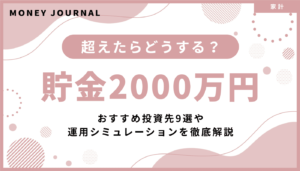- 「4人家族の生活費って、一般的にどのくらいなんだろう…」
- 「今の支出って多すぎ?それとも平均的?」
- 「子どもが大きくなると、やっぱり家計はもっとキツくなるのかな?」
このように感じている方もいるでしょう。
結論、4人家族の生活費の相場は以下の通りです。
| 項目 | 平均支出/月 |
|---|---|
| 生活費全体 | 325,499円 |
| 食費 | 92,033円 |
| 光熱費 | 22,274円 |
この記事では、全国平均や中央値をもとに「4人家族の生活費」の全体像を明確にしつつ、年代や子どもの成長段階による支出変化、東京と地方でのコスト差まで徹底解説します。
「家計にメリハリをつけて貯金したい」という方は、ぜひ参考にしてください。
【統計】4人家族の生活費はいくら?全国平均と中央値を比較

平均値は“全体のざっくりした目安”として参考になり、中央値は“実態に近い家庭のライン”を示してくれます。
4人家族の生活費は、収入・地域・家族構成によってかなり差が出ますが、まずは国の統計データから「平均」と「中央値」の2つの視点で相場を確認してみましょう。
具体的な全国平均値と中央値は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説します。
全国平均|一般家庭の生活費は月32.5万円が相場
4人家族(夫婦と子ども2人)の生活費は、月32.5万円が全国平均とされています。
代表的な支出の内訳は以下の通りです。
| 支出項目 | 平均金額/月 | 割合 | 支出の内容 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 92,033円 | 28.3% | 食材費、外食費など |
| 住居(持ち家含む) | 17,642円 | 5.4% | 家賃、修繕費など(住宅ローンの返済は含まない) |
| 光熱・水道 | 22,274円 | 6.8% | 電気代、ガス代など |
| 家具・家事用品 | 11,810円 | 3.6% | 家具代、家事サービスなど |
| 被服及び履物 | 12,696円 | 3.9% | クリーニング代などを含む |
| 保健医療 | 13,337円 | 4.1% | 病院の医療費、医薬品代など |
| 交通・通信 | 48,810円 | 15.0% | 携帯代、自動車関連費用など |
| 教育 | 27,437円 | 8.4% | 入学金、学費、塾代など |
| 教養娯楽 | 35,919円 | 11.0% | レジャー費、本代など |
| その他の消費支出 | 43,539円 | 13.4% | 雑費、こづかい、交際費など |
| 合計 | 325,497円 | 100.0% | ー |
中央値|4人世帯の中央値は約30万円前後
実際の生活実感に近い目安として「中央値」もよく取り上げられます。統計には明示されていませんが、平均が約32.5万円であることから中央値は30万円前後と推定できます。
平均値と中央値をセットで見ることで、次のような判断が可能です。
- 平均より上→使いすぎの可能性あり
- 中央値より下→節約型の家庭
「うちの生活費は、どのラインに当てはまるかな?」と一度見直してみると、家計の見直しや節約のヒントが見えてくるかもしれません。
【年代×家族構成別】4人家族の生活費変化|子の成長でどう変わる?

子どもの成長にあわせて、4人家族の生活費は大きく変化していきます。
ここでは、家計への影響を年代別に紹介します。
未就学児2人|消耗品・食費で家計が膨らむ
未就学児が2人いる家庭では、日々の支出がじわじわと膨らみやすい傾向があります。乳幼児期は買って終わりではなく、何度も買い替える・使い切る前提の出費が多いためです。
成長スピードも速く、衣類や靴もすぐサイズアウトしてしまいます。
また、保育園に通っている場合は保育料も発生するため、固定的な出費+突発的な支出のダブルパンチになりやすいです。
代表的な出費内容を整理すると以下のようになります。
| 費用 | 内容例 |
|---|---|
| 食費 | 離乳食・幼児用おやつ・粉ミルクなど |
| 消耗品 | おむつ・おしりふき・衛生用品など |
| 衣類・雑貨 | 成長による衣替え・季節ごとの必需品など |
| 医療費 | 小児科・耳鼻科・皮膚科などの通院 |
| 保育料 | 通園先・世帯年収・自治体により金額変動 |
小中学生世帯|教育費・習い事代等で平均支出が上がる
小学生・中学生がいる家庭では、家計に占める教育関連の支出割合が大きくなります。
なかでも「学習費総額」と呼ばれる学校+塾・習い事の合計金額は、年齢が上がるにつれて年間数十万円単位で増加します。
特に注意したいのが学校外活動費(塾や習い事など)です。子どもの進学や習い事への期待が高まる時期でもあり、家計にじわじわ響いてくる費目です。
以下は、文部科学省の統計をもとにした小学生・中学生の平均的な年間支出です。
▼小学生(公立)の年間学習費内訳
| 費目 | 平均額(年) | 内容例 |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 約82,000円 | 教科書・教材・PTA会費など |
| 学校給食費 | 約38,000円 | 月換算で約3,200円 |
| 学校外活動費 | 約216,000円 | 習い事・学習塾・スポーツなど |
| 年間合計 | 約336,000円 | 学年が上がるほど増加傾向あり |
▼中学生(公立)の年間学習費内訳
| 費目 | 平均額(年) | 内容例 |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 約150,000円 | 教材・制服・部活関連費など |
| 学校給食費 | 約36,000円 | 月換算で約3,000円 |
| 学校外活動費 | 約356,000円 | 塾・模試・通信教育など |
| 年間合計 | 約542,000円 | 高校受験に向けた負担が大きくなる |
小学生のうちは習い事中心、中学生では塾代と受験費用が重なってきます。
高校生世帯|受験費用・学費が家計を圧迫
高校生を育てている家庭では、教育費が一気に大きくなる時期です。
文部科学省の調査によると、高校生にかかる年間学習費(教育費+塾・習い事代)は以下のようになっています。
| 区分 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 約351,000円 | 約766,000円 |
| 学校外活動費 | 約246,000円 | 約263,000円 |
| 合計(年間) | 約598,000円 | 約1,030,000円 |
大学生世帯|仕送り・授業料・下宿費で支出が跳ね上がる
大学生がいる家庭では、教育費・仕送り・生活費・家賃がすべて同時に発生します。高校生までと比べて家計への負担が跳ね上がるフェーズです。
私立理系+下宿となると、4年間で1,000万円超の支出になることも珍しくありません。
以下は、日本政策金融公庫などの調査をもとにまとめた大学進学にかかる費用の目安です。
| 区分 | 自宅通学(4年間) | 下宿通学(4年間) |
|---|---|---|
| 国公立大学 | 約520万円 | 約800万円 |
| 私立大学(文系) | 約700万円 | 約990万円 |
| 私立大学(理系) | 約840万円 | 約1,120万円 |
こうした将来の教育費を見据え、今の家計が本当に最適かどうか一度見直してみることをおすすめします。
- 30秒で予約完了
- 相談は何度でも無料
- スマホ・PCからいつでもOK(カメラオフも可)
【黄金比率チェック】4人家族の生活費は収入の何割が理想?

「何にいくら使えばいいのか分からない」という方は、支出の黄金比率を参考にするのがおすすめです。
手取り収入に対する支出の理想的な割合は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説します。
食費|手取りの15~20%以内
4人家族の場合、食費は手取りの15~20%以内に収めるのが理想とされています。手取り30万円の家庭なら、月60,000円以内が目安です。
ただし、総務省の家計調査では4人家族の平均食費は約9.2万円となっており、多くの家庭が理想比率をオーバーしています。
一方、食費は工夫次第で減らしやすい費目でもあります。以下のような対策が効果的です。
- 買い物の頻度を週1~2回にする
- 冷蔵庫内の在庫をチェックしてから買う
- まとめ買い後の食材使いきりレシピを意識する
「食費がかさんで貯金できない…」という方は、最初に見直すべきポイントといえるでしょう。
住居費・固定費|手取りの45%以内
家賃や住宅ローン、光熱費、通信費、保険料などの毎月ほぼ固定されている支出は、手取りの45%以内が目安です。
手取り35万円の家庭なら、住居費+固定費は15万7,000円以内が安全圏。固定費は一度設定すると見直す機会が少ないため、定期的なチェックが必要です。
見直しやすいのは以下のような項目です。
- 不要なサブスクの解約(動画・音楽など)
- スマホの通信プランを格安SIMに変更
- 保険の内容を整理(貯蓄型・重複契約など)
毎月の固定費を下げるだけで、年間数万円〜十数万円の節約も可能です。
支出全体|やりくり費を含めて手取りの82%以内が適正ライン
4人家族の支出全体は、手取りの82%以内に収めるのが家計が安定しているラインとされています。
残りの18%は、貯金・教育資金・緊急費用などに回すのが理想です。
手取り月40万円なら、生活費は33万円以内に抑えるのがベスト。毎月の支出が見えにくい場合は、アプリでグラフ化するなど“見える化”がおすすめです。
家計簿をつけるのが苦手な方は、こちらの記事も参考にしてください。

4人家族の生活費は東京と地方でどれだけ違う?

同じ4人家族でも、どこに住んでいるかで生活費には大きな差が出ます。
ここでは、東京23区などの都市部と、地方都市や郊外エリアとを比較しながら、生活費の主要項目にどのくらいの違いがあるのかを紹介します。
家賃|東京23区は地方都市より3~5倍高い
4人家族で必要になる2LDK以上の賃貸物件は、東京23区と地方都市とで3~5倍の開きが出ています。
以下は、LIFULL HOME’Sの最新データをもとにした、2LDK〜3DK物件の家賃相場です。
| 地域 | 家賃相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 港区 | 約40.5万円 | 超高額エリア・都心オフィス街近く |
| 渋谷区 | 約36.7万円 | 若者に人気・商業地エリア |
| 杉並区 | 約21.9万円 | 東京西部のファミリー向け住宅地 |
| 練馬区 | 約19.2万円 | 23区内でも比較的家賃が抑えられる地域 |
| 足立区 | 約16.1万円 | 東京都内で家賃が安めのエリア |
| 鳥取県鳥取市 | 約7.0万円 | 地方都市のファミリー向け相場 |
参考:LIFULL HOME’S「東京23区の家賃相場情報」
※すべて2LDK〜3DK/徒歩10分圏内基準の物件相場(管理費・駐車場別)
さらに、東京では以下のような「家賃以外のコスト」も重なってきます。
- 敷金・礼金:2ヶ月分ずつが一般的(初期費用だけで60万円以上もザラ)
- 更新料:1〜2年ごとに1ヶ月分(長期で住むほど割高)
収入の25〜30%以内に収めるのが目安とされますが、東京の高額物件では“収入の半分以上”を家賃に使っている家庭も少なくないのが現状です。
通信費・交通費|通勤定期代や自家用車維持費に差が出る
交通費や通信費は意外と地域差が出る費目です。
都市部は電車・バス中心、地方は車通勤が主流という暮らし方の違いが支出の中身に直結します。
| 費目 | 都市部の傾向 | 地方の傾向 |
|---|---|---|
| 交通費 | 定期券利用(月5,000〜1万円) | 自家用車(ガソリン+保険で月2万円前後) |
| 通信費 | 格安SIMや光回線の選択肢が豊富 | 通信環境に制限あり+割高ケースも |
地方では1人1台の車所有が当たり前の地域もあります。ローン代・ガソリン代・駐車場代・自動車保険まで含めると、通信費+交通費で月10万円以上になる家庭も。
都市部の“交通インフラの便利さ”は、意外と見えない節約ポイントにもなっています。
教育費・物価|都市部は進学費+生活コストで二重負担になりやすい
教育費や生活コストは、都市部のほうが「私立校進学の割合」も「物価水準」も高く、教育費+生活費で二重に家計を圧迫しやすい構造です。
文部科学省の調査では、私立高校への進学率は以下のとおり地域差があります。
| 地域 | 進学率 |
|---|---|
| 東京都 | 約58~59% |
| 大阪府 | 約55%前後 |
| 北海道・東北 | 約20%以下 |
| 全国平均 | 約24% |
都市部では「塾代」や「模試代」の相場も高く、教育費全体がかさむ傾向にあります。
加えて、日用品・食品・家賃なども高いため、「教育費+生活費の合算負担」で見ると、地方よりも都市部のほうが苦しくなりやすいというのが実情です。
こうした教育費の負担に備えるには、学資保険などを活用して早めに計画を立てておくことも大切です。

4人家族で生活費が苦しい・お金がない・赤字になる家庭の共通点

「なぜか毎月カツカツ」「気づくとお金が残っていない」など、4人家族でこうした悩みを抱える家庭には共通する家計の落とし穴が存在します。
収入だけでなく、日々の習慣や支出の優先度が家計状況に大きく影響しているケースが多いです。
以下では、4人家族が赤字に陥りやすい「家計の共通パターン」を紹介します。
家計簿をつけていない
家計簿をつけていないと、ムダ遣いにも気づけず「節約したつもりでも赤字になる」状態に陥ってしまいます。
何にいくら使っているかが分からないまま過ごしていると、お金がどんどん消えていく感覚になりやすいです。
最近は、レシートをスマホで撮るだけで自動集計してくれるアプリも増えており、ノートに書くよりずっと手軽に管理ができます。
まずは1週間だけでも記録してみると、「何にいくらかけているか」が見えてくるのでおすすめです。
現金払いを続けている
現金だけでやりくりしていると、「どこで・何に・いくら使ったか」をあとから確認するのが難しくなります。財布から1万円出ていったとしても、レシートがなければ何に使ったかすぐには思い出せません。
一方で、クレジットカードや電子マネーを使えば、明細が自動で残り家計管理の履歴も一目で分かります。
「カードは使いすぎが不安…」という方も、利用額に上限を設定できるプリペイド型や、使った分がすぐに引き落とされるデビットカードを活用すれば安心です。
固定費を見直していない
毎月なんとなく払っている固定費が、家計をじわじわと圧迫しているケースは本当に多いです。
見直していないスマホ代や入ったままの保険、ほとんど使っていないサブスク(定額サービス)など。放置しているだけで月1万円以上ムダが出ている家庭も珍しくありません。
固定費は毎月確実に出ていくので、節約の効果が長続きしやすい項目です。
まずは通帳やクレカの明細を見返して、「勝手に引き落とされているもの」を一度棚卸ししてみてください。
家賃が高すぎる
「子ども部屋がほしい」「駅近が便利」といった希望から、無理して高めの物件を選んでいる方もいるでしょう。
しかし、手取りの3分の1を超える家賃は赤字体質の第一歩。手取り30万円で家賃が12万円を超えると、他の支出をかなり絞らないと貯金は難しくなります。
理想の目安は、手取りの25〜28%以内。家賃が高いと感じたら、次のような対策も検討してみてください。
- 更新時に家賃交渉する
- 少し駅から離れた物件に引っ越す
- 郊外エリアで同じ広さの物件を探す
固定費だからこそ、見直せば一気に家計が楽になります。
収入に対する支出の優先順位が曖昧
「気づけばお金が残っていない」方の多くは、お金の使い方にルールがないまま生活している可能性が高いです。
たとえば、同じ月に「旅行・保険の更新・ゲーム課金・子どもの習い事」が重なれば、どれが優先か分からず結果的にどれも削れなくなってしまいます。
おすすめなのは、次の3ステップです。
- 毎月の収入を紙に書き出す
- 支出を「必要」「優先」「あとまわし」に分類する
- 家族で優先順位ルールを決める
迷わずお金を使えるようになり、家計にゆとりが生まれます。
日用品・雑費を感覚で買っている
ティッシュ、洗剤、お菓子、文具などの日用品や雑費は単価が安いため、「気づいたら使いすぎ」になりやすい落とし穴です。
レシートを見返しても、「100円×10品」などは家計簿の「雑費」にまとめて記録されがちで、無駄が見えにくくなります。
対策として、以下のようなルール化がおすすめです。
- 雑費の月予算をあらかじめ決めておく
- 週1回だけまとめ買いにする
- ストックがなくなってから買う
「感覚買い」をやめるだけで、家計のムダが一気に減ります。まずは買い物メモから始めてみましょう。
【貯金できないを改善】4人家族の生活費節約ポイント3選

4人家族が生活費を節約するときのポイントは次の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
外食費や娯楽費はメリハリをつけて使う
節約のコツ1つ目は、メリハリのある支出を心がけることです。たとえば、外食費は月1回などと決めるといいでしょう。
家族の人数が1人増えても食費は1万円程度しか増えない理由の1つは、家庭で家族全員の食事をまとめて作ることで、1人あたりの食費を抑えているからです。
外食やデリバリーが多くなると、家族の人数に比例して食費も増加します。娯楽やレジャーについても同様です。ときには家族旅行で羽を伸ばすのもいいですが、普段はお金のかからない公園を利用するなどして、教養娯楽費も計画的に節約しましょう。
ちょっとした贅沢も必要ですが、油断すると支出は膨らみやすいので注意しましょう。
教育費は早い時期から準備する
節約のコツ2つ目は、教育費は早い時期から準備をスタートして教育費の負担を平準化することです。前述の通り、子供の小さいうちは教育費もあまりかかりませんが、高校、大学と進むごとに費用は高額になります。
奨学金や教育ローンを利用する場合でも、ある程度の教育資金を準備したほうがいいでしょう。
お金が必要な時期は事前にわかっているので、上手に節約して教育資金づくりを進めましょう。
毎月の固定費を下げる
節約のコツ3つ目は、毎月の固定費を下げることです。
特に、携帯代については大手キャリアと格安スマホ会社の価格差は大きいので、家族4人が携帯を使用している場合は、携帯会社の切り替えで毎月数万円も節約できるケースもあります。
契約先を変えたあとは節約を意識することなく支出を抑えられるため、固定費の削減は有効な節約方法と言えます。
【収入別シミュレーション】4人家族はいくらなら貯金できる?

「手取り収入でどのくらいの生活ができるのか」気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、手取り20万円では生活だけで精一杯、30万円でやりくりが必要、40万円以上でようやく貯金が見えてくるのが現実です。
下記では手取り額別に、4人家族の生活費と貯金可能ラインを具体的にシミュレーションしていきます。
「自分の家計は大丈夫?」と感じた方も、支出の見直しや備えの参考にしてみてください。
手取り20万円|生活費でほぼ全額消え“赤字寸前”が現実
手取り月20万円では、4人家族の生活費をまかなうだけで精一杯というのが正直なところです。
地方在住でも、家賃が月6万〜7万円、食費で8万円前後、光熱費や日用品でさらに数万円。収入だけでは到底カバーしきれない月も出てくる水準です。
支出の内訳イメージは以下の通りです。
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 家賃 | 65,000円 |
| 食費 | 80,000円 |
| 光熱・通信費 | 25,000円 |
| 日用品・雑費 | 15,000円 |
| 合計 | 185,000円~210,000円 |
手取り20万円の収入帯では、児童手当や地域の子育て支援制度のフル活用が前提になります。また、生活費のうち「家賃・通信費・保険料」などの固定費をどれだけ圧縮できるかが生存ラインを左右するでしょう。
「いまの支出のままでは厳しい…」という方は、予算をゼロベースで見直して再構築することをおすすめします。
手取り30万円|家賃次第で貯金ゼロ、節約前提の生活ライン
手取り月30万円あれば、生活は可能ですが貯金できるかどうかは住居費次第で大きく変わってきます。
都市部で家賃10万円の物件に住んでいる場合、そこに食費・光熱費・通信費・保険料を加えると月25万円はすぐに超えます。残り5万円から急な出費やレジャー費が出ていくと、貯金は限りなくゼロに近づくのが現実です。
以下は支出イメージです。
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 家賃 | 100,000円 |
| 食費 | 85,000円 |
| 光熱・通信費 | 30,000円 |
| 保健・日用品 | 40,000円 |
| 合計 | 約255,000円 |
「少しでも貯めたい」という方には、固定費を圧縮したうえで家計簿アプリでの管理習慣化が効果的です。
「食費が高すぎる気がする…」と感じたら、週単位で予算を決めて買い物回数を減らすだけでも成果は出ます。
月3万円のやりくりができれば、年間36万円の貯蓄につながります。
手取り40万円|支出の管理次第で月3〜5万円の貯蓄が可能
手取り40万円クラスになると、家計に少し余裕が出てきます。支出をコントロールすれば、月3万〜5万円の貯金も十分に狙えるラインです。
ただし油断は禁物。収入が増えると支出もつい緩みやすく、気づけば「出ていくペースも増えていた」なんてことも。
支出バランスの一例を表にまとめました。
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 家賃 | 120,000円 |
| 食費 | 90,000円 |
| 教育費 | 30,000円 |
| 固定費+雑費 | 100,000円 |
| 合計 | 約340,000円 |
上記でも6〜7万円ほど余る構造になるため、そこから3万〜5万円を先取り貯金に回すのがコツです。
教育費や医療費のように「じわじわ増えていく支出」は月ベースでは見えにくいため、年単位で予備費枠を確保しておくことをおすすめします。
手取り50万円|家計に余裕が生まれ“計画的な貯金”が可能に
手取り月50万円までくると、生活にかなりのゆとりが出ます。貯金も月5〜10万円以上が現実的で、教育資金・老後資金の準備もスタートしやすいステージです。
ただし気をつけたいのが、「収入がある=無意識に浪費しやすい」状態に陥ること。旅行・外食・習い事・趣味などが増える一方で、「気づけばお金が残っていない…」という家庭も少なくありません。
理想的な支出配分は以下のようになります。
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 家賃 | 150,000円 |
| 食費 | 100,000円 |
| 教育費 | 50,000円 |
| 固定費・趣味・その他 | 150,000円 |
| 貯金 | 50,000円 |
上記ラインの家庭では、貯金の自動化(先取り貯金)と、定期的な支出見直しのルーティン化がポイントです。
「家計にゆとりがある今こそ整えるタイミング」と考え、未来に備える土台づくりを始めましょう。
とはいえ、「うちは本当にこの支出配分で大丈夫?」「もっと効率的な貯金方法があるのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
- 何度相談しても無料
- スマホやPCからいつでもOK(カメラオフ対応)
- 30秒で予約完了。今すぐ相談スタート!
収入額に合わせた支出バランスの見直しや、将来を見据えた資産形成プランまで、暮らしのお金のプロが中立的にサポートしてくれます。
今の家計が“使いすぎゾーン”に入っていないか、一度チェックしてみてください。
【もらえる給付制度まとめ】4人家族が申請すべき支援金・補助一覧

4人家族(子育て世帯)なら受け取れる支援制度がたくさんあります。
申請または自動で支給される代表的な制度は以下の通りです。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 児童手当 | 0~3歳:月15,000円 3歳~高校生:月10,000円※第3子以降は月30,000円 |
| 出産・子育て応援給付金 | 妊娠届出時:5万円 出産後:子ども1人につき5万円 |
| 出産育児一時金 | 出産1回につき50万円(健康保険加入者) |
| 育児休業給付金 | 休業開始〜6ヶ月:賃金の67% 6ヶ月以降:賃金の50% |
今すぐ使える制度を1つでも活用すれば、年間数十万円単位の支援になる可能性があります。
「知らずに損していた…」とならないように、まずは手元の家計状況と照らし合わせながら、もらえる支援を確認してみましょう。
4人家族の生活費に関するよくある質問

4人家族の家計に関しては、「みんなどうしてる?」「どれくらいが普通?」といった疑問を抱える方が多くいます。
ここでは、特に関心の高い質問を5つに絞り、統計データや家計のリアルに基づいた回答を紹介します。
4人家族の生活費の内訳はどうなってる?
総務省「家計調査(2024年)」によると、4人家族の生活費の内訳は以下のとおりです。
| 支出項目 | 平均金額/月 |
|---|---|
| 食料 | 92,033円 |
| 住居(持ち家含む) | 17,642円 |
| 光熱・水道 | 22,274円 |
| 家具・家事用品 | 11,810円 |
| 被服及び履物 | 12,696円 |
| 保健医療 | 13,337円 |
| 交通・通信 | 48,810円 |
| 教育 | 27,437円 |
| 教養娯楽 | 35,919円 |
| その他の消費支出 | 43,539円 |
| 合計 | 325,497円 |
一般的な4人世帯(一家4人)はいくらもらってる?
一般的な4人世帯の手取り収入は、月30万〜40万円台がボリュームゾーンです。もちろん、地域差や職業・雇用形態によって幅があります。
なお、厚生労働省の調査では、児童のいる世帯の平均所得は年間約524万円というデータもあります。
参考:厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査 平均所得金額-平均世帯人員-平均有業人員,年次別」
「いくらもらっているか」は家庭により違いますが、手取り月35万円前後で平均的とされるラインです。
子供1人の場合の平均生活費や雑費平均はいくら?
子供が1人だけの家庭、いわば3人家族の平均生活費は35.7万円(月)です。
食料品は約85,000円、雑費は約70,000円前後となっています。
参考:厚生労働省「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)」
共働きでも生活ギリギリなのはなぜ?
共働きでも生活がギリギリになる理由の多くは、「支出の優先順位が曖昧」「固定費が高い」「家計管理がされていない」という点にあります。
共働き世帯は収入が2本ある安心感から、家賃・保険・車・教育費・外食費などが無意識に膨らみやすく、結果的に支出過多になりがちです。
また、子どもの教育や保育費、通勤交通費、外食の増加なども、片働き世帯より出費が多くなりやすい要因です。収入が多くても、家計管理が追いついていなければ貯まらない家庭になります。
4人家族(一般家庭)に必要なお金や一般的な生活費はいくら?
一般的な4人家族(夫婦+子供2人)が普通に暮らすために必要な生活費は、月30万〜35万円が目安です。
この中には、食費・住居費・光熱費・通信費・教育費・雑費などが含まれ、生活水準を大きく落とさずに維持できるラインとされています。
仮に家賃込みで月40万円を超えている場合は、「支出の見直しが必要なゾーン」と捉えるのが妥当です。
まとめ:支出にメリハリをつけて生活費をコントロールしよう
四人家族の生活費相場や支出の目安、収入別の貯金ライン、都市部と地方のコスト差まで解説しました。
生活費はなんとなくで使っていると気づかぬうちに赤字に陥ってしまいます。収入とのバランスを確認しながら、家庭ごとの支出配分を明確にしておくことが大切です。
- 相談は何度でも無料
- スマホやPCで手軽に診断OK(カメラオフも可)
- 30秒で予約完了!今すぐ相談スタート
今の家計の弱点や見直しポイントがわかるだけでなく、将来に向けた具体的な対策までアドバイスがもらえます。
まずはお気軽に、あなたの家計を“見える化”してみてください。