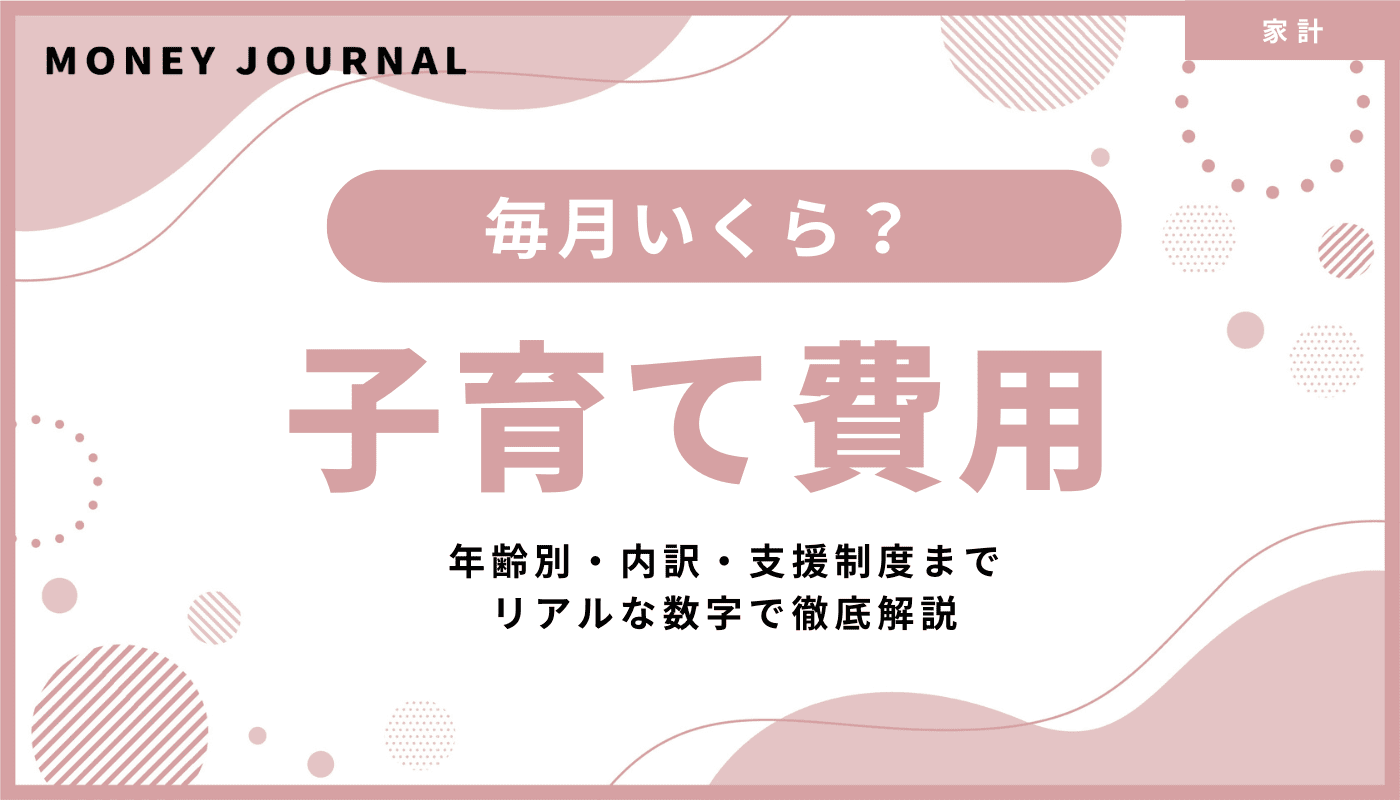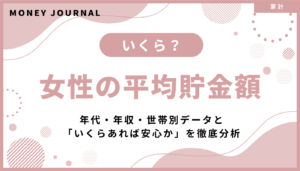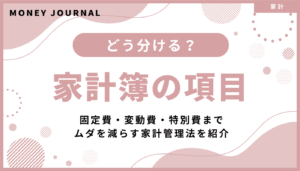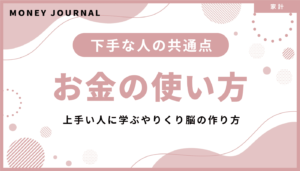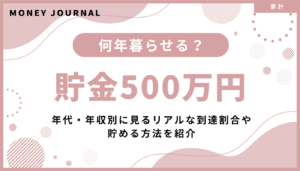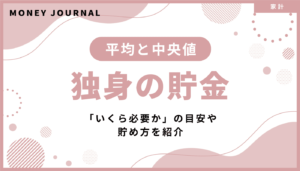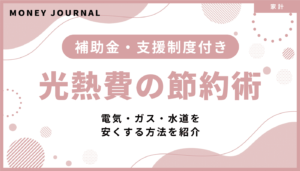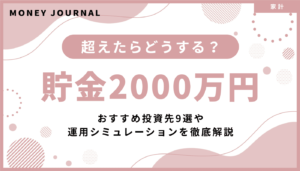- 「子どもにかかる毎月の費用、どこまでが普通なんだろう…」
- 「私立や習い事って、正直みんなどれくらい出してるの?」
- 「支援制度があるって聞くけど、実際どれくらい助かるの?」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、子育て費用は年齢や通う学校によって大きく変動します。
以下に、年齢別の毎月の目安を一覧でまとめました。
| 年齢・学年 | 月々の平均費用 | 主な出費の内訳(上位) |
|---|---|---|
| 0歳 | 約7.7万円 | 初期用品、紙おむつ、祝い事など |
| 1~3歳 | 約7.9万円 | 食費、衣料費、おもちゃなど |
| 4~6歳 | 約9.9万円 | 保育料、給食費、習い事 |
| 小学生 | 約9.7万円 | 学校関連費、学童、食費 |
| 中学生 | 約12.9万円 | 塾代、制服、交通費など |
| 高校生 | 約12.8〜26.2万円 | 授業料(公立or私立)、スマホ代など |
| 大学生 | 約11.4〜16.1万円 | 学費、仕送り、生活費 |
参考:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
参考:内閣府政策統括官「インターネットによる子育て費用に関する調査 報告書」
参考:日本学生支援機構「令和2年度学生生活調査結果」
※金額は全国平均をベースにした概算です
本記事では、毎月の子育て費用の実態を「年齢別×内訳」で具体的に解説します。さらに「家計のどこを見直せばいいのか」「使える支援制度には何があるか」まで徹底的にカバーしています。
「今の家計で足りるのか不安…」という方は、ぜひ参考にしてください。
こんなにかかるの?毎月の子育て費用が重くなる3つの理由

子育て費用は「必要なものを買っているだけなのに、いつの間にか支出が増えている」と感じる家庭がほとんどです。
その理由は、大きく以下の3点に分けられます。
育児費用は「年齢とともに右肩上がり」になる
育児にかかるお金は年齢が上がるほど増えるのが一般的です。0歳の頃はおむつ・ミルク・ベビー用品などが中心ですが、成長するごとに支出の項目が増えていきます。
具体的には、以下のようなイメージです。
| 年齢 | 主な支出内容 |
|---|---|
| 0歳 | おむつ・ミルク・ベビー服・予防接種など |
| 1~3歳(未就学児) | 保育料・おやつ・衣類・外遊び関連の道具 |
| 4~6歳(幼稚園児) | 幼稚園・保育園の費用、習い事、行事費 |
| 小学生 | 学校関連費(教材・給食・PTA)・学童・文具 |
| 中高生 | 塾代・スマホ代・交通費・部活動費・私服代など |
小学生の頃は月に数千円〜1万円ほどだった支出が、中学生になると塾代だけで月2〜3万円、さらにスマホや定期代、制服費用なども加わります。高校生になると通学費や外食費、大学受験の準備費用までかかるようになり、月10万円を超える家庭も実際にあります。
私立or習い事次第で月10万円以上の差も
同じ年齢の子どもでも、どんな学校に通わせるか、どんな習い事をしているかによって、出ていくお金の幅は大きく変わります。
私立小・中・高校の学費は公立の3〜10倍になるのが特徴的です。また、スイミングやピアノ、英会話などの習い事も月5,000円〜2万円程度かかるため、2つ3つと掛け持ちすればそれだけで月5万円近くになることもあります。
家計簿をつけていないと“なんとなく出費”が増える
毎日がバタバタしている中で、家計管理が後回しになっている家庭はとても多いです。どこにいくら使ったのかをきちんと把握していないと、「なんとなく使っていたつもりが、気づけば家計が回らない」という状況に陥りやすくなります。
たとえば、以下のような出費が知らないうちに積み重なっている方も多いでしょう。
- 週末の外食(1回4,000円 × 週2回で月3万円超)
- 日用品の買い足し(1回1,000円 × 月8回で8,000円)
- おもちゃや衣類(セールでつい購入、月1〜2万円)
- レジャー費(テーマパーク・遊園地で1回1万円前後)
ざっくり合計するだけでも、月5万円以上になっていることもあります。
とはいえ、「家計簿をつける時間がない」「やってみたけどうまく続かない」という悩みを抱える方も少なくありません。
そんなときこそ活用したいのが、プロのファイナンシャルプランナーによる無料のオンライン家計診断です。
「気づかない出費が多いかも…」という方も、家計の見える化から始めてみましょう。
診断は何度でも無料、スマホ・PCから気軽に相談できるので、家計の不安がある方は一度試してみてください。
【年齢別】毎月の子育て費用

この章では、国の統計や平均データをもとに、年齢別の「毎月のリアルな子育て費用」をわかりやすく紹介していきます。
費目の内訳や支出のポイントも解説していますので、「うちは高いの?普通なの?」と気になっている方はぜひ参考にしてください。
0歳/約7.7万円|初期費用やお祝い事で費用がかさむ
赤ちゃんが生まれて最初の1年は、お金の使い方が特殊な時期です。
毎月平均で約7.7万円かかりますが、実際は生後すぐにドンと費用が集中する構造になっています。
以下が、0歳児の年間費用と月換算の平均です。
| 費目カテゴリ | 年間費用(円) | 月額換算(円) |
|---|---|---|
| 衣類・服飾雑貨費 | 88,513 | 約7,376 |
| 食費 | 111,126 | 約9,260 |
| 生活用品費 | 222,491 | 約18,541 |
| 医療費 | 12,608 | 約1,051 |
| 保育費 | 51,453 | 約4,288 |
| 学校外教育費 | 8,581 | 約715 |
| 学校外活動費 | 2,394 | 約199 |
| 子どもの携帯電話料金 | 0 | 0 |
| おこづかい | 159 | 約13 |
| お祝い行事関係費 | 159,354 | 約13,279 |
| 子どものための預貯金・保険 | 221,193 | 約18,433 |
| レジャー・旅行費 | 53,375 | 約4,448 |
| 合計 | 931,246 | 約77,604 |
出産祝いのお返しや内祝い、百日祝いの記念撮影など、イベントに関連する文化的支出が想像以上に重なります。
「出産=命がけの初期投資」とも言えるくらい、0歳の支出は“祝いと準備”に集約されています。
また、学資保険や定期預金といった「将来への備え」もすでに始まるタイミングです。
1~3歳/約7.9万円|子ども用品・衣料費が約2割
1〜3歳になると、生活は少しずつ安定してきますが、支出の波は相変わらず大きいままです。
月平均は約7.9万円。衣類・生活用品・保育費の負担が家計をじわじわ圧迫してきます。
以下が実際の年間支出と月換算です。
| 費目カテゴリ | 年間費用(円) | 月額換算(円) |
|---|---|---|
| 費目カテゴリ | 年間費用(円) | 月額換算(円) |
| 衣類・服飾雑貨費 | 66,941 | 約5,579 |
| 食費 | 188,336 | 約15,695 |
| 生活用品費 | 126,457 | 約10,538 |
| 医療費 | 11,641 | 約970 |
| 保育費 | 180,522 | 約15,043 |
| 学校外教育費 | 18,222 | 約1,519 |
| 学校外活動費 | 13,712 | 約1,143 |
| 携帯電話料金 | 64 | 約5 |
| おこづかい | 417 | 約35 |
| お祝い行事関係費 | 33,521 | 約2,793 |
| 預貯金・保険 | 202,361 | 約16,863 |
| レジャー・旅行費 | 112,786 | 約9,399 |
| 合計 | 954,381 | 約79,532 |
おむつ代こそ落ち着いてきますが、服と靴がどんどんサイズアウトしていく時期です。春・秋・冬と毎シーズン服を揃える必要があり、靴も半年で買い替えという家庭も珍しくありません。
さらに、食事量が増えることで食費も上昇し、保育料やレジャー費も加わると、支出全体が底上げされていきます。
4~6歳/約9.9万円|幼稚園・保育園関係費が約4割
子どもが4〜6歳になると、集団生活が日常となり教育費が一段と存在感を増してきます。
月平均は約9.9万円、年間では120万円近く。保育料だけで支出の3割を占めています。
以下に、年齢別の平均支出をまとめました。
| 費目カテゴリ | 年間費用(円) | 月額換算(円) |
|---|---|---|
| 衣類・服飾雑貨費 | 64,961 | 約5,413 |
| 食費 | 237,657 | 約19,805 |
| 生活用品費 | 79,690 | 約6,641 |
| 医療費 | 13,178 | 約1,098 |
| 保育費 | 347,019 | 約28,918 |
| 学校外教育費 | 35,540 | 約2,962 |
| 学校外活動費 | 56,853 | 約4,738 |
| 携帯電話料金 | 162 | 約13 |
| おこづかい | 1,874 | 約156 |
| お祝い行事関係費 | 39,424 | 約3,285 |
| 預貯金・保険 | 171,089 | 約14,257 |
| レジャー・旅行費 | 144,849 | 約12,071 |
| 合計 | 1,192,296 | 約99,358 |
習い事を始める子も多くなり、「英語+ピアノ+スイミング」で月2万円を超えるご家庭も出てきます。
また、入園時の制服代・カバン・教材費など入学前後のイレギュラー出費も大きなインパクトになります。
行事費・写真代・親の参加費も積み重なり、「月謝だけのつもりが毎月追加出費がある」という感覚になりやすいです。
小学生/約9.7万円|食費・学校関連費が約5割
小学生になると、家庭での生活リズムが整う一方で、毎月の出費も本格的に増え始めます。
月平均の子育て費用は約9.7万円。中でも目立つのが、食費と学校関連の支出です。
以下は、小学1年〜6年を通じた平均的な費用の内訳です。
| 項目 | 年間平均費用(円) | 月間平均費用(円) |
|---|---|---|
| 食費(家庭内+外食+おやつ) | 174,220 | 14,518 |
| 衣類・身の回り品 | 46,208 | 3,851 |
| 学校教育関連費 | 139,791 | 11,649 |
| 学校外学習費(塾・通信など) | 97,643 | 8,137 |
| 習い事・課外活動費 | 87,956 | 7,330 |
| 医療・医薬品関連 | 16,024 | 1,335 |
| 子ども用品・家具・寝具類 | 56,076 | 4,673 |
| 行事・祝い費 | 39,318 | 3,276 |
| 貯蓄・保険 | 75,982 | 6,332 |
| レジャー・旅行費 | 106,403 | 8,867 |
| 合計 | 839,621 | 69,968 |
家庭での食事・おやつ・外食などを含めた食費だけで月1.4万円超かかっており、成長に伴って食べる量も増えるため、学年が上がるごとに負担は大きくなります。
小学校の6年間は「教育投資の基盤づくり」ともいえる時期です。
次の中学進学で費用がさらに増えることを想定して、今のうちから支出傾向を把握し、備えておくことが大切です。
中学生/約12.9万円|学校関連費が約4割
中学生になると、学校にかかるお金と学習費の負担が一気に増えます。
月平均では約12.9万円。とくに目立つのが、学校関連費と塾代の2本柱です。
下記は中学1年〜3年の平均的な支出データです。
| 項目 | 年間平均費用(円) | 月間平均費用(円) |
|---|---|---|
| 食費(家庭+外食+おやつ) | 369,492 | 30,791 |
| 衣類・身の回り品 | 35,077 | 2,923 |
| 医療・医薬品関連 | 19,690 | 1,641 |
| 子ども用品・家具・寝具類 | 60,285 | 5,024 |
| 学校関連費(授業料・教材・給食・交通など) | 274,691 | 22,891 |
| 学校外学習費(塾・通信・家庭教師など) | 297,057 | 24,755 |
| 習い事・課外活動費 | 66,680 | 5,557 |
| 行事・祝い費 | 38,251 | 3,188 |
| 貯蓄・保険 | 193,389 | 16,116 |
| レジャー・旅行費 | 106,715 | 8,893 |
| 合計 | 1,460,327 | 121,694 |
公立中学でも、教科書以外の教材・クラブ活動費・交通費・給食費・修学旅行代などが月2.2万円超。制服や部活動用の道具も高額になるため、「進級しただけでこんなに増えるの?」と驚くご家庭も多いです。
高校・大学進学を見据えた資金づくりを始めるなら、中学時代が分岐点です。毎月の収支を整理して、先の出費にも耐えられる家計をつくっていきましょう。
高校生/12.8万円~26.2万円|公立・私立で異なる
高校生になると、子育て費用は一段と跳ね上がります。文部科学省の調査によると、高校3年間の学習費総額は、公立で約154万円、私立では約315万円にのぼります。
1年あたりで見たときの目安は以下のとおりです。
| 学校区分 | 年間費用 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 公立高校 | 約45万〜60万円 | 約3.8万〜5万円 |
| 私立高校 | 約93万〜120万円 | 約7.8万〜10万円 |
この金額には、授業料・教材費・制服代・交通費・クラブ活動費などが含まれています。
大学生/11.4万円~16.1万円|国立・公立・私立で異なる
大学生になると、家庭が負担する費用の考え方も少し変わります。
学費や生活費を含めた年間支出のうち、家庭が支援するのは全額ではなく一部であることが一般的です。
以下は、日本学生支援機構の調査に基づく「家庭からの給付」の平均額をもとにした、子育て費用の実質的な目安です。
| 居住形態・大学区分 | 家庭からの年間支援額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 自宅通学(国公立) | 約99万円 | 約8.2万円 |
| 自宅通学(私立大学) | 約170万円 | 約14.2万円 |
| 自宅外通学(国公立) | 約150万円 | 約12.5万円 |
| 自宅外通学(私立) | 約225万円 | 約18.7万円 |
*国公立…国立大学、公立大学
大学生活の支出は“親子で支えるもの”という考え方も広まりつつありますが、家計としては最低でも年間100万円前後を想定しておくとよいでしょう。
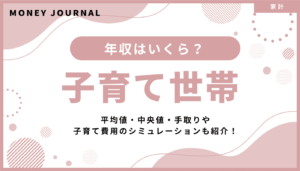
毎月の子育て費用に使える支援制度一覧
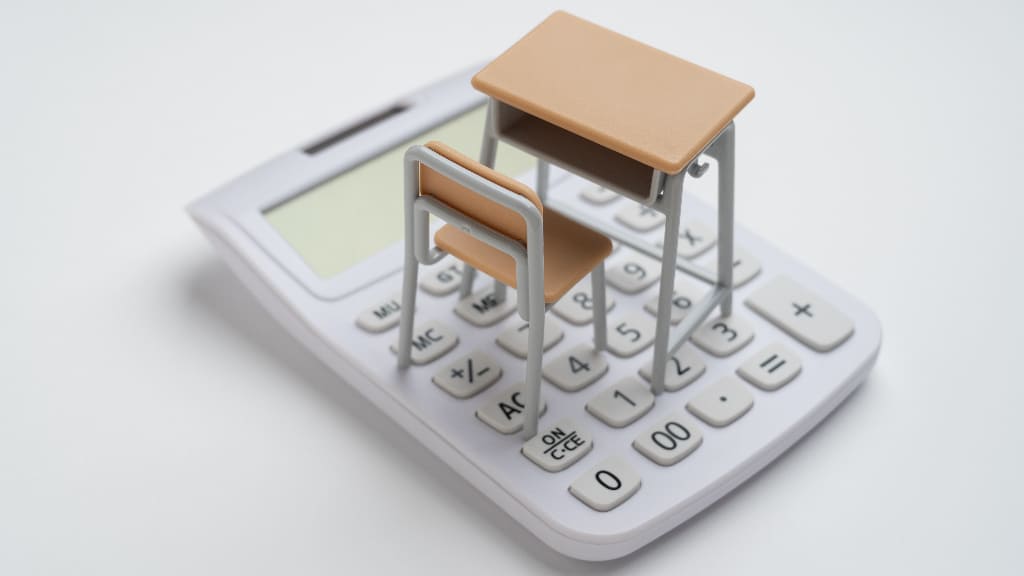
子育て家庭が活用しやすい支援制度をピックアップして紹介します。
児童手当
児童手当は、0歳から高校卒業まで(18歳年度末まで)の子どもを養育している家庭に支給される子育て支援です。
2024年10月からは支給対象が高校生相当まで拡大され、金額や所得制限の仕組みも見直されています。
以下に、年齢・子の人数による支給額の目安をまとめます。
| 子どもの年齢 | 支給額(月額) |
|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円(第3子以降:30,000円) |
| 3歳〜高校生年代まで | 10,000円(第3子以降:30,000円) |
※「第3子以降」とは、18歳までの子ども全体で3人目以降を指します。過去の数え方(同一世帯で第3子以降)とは異なるため注意が必要です。
出産・育児休業給付金
出産や育児で仕事を休む場合、雇用保険・健康保険に加入していれば、給与の一部が補償されます。
- 出産手当金:出産前後の約14週間、給与の約3分の2を支給(会社員・公務員等が対象)
- 育児休業給付金:育休開始から180日までは賃金の67%、それ以降は50%
妊婦のための支援給付
妊婦さんへの経済的支援として、「妊婦のための支援給付」が各自治体で実施されています。胎児の心拍が確認されると申請でき、原則5万円+子どもの人数×5万円が支給されます(自治体によりクーポン支給の場合あり)。
申請は住民票のある市区町村の窓口で行い、申請時には保健師との面談を通じて、妊娠・出産に関する相談や他制度の紹介も受けられます。
幼児教育・保育の無償化
2019年にスタートした制度で、3歳〜5歳の子どもは全世帯が保育料・幼稚園料の無償対象となります。
0〜2歳も、住民税非課税世帯なら保育施設の利用料が無料です。
注意点は、給食費・延長保育・送迎バス代などは自己負担となる点です。
申請は自治体の子ども家庭課などで受け付けています。
子ども医療費助成
子どもの医療費をサポートしてくれる制度で、通院・入院にかかる費用を無料または一部負担で済ませられる仕組みです。
一例として、東京23区内では以下の内容となっています。
| 年齢区分 | 助成内容 |
|---|---|
| 中学生まで | 通院・入院ともに無料 |
| 高校生以上 | 一部自己負担(上限あり) |
対象年齢・所得制限・自己負担の有無などは自治体によって異なります。
高等学校等就学支援金
高校生の授業料を支援する制度で、保護者の所得に応じて支給額が決まります(年収目安は910万円未満)。公立は実質無償、私立も最大年間約40万円〜67万円の支給があります。
| 学校種別 | 月額支給額 | 年間上限額 |
|---|---|---|
| 公立高校(全日制) | 9,900円 | 約118,800円 |
| 私立高校(目安) | 最大33,000円+加算 | 最大約670,000円程度 |
申請は入学時に学校を通じて行いますが、提出忘れや期限超過は支給されないため注意が必要です。進学前に制度内容を確認しておくと安心です。
学資保険
学資保険は公的制度ではありませんが、教育資金を計画的に準備したい方に適した民間サービスです。
加入後は、子どもの進学タイミングにあわせて満期金や祝い金が支給されます。
主な特徴は以下のとおりです。
- 中学・高校・大学進学時に一時金を受け取れる
- 契約者(親)が万が一の場合、保険料の支払い免除+満額保証
- 契約期間中は資産形成効果もある
0〜3歳ごろの早期加入が有利とされており、後悔しない教育資金づくりをしたい方には特におすすめです。

毎月の支出を“見える化”!子育て家計の管理術3選

誰でも実践できる3つの家計管理術を紹介します。
エクセル管理は「年齢×費目×月次」で見える化に最適
家計簿アプリが続かない方には、エクセル管理がシンプルで効果的です。
たとえば以下のような構成でシートをつくると、見やすく整理できます。
- 行:おむつ・保育料・食費・習い事・教育費などの費目
- 列:月ごと(1月〜12月)
- シート:子どもごと、または年齢別で分ける
1行1列に支出を入力するだけで、どの時期に何にお金がかかっているかがひと目で見えるようになります。
家計簿アプリは自動分類×通知で三日坊主を防ぐ
手入力が続かない場合は、アプリの自動記録機能が便利です。
銀行口座やクレジットカードと連携すれば、使ったお金が自動で分類されます。アラート通知を活用すれば、予算を超えそうな費目にも早めに気づけるでしょう。
子ども用口座を活用して「支出と貯金」を分けて管理
教育資金と生活費が混ざると、うっかり使い込みやすくなります。
児童手当や祝い金は子ども名義の口座に入れておき、日々の支出は家庭口座で管理すると安心です。
子どもに通帳を見せながら貯金の話をすることで、お金の使い方を学ばせるきっかけにもなります。

毎月の子育て費用に関するよくある質問

毎月の子育て費用に関するよくある質問と回答を紹介します。
子ども1人育てるのにトータルでいくらかかる?
内閣府や文部科学省のデータによると、子ども一人を大学まで育てるためには、総額で約2,000万円〜3,000万円がかかるとされています。
0歳の育児費用は具体的にどんな項目がある?
0歳児にかかる主な費用は、おむつ代・ミルク代・ベビー服・生活用品・医療費などです。
第2子以降で本当に費用は軽くなるの?
第2子以降は、衣類やベビー用品のお下がり活用・育児グッズの使い回しができるため、初期費用が抑えやすいです。
教育費と養育費の違いは?どう分けて考える?
教育費は学校・塾・教材などの「学び」にかかる費用で、養育費は衣食住・医療・生活費など「生活」にかかる費用です。
「子ども手当」だけで備えるのは危険?
児童手当は月15,000円年18万円)なので、子育てにかかる総額に比べるとごく一部の補助にすぎません。
家計が苦しいとき、削るべき費目はどれ?
まずは固定費(通信費・保険料・サブスク)の見直しを優先しましょう。次に、外食やレジャーなどの変動費を月ごとに上限を決めてコントロールするのが効果的です。
習い事は月いくらまでが妥当?世間の平均は?
文部科学省の統計によると、小学生の習い事にかかる月額相場は約1.4万円〜2万円です。ただしピアノや英会話など個別指導型は1教室で1万円以上かかるため、家庭の収入に対する割合(目安は5〜10%)を意識し、無理のない範囲で継続することが大切です。
まとめ:月ごとの子育て費用を「見える化→対策」で未来の不安は消せる
この記事では、子どもの年齢別にかかる毎月の子育て費用やその内訳、活用できる支援制度について解説しました。
支出は年齢とともに増加し、家庭ごとの教育方針によっても変動します。そのため、まずは“見える化”で現状把握を進め、無理のない範囲で備えることが大切です。
少しずつでも構いません。できるところから管理を始めて、安心できる未来を描いていきましょう。