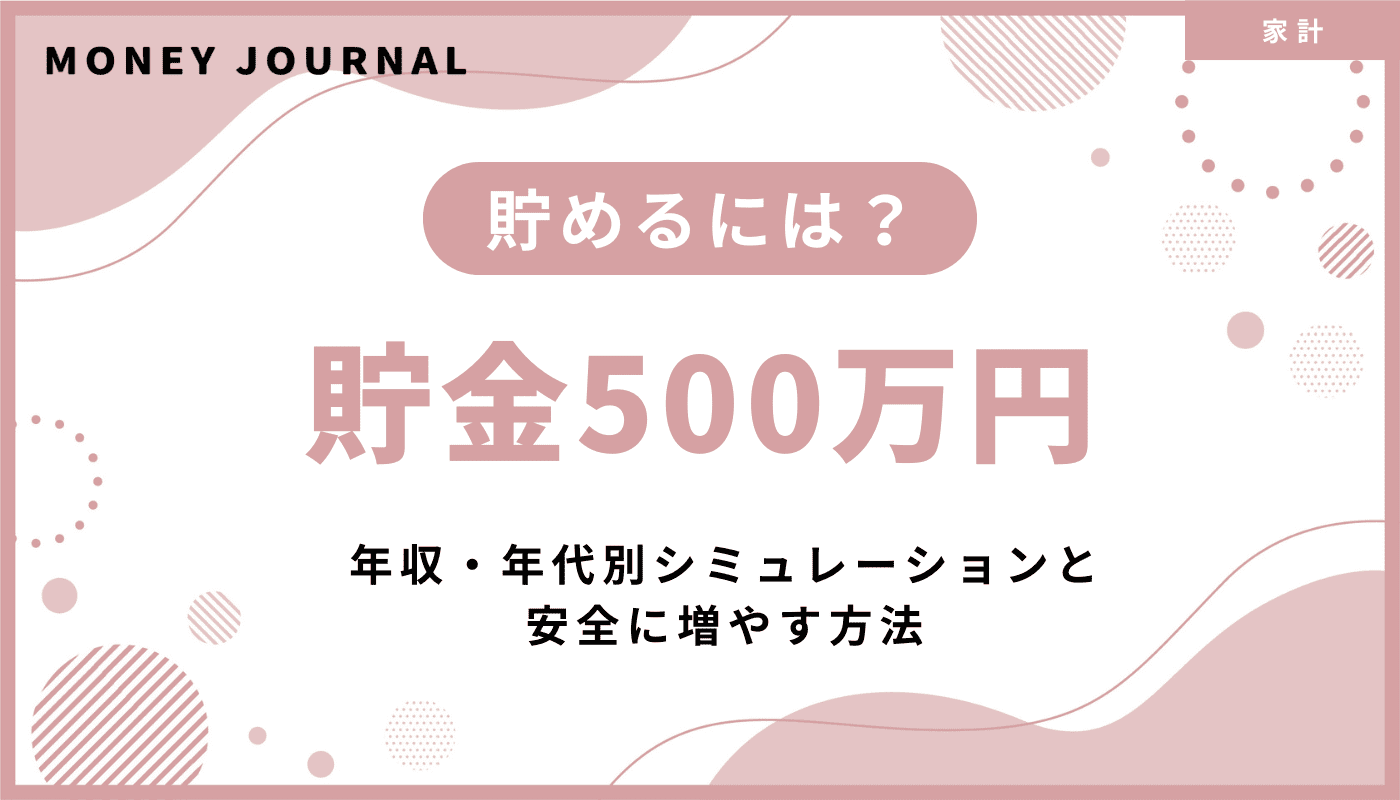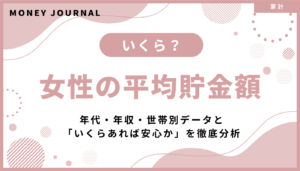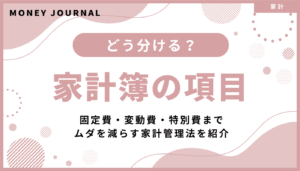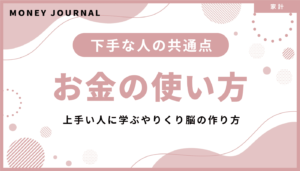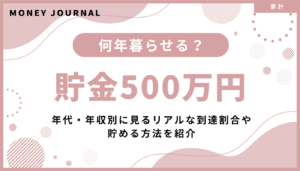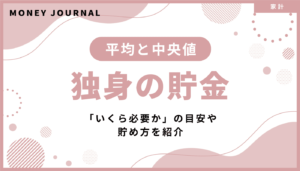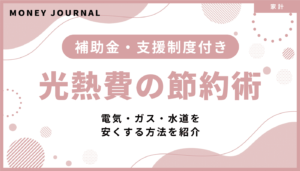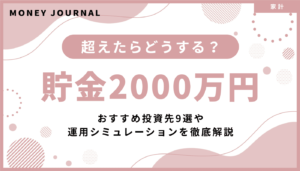- 「なかなか貯金が増えない」
- 「500万円ってすごい金額に感じる」
- 「自分の収入で本当に到達できるのか不安」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、貯金500万円を貯める方法としては以下が有効です。
- 目的と期間を明確にする
- 家計簿で収支を把握する
- 固定費を削減する
- 変動費をコントロールする
- 生活費と貯金口座を分ける
- 自動積立・先取り貯金を活用する
- 初心者向け資産運用を始める
本記事では、500万円という貯金額の世間での位置づけから、教育費や老後資金などの安心できる水準との比較、そして具体的な積立額の目安まで整理して解説します。
着実に貯金額を増やしていきたい方は、ぜひ参考にしてください。
貯金500万円は多いのか?世間的な位置づけ

自分と同じ年収・年代の人はいくら貯金があるのか気になるでしょう。
ここでは年収別の平均貯金額と、年代別の平均貯金額を紹介します。
年収別の平均貯金額と割合
まずは30歳代の年収別の平均貯金額を紹介します。
| 年間収入 | 平均金融資産保有額※ |
|---|---|
| 300万円未満 | 256万円 |
| 300万円以上~500万円未満 | 450万円 |
| 500万円以上~750万円未満 | 851万円 |
| 750万円以上~1,000万円未満 | 1,030万円 |
| 1,000万円以上~1,200万円未満 | (データ無し) |
| 1,200万円以上~ | 2,448万円 |
出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)」」設問間クロス集計
この結果より、収入が多いほど、貯金を含めた金融資産の所有額が多いことが分かります。

年代別の中央値と金融資産
次に20代からの年代別の平均貯金額(単身世帯)を紹介します。
年収300万円以上~年収500万円未満の場合:
| 年代 | 平均金融資産保有額※ |
|---|---|
| 20歳代 | 230万円 |
| 30歳代 | 450万円 |
| 40歳代 | 772万円 |
| 50歳代 | 613万円 |
| 60歳代 | 2,704万円 |
年収500万円以上~年収750万円未満の場合:
| 年代 | 平均金融資産保有額※ |
|---|---|
| 20歳代 | 554万円 |
| 30歳代 | 851万円 |
| 40歳代 | 1,384万円 |
| 50歳代 | 1,595万円 |
| 60歳代 | 4,230万円 |
出典:金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)』クロス集計
これらの結果より、40代や50代になるほど、貯金を含めた金融資産の保有額が多いことが分かります。

単身世帯と夫婦・2人以上世帯の内訳
世帯構成別にみる割合は、下記のとおりです。
| 世帯構成 | 非保有 | 500万円未満 | 500~700万円未満 | 700万円以上 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 34.5% | 32.5% | 5.4% | 25.3% | 871万円 | 100万円 |
| 2人以上世帯 | 23.1% | 28.1% | 6.9% | 38.6% | 1,291万円 | 400万円 |
参照元: 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年)」
単身世帯の場合は貯金額500万円未満の割合が約65%、2人以上世帯の場合は貯金額500万円未満の割合が約51%です。
貯金額500万円について、単身世帯の場合は貯金額が多い方、2人世帯の場合は平均的な貯金額やや多めであるとわかります。

貯金ゼロ世帯の割合
金融広報中央委員会が実施した「家計の金融行動に関する世論調査2022年」によると、貯金を含めた金融商品を「いずれも保有していない」と回答した世帯の割合は4.9%でした。
5.6%であった2018年から見ると、徐々に減少傾向ではありますが、ある一定程度の世帯の貯金を含めた金融商品をまったく保有していない状態であることが分かります。
このデータから見えるのは、「少数派とはいえ貯金ゼロ世帯が一定数存在する」という現実です。一度も金融商品を持っていないという状況は、将来の突発的な支出や老後資金に対して非常にリスクが高い状態といえます。
「今のままで大丈夫だろうか」「貯金を始めたいけど何ができるのかわからない」と感じる方は、マネーコーチの無料オンライン家計診断を利用してみるとよいでしょう。

貯金はいくらあれば安心?500万円じゃ足りない?

「とにかく貯金は多いに越したことはない」と考え、貯め続けている方も多いですが、実際はいくらくらいあると安心できるものなのでしょうか。
ここでは、人生の二大出費である「子供の教育費用」と「老後の必要な資金」を紹介します。
子供の教育に必要な金額
子供の教育費用はどれくらい準備しておけばいいのでしょうか?仮に子供が3歳から幼稚園に通い、大学まで進学した場合、教育費が必要になる期間は19年にもなります。
住友生命の調査では、以下の数字が公開されています。
- 幼稚園から大学まで全て国公立に通った場合:546万円
- 幼稚園から中学まで公立で、高校・大学は私立(文系)に通った場合:833万円
- 幼稚園から中学まで公立で、高校・大学は私立(理系)に通った場合:974万円
さらに中学・高校で塾に通ったとすると、ここに加えて約170万円が必要になります。子供の教育費用には莫大な金額が必要になります。
参考:住友生命「教育費の平均は?幼稚園~大学の教育費を解説!【4パターン】」より算出

老後に必要な金額
老後には、どれくらいの費用が必要となるのでしょうか?定年退職後の大きな収入となるのが、公的年金です。
厚生労働省の発表によると、老齢年金受給額の平均は月14.6万円でした。
年金だけでは月に7.5万円の生活費が不足します。定年退職を65歳として平均寿命から考えると老後は20年近く続きます。月7.5万円の不足は、20年間を合計すると1,800万円となります。つまり、老後に対しては最低でも1,800万円の蓄えが必要となってきます。
しかし、これも最低限の生活費を賄うための資金となることは忘れてはいけません。余裕ある老後を送るには、これ以上の金額が必要です。

ケガ・病気・災害に備えるための生活防衛資金
500万円を貯める前に、元本割れしない生活防衛資金を準備しましょう。仕事ができなくなったときに生活を維持するためのお金です。
目安は生活費の3〜6か月分です。月20万円の独身なら60万〜120万円、月30万円の家族世帯なら90万〜180万円程度。元本が減らない形で預貯金や定期預金に置いておきましょう。
生活防衛資金があれば、不意の支出があっても生活を続けられます。そのうえで余ったお金を貯金や投資に回せば、無理なく500万円の目標に近づけるでしょう。

500万円を貯めるには何年必要?月いくら積立すべきか

貯金500万円を貯めるために必要な年数は、下記のとおりです。毎月、そして年2回のボーナス時に同じ金額を貯金すると考えて算出しています。
| 月・ボーナスごとの貯金額 | 500万円貯まるのに必要な期間 |
|---|---|
| 10,000円 | 35.7年 |
| 20,000円 | 17.9年 |
| 30,000円 | 11.9年 |
| 40,000円 | 8.9年 |
| 50,000円 | 7.1年 |
| 60,000円 | 6.0年 |
| 70,000円 | 5.1年 |
| 80,000円 | 4.5年 |
| 90,000円 | 4.0年 |
| 100,000円 | 3.6年 |

貯金500万円を貯められない人の共通点

貯金が思うように増えない人には、いくつかの共通点があります。理由は収入の多さや少なさだけではありません。考え方や行動のパターンが似ているため、気づかないうちに貯まらない生活を繰り返してしまいます。
ここでは代表的な3つの特徴を紹介します。
「貯金できない」と思い込んでいる
「自分は貯金できない」と決めつけている人は多いもの。趣味や買い物を優先して、給料日前にはお金が残っていないような生活を繰り返している人に多いです。
けれども、いきなり大きな額を貯める必要はありません。月に3,000円だけでも構いません。口座に数字が積み上がっていく感覚を一度でも味わえば、自然と次につながります。
よく「給料が上がったら始める」と言う人がいますが、それでは一生始まりません。収入が増えると、外食や買い物など出費も増えるからです。
収支を把握していない
お金が残らない人の多くは、収支を把握していません。気づけば財布が空っぽでも、何に使ったかは思い出せないというような暮らしです。
銀行の明細やカードの履歴を確認すれば、出費の傾向はすぐに見えてきます。外食代が月3万円を超えている、コンビニに週5回以上寄っているなどなど、数字にすれば一目瞭然です。
目標額を設定していない
「いくら貯めたいか」を決めていないと、貯金は長続きしません。「将来のために何となく」では途中で崩れてしまうのです。
数字に直すとさらに分かりやすくなります。
| 目的 | 必要額 | 期間 | 毎月の積立額 |
|---|---|---|---|
| 国内旅行 | 30万円 | 2年 | 12,500円 |
| 車の購入 | 150万円 | 5年 | 25,000円 |
| 老後資金 | 2,000万円 | 30年 | 55,500円 |
目標を具体化すれば、「いま必要な積立額」がはっきり見えるため、途中で迷うことがなくなります。
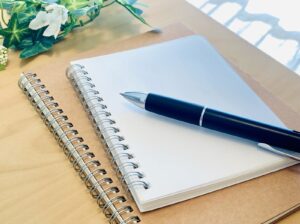
貯金500万円を貯められる人の特徴

お金を貯められる人は、特別な収入源を持っているわけではありません。日常の中で自然にお金が残る仕組みを整えている点が共通しています。
ここでは代表的な特徴を紹介します。
習慣化で自然にお金が貯まる
お金を貯められる人は、特別な節約をしているわけではありません。毎月同じ流れを自動で回すことで、意識せずともお金が残る環境をつくっているのです。
一番わかりやすいのが「先取り貯金」です。給料が入った瞬間に5万円を自動で別口座に移せば、残りのお金だけで生活する形になります。
取り入れやすい例は次のとおりです。
- 給与天引きの財形貯蓄
- 自動積立定期預金
- ネット銀行の口座分け機能
一度設定してしまえば、余計な努力をしなくても貯金が積み上がっていきます。
家計管理をしている
貯金ができる人は、毎月のお金の流れをきちんと見ています。収入と支出を並べてみれば、お金の流れは一目で分かるからです。
たとえば食費や通信費を振り返ると、思った以上に余分な出費が見つかるものです。「外食を減らしたら月5,000円浮いた」「格安SIMに切り替えて年間5万円安くなった」といった効果も数字で確認できます。

500万円を貯める方法|成功する7つのステップ
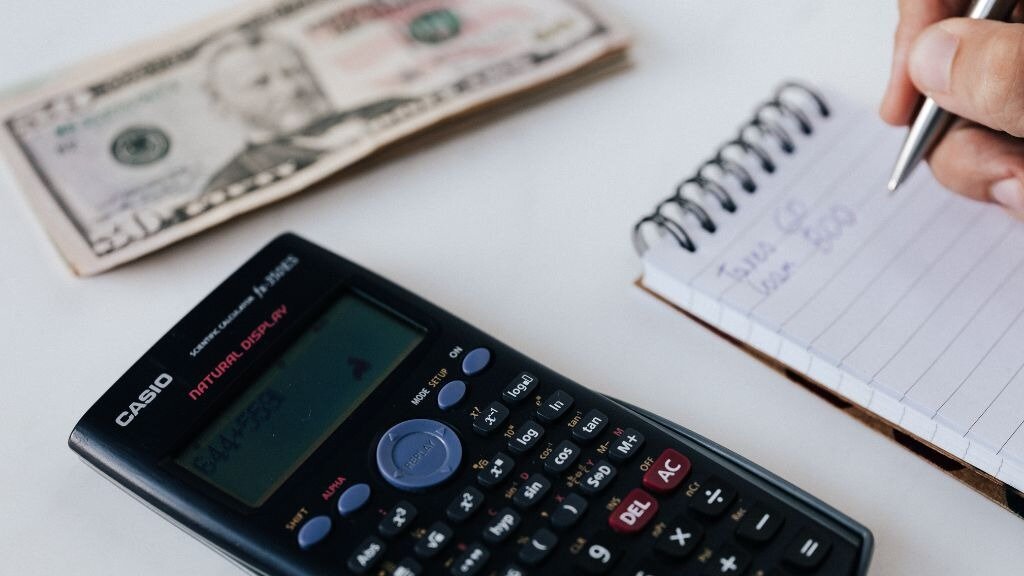
ここでは、日常生活に取り入れやすい具体的な方法を紹介します。
目的と期間を明確にする
まず、お金を貯める目的を明確にしましょう。ただ「なんとなく500万円貯めたい」と思っていても、途中で挫折してしまう可能性があるからです。
たとえば、マイホーム購入の頭金として3年後までに貯める、子どもの教育費用として7年後までに貯めるなど。
家計簿で収支を把握する
家計簿をつけて、お金の流れを把握するのも大切です。お金の流れを数値で客観的に見ることで、自分が思っていたよりもお金を使いすぎていることに気づくきっかけを得られるからです。
また、「収入を増やす必要がある」「何に使ったのかわからない出費が多い」などの問題発見につながることもあります。
固定費を削減する
固定費を削減するのも重要です。なぜなら、固定費の無駄を改善すると、効果が何ヶ月も続くため大きな額を削減できるからです。
固定費を削減する方法には、住宅費を抑えるために家賃の安い家に引っ越す、通信会社を安いところに変える、保険のプランを見直すなどがあります。使っていないサブスクリプションを解約する、子どもの塾をオンラインに切り替えるなどの方法も効果的です。
変動費をコントロールする
変動費は、食費や日用品のように毎月額が変わる支出です。固定費と違って調整が効きやすく、工夫した分がそのまま節約につながります。
まずやるべきは記録です。1か月分のレシートを集めれば、無駄がはっきりします。買い過ぎた食材、気づかないうちに重なるコンビニ出費、消耗品の買い置きのしすぎなど、削るべきポイントが見えてきます。
- 週1回のまとめ買いに絞る
- クーポンやポイントを活用する
- 外食の上限を月○回と決める
こうした工夫を続ければ、無理をせずに手元に残るお金を増やせます。
生活費と貯金口座を分ける
ひとつの口座で生活費と貯金を管理すると、支出のたびに残高が変わり、貯金がいくらあるのか見えなくなります。
専用の貯金口座をつくれば、積立額が一目で確認可能です。数字で確認できるとやる気が続き、引き出してしまう誘惑も減ります。目的ごとに口座を分けておくと管理はさらにしやすくなります。
- 給与口座から自動振替で貯金専用口座へ送る
- 引き出しにくいネット銀行を利用する
- 教育費や老後資金ごとに口座を分ける
こうして生活費と貯金を切り分ければ、管理に迷わず着実にお金を残せます。
自動積立・先取り貯金を活用する
自動的に先取り貯金ができる仕組みを利用するのも、貯金500万円を貯める際のコツです。自動的に先取り貯金ができる仕組みを使えば、お金が余らなくて貯金ができない事態を防げるからです。
自動的に先取り貯金ができる仕組みには、財形貯蓄や貯蓄型保険・積み立て型定期預金などがあります。あなたに合った仕組みを探してみてください。貯金が苦手な場合は、自動的に先取り貯金ができる仕組みを活用しましょう。
初心者向け資産運用を始める
節約だけでは目標の500万円が遠く感じる人には、資産運用を取り入れる方法があります。リスクはありますが、初心者でも始めやすい方法はいくつかあります。
| 運用方法 | 特徴 | リスク水準 |
|---|---|---|
| 債券 | 利息収入が定期的に得られる | 低 |
| 投資信託 | 少額で分散投資ができる | 中 |
| 株式投資 | 値上がり益や配当が期待できる | 中〜高 |
| REIT | 小口で不動産に投資できる | 中 |
投資信託は1万円程度から始められ、分散効果があるため初心者にとって扱いやすい商品です。安定性を重視するなら債券が向いています。

貯金500万円を超えたら検討したい資産運用3選

貯金500万円を達成したら、次はセミリタイアや資産運用に挑戦してみましょう。資産運用をすれば、貯金を効率的に増やせる可能性が高まります。貯金が500万円貯まった後におすすめの資産運用方法は、下記の3つです。
順に解説します。
iDeCo
iDeCoとは、自分の老後の生活を支えるための私的年金制度です。毎月一定の金額を積み立てて、その資金を金融商品に投資します。運用した資産は、60歳を過ぎてから引き出せます。
iDeCoの魅力は、3つの段階で税金の優遇措置が受けられることです。まず、積み立てた金額は全額所得控除の対象となります。次に、投資の利益は非課税。最後に、受け取る際には、公的年金等の控除や退職所得控除が適用されます。

NISA
NISAは、投資信託や株式での資産形成を支援するための制度です。年間360万円までの積立が可能で、その範囲内での利益は非課税なのが特徴。生涯にわたって積立ができ、長期・積立・分散投資に向いています。

投資信託
投資信託は、株式や債券・不動産などへの投資を専門家にしてもらえる金融商品です。運用の結果得られた利益は、投資家に分配されます。さまざまな商品に少額分散投資ができるため、リスクが軽減できるメリットがあります。
また、運用状況は定期的に報告され、投資家はその状況を確認可能。投資信託は投資初心者でも利用しやすく、少額から始められるのが特徴です。

貯金500万円を貯めるに関するよくある質問

貯金500万円を貯めるに関するよくある質問は以下のとおりです。
- 年収300万円でも500万円は貯められる?
- 女性の一人暮らしでも500万円を貯められる?
- 貯金と投資はどちらを優先すべき?
- 500万円あると何年暮らせる?人生での安心度は?
年収300万円でも500万円は貯められる?
可能です。年収300万円の場合、手取りはおおよそ230万〜240万円程度です。毎月2万円を貯金し、ボーナスからも年間10万円を積み立てれば、年間の貯金額は約34万円。単純計算で15年程度で500万円に到達します。
もちろん途中で収入アップや副業収入を加えれば期間を短縮できます。
女性の一人暮らしでも500万円を貯められる?
貯められます。家賃を収入の25%以内に抑え、通信費を格安プランにするだけで年間10万円以上節約できます。女性の一人暮らしでも、支出を管理して無理なく固定費を減らすことができれば、500万円は十分に可能な金額です。
貯金と投資はどちらを優先すべき?
まずは貯金を優先するべきです。理由は、無職になったり急なケガ・病気・災害で収入が途絶えたときに備える「生活防衛資金」がないと安心して生活できないからです。
目安としては生活費の3〜6か月分(独身なら60万〜120万円程度、夫婦なら100万〜200万円程度)を現金や預貯金で確保しましょう。そのうえで余剰資金ができたら、投資へ回すのが理想です。
500万円あると人生でどのくらい安心?
大きな安心材料になります。例えば独身で生活費が月15万円なら、働かなくても約33か月=2年9か月暮らせます。夫婦で生活費が月25万円の場合でも、20か月=1年8か月分の生活費に相当します。
まとめ:貯金500万円は誰でも達成できる現実的な壁
この記事では、貯金500万円の位置づけや積立のシミュレーション、達成するための実践的な方法を解説しました。
大切なのは「目的を決めて」「毎月いくら積み立てるか」を数値で把握することです。
まずは生活費の3〜6か月分を「生活防衛資金」として備え、そのうえで500万円を目指しましょう。行動を変えた人から結果が出ます。今日から小さくても一歩を踏み出して、貯金を積み上げてください。