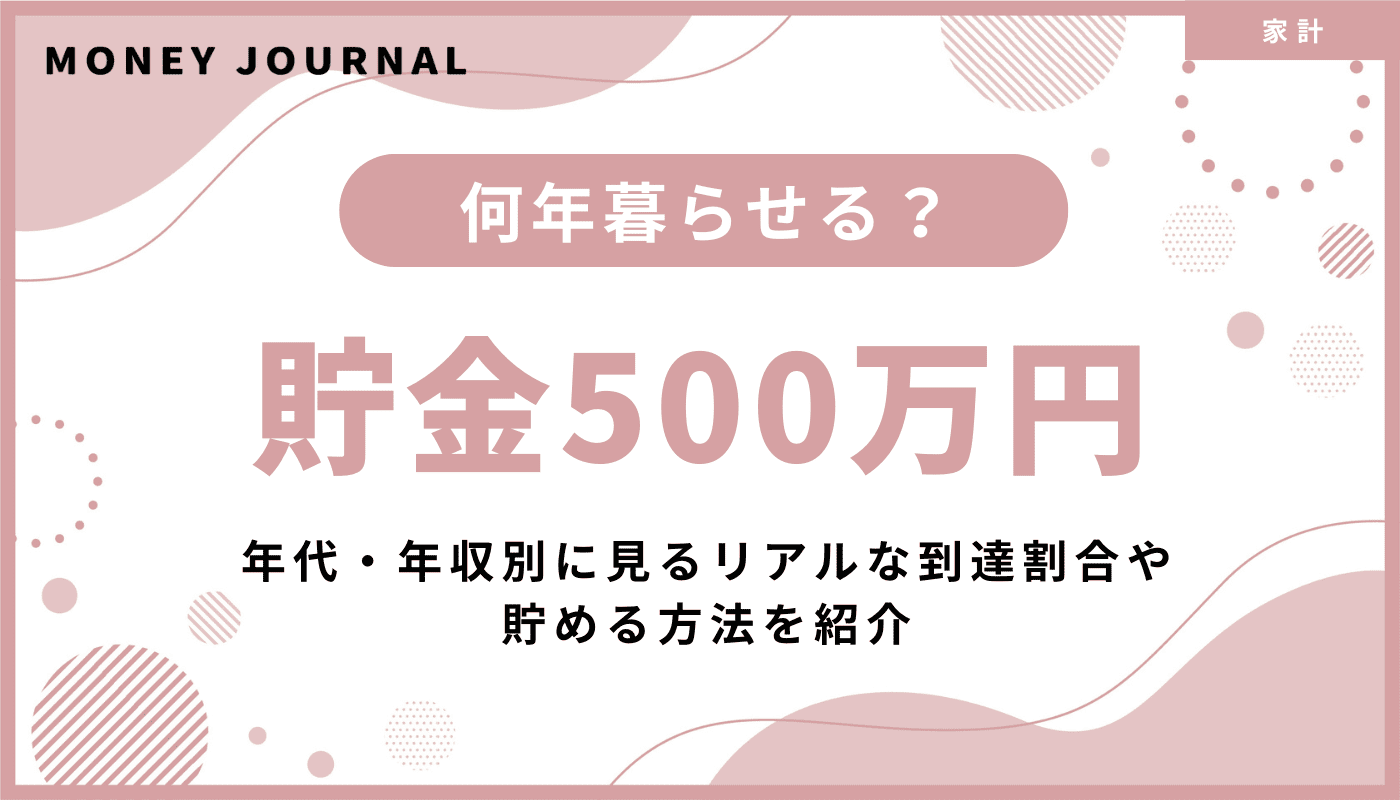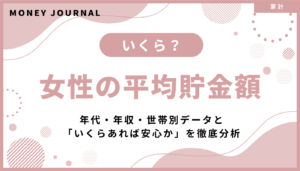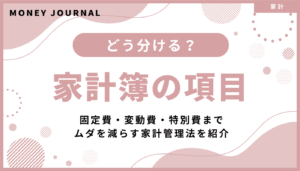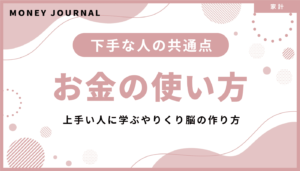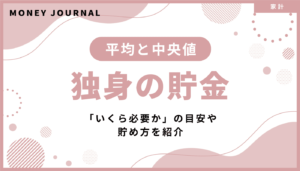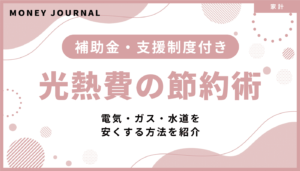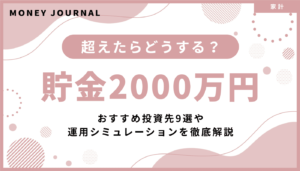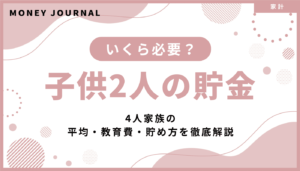- 「もし今の貯金が500万円しかなかったら、あと何年暮らせるのだろう…」
- 「仕事を辞めたら、このお金でどれくらい持つんだろう」
- 「500万円って、他の人と比べて多いの?少ないの?」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、貯金500万円で暮らせる期間の目安は、生活費や家族構成によって大きく変わります。おおよその目安を以下にまとめました。
| 世帯区分 | 想定生活期間(目安) | 想定月支出 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 約2年半 | 月17万円前後 | 家賃・食費を抑えたミニマム生活 |
| 夫婦世帯 | 約1年半 | 月27万円前後 | 家賃・食費・光熱費込みで想定 |
| 子育て世帯 | 約1年未満 | 月40万円前後 | 教育費・生活費を含めると短期化 |
本記事では、貯金500万円で何年暮らせるかをリアルなデータとシミュレーションをもとに徹底解説します。さらに、貯金を切り崩して生活する際の注意点や、もし病気・失業した場合の乗り切り方、そして貯金500万円を超えて次に目指すべき金額・資産運用の考え方までわかりやすく整理しました。
- 貯金500万円で暮らせる年数(単身・夫婦・家族別のリアルな試算)
- 生活を続けるために守るべき「生活防衛資金」の考え方
- 病気・失業時に使える公的支援制度
- 年代・年収別の貯金500万円の到達割合
- 500万円を貯めるための具体的なステップと習慣化のコツ
- 貯金500万円から始められるおすすめの資産運用方法
貯金500万円で何年暮らせる?世帯別・生活費別に徹底シミュレーション

貯金500万円が「多いのか少ないのか」を判断するには、生活費の水準と世帯構成を切り離して考えることはできません。独身で一人暮らしをしているのか、夫婦で暮らしているのかによって、お金の減り方は異なるからです。
ここでは、総務省「家計調査(2024年版)」の支出データをもとに、単身世帯と夫婦世帯それぞれの平均支出からリアルなシミュレーションを行います。単なる机上の数字ではなく、実際の生活に近い現実的な目安として参考にしてください。
単身世帯:500万円で約2年半の生活が可能
単身者の場合、1ヶ月あたりの平均生活費はおよそ17万円〜18万円です(総務省2024年調査より)。この水準をもとに、500万円がどのくらい持つのかを試算すると、以下のようになります。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 1ヶ月の生活費 | 約17万円 |
| 1年間の生活費 | 約204万円 |
| 500万円で暮らせる期間 | 約2年5ヶ月(約29ヶ月) |
つまり、定期収入が一時的に途絶えても約2年半は生活を維持できる計算です。ただし、これは家賃7万円・食費3万円・光熱費1.5万円・通信費1万円・その他4.5万円を想定した最低限の生活水準に基づいた数字です。現実には、次のような支出が発生しやすくなります。
- 引っ越しや家具・家電の買い替え
- 医療費や冠婚葬祭などの突発的な支出
- 物価上昇やインフレによる生活費の増加
このため、実際には約2年持たせるくらいの余裕を持った資金計画を立てておくのが安全です。
単身で暮らす場合、貯金を長持ちさせるポイントは次の3つです。
- 家賃を収入の25%以内に抑える
- 食費は自炊中心にして月3万円台を意識する
- サブスク・保険などの固定費を最小限に整える
貯金500万円は、転職活動中や一時的な無職期間を安心して乗り切るための生活防衛資金として十分な水準です。
夫婦世帯:500万円で約1年半が目安
夫婦2人暮らしになると、生活費の平均は月27万〜30万円前後に上がります。この支出を基にした試算は次のとおりです。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 1ヶ月の生活費 | 約28万円 |
| 1年間の生活費 | 約336万円 |
| 500万円で暮らせる期間 | 約1年5ヶ月(約17〜18ヶ月) |
夫婦世帯では、単身より生活コストが上がりますが、共働きであれば支出を分担できるため貯金の増えるスピードは早い傾向があります。一方で、出産や育児、どちらかの休職などによって収入が減少すれば、想定より早く資金が尽きることもあります。
そのため、家計管理の考え方としては以下の二段構えが理想です。
- 最低でも半年〜1年分の生活費を生活防衛資金として確保する
- それ以上の余剰分は運用や積立に回してお金を育てる
また、夫婦の場合は生活費+安心コストも意識する必要があります。たとえば、生命保険・医療保険・教育費といった将来の安心に関わる支出は、単身者にはない固定的な負担です。

貯金500万円を切り崩しながら暮らす際の注意点

貯金を取り崩して生活することは、決して悪いことではありません。一時的に収入が減ったり、転職や療養などで生活が変化したりすると、貯金に頼る時期は誰にでも訪れます。
ただし、無計画に使い続けると、気づいたときには残高が数十万円しかないという事態にもなりかねません。そうならないためには、先に「使ってよいお金」と「絶対に守るお金」を明確に分けておくことが必要です。
ここでは、貯金500万円で生活を続けるうえで必ず意識しておくべき5つのポイントを整理しました。
生活防衛資金(最低3〜6ヶ月分)を残しておくことが大前提
まず最初に守るべきは、生活防衛資金を絶対に崩さないことです。生活防衛資金とは、病気・失業・災害などで収入が途絶えたときに生活を支えるお金のことを指します。
生活防衛資金は最後まで手をつけないお守りとして扱うのが鉄則です。生活防衛資金を確保したうえで、残りを以下のように分けると管理しやすくなります。
- 生活費:毎月の固定・変動支出
- 娯楽費:旅行・外食などの自由支出
- 運用資金:将来に備えるお金
防衛資金まで使い始めると、「あとどれくらい持つだろう」と不安が募り、冷静な判断ができなくなります。まずは「守る資金」と「使う資金」を分けることから始めましょう。
突発支出(家電・医療・冠婚葬祭)を年10〜20万円で想定する
生活費のシミュレーションを立てる際、多くの人が見落とすのが突発的な支出です。冷蔵庫や洗濯機の故障、歯の治療費、友人の結婚式など、毎年必ず想定外の出費が発生します。
たとえば、年間で発生しやすい支出を以下に整理するとイメージしやすいです。
| 支出項目 | 想定金額 | 頻度の目安 |
|---|---|---|
| 家電の買い替え(冷蔵庫・洗濯機など) | 約5〜10万円 | 2〜3年に1回 |
| 医療費(検査・治療など) | 約3〜5万円 | 毎年 |
| 冠婚葬祭費 | 約5万円 | 年1〜2回 |
突発支出をあらかじめ想定しておくと、急な支払いにも慌てず対応できます。「思わぬ出費で貯金計画が崩れた」という事態を防ぐためにも、年間10〜20万円は予定外のバッファ資金として組み込んでおきましょう。
インフレや物価上昇で実質価値は目減りする
もう一つの見落としがちなリスクが、インフレ(物価上昇)によるお金の価値の目減りです。たとえばインフレ率が年2%で続いた場合、10年後の500万円は実質410万円程度の購買力に下がります。つまり、何もしていなくてもお金の価値が減っていくということです。
インフレを見越した資産の置き方を、期間別に整理すると以下のようになります。
| 資産の置き場所 | 目的 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 預金 | 日常生活・緊急支出用 | 生活費6ヶ月分まで |
| 積立型保険・債券 | 安定性を重視した中期資金 | 3〜5年 |
| 投資信託・NISA・iDeCo | 将来の資産形成を狙う長期資金 | 10年以上 |
精神的ストレスを減らす固定費のミニマム設計が重要
貯金を切り崩して暮らしている期間は、どうしてもお金が減っていく不安に悩まされやすくなります。そのストレスを和らげる一番の方法は、毎月の固定費をできる限り小さく保つ設計です。
固定費が下がるほど、毎月の支出に余裕が生まれ「あと何ヶ月暮らせるか」という焦りが減ります。実際に見直すポイントは次のとおりです。
| 項目 | 見直しの方法 | 期待できる節約額(目安) |
|---|---|---|
| 家賃 | 住居をコンパクト化、郊外やUR賃貸を検討 | 月1〜2万円 |
| 通信費 | 格安SIMやネット回線のプラン変更 | 月3,000〜5,000円 |
| 保険料 | 重複補償を解消し、必要最小限に整理 | 月5,000〜1万円 |
| サブスク | 使用頻度の低いサービスを解約 | 月2,000〜3,000円 |
固定費を2〜3万円減らすだけで、年間30万円以上の節約につながります。単なる節約ではなく、心の安心を買うための行動です。
貯金を減らすだけでなく増やさないと続かない意識を持つ
貯金を取り崩す生活が続くと、精神的にも経済的にも息苦しくなっていきます。そこで意識したいのが、減らさない工夫と増やす行動を同時に持つことです。
大きな収入でなくても構いません。少しでもお金が入ってくる流れを作るだけで、生活の持続力が上がります。
具体的な方法は以下のとおりです。
- フリマアプリで不要品を販売してお小遣いを得る
- クラウドワークスなどで在宅ワークに挑戦する
- ポイント還元やキャッシュレス決済を積極的に活用する
- 少額から投資信託を始めてお金を育てる習慣をつける
たとえ月5,000円でも収入があると、完全に減るだけの生活から抜け出せます。貯金を減らさない工夫を積み重ねながら、同時に増やす習慣を育てていきましょう。

もし病気・失業したら?貯金500万円で乗り切れる期間

「病気で働けなくなった」「転職活動が長引いた」など、誰にでも起こり得る状況では、生活コストを抑えつつ制度を上手に使うことが大切です。
ここでは、無職になったときにどのくらい暮らせるのかをシミュレーションし、さらに失業手当や傷病手当金などの公的支援を活用して生活を延命する具体的な方法を解説します。
無職になった場合の平均生活費シミュレーション
無職になったときに支出の中心となるのは、住居費・食費・光熱費・通信費といった最低限の生活コストです。
ここでは月15万円で計算した場合のシミュレーションを示します。
| 項目 | 想定額 |
|---|---|
| 月間支出 | 15万円 |
| 年間支出 | 180万円 |
| 500万円で暮らせる期間 | 約2年9ヶ月(約33ヶ月) |
およそ2年半〜3年は生活できる計算ですが、医療費や冠婚葬祭などの臨時支出を含めると、実際は約2年が現実的なラインです。
生活費を長持ちさせるには、以下の工夫が効果的です。
- 実家に一時的に戻り家賃を下げる
- 車を売却・一時保管して維持費を減らす
- 不要な保険やサブスクを整理して月1〜2万円の節約
支出を1万円減らすだけで、年間12万円の延命効果があります。
失業手当・傷病手当などの公的支援を活用すれば延命可能
収入が途絶えても、国の制度を活用すれば生活期間を延ばすことができます。代表的なのが失業手当と傷病手当金です。
失業手当(雇用保険)
退職後にハローワークへ申請すると、離職前6ヶ月の平均給与の50〜80%が一定期間支給されます。
受給期間はおおよそ3〜12ヶ月です。たとえば月25万円の給与だった人なら、月13万〜20万円前後の給付が見込めます。
傷病手当金(健康保険)
病気やケガで働けなくなった場合に支給される制度です。給与の約3分の2が最長1年6ヶ月受け取れます。たとえば手取り20万円なら、月13万円ほどが支給される計算です。
支出の優先順位を決めて生活の軸を守る
無職や療養中の時期は、「何を削るか」よりも「何を残すか」を意識することが生活再建の近道です。支出の優先順位を整理すると、次のようになります。
| 優先度 | 支出項目 | 理由 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 住居費 | 生活の基盤。失うと再起が難しくなるため最優先。 |
| ★★★★☆ | 食費・光熱費 | 健康と生活維持に直結する支出。最低限は確保。 |
| ★★★☆☆ | 医療費・通信費 | 健康管理と情報収集に必要。削りすぎは危険。 |
| ★★☆☆☆ | 保険料・娯楽費 | 状況に応じて調整可能。優先度は下げてOK。 |
支出をなくすのではなく、守る支出を決めて他を整理する考え方が大切です。住居や健康に関わる費用を削ると、結果的に生活の立て直しが遅れてしまいます。
また、無職期間が長引くほど不安も膨らみやすいため、ハローワーク・職業訓練・転職支援など無料で使える公的サービスを積極的に利用しましょう。

貯金500万円はすごい?少ない?年代・年収別のリアルな割合

貯金500万円は、多いのか少ないのかを下記の3つの観点から比較します。
- 年代別
- 年収別
- 世帯構成別
貯金500万円と聞くと、多いと感じる方も少ないと感じる方もいるでしょう。感覚的なものではなく、実際の位置付けを年代・年収・世帯構成別に見ていきます。
年代別に見る貯金500万円の到達率
年代別にみる貯金500万円の割合は、下記のとおりです。
| 年齢 | 非保有 | 500万円未満 | 500~700万円未満 | 700万円以上 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳代 | 40.6% | 47.3% | 4.6% | 5.5% | 185万円 | 20万円 |
| 30歳代 | 26.7% | 40.6% | 8.6% | 21.5% | 515万円 | 150万円 |
| 40歳代 | 28.4% | 33.8% | 6.7% | 27.4% | 785万円 | 200万円 |
| 50歳代 | 28.4% | 27.2% | 4.5% | 35.7% | 1,199万円 | 260万円 |
| 60歳代 | 23.1% | 22.3% | 5.5% | 46.1% | 1,689万円 | 552万円 |
| 70歳代 | 21.8% | 19.6% | 7.9% | 48.5% | 1,755万円 | 650万円 |
単身世帯・2人以上の世帯ともに、20代・30代・40代・50代において貯金500万円未満の世帯が半分以上を占めています。500~700万円未満貯金している世帯の割合は、700万円以上貯金している世帯の割合よりも少ないです。
年収別に見る貯金500万円のハードル
年収別にみる貯金500万円の割合は、下記のとおりです。
| 年収 | 非保有 | 500万円未満 | 500~700万円未満 | 700万円以上 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入なし | 62.6% | 17.8% | 2.4% | 7.9% | 260万円 | 0円 |
| 300万円未満 | 37.5% | 33.4% | 5.4% | 20.9% | 650万円 | 50万円 |
| 300~500万円未満 | 23.6% | 33.4% | 7.4% | 33.4% | 974万円 | 300万円 |
| 500~750万円未満 | 17.6% | 30.6% | 7.7% | 41.4% | 1,319万円 | 500万円 |
| 750~1,000万円未満 | 13.0% | 19.2% | 8.0% | 56.3% | 1,873万円 | 967万円 |
| 1,000~1,200万円未満 | 12.5% | 18.9% | 3.8% | 62.8% | 2,687万円 | 1,063万円 |
| 1,200万円以上 | 14.0% | 12.6% | 4.1% | 66.1% | 3,595万円 | 1,800万円 |
単身世帯・2人以上世帯ともに、年収500万円未満の場合は、貯金額500万円未満の割合が半分以上を占めています。また、年収が上がるにつれて、貯金額も基本的には上がる傾向にあります。
国税庁のデータによると、令和4年度の平均給与は458万円でした。(参照元:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)それを踏まえると、貯金500万円は平均的な貯金額よりもやや多いと言えるでしょう。
世帯構成別にみる貯金500万円の割合
世帯構成別にみる割合は、下記のとおりです。
| 世帯構成 | 非保有 | 500万円未満 | 500~700万円未満 | 700万円以上 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯構成 | 非保有 | 500万円未満 | 500~700万円未満 | 700万円以上 | 平均値 | 中央値 |
| 単身世帯 | 34.5% | 32.5% | 5.4% | 25.3% | 871万円 | 100万円 |
| 2人以上世帯 | 23.1% | 28.1% | 6.9% | 38.6% | 1,291万円 | 400万円 |
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年)」
単身世帯の場合は貯金額500万円未満の割合が約65%、2人以上世帯の場合は貯金額500万円未満の割合が約51%です。貯金額500万円について、単身世帯の場合は貯金額が多い方、2人世帯の場合は平均的な貯金額やや多めであるとわかります。

安心できる貯金額はいくら?貯金500万円に向けた前提知識

「とにかく貯金は多いに越したことはない」と考え、貯め続けている方も多いですが、実際はいくらくらいあると安心できるものなのでしょうか。ここでは、人生の二大出費である「子供の教育費用」と「老後の必要な資金」を紹介します。
教育資金の必要目安
子供の教育費用はどれくらい準備しておけばいいのでしょうか?仮に子供が3歳から幼稚園に通い、大学まで進学した場合、教育費が必要になる期間は19年にもなります。住友生命の調査では、以下の数字が公開されています。
- 幼稚園から大学まで全て国公立に通った場合:546万円
- 幼稚園から中学まで公立で、高校・大学は私立(文系)に通った場合:833万円
- 幼稚園から中学まで公立で、高校・大学は私立(理系)に通った場合:974万円
さらに中学・高校で塾に通ったとすると、ここに加えて約170万円が必要になります。子供の教育費用には莫大な金額が必要になります。
参考:住友生命「教育費の平均は?幼稚園~大学の教育費を解説!【4パターン】」より算出
老後資金の必要目安
老後には、どれくらいの費用が必要となるのでしょうか?定年退職後の大きな収入となるのが、公的年金です。
厚生労働省の発表によると、老齢年金受給額の平均は月14.6万円でした。
一方、公益財団法人生命保険文化センターの発表(令和元年度「生活保障に関する調査」)では、老後を夫婦2人で暮らしていくのに最低限必要な生活費は月に22.1万円とされています。
年金だけでは月に7.5万円の生活費が不足します。定年退職を65歳として平均寿命から考えると老後は20年近く続きます。月7.5万円の不足は、20年間を合計すると1,800万円となります。つまり、老後に対しては最低でも1,800万円の蓄えが必要となってきます。

貯金500万円を貯めるには何年必要?

貯金500万円を貯めるために必要な年数は、下記のとおりです。毎月、そして年2回のボーナス時に同じ金額を貯金すると考えて算出しています。
| 月・ボーナスごとの貯金額 | 500万円貯まるのに必要な期間 |
|---|---|
| 1万円 | 35.7年 |
| 2万円 | 17.9年 |
| 3万円 | 11.9年 |
| 4万円 | 8.9年 |
| 5万円 | 7.1年 |
| 6万円 | 6.0年 |
| 7万円 | 5.1年 |
| 8万円 | 4.5年 |
| 9万円 | 4.0年 |
| 10万円 | 3.6年 |
1万円ずつ貯める場合は、約36年かかる計算です。2万円ずつ貯めると約18年、3万円ずつ貯めると約12年、4万円ずつ貯めると約9年と続きます。10万円ずつ貯める場合は、わずか3年半ほどで貯金額500万円を達成できます。

貯金500万円を達成するための5つの成功のコツ

貯金500万円が平均的な貯蓄額よりもやや多めであることがわかりました。それでは、貯金500万円を達成するためにはどうすればよいのでしょうか。500万円貯金するためのコツは、下記の7つです。
それぞれのコツについて、順番に解説します。
①何のために500万円の貯金をするか明確にする
まず、お金を貯める目的を明確にしましょう。ただ「なんとなく500万円貯めたい」と思っていても、途中で挫折してしまう可能性があるからです。たとえば、マイホーム購入の頭金として3年後までに貯める、子どもの教育費用として7年後までに貯めるなど。
具体的な目的があれば、「貯金のために本当に必要なもの以外は買うのはやめよう」と思えます。貯金500万円を達成するには、目的を明確にしてその目的に向かってコツコツと貯金をすることが重要です。
②家計簿をつけて収支を把握する
家計簿をつけて、お金の流れを把握するのも大切です。お金の流れを数値で客観的に見ることで、自分が思っていたよりもお金を使いすぎていることに気づくきっかけを得られるからです。また、「収入を増やす必要がある」「何に使ったのかわからない出費が多い」などの問題発見につながることもあります。
③まずは固定費から見直しをする
固定費を削減するのも重要です。なぜなら、固定費の無駄を改善すると、効果が何ヶ月も続くため大きな額を削減できるからです。
固定費を削減する際は、削減する金額目標を設定したうえで行うことも重要です。生活の質を落とし過ぎてストレスをためないことにも注意しましょう。
④生活費の口座と貯金の口座を別にする
生活費の口座と貯金の口座を別にするのも、お金を貯めていく際のコツのひとつです。生活費と貯金用で分けると、毎月どれくらい貯金できているのかがわかるのでモチベーションが上がります。お金を目的別に管理すると、使ってしまうのを防げたり銀行のトラブルや破綻のリスクを分散できたりとメリットもあります。
また、貯金の口座を選ぶ際は、できるだけ金利の高い銀行口座を選びましょう。金利が高いほど、効率的にお金を増やせます。貯金の口座は金利の高いネット銀行の口座がおすすめです。
⑤自動的に先取り貯金ができる仕組みを利用する
自動的に先取り貯金ができる仕組みを利用するのも、貯金500万円を貯める際のコツです。
自動的に先取り貯金ができる仕組みを使えば、お金が余らなくて貯金ができない事態を防げるからです。貯金額を差し引いた金額でやりくりをする能力も身に付きます。
⑥変動費は贅沢や無駄な費用を確認して削減する
変動費は、支払額が変動する費目のことです。具体的には、食費や日用品費などが該当します。
家計の収支を把握し変動費の内訳を確認することが重要です。変動費の出費の中から、無駄な費用がないかを確認し、削減できるものがないか検討しましょう。
変動費は、毎日の暮らしに直結する費用のため、ゼロにすることはできません。一度に削減するとストレスが溜まるため「毎月少しずつ減らしていく」「お金を使う日と使わない日のメリハリをつける」という2点が大切です。
⑦資産運用を始める
支出の見直しで対応できない場合は、資産運用や収入を増やすことを検討しましょう。初心者におすすめの資産運用は次のようなものがあります。
- 債権
- 投資信託(ファンド)
- 株式投資
- REIT

500万円を貯金できない人の特徴

貯金ができない人には、主に3つの特徴があります。
それぞれ1つずつ見ていきましょう。
特徴1. 貯金ができないと思い込んでいる
貯金のできない人には「ほしいものがあるから」や「やりたい趣味があるから」などの理由をつけて、自分は貯金ができないと諦めている人が多いです。
貯金はいきなり大きな金額を目指すのではなく「月3,000円」など少額から始めて問題ありません。慣れてきたら徐々に貯金する金額を増やしていきましょう。
特徴2. 収支を把握していない
お金の流れを把握することは貯金のために大切です。貯金ができない人は、収入の中から一体いくら支出しているかを把握できていないことが多いです。
ご自身の銀行口座を確認して「先月はこんなにお金を使っただろうか?」と驚くことの多い方は、要注意です。
特徴3. 目標がない
貯金をするためのモチベーションがないことも特徴として挙げられます。漠然と将来に備える、というだけでなく、「旅行をするため」「少し高額なものを買うため」というように、貯金をする明確な目標を持つことでお金を貯めやすくなります。
貯金するための方法を本記事で紹介しますが、貯金をする目的と期間が明確でない人は、貯金を継続することが難しいでしょう。

500万円を貯金できる人の特徴

貯金ができる人には、主に2つの特徴があります。
それぞれについて見ていきましょう。
特徴1. お金が貯まる習慣を作っている
貯金ができる人は、特別な生活をしているわけではありません。お金が貯まる仕組みを習慣化して、着実に貯金を増やしていることが特徴です。
「先取り貯金」もその仕組みの1つです。収入から一定の金額を先に貯金に回すことで、大きな手間がなく、貯金を増やしていくことが可能になります。給与天引きでの貯金などを活用していることもあります。
特徴2. 家計管理をしている
貯金のできない人が収支を把握していないのと反対で、貯金のできる人はしっかりと家計管理をし、収支を把握しています。
家計管理をすることで、自分がどの程度のお金をつかっているのかが分かりますし、支出を減らす場合も、減らした金額と実際に自分の生活がどう変わったかを振り返ることができます。

貯金500万円から次に目指すべき金額目標

多くの家庭で最初の大きな節目となるのが、貯金1,000万円です。生活防衛資金に加えて将来の大型支出(家電・車・引っ越し・医療・教育など)をまかなうのに十分な水準です。
貯金1,000万円が目標となる理由は、以下のとおりです。
- 生活防衛資金(生活費6ヶ月分)…約120万円
- 突発支出・ライフイベント費…約200〜300万円
- 老後や運用への先行投資…約500万円
こうしてみると、500万円は守るための資金であり、1,000万円から攻め(増やす)のステージに入る金額ラインといえます。

貯金500万円貯まったらおすすめする3つの資産運用方法

貯金500万円を達成したら、次は資産運用に挑戦してみましょう。資産運用をすれば、貯金を効率的に増やせる可能性が高まります。貯金が500万円貯まった後におすすめの資産運用方法は、下記の3つです。
順に解説します。
おすすめの資産運用①:iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、自分の老後の生活を支えるための私的年金制度です。毎月一定の金額を積み立てて、その資金を金融商品に投資します。運用した資産は、60歳を過ぎてから引き出せます。
iDeCoの魅力は、3つの段階で税金の優遇措置が受けられることです。まず、積み立てた金額は全額所得控除の対象となります。次に、投資の利益は非課税。最後に、受け取る際には、公的年金等の控除や退職所得控除が適用されます。
おすすめの資産運用②:NISA
NISAは、投資信託や株式での資産形成を支援するための制度です。年間360万円までの積立が可能で、その範囲内での利益は非課税なのが特徴。生涯にわたって積立ができ、長期・積立・分散投資に向いています。
おすすめの資産運用③:投資信託
投資信託は、株式や債券・不動産などへの投資を専門家にしてもらえる金融商品です。運用の結果得られた利益は、投資家に分配されます。さまざまな商品に少額分散投資ができるため、リスクが軽減できるメリットがあります。
また、運用状況は定期的に報告され、投資家はその状況を確認可能。投資信託は投資初心者でも利用しやすく、少額から始められるのが特徴です。

貯金500万円に関するよくある質問

貯金500万円は、金額としては節目にあたるラインです。「30歳で達成できたらすごいの?」「無職になっても暮らせる?」「投資を始めるべき?」など、気になる点は多いでしょう。
ここでは、500万円を貯めた人・これから目指す人のどちらにも役立つよう、よくある疑問をデータと根拠をもとに整理しました。将来の見通しを立てるための参考にしてください。
貯金が0(ゼロ)の世帯の割合は?
金融広報中央委員会が実施した「家計の金融行動に関する世論調査2022年」によると、貯金を含めた金融商品を「いずれも保有していない」と回答した世帯の割合は4.9%でした。
5.6%であった2018年から見ると、徐々に減少傾向ではありますが、ある一定程度の世帯の貯金を含めた金融商品をまったく保有していない状態であることが分かります。
30歳で貯金500万円は多い?
30歳で貯金500万円はかなり多い部類です。金融広報中央委員会の調査では、30代単身世帯の平均貯蓄額は約330万円、中央値は150万円。つまり500万円あれば上位20%前後に入る水準です。
無職でも500万円で安心して暮らせる?
支出を抑えれば、無職でも約2年間は生活可能です。総務省の家計調査を基準にすると、月15万円で暮らせば約33ヶ月(2年9ヶ月)持ちますが、実際は突発支出を考慮して2年が現実的な上限です。
生活を長持ちさせるポイントは次のとおりです。
- 実家に戻って家賃を下げる
- サブスク・保険を整理して毎月の支出を減らす
- 車を手放して維持費を節約する
さらに、失業手当や傷病手当などの公的支援を併用すれば、資金を1〜2年延ばすことも可能です。安心して暮らしたい場合は、500万円のうち最低100万円を生活防衛資金として残すことを意識しましょう。
貯金500万円を超えたら投資を始めるべき?
はい。貯金が500万円を超えたら、増やすフェーズへの移行を考えるタイミングです。日本の預金金利は年0.001%前後しかなく、インフレを踏まえると現金のままでは価値が目減りします。
理想の資産配分は次のとおりです。
| 用途 | 金額の目安 | 管理方法 |
|---|---|---|
| 生活費6ヶ月分 | 約100万円 | 普通預金で保管 |
| 余剰資金 | 約400万円 | NISA・iDeCoなどで積立運用 |
老後資金として500万円で足りる?
残念ながら、老後資金として500万円のみでは足りません。金融庁の試算では、夫婦2人で老後を20〜30年間過ごすには、年金を含めても約2,000万円が不足するとされています。単身でも家賃や医療費を含めると、500万円は数年分の生活費にしかなりません。
貯金が苦手な人が最初にやるべきことは?
貯金できない原因は性格ではなく、仕組みが整っていないことにあります。まずは次の3つを実践してみましょう。
- 目的を決める
- 先取り貯金を自動化する
- 家計簿アプリで支出を可視化する
まとめ
この記事では、貯金500万円で何年暮らせるかという現実的なテーマについて、世帯別の生活費シミュレーションや、貯金を減らさず活かす方法を解説しました。
500万円は一見まとまった金額に見えても、家賃や食費を含む生活費に充てると、単身世帯で約2年半、夫婦世帯で約1年半ほどで尽きてしまいます。そのため、守るお金と増やすお金を切り分けることが大切です。
いまの貯金を減らすことに不安を感じている方こそ、「あと何年暮らせるか」ではなく「どうすればお金を育てられるか」を意識してみてください。今日から生活費を見直し、守りながら増やす仕組みを作っていきましょう。