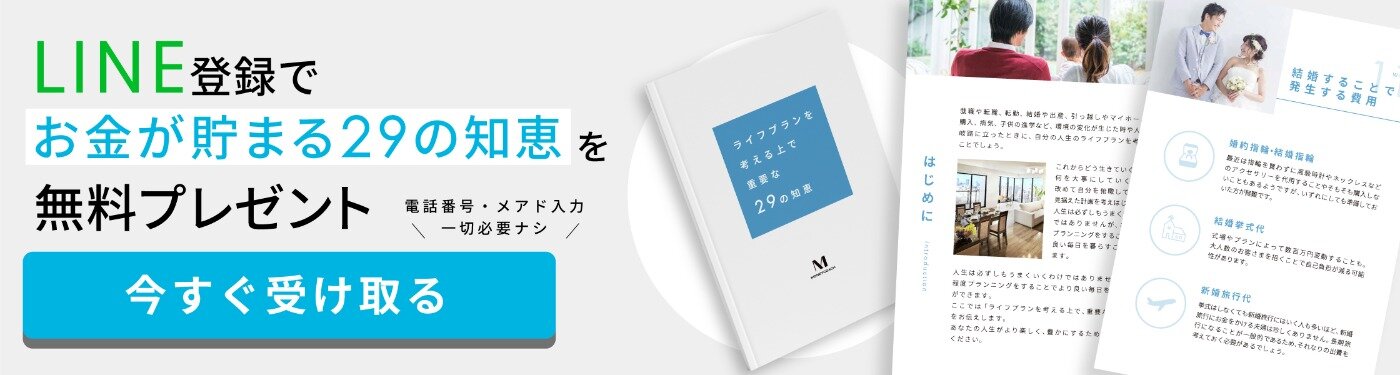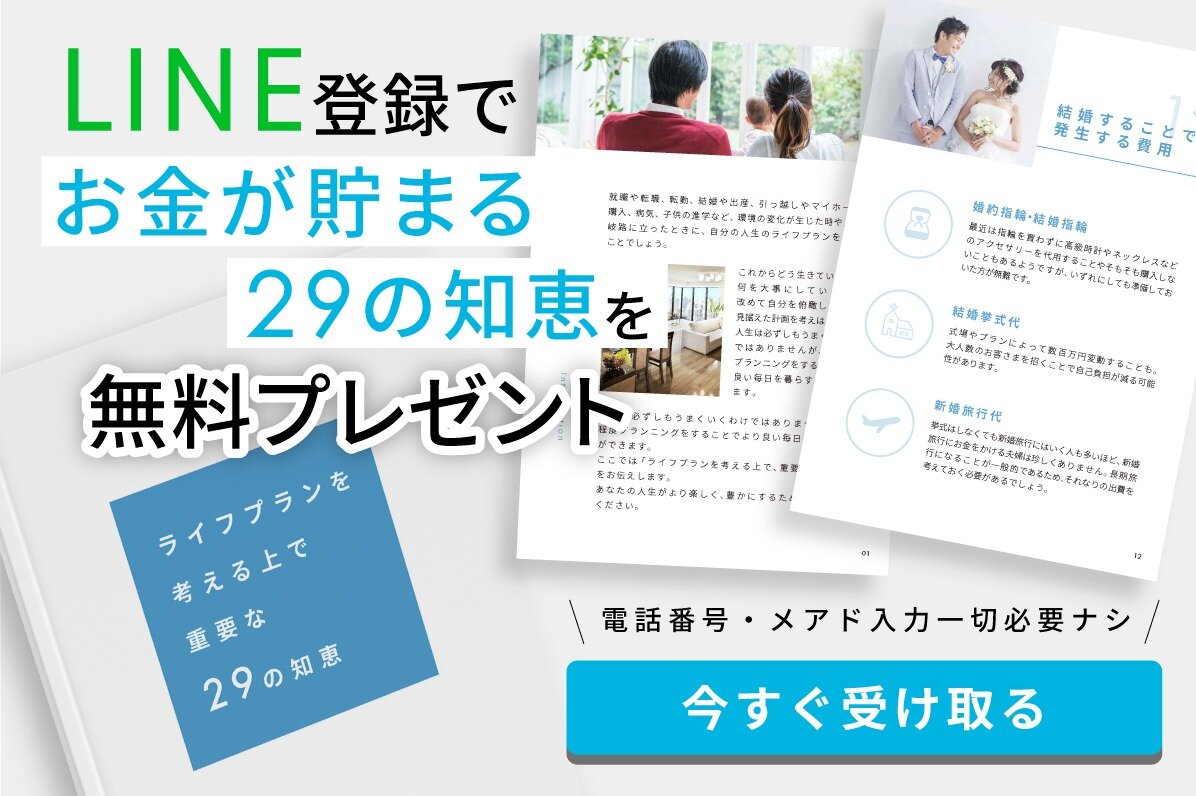パートとして雇用されていると、「130万を超えて働いてはいけない」「うっかり130万を超えたら損をしてしまう」と聞く機会があるでしょう。さらには103万円や106万円、150万円といった金額が話題に上がることもあります。 これらの金額は、以下の2点で重要な境目になる金額です。
- 税金と保険料の支払い義務が発生する点
- 控除を上限額まで受けることができる点
なかでも、130万円はパートの人にとっては労働時間をセーブする基準である可能性も高いといえるでしょう。 この記事では、130万円を超えるメリットとデメリットについてご紹介します。損をせずにパートで収入を得たい人は、ぜひ参考にしてください。
130万の壁とは

130万の壁とは、健康保険の扶養から外れる境界線のことです。年収が130万円を超える時には、自分で国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
このように、保険料を負担する必要が出てくることから「130万の壁」とも言われています。条件によっては、年収が106万円を超える段階でパート先の社会保険に加入しなければいけないこともあります。
社会保険と国民健康保険のどちらに加入しなければいけないのか、わからない人もいるでしょう。年収が106万円を超えるパターンと130万円を超えるパターンの2つを詳しく解説していきます。
今回は妻がパートで働くケースで説明します。
年収が106万円を超える場合
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、年収に関係なくパートでも社会保険に加入しなければなりません。
これに該当しない人で、年収が106万円を超える場合には、以下の条件に当てはまるか確認しましょう。
- 1週間の所定労働時間が、20時間以上である(残業時間は含めない)
- 1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上である(賞与や残業代、通勤手当などは含めない)
- 雇用期間の見込みが1年以上である(2022年10月以降、2ヵ月超に適用拡大)
- 学生でない(夜間、通信、定時制の学生は対象となる)
以下のいずれかに該当する
- 従業員の数が501人以上の会社で働いている
- 従業員の数が500人以下の会社で働いているが、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
(2022年10月以降101人以上、2024年10月以降51人以上に適用拡大)
これら5つの条件の全てに当てはまる場合、パート先の社会保険に加入することになります。当てはまらない場合には、年収が130万円を超えるまで夫の健康保険の扶養に入り続けることが可能です。
年収が130万円を超える場合
年収が130万円を超え、パート先の社会保険に加入しない場合には、自分で国民健康保険に加入しなければいけません。保険料も発生します。 自分の住所を置いている市区町村役所の窓口にて手続きしましょう。
- 運転免許証をはじめとする本人確認書類
- マイナンバーカードや番号通知カード
- 健康保険脱退証明書(健康保険資格喪失証明書)
- キャッシュカードや通帳、通帳使用印
- 年金手帳
といった、手続きに必要なものを忘れずに用意してください。必要なものは市区町村役所によって変わります。手続きの前に必要なものを確認すると安心です。
所得税も意識しよう

所得税は、年収が103万円を超えた段階で発生する税金です。130万円を超えたらどうしよう、と考えている人の多くは既に支払っているでしょう。 しかし、130万円を超えて収入を得る時には、改めて確認しなければいけない税金です。
- 年収が103万円を超えた段階で、どのような計算式で所得税が発生しているのか
- 130万円を超えて収入を得る時には、気をつけることはあるのか
この2つについて解説していきます。
年収が103万円を超えた時の所得税
年収が103万円を超えると、所得税が発生します。これを103万円の壁と呼びます。
なぜ103万円がボーダーラインとして設定されているのか、疑問に思う人もいるでしょう。これは、雇用されで働く給与所得者に適用される控除の金額が影響しています。
雇用されで働く給与所得者に適用される控除に、基礎控除と給与所得控除が存在します。基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円(給与収入1,625,000円以下の場合)です。この2つを足すと、合計103万円になります。この103万円までは控除されることによって、所得税を支払う対象となる収入が計算上はなくなるのです。
そのため、年収から103万円を引いた、残りの所得に所得税が課税されて支払い義務が発生します。所得税の税率は、5%〜45%までの7区分。所得が高くなるほど税率が高くなるのです。
年収が130万円を超える時に気をつけたいこと
年収が103万円を超えると、所得税・住民税を計算する基準となる夫の所得から38万円(住民税は33万円)を控除できる「配偶者控除」の適用は受けられなくなります。ここで年収103万円を超えているから関係ないと思っている人は要注意です。なぜなら103万円を超えるとすぐに控除額が0円になるわけではなく、収入に応じて控除額は段階的に減っていくからです。この仕組みを「配偶者特別控除」といいます。
配偶者特別控除では、年収150万円までは配偶者控除と同額の38万円(同33万円)を控除できます。年収が150万円を超えると控除額は減額されていき、201.6万円を超えると控除額は0円になります。つまり妻の年収が150万円を超えると、夫の所得税や住民税が増えてしまうのです。
配偶者特別控除は夫の年収にも注意が必要配偶者特別控除は、必ずしも38万円が上限になるわけではありません。2018年に法改正がされ、年収要件が3つの区分に分かれました。
- 夫の年収が1,095万円以下は控除額が38万円
- 夫の年収が1,095万円を超え、1,145万円以下は26万円
- 夫の年収が1,145万円を超え、1,195万円以下は13万円
- 夫の年収が1,195万円以上は配偶者特別控除が受けられない
※夫の収入が給与のみの場合
配偶者特別控除を受けることができる年収は、1,195万円以下までとなりました。さらに区分ごとに金額が変わります。 配偶者特別控除を受けている場合には、自分の年収だけでなく夫の年収も確認しましょう。
この記事の内容の他にも、「お金が貯まる29の知恵」を1冊にまとめました。
今ならLINE登録するだけで、無料でプレゼントしています。
この機会に是非一度LINE登録して、特典を今スグ受け取ってください。
年収が130万円を超えると必要な申請とは

妻の年収が130万円を超えたら、いくつか必要となる申請があります。夫の勤め先の協力も必要になるので、できるだけ早く申請を進めましょう。
書類を使った手続きは面倒に感じることも多く、ついつい先延ばししがちです。しかし、申請が遅くなってしまうと、後から多額の返還請求が来てしまいます。
あらかじめ家庭で話し合っておくと安心です。
所得税の手続き
会社に勤めている夫は、扶養控除申告書という書類を提出しています。この書類はその年の最初の給与を受け取る前日までに、毎年提出しています。
妻の年収が103万円を超えると、配偶者控除を受けることができません。扶養控除申告書の修正が必要です。配偶者特別控除の申請をすることで、引き続き控除の利用ができます。
配偶者控除と配偶者特別控除は名前が似ています。申請をする時には、間違えないよう気をつけましょう。
夫の健康保険から外れる手続き
夫の健康保険から外れる時には、会社を通して手続きが必要です。妻の月収が10万8,333円を継続して超えることが予想された時点で、手続きをしましょう。年の途中でも問題はありません。
申請の期限は、収入が増えた日(年収が130万円を超える見込みとなった日)から5日以内と決まっています。忘れずに、必ず申請をしてください。130万円を超えた翌月1日が、実際に扶養が外れるタイミングになります。
手続きをしないまま健康保険を使ってしまうと、医療費の返還請求が来ます。気をつけましょう。
年末調整の手続き
年末調整は、妻の収入は見込みで計算が行われます。そのため、実際の収入と違う場合もあるのです。
差額がある時には、夫の会社に年末調整の修正を依頼しましょう。修正は翌年の1月31日まで可能ですが、事務処理が必要であり、間に合わない可能性もあります。修正が間に合わない場合、あるいは修正を行わず、自分で確定申告をする方法もあります。この場合、確定申告は年末調整の上書きとして扱われます。
夫の扶養を抜けるメリット・デメリット

収入を増やしたいけれど、収入が130万円を超えて扶養を外れることは、デメリットが多いのではないかと思う人も多いでしょう。損をするイメージを持ち続け、仕事を控えているという人も存在します。
しかし、扶養を抜けることで得られるメリットもあります。金額的な面のみならず、生活の状況や子どもの有無なども検討して、メリット、デメリットを総合的に判断することが大切です。
また、一度扶養を抜けても、再び入ることが可能です。扶養の再加入を申請する場合、勤め先によっては、収入減少を証明する書類の提出を求められることもあります。雇用契約書や収入の見込証明書、給与明細の写しなどを残して、収入を証明できるようにしておきましょう。
扶養を抜けるメリットとデメリットをご紹介するので、参考にしてください。
夫の扶養を抜けるメリット
扶養を抜けるメリットは2つ。どちらも妻のお金に関わる大きな項目です。
子どもの教育費にお金をかけたい、もっと生活に余裕を持ちたいという考えの女性は、夫の扶養を抜ける人が多いです。
収入が増える年収を抑える必要がなくなります。そのため、給与面でより条件の良い勤め先を探し、やってみたかった仕事に就くこともできるでしょう。パートだけでなく、正社員としてフルタイムで勤務する選択肢も現れます。
配偶者特別控除から外れることになってしまっても、それ以上に収入を増やすことで世帯の手取りを増やすことも可能です。世帯の手取りが増えるということは、生活に余裕が生まれるということでもあります。
より社会で活躍したいと考えている女性にとっては、扶養控除を受ける年収を考慮して仕事を選択するよりも、自分が本当にしたい仕事をすることに魅力を感じるでしょう。
扶養に入っている場合、妻が将来受け取ることのできる年金は国民年金(老齢基礎年金)だけしかありません。
令和3年度の国民年金受給額は、最高で年間780,900円、月額にすれば65,075円であり、これだけで生活するのは厳しいといえます。貯金をしていたとしても不安が残るかもしれません。
また、年金の受給額は減っていくとも言われています。
扶養を抜けることで、妻は厚生年金に加入することにもなります。将来は、国民年金と合わせて厚生年金も受給できるのです。
厚生年金は、収入に比例して金額が増える年金です。収入を増やし厚生年金に加入すれば、老後の年金額を増やすことにつながるのです。
夫の扶養を抜けるデメリット
扶養を抜けるデメリットも、もちろんあります。メリットが将来の生活への備えができる点だとすると、デメリットは目の前の生活が圧迫されるかもしれないという点です。
130万円を少し上回る収入の場合、税金の支払いから手取りが少なくなってしまいます。これではデメリットの方が大きくなるので損です。
年収が130万円よりも大きく上回らないのであれば、入ったままでいることをおすすめします。
社会保険料や税金の支払いが増える扶養に入っていると、妻は保険料を収めずに、国民年金に加入することができます。しかし、扶養を抜けると、保険料を自分で納付しなければいけません。
さらに、健康保険料や住民税、所得税の支払いも発生します。配偶者特別控除で節税をしていた場合には、節税効果もなくなるのです。
扶養を抜けるか考える時には、個人の収入だけでなく世帯収入でもシュミレーションをしましょう。
扶養手当を支給される会社に勤めている場合、手当がなくなることもあります。扶養手当は会社独自の制度なので、有無や金額もさまざま。手当が支給されているのか、支給額はいくらなのか確認しましょう。
微々たる金額であれば気にする必要はありませんが、生活の足しになっている可能性も。扶養手当がなくなった時に妻の収入でカバーができるのか、生活に影響はないのか話し合うことが大切です。
まとめ:年収が130万円を超えた時のシュミレーションをして、賢く扶養制度を利用しよう
年収が130万円を超えたら何が起きるのか、そのメリットとデメリットについてご紹介しました。
年収の金額によって、利用できる扶養制度とその控除金額が変わります。生活への影響や将来のプランを考えて、働き方を決めましょう。
扶養を抜けて、再度入ることは可能です。期限を決めて働けるうちにしっかりと稼いで、貯蓄を増やしても良いかもしれません。ただし、うっかり130万円を超えてしまったということだけは避けましょう。