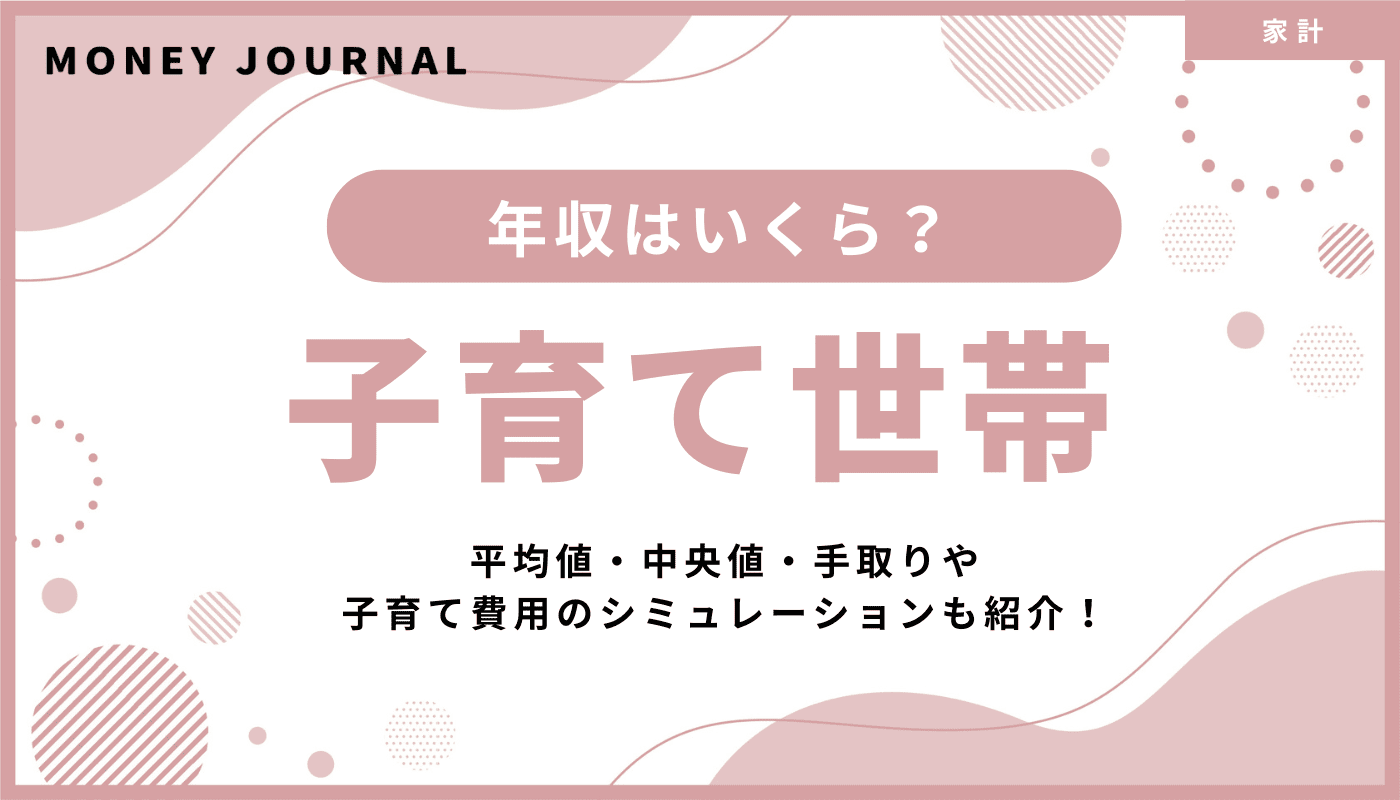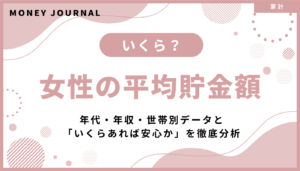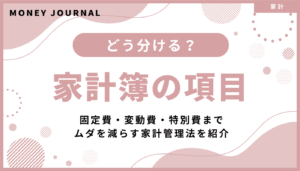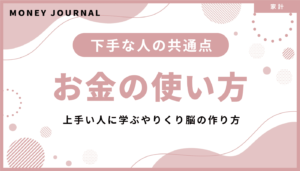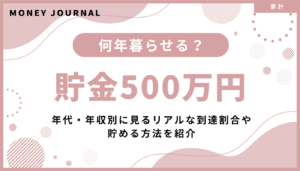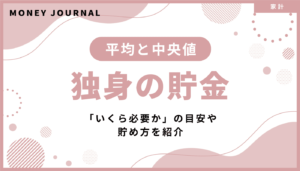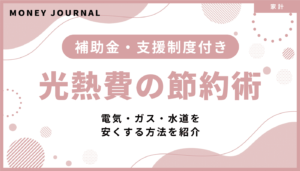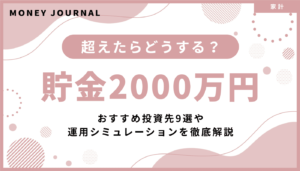- 「子どもにかかるお金ってどれくらい?」
- 「今の年収で、将来までやっていけるのか不安…」
- 「支援制度や貯め方を知って、もっと安心して子育てしたい!」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、子育て世帯の平均年収は、子ども1~2人の場合、約618~約916万円*です。
収入に不安がある方も、制度や計画次第で子育てが楽になるのでぜひ参考にしてください。
*参考:総務省「2024年 家計調査 家計収支編 第3-11表 妻の就業状態,世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と支出」より実収入×12ヶ月で算出
子育て世帯の年収はいくら?平均値・中央値・手取り
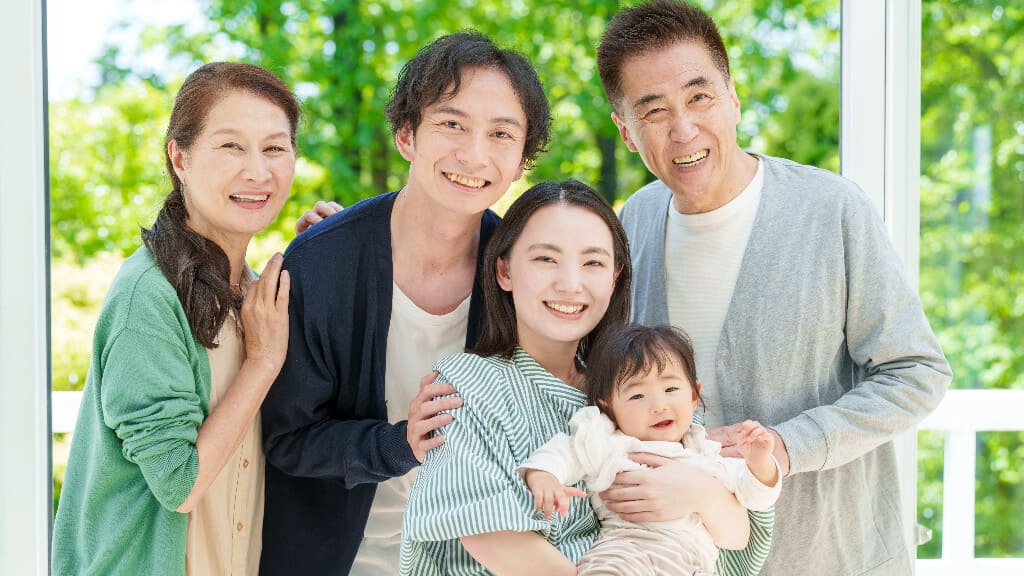
子育て世帯の年収は「共働きかどうか」だけでなく、「子どもの人数」によっても大きく変わります。
以下は総務省の家計調査に基づき、夫婦共働き世帯と、夫のみ働いている世帯それぞれについて、年収の平均額(実収入×12ヶ月)を算出した比較表です。
| 家族構成 | 夫婦共働き世帯の年収 | 夫のみ働いている世帯の年収 |
|---|---|---|
| 夫婦のみ | 約773万円(645,461×12) | 約618万円(514,520×12) |
| 子ども1人 | 約854万円(711,377×12) | 約707万円(589,389×12) |
| 子ども2人 | 約916万円(763,210×12) | 約778万円(648,379×12) |
上記はあくまで“額面年収”であり、実際に自由に使える「手取り額」は以下のように目安を引いた金額で考える必要があります。
| 年収 | 想定手取り(目安) |
|---|---|
| 900万円台 | 約650~700万円 |
| 700万円台 | 約550~600万円 |
| 600万円台 | 約470~520万円 |
税金・社会保険料・住民税などを差し引いた「可処分所得」で見ると、「子ども2人で年収900万円あっても余裕があるとは限らない」といえるでしょう。

子育て世帯の支出の中心は?

子育て費用というと、教育費が頭に浮かぶ人も多いでしょう。しかし、子育て費用は教育費と養育費に大きく分けられます。
養育費とは、子どもの食費や生活用品費、医療費等です。教育費は、学校教育費と学校外教育費、学校外活動費の3種類に分けられます。
教育費と養育費について、それぞれの詳細を以下で解説します。
教育費
教育費は大きく分けて次の3種類です。
- 学校教育費:入学金や授業料、給食費、修学旅行費、制服・通学用品費など
- 学校外教育費:学習塾費や通信教育費、家庭内学習用図書費など
- 学校外活動費:学習塾以外の習い事の月謝や用具費、発表会・試合の費用など
進学を考える場合、直接の学校教育費だけではなく、学校外の教育費と活動費の負担が増えやすいです。自分たちがどの程度準備できるかどうかを検討し、「これは無理」と線引きする必要も起こり得るでしょう。
養育費
養育費とは、子どもが健やかに生育するために必要な費用です。主な内容は以下のとおりです。
- 食費:家庭内での食事代や弁当材料費、外食費、おやつ代など
- 衣類・服飾雑貨費:衣類や下着類、靴、カバン、その他身の回り品の費用
- 生活用品費:生活消耗品や文房具、おもちゃ、子ども用家具・家電などの費用
- 医療費
- 保育費
- 預貯金や保険
- レジャー・旅行代など
食費や衣類費、医療費といった不可欠なものから、レジャー代など生活を充実させるものまで幅広いです。

子育て世帯が必要とする総費用は?
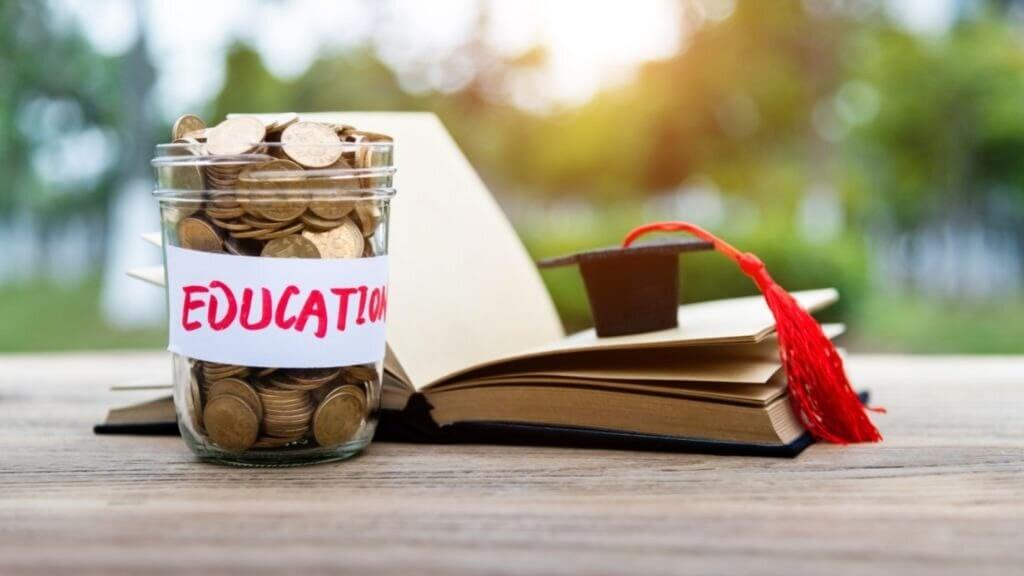
0歳から大学卒業までにかかる子育て費用は、世代を問わず総額でおおよそ3,000万~5,000万円です。内訳としては、教育費が1,000万円以上、養育費がおよそ2,000万円です。
子育て費用総額を大きく左右するものが教育費です。公立と私立では、学費や進学準備に必要な塾の費用などが異なるため、教育費のばらつきが大きくなります。
教育費の総額
幼稚園から大学まで、すべて公立(大学は国立)の場合と、すべて私立の場合の教育費を比較してみましょう。
| 項目 | 公立(大学は国立) | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 47万2,746円 | 92万4,636円 |
| 小学校 | 211万2,022円 | 999万9,660円 |
| 中学校 | 161万6.317円 | 430万3,805円 |
| 高校 | 154万3,116円 | 315万6,401円 |
| 大学 | 481万2,000円 | 821万6,000円(私立文系) |
| 合計 | 1,055万6,201円 | 3,490万502円 |
参考:日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果」(PDF)
教育費総額において、公立と私立では約2,500万円の差がつきます。また、大学で私立の理系を選んだ場合は教育費がさらに高くなります。
私立の学校に進学させたい場合、どの段階で私立を選ぶかによって必要となる教育費が違ってくるため、十分な検討が必要です。
養育費の総額
養育費についてもみていきましょう。幼稚園から大学までの各期間の生活費の総額は下記の表のようになります。
| 項目 | 生活費(各期間の合計) |
|---|---|
| 幼稚園 | 242万5,964円 |
| 小学校 | 420万0,966円 |
| 中学校 | 251万3,475円 |
| 高校 | 251万3,475円 |
| 大学 | 573万0,659円 |
| 合計 | 1,738万4,539円 |
参考:日本学生支援機構「平成30年度 学生生活調査結果」
合計で2000万円ほどの生活費がかかることがわかります。大学の生活費が高くなっているのは、下宿や食費などの生活費用を親が一部負担していることによるものと考えられます。

子育て世帯は年収いくらあればいい?支出シミュレーション

子育て費用はいつどのくらいかかるか、気になるでしょう。そこで、子どもの年齢・段階別に子育て費用がいくらなのか、調査結果を参考にシミュレーションします。
「〇歳頃には〇〇万円程度」とわかると、今後の計画が立てやすくなります。本記事のシミュレーションを例として、子育ての計画・準備に役立ててみてください。
未就学児(0~6歳)
0~6歳の未就学児の子育て費用についてみてみましょう。
乳児・未就園児
保育所や幼稚園に入る前の小さな子どもにかかる子育て費用は、年間平均84万3,225円です。比重の高い費目トップ3は次のとおりです。
| 子育て費用における比重が高い費目 | 費用(1年間あたり) |
|---|---|
| 子どものための預貯金・保険 | 19万9,402円 |
| 食費 | 16万6,387円 |
| 生活用品費 | 14万9,425円 |
子どもが生まれた時にはベビー用品等を用意する必要があるため、生活用品費が一定かかると推測されます。ベビー用品の準備に関しては、以下の記事を参考にしてください。
保育所・幼稚園児
保育所や幼稚園に通う子どもの子育て費用は、年間平均121万6,547円です。比重の高い費目トップ3は次のとおりです。
| 子育て費用における比重が高い費目 | 費用(1年間あたり) |
|---|---|
| 保育費 | 37万9,407円 |
| 食費 | 22万4,627円 |
| 子どものための預貯金・保険 | 18万7,212円 |
幼稚園児の教育費(保育所児は除く)について公立・私立別にみると、公立が年間平均16万5,126円に対し、私立は30万8,909円です。私立の幼稚園に通う場合、公立の2倍近く教育費をかけるといえるでしょう。
小学校
小学校での子育て費用の年間総額の平均は約115万3,500円です。最新の調査で、11歳の子どもの1か月あたりの子育て費用の割合が示されています。11歳の子どもに対する毎月の子育て費用の割合は次のとおりです。
| 1か月あたりの子育て費用 | 家計の割合 |
|---|---|
| 1万~2万円未満 | 10.6% |
| 2万~3万円未満 | 18.8% |
| 3万~4万円未満 | 20.5% |
| 4万~5万円未満 | 13.7% |
| 5万~6万円未満 | 13.4% |
| 6万円以上 | 19.5% |
1か月あたりの子育て費用には、金額の分布にばらつきがあることがわかります。その一因といえるのが教育費です。小学校に入学すると、教育費の比重が増してきます。公立・私立別にみた1年間の教育費は次のとおりです。
| 項目 | 公立小学校 | 私立小学校 |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 6万5,974円 | 96万1,013円 |
| 学校給食費 | 3万9,010円 | 4万5,139円 |
| 学校外活動費(塾等も含む) | 24万7,582円 | 66万797円 |
| 合計 | 35万2,566円 | 166万6,949円 |
私立小学校の学校教育費は公立の15倍以上にもなっており、教育費総額も4倍以上に達することがわかります。小学校から私学に進ませたい場合、子どもが幼い段階で相当の教育資金を準備する必要があります。
中学校
中学校での子育て費用の年間総額の平均は約155万5,600円です。子育て費用に大きな比重を占めている教育費について見てみましょう。
| 項目 | 公立中学校 | 私立中学校 |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 13万2,349円 | 106万1,350円 |
| 学校給食費 | 3万7,670円 | 7,227円 |
| 学校外活動費(塾等も含む) | 36万8,780円 | 36万7,776円 |
| 合計 | 53万8,799円 | 143万6,353円 |
小学校の場合と同様に、中学校でも公立と私立では学校教育費が大きく異なることがわかります。そのため、義務教育を私立で受けさせたい場合、世帯年収が一定以上必要です。
高校
高校の子育て費用総額および養育費に関してのデータはありません。生活水準が中学3年生段階とさほど差がないと考えた場合、年間養育費は中学3年生時の年間子育て費用181万1,802円から教育費を引いた95万7,853円と推定できます。
参考:内閣府「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査」
高校の教育費に関しては次のとおりです。
| 項目 | 公立高校 | 私立高校 |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 30万9,261円 | 75万362円 |
| 学校給食費 | ー | ー |
| 学校外活動費(塾等も含む) | 20万3,710円 | 30万4,082円 |
| 合計 | 51万2,971円 | 105万4,444円 |
公立と私立では学校教育費に大きな差があります。また、高校卒業後の進路をどう選択するかによって、学校外活動費が異なってきます。進学を考える場合、予備校や塾の費用をどれほど準備するかがポイントになるでしょう。
大学
大学での子育て費用の総額の目安は、国立と私立ごとに以下の通りです。
| 項目 | 国立 | 私立 |
|---|---|---|
| 教育費 | 59万2,000円 | 131万700円 |
| 生活費 | 83万9,800円 | 61万7,900円 |
| 合計 | 143万1,800円 | 192万8,600円 |
私立大学の教育費(授業料やその他納付金、課外活動費等)は国立大学の2倍以上であることがわかります。私立大学に進路を設定する場合、教育費をより多く準備することが必要です。

子育て世帯の年収を支える!使える支援制度・助成金一覧

「こんなに費用がかかるのなら、自分たちには子どもは無理かも」と、落ち込んでしまうかもしれません。しかし、現在の日本では、子育てに対してさまざまな支援制度や助成金が設けられています。各制度等を活用すれば、子育て費用の自己負担分を減らせます。
そのため、どのような支援制度や助成金があるのかを事前に知っておくことが重要です。子育ての最中は時間や仕事に追われ、各制度を確認するのが難しくなるかもしれません。
以降で各制度について解説するので、ぜひ無理のない子育てをする上で参考にしてみてください。
出産手当金
出産手当金は、出産のために会社(その他勤務先)を休んでいるときに、出産日以前42日間と出産日以降56日間の範囲内で支給される手当金です。出産で休んだ分の収入を補償する役割を果たしています。
会社員や公務員など、勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合に加入している人が対象であり、パートやアルバイトも含まれます。しかし、自営業者や個人事業主は対象外です。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産費用負担を軽減するためのものであり、出産後申請すると1児につき50万円支給されます(産科医療補償制度対象外の場合は48.8万円)。受給できるのは、健康保険や国民健康保険等の被保険者または被扶養者です。
つまり、会社員や公務員だけではなく、自営業者や個人事業主も受給できます。
出産育児一時金と出産手当金は名称が似ており、混同するかもしれません。それぞれについて、ぜひしっかりとご確認ください。
育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業期間中に一定の要件を満たすと支給される給付金です。正規雇用と非正規雇用によって要件が異なりますが、パートやアルバイトの人も要件を満たせば受給できます。ただし、自営業者や個人事業主など雇用保険未加入の人は受給できません。
男女問わず育児休業給付金を申請できますが、男性の場合は「産後パパ育休」を取得すると「出生時育児休業給付金」を受給できます。
子ども医療費助成制度
乳幼児や児童等、子どもへの医療費の助成制度が全国の自治体で実施されています。子どもがケガをしたり病気になった場合、安価な自己負担分または無料で通院や入院が可能となります。
医療費の助成金額や対象年齢、所得制限は各自治体によって異なるため、詳細に関してはお住まいの地方自治体にお問い合わせください。
なお、都道府県による助成は、通院・入院ともに就学前までおこなわれる場合が最も多いです。一方で、市区町村による助成は通院が15歳の年度末まで、入院が18歳の年度末までの場合が多いです。
児童手当
児童手当は、子育て世帯の生活の安定と子どもの成長を目的とした手当です。子どもの出生後から中学卒業(15歳の誕生日後の3月31日まで)の間に支給されます。申請が遅れるとその分受給できなくなるため、出生後はすみやかな申請が必要です。支給額は以下のとおりです。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律1万5,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 1万円(第3子以降は1万5,000円) |
| 中学生 | 一律1万円 |
ただし、児童手当には所得制限限度額と所得上限限度額があり、所得が高い人は手当額が減額または受給できない場合があります。
幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化とは、就学前の子どもの教育・保育の費用を国や地方自治体が担うことで子育て世帯の負担を軽減する施策です。
幼稚園や保育園、認定こども園等を利用する場合、以下の支援を受けられます。
- 0~2歳児クラス:住民税非課税世帯は無料
- 3~5歳児クラス:無料(制度対象外幼稚園は上限あり)
また、幼稚園での預かり保育や認可外保育施設を利用する場合も、月額上限額までは無償となります。ただし、いずれの場合においても行事費や食材料費、送迎費は自己負担です。
高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金は、公立・私立を問わず高校の授業料に充当するための支援金です。制度改正によって2020年4月から、私立高校に通う場合の支給額が最大39万6,000円となり、実質無償化がおこなわれました。
また、私立の通信制高校なら最大29万7,000円、国公立の高等専門学校なら最大23万4,600円が支給されます。支給額は世帯年収にもとづく計算式「市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額」によって決定されます。計算式の算出額による支給額は次のとおりです。
- 上記式の算出額が15万4,500円未満:最大39万6,000円支給
- 上記式の算出額が15万4,500円以上30万4,200円未満:11万8,800円支給
高等学校等就学支援金があることで世帯年収のハンディキャップが取り除かれ、子どもの進路選択の幅が広がります。
高等教育の就学支援新制度
高等教育の修学支援新制度は、高等教育の各種学校への進学に際して、授業料や入学金の免除または減額と、給付型奨学金の拡充で支援します。対象となるためには、次の3条件を満たす必要があります。
- 国によって一定要件を満たしていると確認された、大学や短大、専門学校等に進学する
- 世帯収入や資産の要件を満たしている(住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯)
- 進学先で学ぶ意欲がある(成績だけではなくレポート等でも確認)
世帯収入だけでは進学が難しい場合でも、子どもの意欲があれば支援を受けることで進学が可能となりました。

【将来が不安な子育て世帯向け】費用準備の3つの方法

各種支援を活用することはもちろん大切ですが、子育てのためにお金を準備しておくことも必要です。特に教育費は、学費だけではなく課外活動やお稽古、学習塾などの学外活動費や、大学の下宿代など想定以上にかかる可能性もあります。
しかし、早い段階からコツコツと準備しておくと、生活で無理をすることなく資金を貯められます。おすすめの方法が、学資保険と貯金、NISAを活用した積立投資の3つです。
いずれも少しずつの積み重ねでできる方法なのでぜひ取り組んでみてください。
出典:金融庁「新しいNISA」
学資保険
学資保険は、子どもの教育費準備を目的とした貯蓄型保険です。入学や進学の際に祝金や満期返戻金という形で資金を受け取れます。また、保険によっては、契約期間中に契約者の保護者が死亡した場合、それ以降の掛け金が免除され祝金等は受け取れるタイプもあります。
貯金
単純な「貯金」も、子育て費用を準備する有効な方法です。
「貯金で教育費を作れるほど、自分たちの年収は高くないし正直きつい」と思う人がいるかもしれません。しかし、高年収ではなくても一定額を貯めることは可能です。コツコツ取り組むと1,000万円も不可能ではありません。
NISAを活用した積立投資
NISAを子育て費用目的で活用することもおすすめです。2024年からNISA制度が変わり、新NISAでは制度期間が無期限となり、非課税枠も増加しています。
貯金は着実に貯められますが、利息が低いためローリスクローリターンです。いっぽう、投資信託の積み立てだと、リターンが見込めるうえに、長期保有と分散投資であるためリスクを低減できます。
しかも、運用益は非課税なので税制面でもお得です。貯金と併用することで子育て費用を準備しやすいでしょう。

子育て費用を計画的に管理するポイント

子育てをしていると子どものためと思い、ついつい子どもにお金をかけてしまうかもしれません。親としては、子どもの行きたい場所や欲しい物、やりたいことを全部かなえてあげたくなるでしょう。
しかし、目先の喜びのために出費していると、子育て費用はいくらあっても足りなくなります。子育て費用を計画的に管理するために、4つのポイントをおさえておきましょう。
将来の教育・生活費を年収から逆算して計画する
まず、子育てに必要な費用を予想し計画を立てましょう。公立と私立のいずれに進むのか、習い事や塾はどの程度可能なのかなど、子どもの成長に伴うさまざまな事項およびその費用をあらかじめシミュレーションしてみます。
子どもの年齢や進学のタイミングで、何にどの程度費用が必要かを予想しておくと、そこからの逆算で資金準備計画もスムーズに設計できます。
年収に見合った支出で乳幼児期を乗り越える
乳幼児期にお金を使い過ぎないことも、子育て費用を準備する上で重要です。子どもが幼い段階では、本来はさほど子育て費用はかかりません。教育費や食費、その他必要費用は就学以降と比較すると、少ない支出で済みます。
必要費用が少ない分、乳幼児期についつい子どもへ余分なお金をかけてしまう場合があります。かわいいベビー服を何着も着せたり、子連れでいろいろな場所へ旅行したりしがちです。子どもも喜ぶためお金を使いたくなりますが、子どもの将来のためにある程度抑制しましょう。
習い事は本当に必要か考慮する
子どもに習い事をさせる時には、その習い事が本当に必要かどうか考慮しましょう。子どもが「やりたい」と言う動機には、本心からやりたいと思っている場合と、「友達もやっている」など何となくの理由による場合があります。
子どもが本当にやりたいと思うものでないなら、時間と費用の喪失になりかねません。親が習い事を決める場合も同様で、周囲に流されないことが大切です。習い事も積み重なると相当の出費になります。月々の費用を見極めつつ、適切な範囲で子どものやる気や自主性を尊重しましょう。
子育て費用の準備に早くからとりかかる
子育て費用の準備には、できるだけ早くからとりかかることが重要です。子どもが成長するにつれ、子育て費用の額面は大きくなりますが、その金額を短時間で準備することは難しいです。早いうちから子育て費用をコツコツ準備することで、無理なく必要金額を用意できます。
子育て費用を準備するために、子ども名義の口座を作っておくこともおすすめです。親名義の口座で貯金すると、つい日常生活費の補てん等に使ってしまうリスクがありますが、子ども名義ならその心配はありません。

子育て世帯の年収に関するよくある質問

子育て世帯の年収に関するよくある質問は以下のとおりです。
子育て世帯にとって共働きのメリット・デメリットは?
共働きの最大のメリットは、給料収入が増えることで教育費や住宅費に余裕が持てる点です。加えて、出産手当や育児給付金、将来の年金額も夫婦それぞれが得られます。一方で、保育料や外注コストが増え、時間と体力の余裕が削られる点がデメリットです。
家族手当や配偶者手当は子育て世帯の年収にどれくらい影響する?
配偶者手当は月1〜2万円、家族手当は子ども1人あたり月5,000〜1万円が相場です。年間にすると数十万円の支給となるため、収入が少ない家庭には大きな助けになります。ただし共働き世帯では対象外になるケースも多く注意が必要です。
子ども2人を育てる場合、どのくらいの世帯年収が必要?
公立中心で切り詰めても最低600万円、私立や習い事を希望するなら800万円以上が目安です。一人っ子でも教育費は1人あたり平均1,000〜2,000万円かかるため、年収だけでなく貯蓄や制度活用も重要です。
終身保険って子育て世帯に本当に必要?負担にならない?
終身保険は「万が一の保障+資産形成」の役割があり、学資目的で活用されることもあります。ただし保険料が高めで家計を圧迫しがちです。貯金やNISAで代替できるなら、必ずしも加入は必要ではありません。
シングルマザーでも子どもを育てられる年収の目安は?
最低ラインは年収300万円ほどですが、30代のシングルマザーでも児童扶養手当や医療費助成を活用することで実質収入はもう少し上がります。実家のサポートや保育園の優先枠も活かすと、収支バランスを保ちやすくなります。
子持ち世帯の生活レベルってどこまで落とさなきゃいけない?
子ども3人の家庭でも、すべてを削る必要はありませんが、固定費(通信・保険・住宅)を見直すだけで大幅に改善できます。「生活を楽しむ余地」を残しつつ、無駄を絞るのが理想です。目安は手取りの7〜8割以内で生活を回すことです。
ワーママでも家計が苦しい…何を見直せばいい?
見直すべきは「固定費」「保険のかけすぎ」「支出の把握漏れ」です。特に保険料が収入の1割以上なら見直しを。つみたてNISAなどの活用も含めて、先取り貯蓄と投資の仕組み化がおすすめです。
世帯年収とは具体的にどの収入を指すの?
世帯年収は、住居と生計を共にする家族全員の年間の額面収入を合計したものです。手取りではなく、税金・社会保険料控除前の収入です。共働き世帯では夫婦それぞれの給与や賞与を合算します。
子育て世帯が感じる“生活レベルの限界”ってどのあたり?
手取り月25万円未満の4人家族では、家賃・食費・教育費を賄うだけで精一杯になる傾向があります。「趣味やレジャーが減った」「貯金がゼロに近い」と感じる水準が限界ラインです。
双子の子育て、年収が足りなくてやばい…どうすれば?
双子育児は出費が一度に重なるため家計が急激に苦しくなります。まずは児童手当・医療費助成・保育料軽減制度を最大限活用しましょう。お金の流れを整理し、FPに家計のシミュレーションを依頼するのもおすすめです。
まとめ:資金準備と制度の活用で無理のない子育てが可能
子育て費用がどの程度必要なのかと、活用できる支援制度や助成金、資金の準備方法、子育て費用を計画的に管理するポイントを解説しました。子育てにお金がかかるのは事実です。
しかし、早くから少しずつ資金を準備し、支援制度等をうまく活用すると無理なく子育てができます。