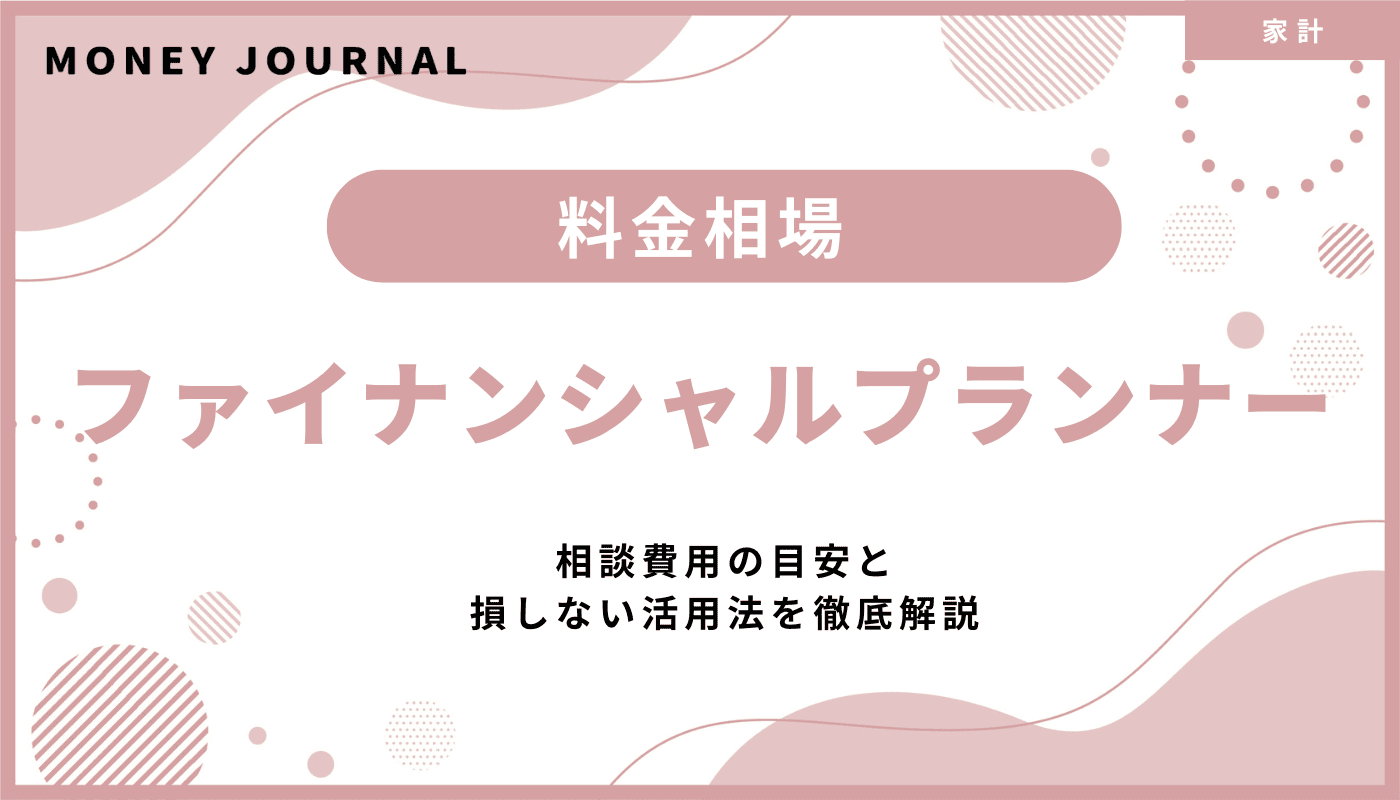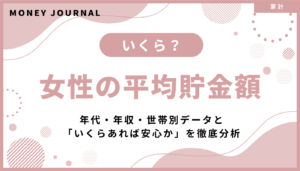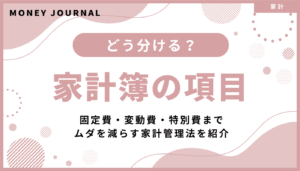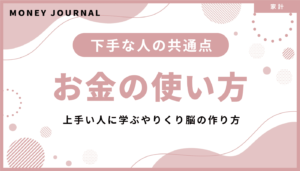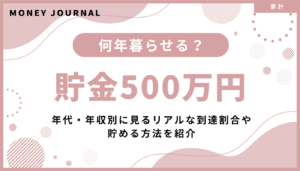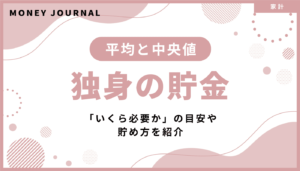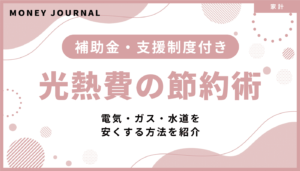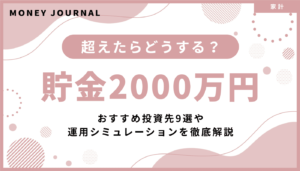- 「ファイナンシャルプランナーって、結局いくらかかるの?」
- 「無料と有料、どう違うのか分からない…」
- 「相談したいけど、どこまで話していいのか不安…」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談する際の料金相場は以下のとおりです。
| 相談形式 | 料金相場(税込) | 特徴 |
|---|---|---|
| 単発相談(1回) | 5,000〜20,000円/1時間 | 初回ヒアリングやざっくり相談向き |
| 面談パック | 30,000〜100,000円前後 | ライフプランや投資設計など継続前提 |
| 無料相談 | 0円 | 商品提案が前提。中立性には注意が必要 |
| 継続顧問契約 | 月5,000〜20,000円 | 家計・資産・保険を定期的に見直し可能 |
本記事では、ファイナンシャルプランナーの料金相場だけでなく、相談形式別の特徴や無料相談で損しない見極め方もわかりやすく解説していきます。
「必要な費用は払ってでも、価値のある提案がほしい」という方は、ぜひ参考にしてください。
ファイナンシャルプランナーの料金相場・費用体系

ファイナンシャルプランナーへの相談料金は、「時間制」だけでなく、「相談の形式」や「依頼内容」によっても変わってきます。
以下では、相場感・形式ごとの違い・追加費用がかかるケースまで順に整理していきます。
相場は1時間5,000〜20,000円
ファイナンシャルプランナーの料金は1時間あたり5,000円〜20,000円が一般的な相場です。
個人向けの単発相談では1時間1万円前後で設定している事務所が多いものの、初回は割安なプランを設けている例も見られます。
たとえば、相談後に10ページ以上のライフプラン資料を提供するファイナンシャルプランナーは、1時間あたり15,000円〜20,000円を超えることもあります。金額だけで判断せず、何が含まれているかに注目することが大切です。
相談形式別の料金体系
ファイナンシャルプランナーの料金体系は、相談の形式によって大きく3つに分かれます。
| 相談形式 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単発相談 | 5,000〜20,000円/回 | 必要なテーマを短時間で解決 |
| 継続サポート | 5万〜20万円/数ヶ月 | 定期面談+メール相談付き |
| 顧問契約 | 月1万〜3万円 | 節税・相続など継続支援に対応 |
このように、相談の深さと期間に応じて費用は変わります。
相談内容によって別料金が発生する
ファイナンシャルプランナーへの相談では、内容によっては基本料金とは別に追加費用がかかる場合があります。
以下に代表的な3パターンとその特徴をまとめました。
| 相談内容 | 追加料金の一例 |
|---|---|
| ライフプラン作成 | 長期キャッシュフロー資料付き:+5,000〜15,000円 |
| 保険診断 | 保障額の見直し・複数社比較:+3,000〜10,000円 |
| 投資プラン設計 | ポートフォリオ作成+試算:+10,000〜20,000円 |
初回相談料にすべて含まれている場合もあれば、資料作成や分析に追加費用を設定している場合もあります。予約前に「料金に何が含まれているか」「レポート作成費は別かどうか」を必ず確認しましょう。
とはいえ、「どこまでが無料で、どこからが追加費用なのか分かりづらい…」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
そんな方には、何度相談しても無料で、中立的なアドバイスが受けられるマネーコーチのオンライン家計診断の活用がおすすめです。
まずは30秒で予約完了。将来のお金の不安を軽くしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ファイナンシャルプランナーへの無料相談と有料相談の違い

ファイナンシャルプランナーに相談しようと調べると、「無料」「初回無料」といった言葉をよく見かけます。金額が気になる方にとっては魅力的に映りますが、その裏側にはしっかりとしたビジネスの構造があります。
ここでは無料と有料、それぞれのFP相談がどのような考え方で成り立っているのかを整理していきます。
無料相談は商品提案前提
無料で相談できる場合の多くは、保険会社や証券会社などと提携している販売系ファイナンシャルプランナーです。
初回相談では丁寧にヒアリングしてくれますが、最終的には自社または提携先の保険や金融商品の提案につなげることが前提となっていることがほとんどです。
無料相談の前には、下記ポイントを意識してください。
- FPが「保険募集人」や「証券外務員」資格を持っていないか確認する
- 事前に料金表や商品販売の有無を問い合わせる
- 目的が売ることではないかを見極める
「無料=中立」とは限りません。提案内容が偏らないかを冷静に見ておくとよいでしょう。
有料相談は中立性と提案の深さが強み
有料で相談を受けているファイナンシャルプランナーは、商品販売から報酬を得ていない独立系が多く、中立的な視点で本当に必要な提案をしてくれます。
支出が多くて貯金ができないという悩みに対しては、保険や投資を無理に勧めるのではなく、家計改善のアドバイスや支出管理の仕組みまで落とし込んだ具体策を提示してくれることもあります。
代表的なサポート内容は以下のとおりです。
- 支出の見直し・キャッシュフロー表の作成
- 複数金融商品を比較したシミュレーション
- 将来設計に沿ったライフプランの提案
必要がなければ「今は動かさなくてOK」とはっきり言ってくれることもあり、利益より信頼を重視している姿勢が伝わります。

ファイナンシャルプランナー相談で損する人の典型パターン

ファイナンシャルプランナーに相談したものの、「何を聞けばいいか分からなかった」「言われるがままに契約して後悔した」という声は少なくありません。
ここでは、相談でありがちな失敗パターンを3つ紹介します。
「なんとなく」で相談すると時間もお金もムダになる
ファイナンシャルプランナーに「とりあえず相談してみよう」という曖昧な目的で臨むと、時間も相談料もムダになる可能性が高いです。
「老後が不安」と伝えるだけでは、ファイナンシャルプランナー側も具体的な分析ができず、表面的なアドバイスで終わってしまいます。
たとえば以下のように明確にしておくと、相談の質が格段に上がります。
- 現状の悩み:「毎月赤字で貯金ができない」
- 目指したい状態:「5年以内に年間100万円の貯蓄ペースにしたい」
このようにゴールを明確にすると、ファイナンシャルプランナーも的確な改善案を出しやすくなります。
提案内容を鵜呑みにすると“手数料負け”する可能性も
ファイナンシャルプランナーから紹介された商品をそのまま契約してしまうと、コストが足を引っ張り、思ったようにお金が増えないことがあります。
外貨建て保険やアクティブ型投資信託のように、見えづらい手数料が毎年差し引かれる商品は長期で見て元本割れすることも。
相談後は以下のチェックを忘れずに行いましょう。
- 手数料・解約条件に不明点がないか
- 提案内容と同等の機能を持つ商品を比較したか
- 自分の目的に本当に合っている内容か
「FPが言うから大丈夫」と思わず、提案はひとつの選択肢として冷静に見直す姿勢が必要です。
継続契約が割安になるとは限らない
「顧問契約の方が割安ですよ」と勧められることもありますが、継続契約が必ずしもお得とは限りません。
たしかに相談頻度が高い人であればコスパは見合いますが、テーマが明確な場合は単発相談の方が合理的です。
以下のような場合は、継続契約より単発相談が向いています。
- 住宅購入や保険の見直しなど、特定の課題だけ解決したい
- 資産形成の軸は決まっていて、時々相談できれば十分
契約を結ぶ前に、「年額の相談料」と「得られるサービス内容」を冷静に比較しましょう。

費用ではなく価値で選ぶファイナンシャルプランナーの選び方

料金より価値を重視してファイナンシャルプランナーを選ぶための3つの視点を解説します。
保有資格・得意分野・実績から向き不向きを見抜く
ファイナンシャルプランナーを選ぶ際は、単に安いかどうかではなく、その人の得意分野やこれまでの支援実績を確認することが大切です。
肩書きだけでは得意領域までは見えないため、保有資格や実績を手がかりに向き不向きを判断しましょう。
以下は資格ごとの特徴です。
| 資格 | 特徴 | 向いている相談内容 |
|---|---|---|
| AFP/CFP® | より高度なFP資格(CFPは国際ライセンス) | 総合的な資産設計、ライフプラン |
| 証券外務員 | 金融商品の取り扱い可 | 投資、資産運用の相談 |
| 宅地建物取引士 | 不動産取引の専門資格 | 住宅購入や資産売却 |
| 社会保険労務士 | 年金・社会保障制度の専門家 | 老後資金、保障の制度面相談 |
FPの公式サイトやSNSで、過去の相談内容や得意分野を確認してみてください。自分の悩みと重なる事例があれば、相談のミスマッチを防げます。
商品販売の有無で中立性を確認する
ファイナンシャルプランナーには、大きく分けて2タイプいます。「商品を販売するFP」と「販売を行わない独立系FP」です。
この違いは、アドバイスの中立性に直結します。
下記に違いをまとめました。
- 販売を行うFP:提案に販売手数料が含まれる可能性あり
- 完全独立FP:相談料のみで報酬を得るため、提案が中立的
ホームページや所属機関をチェックし、「保険募集人登録があるかどうか」「特定商品を販売しているか」を確認してみてください。
本当に必要かどうかを判断してほしいなら、販売をしない立場のファイナンシャルプランナーを選ぶのが無難です。
口コミは“評価軸”で見極める
口コミを見るときに大切なのは、「誰が」「どんな観点で」評価しているかを意識することです。
たとえば「話しやすかった」という声が多くても、自分が求めているのが専門的な資産運用の助言であれば、親しみやすさだけでは判断材料として不十分です。
口コミで見るべきポイントは以下のとおりです。
- 相談内容が自分と近いか
- 提案の効果が行動に結びついているか
- 手数料や販売前提の提案がなかったか
Googleのレビューや公式サイトの体験談だけでなく、SNSや専門サイト(FP検索サービスなど)も併用し、自分の目的に近い評価軸で選ぶことが失敗を防ぐポイントです。

【比較】ファイナンシャルプランナーと他の相談先との違い

お金の悩みを相談したいと思ったとき、ファイナンシャルプランナー以外にも相談できる場所はいくつかあります。
ただし、どこに相談するかによって受けられるアドバイスの中身や中立性が大きく変わる点には注意が必要です。
ここではFPと他の相談先を比較しながら、それぞれのメリット・注意点を整理していきます。
IFAは資産運用に強いが報酬体系に注意
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、金融機関に属さず中立な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
投資信託・株式・債券などの運用設計に強みがあり、証券口座の開設から商品の選定まで一貫してサポートしてくれる点が特徴です。
IFAに相談する場合は、以下を確認しましょう。
- 報酬の仕組み:販売手数料かフィーベースか
- 商品の偏り:特定の証券会社や商品に偏っていないか
- 口座管理料などの継続費用は発生するか
中立に見えても、実際には特定商品に誘導されることもあるため、相談料以外にどのような費用が発生するのか事前に細かく確認しておきましょう。
銀行・保険会社の相談窓口は自社商品前提が基本
銀行や保険会社でも「無料相談会」や「ライフプランシミュレーション」を提供していますが、基本的には自社商品の販売を目的とした相談対応である点を押さえておく必要があります。
銀行で資産運用の相談をすると、自社が取り扱う投資信託や定期預金、外貨商品などが中心。保険会社では、主に自社の生命保険や医療保険の設計がメインとなります。
このような相談窓口では以下のような傾向があります。
- 中立的な商品比較は行われない
- 他社の商品や制度を積極的に案内することは少ない
- 長期的な視点より、契約成立を急がれることもある
もちろん、特定商品を検討している場合には便利ですが、「自分に本当に合ったプランを一から設計したい」場合には、制約の少ない独立系FPやIFAの方が適しています。

【準備】ファイナンシャルプランナー相談時に持参すべき資料一覧

ファイナンシャルプランナーへの相談で成果を出すには、具体的な数字をもとに話せるかどうかが重要です。
口頭だけでは曖昧になりがちな情報も、資料があれば正確な分析が可能になります。
ここでは相談内容別に、持参しておくと役立つ資料をテーマごとにまとめました。
家計相談に必要な資料|家計簿・明細・クレジット履歴など
家計改善の相談をしたい場合は、「毎月いくら使っていて、何に使っているのか」がわかる資料が必須です。
収入と支出のバランスがわからないと、ファイナンシャルプランナー側も改善ポイントを提案できません。
持参すべき代表的な資料は以下のとおりです。
- 家計簿(手書きでもアプリでもOK)
- 銀行口座の入出金履歴(直近3ヶ月分程度)
- クレジットカード利用明細
- 公共料金の引き落とし明細や請求書
- 給与明細や源泉徴収票(収入の把握用)
「全部そろえるのは大変…」という方も、最低限のメモやスマホ画面のキャプチャだけでも十分ですので、できる範囲でご準備ください。
保険・運用相談に必要なもの|証券・運用状況・定期便など
保険の見直しや資産運用の相談では、「いま何にいくら払っていて、どんな保障・運用になっているか」を示す資料が必要です。
以下を事前にそろえておきましょう。
- 加入中の保険証券(生命保険・医療保険・がん保険など)
- 保障内容の一覧(保険会社から送付された設計書や契約内容のお知らせ)
- 投資信託・株式・外貨などの運用状況一覧(証券会社の残高明細やアプリ画面の印刷でも可)
- ねんきん定期便(年金受取見込みの把握に必要)
最新版でなくても問題ありませんが、商品名・月々の支払い・積立残高などが明確に分かることが大切です。相談後の提案にも直結するため、漏れなく準備しておきましょう。
住宅・相続・進学相談にあると便利な書類一覧
人生の節目となるイベントでは、今後のライフプランを見据えた具体的な数字の資料があるとFPがより現実的な提案を行いやすくなります。
相談テーマ別に、持参しておきたい資料は以下のとおりです。
| 相談テーマ | 持参すると役立つ資料 |
|---|---|
| 住宅購入 | 住宅ローン仮審査書、物件概要書、頭金予定額のメモ |
| 相続対策 | 遺言書(写し)、不動産登記簿、相続対象の資産一覧 |
| 教育費 | 進学先の学費一覧、教育費の積立計画、学資保険証券 |
これらの書類があることで、FPは具体的な金額ベースで提案できます。資料が手元にない場合は、メモ書きやスクリーンショットだけでも十分なヒントになりますので、持ち物無しで行かないようにすることは忘れず実施しましょう。

ファイナンシャルプランナー相談当日の流れと所要時間の目安

初めてファイナンシャルプランナー(FP)に相談する際、「何を聞かれるのか」「どれくらい時間がかかるのか」がわからず不安に感じる方も多いでしょう。
ここでは、相談当日の一般的な流れとそれぞれの目安時間をわかりやすく解説します。
まず最初に行われるのが、相談者の希望や悩みをヒアリングするステップです。
たとえば「家計の赤字を解消したい」「老後資金が足りるか不安」「教育費をいつまでにどれだけ用意すべきか」など、将来に向けた漠然とした不安でも問題ありません。
ファイナンシャルプランナーは以下のような質問を通じて、目的を明確化してくれます。
- どんなことに不安や課題を感じていますか?
- いつまでに、どんな状態を実現したいですか?
- お金に関する決断で悩んでいることはありますか?
FPからは「何に困っているか」「いつまでにどうなりたいか」といった質問がされ、漠然とした不安を“具体的な相談テーマ”に変える作業が行われます。所要時間の目安は30〜40分程度です。
続いて、収入・支出・資産・加入保険など、現在の経済状況を整理・分析するフェーズに入ります。
持参した資料を元に、ファイナンシャルプランナーが以下の項目を可視化してくれます。
- 月々の支出項目と貯蓄ペース
- 金融資産・負債の全体像
- 保険の保障内容と保険料のバランス
- 公的年金の将来見込額(ねんきん定期便など)
この工程を経て「どこにムダがあるか」「リスクはどこか」が明確になります。数字に向き合うことで、お金の使い方に対する意識も自然と変わるはずです。時間の目安は20〜30分程度です。
現状の課題が明らかになったあとは、それに対する具体的な改善策の提案が行われます。
この段階では、ファイナンシャルプランナーから以下のようなアドバイスが提示されます。
- 家計改善:通信費・保険料の見直しで固定費を削減
- 資産運用:毎月の積立額と商品配分のシミュレーション
- 教育資金:効率的な積立方法とタイミングの計画
- 相続:生前贈与や遺言書作成の必要性の検討
多くの場合、複数の方向性が提示され、相談者が納得したうえで行動できるよう配慮されています。この提案ステップに30分前後を使うケースが一般的です。
最後に、相談内容を踏まえて何から始めるか、どのような行動を取るかを明確にし、必要に応じて継続サポートの提案が行われます。
- まず実行すべきことを優先順位ごとに整理
- 必要があれば後日、提案レポートやライフプラン表を送付
- 継続契約(半年・1年)やスポット相談の追加を案内されることも
ファイナンシャルプランナーから無理に契約を勧められることは少なく、相談者の判断に委ねるスタンスが基本です。
所要時間は10〜20分程度です。初回相談は全体で90分前後が目安となります。
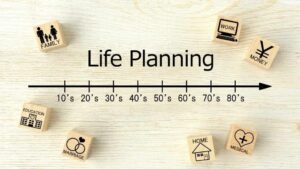
ファイナンシャルプランナーに関するよくある質問

ここでは、相談前によく寄せられる5つの質問をピックアップして紹介します。
FP相談料の費用相場はなぜこんなに違う?
相談料金が異なるのは、FPの資格や経験年数、提供するサービス内容が違うからです。雑談中心のアドバイスだけなら1時間5,000円前後ですが、詳細なシミュレーションや提案書まで作る相談では、2〜3万円を超えることもあります。
無料相談で営業されるのが不安…どう見分ける?
無料相談の多くは、保険や金融商品の販売を目的としたサービスです。
中立性を見極めるには、ファイナンシャルプランナーが「保険募集人」や「特定企業に所属」しているかをチェックしてください。
無料でも丁寧な人はいますが、「無料=商品提案がある可能性」と理解しておけば、違和感なく受け止められるでしょう。
個人でも相談できる?法人との違いは?
もちろん個人でも問題ありません。
個人の相談では、家計・教育費・保険・資産運用など生活に直結したテーマが中心です。一方、法人向けは退職金や福利厚生、節税や事業承継といった経営課題がメインになります。相談テーマに合った分野を得意とするファイナンシャルプランナーを選びましょう。
FP相談って恥ずかしい?失礼な態度を避けるコツは?
「こんなこと聞いていいのかな」と心配される方もいますが、ファイナンシャルプランナーにとってお金の悩みは日常業務です。
恥ずかしがる必要はまったくありません。ただし、何を聞きたいのかが曖昧だと困らせてしまうので、相談の目的と簡単な収支状況だけでも整理しておくとよいでしょう。
フリーFPと所属FPはどちらが安心?
安心感はどちらにもあります。フリーFPは商品販売をせず中立な立場で提案してくれる人が多く、将来設計や家計の見直しに向いています。
一方、所属FPは特定商品の知識が深く、契約手続きまで一貫してサポートしてくれるのが魅力です。相談テーマに応じて使い分けるのが理想的です。
まとめ:高いかどうかより「得られる価値」で判断しよう
この記事では、ファイナンシャルプランナーの料金相場や相談形式ごとの違い、有料と無料の注意点まで解説しました。
料金は1時間5,000円からと幅がありますが、大切なのは金額より中身。費用だけで判断すると、あとで後悔してしまうかもしれません。
たとえば、以下のような場合は相談形式の選び方も変わります。
- 家計の見直しを一度だけしたい→単発相談
- 定期的にお金の相談をしたい→継続顧問契約
- とにかく何か始めたいけど不安→中立な有料FP
まずは「何に悩んでいるのか」「どんな未来を描きたいのか」を簡単に整理してみましょう。メモひとつあるだけで、相談の質はまるで違います。
納得できるお金の判断をしたい方こそ、勇気を出してプロに相談してみてください。