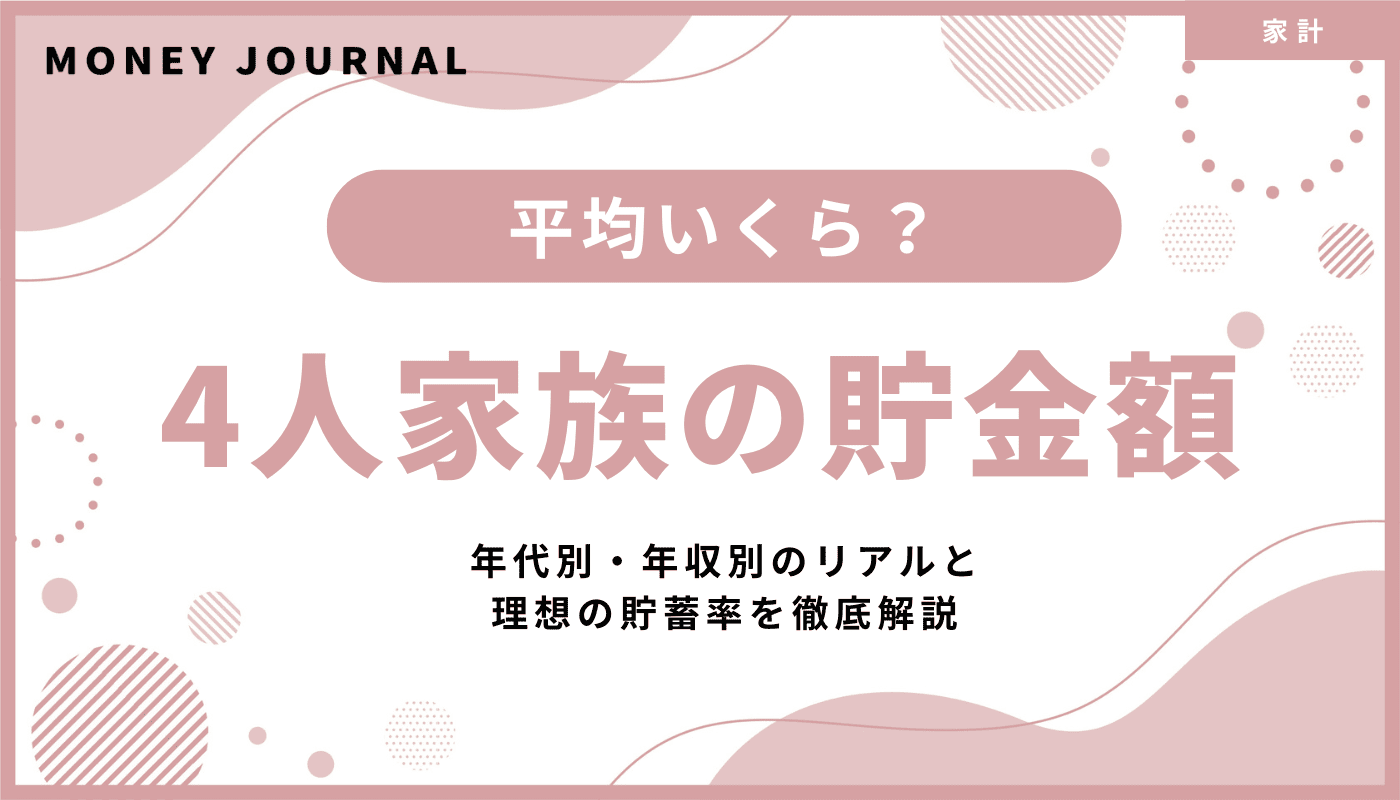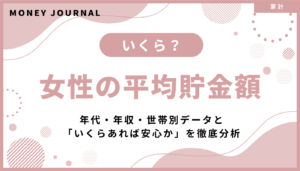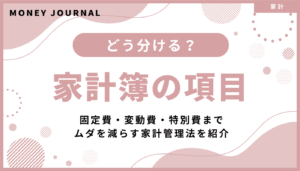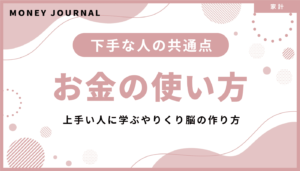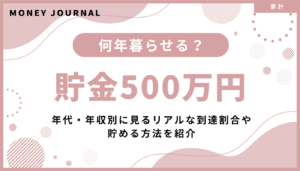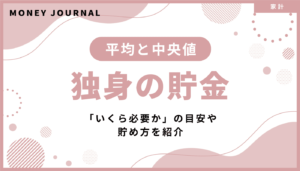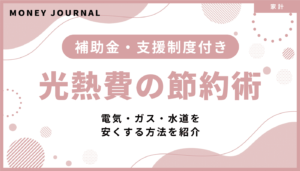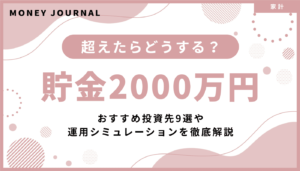- 「周りの家庭がぶっちゃけどれくらい貯めているのか知りたい」
- 「自分の貯金額が平均より多いのか少ないのか知りたい」
- 「子ども2人世帯の貯金はいくらあればいい?」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、4人家族の平均貯金額は以下のとおりです。
| 分類 | 平均貯金額 | 中央値 |
|---|---|---|
| 全体(児童のいる世帯) | 約1,030万円 | 約650万円 |
| 30代 | 約601万円 | 約150万円 |
| 40代 | 約889万円 | 約220万円 |
| 50代 | 約1,147万円 | 約300万円 |
出典:金融広報中央委員会「各種分類別データ(令和5年)」
本記事では、上記のデータをもとに年代別・年収別のリアルな貯金額から、理想的な貯蓄率や毎月の貯金目安まで徹底解説します。さらに「なぜ貯まらないのか」という原因と、今日から実践できる貯金の増やし方も紹介します。
「わが家も計画的に資産を増やしたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
4人家族の貯金額|平均・中央値はいくら?

本章では、児童のいる世帯の平均・中央値や、1,000万円以上保有する世帯の割合、そして貯金ゼロ世帯の実態まで紹介します。
児童のいる世帯の平均貯蓄額は約1,030万円
厚生労働省「国民生活基礎調査の概況(2022年)」によると、児童のいる世帯(4人家族を含む)の平均貯蓄額は1,029.2万円*です。
ここでいう貯蓄には、定期・普通預金だけでなく、株式・投資信託・保険商品など、将来のために蓄えている金融資産が含まれます。
平均額は、高額資産を保有する一部の家庭によって引き上げられるため、実感としては中央値(650万円前後)*のほうが近い場合もあります。それでも子育て世帯で1,000万円を超える水準は全国的に見ても高めです。
*出典:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
貯金1,000万円越え世帯は約37.9%
同調査では、児童のいる世帯のうち37.9%*が1,000万円以上*の貯金を保有している結果が出ています。
住宅ローン残高や教育費の有無にかかわらず、長期間にわたってコツコツ資産を積み上げてきた家庭が一定数あることを意味します。
一方で、裏を返せば6割以上の家庭は1,000万円未満のため、「1,000万円越えは少数派」という現実も見えてきます。
*出典:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
貯金なし世帯は約9.2%
一方で、まったく貯金を持たない世帯も約9.2%存在します。理由としては、教育費や住宅ローンの返済で家計が圧迫され、貯蓄に回す余裕がない、事故や病気など予期せぬ出費で貯金を使い切ってしまったなどが挙げられます。
年代別では、若い世帯ほど貯金なしの割合が高く、年齢を重ねるにつれて減少する傾向があります。
まずは少額でも、継続して貯める仕組みづくりを意識しましょう。
一方で、「何から始めればいいかわからない」「家計のどこを見直せば貯金できるのか不安」という方も多いのではないでしょうか。
そのような場合は、プロのFPが個人の家計を丸ごとチェックしてくれるマネーコーチのオンライン家計診断を活用するのも有効です。
スマホやPCから無料で相談でき、貯金を生み出す具体的な改善ポイントを提案してくれるため、今の生活を大きく変えずに貯蓄体質へ近づけます。
まずは現状を知ることから、未来の安心づくりを始めてみてはいかがでしょうか。

【年代別】4人家族の貯金額

続いては、年代ごとの平均額・中央値と特徴を詳しく見ていきましょう。
20代:平均249万円・中央値30万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 36.8 |
| 〜200万円未満 | 21.6 |
| 〜300万円未満 | 9.9 |
| 〜400万円未満 | 8.2 |
| 〜500万円未満 | 4.7 |
| 〜700万円未満 | 4.7 |
| 〜1,000万円未満 | 4.1 |
| 〜1,500万円未満 | 2.3 |
| 〜2,000万円未満 | 1.2 |
| 〜3,000万円未満 | 0.0 |
| 3,000万円以上 | 2.3 |
| 無回答 | 0.6 |
| 平均 | 249万円 |
| 中央値 | 30万円 |
20代では金融資産非保有が36.8%と全世代で最も高く、平均249万円・中央値30万円と低水準です。就職や結婚、出産などで支出が多く、貯蓄に回す余力が少ない時期といえます。
30代:平均601万円・中央値150万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 28.4 |
| 〜200万円未満 | 12.3 |
| 〜300万円未満 | 9.9 |
| 〜400万円未満 | 7.6 |
| 〜500万円未満 | 5.6 |
| 〜700万円未満 | 4.5 |
| 〜1,000万円未満 | 6.6 |
| 〜1,500万円未満 | 5.2 |
| 〜2,000万円未満 | 6.3 |
| 〜3,000万円未満 | 2.2 |
| 3,000万円以上 | 2.6 |
| 無回答 | 4.0 |
| 平均 | 601万円 |
| 中央値 | 150万円 |
30代では平均601万円・中央値150万円に上昇。非保有世帯は28.4%まで減少し、1,000万円以上の世帯も増えますが、住宅ローンや教育費が重く、資産差が広がる時期です。
40代:平均889万円・中央値220万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 26.8 |
| 〜200万円未満 | 9.6 |
| 〜300万円未満 | 8.9 |
| 〜400万円未満 | 4.9 |
| 〜500万円未満 | 5.7 |
| 〜700万円未満 | 3.8 |
| 〜1,000万円未満 | 7.4 |
| 〜1,500万円未満 | 5.6 |
| 〜2,000万円未満 | 7.4 |
| 〜3,000万円未満 | 3.5 |
| 3,000万円以上 | 5.3 |
| 無回答 | 6.5 |
| 平均 | 889万円 |
| 中央値 | 220万円 |
40代は平均889万円・中央値220万円。非保有世帯は26.8%と依然4分の1を占めます。教育費と住宅ローンの両立が課題です。
50代:平均1,147万円・中央値300万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 27.4 |
| 〜200万円未満 | 9.1 |
| 〜300万円未満 | 6.4 |
| 〜400万円未満 | 3.8 |
| 〜500万円未満 | 3.9 |
| 〜700万円未満 | 3.8 |
| 〜1,000万円未満 | 5.6 |
| 〜1,500万円未満 | 5.5 |
| 〜2,000万円未満 | 8.9 |
| 〜3,000万円未満 | 4.2 |
| 3,000万円以上 | 5.4 |
| 無回答 | 11.2 |
| 平均 | 1,147万円 |
| 中央値 | 300万円 |
50代は平均1,147万円・中央値300万円。非保有率はやや上昇して27.4%。退職金や子どもの独立を見据えて老後資金積立を加速させたい時期です。
60代:平均2,026万円・中央値700万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 21.0 |
| 〜200万円未満 | 5.9 |
| 〜300万円未満 | 4.5 |
| 〜400万円未満 | 4.3 |
| 〜500万円未満 | 3.0 |
| 〜700万円未満 | 1.9 |
| 〜1,000万円未満 | 7.2 |
| 〜1,500万円未満 | 6.7 |
| 〜2,000万円未満 | 6.8 |
| 〜3,000万円未満 | 5.4 |
| 3,000万円以上 | 9.5 |
| 無回答 | 20.5 |
| 平均 | 2,026万円 |
| 中央値 | 700万円 |
60代は平均2,026万円・中央値700万円でピーク期。非保有率も21.0%に下がり、多くが老後資金を確保済みです。
70代:平均1,757万円・中央値700万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 19.2 |
| 〜200万円未満 | 5.6 |
| 〜300万円未満 | 5.1 |
| 〜400万円未満 | 4.3 |
| 〜500万円未満 | 4.7 |
| 〜700万円未満 | 2.5 |
| 〜1,000万円未満 | 6.2 |
| 〜1,500万円未満 | 5.8 |
| 〜2,000万円未満 | 10.2 |
| 〜3,000万円未満 | 6.6 |
| 3,000万円以上 | 7.4 |
| 無回答 | 19.7 |
| 平均 | 1,757万円 |
| 中央値 | 700万円 |
70代は平均1,757万円・中央値700万円とやや減少。80代にかけても非保有世帯は19.2%で、資産を取り崩しながら生活する段階に入ります。

【年収別】4人家族の貯金額

続いては、年収別の平均額・中央値と特徴を見ていきましょう。
収入なし世帯:平均326万円・中央値0円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 62.8 |
| 〜200万円未満 | 5.3 |
| 〜300万円未満 | 3.7 |
| 〜400万円未満 | 2.1 |
| 〜500万円未満 | 1.6 |
| 〜700万円未満 | 0.0 |
| 〜1,000万円未満 | 1.1 |
| 〜1,500万円未満 | 0.5 |
| 〜2,000万円未満 | 0.0 |
| 〜3,000万円未満 | 1.1 |
| 3,000万円以上 | 0.5 |
| 無回答 | 1.6 |
| 平均 | 326万円 |
| 中央値 | 0円 |
収入がない世帯では金融資産非保有率が62.8%と極めて高く、中央値は0円です。生活の多くを年金や家族からの援助に頼っていることが中心で、日々の生活費をまかなうために過去の貯蓄を取り崩す段階に入っている家庭が目立ちます。
年収300万円未満:平均618万円・中央値50万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 37.9 |
| 〜200万円未満 | 13.0 |
| 〜300万円未満 | 7.8 |
| 〜400万円未満 | 5.4 |
| 〜500万円未満 | 3.7 |
| 〜700万円未満 | 3.6 |
| 〜1,000万円未満 | 5.9 |
| 〜1,500万円未満 | 3.5 |
| 〜2,000万円未満 | 5.0 |
| 〜3,000万円未満 | 2.8 |
| 3,000万円以上 | 3.2 |
| 無回答 | 5.3 |
| 平均 | 618万円 |
| 中央値 | 50万円 |
年収300万円未満の世帯では非保有率37.9%と高く、中央値は50万円にとどまります。生活費で手一杯になり、毎月の貯金額を確保するのが難しい傾向があります。

年収300〜500万円未満:平均1,051万円・中央値274万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 25.6 |
| 〜200万円未満 | 9.3 |
| 〜300万円未満 | 8.0 |
| 〜400万円未満 | 5.3 |
| 〜500万円未満 | 5.5 |
| 〜700万円未満 | 2.8 |
| 〜1,000万円未満 | 6.2 |
| 〜1,500万円未満 | 6.3 |
| 〜2,000万円未満 | 7.1 |
| 〜3,000万円未満 | 5.0 |
| 3,000万円以上 | 5.1 |
| 無回答 | 10.2 |
| 平均 | 1,051万円 |
| 中央値 | 274万円 |
年収300〜500万円未満では非保有率が25.6%まで下がり、平均は1,000万円を超えます。生活費と貯蓄のバランスが取りやすくなり、本格的な資産形成を始められる層です。中央値274万円は、日常的に貯蓄している家庭とそうでない家庭の差が現れ始めていることを示します。
年収500〜750万円未満:平均1,193万円・中央値400万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 20.1 |
| 〜200万円未満 | 8.6 |
| 〜300万円未満 | 7.1 |
| 〜400万円未満 | 5.2 |
| 〜500万円未満 | 5.6 |
| 〜700万円未満 | 3.9 |
| 〜1,000万円未満 | 8.8 |
| 〜1,500万円未満 | 6.7 |
| 〜2,000万円未満 | 7.7 |
| 〜3,000万円未満 | 4.2 |
| 3,000万円以上 | 7.4 |
| 無回答 | 11.7 |
| 平均 | 1,193万円 |
| 中央値 | 400万円 |
年収500〜750万円未満では非保有率が20.1%まで減少し、安定的に貯蓄ができる層といえます。中央値は400万円に達し、全体的に底上げされています。共働きや昇給によって可処分所得が増え、教育費や住宅ローンを支払いながらも計画的な資産形成が進めやすい時期です。

年収750〜1,000万円未満:平均1,681万円・中央値850万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 13.0 |
| 〜200万円未満 | 6.4 |
| 〜300万円未満 | 5.0 |
| 〜400万円未満 | 4.6 |
| 〜500万円未満 | 3.9 |
| 〜700万円未満 | 3.9 |
| 〜1,000万円未満 | 7.2 |
| 〜1,500万円未満 | 6.4 |
| 〜2,000万円未満 | 13.4 |
| 〜3,000万円未満 | 5.1 |
| 3,000万円以上 | 9.4 |
| 無回答 | 17.2 |
| 平均 | 1,681万円 |
| 中央値 | 850万円 |
この年収帯では非保有率13.0%とさらに低下し、中央値も850万円に上昇します。ただし、教育費や住宅ローンの支払いが同時期にピークを迎える家庭も多く、支出が膨らむことで貯蓄が停滞するリスクもあります。

年収1,000〜1,200万円未満:平均2,400万円・中央値1,280万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 11.5 |
| 〜200万円未満 | 3.2 |
| 〜300万円未満 | 4.4 |
| 〜400万円未満 | 2.8 |
| 〜500万円未満 | 2.8 |
| 〜700万円未満 | 3.2 |
| 〜1,000万円未満 | 4.8 |
| 〜1,500万円未満 | 7.1 |
| 〜2,000万円未満 | 12.3 |
| 〜3,000万円未満 | 6.7 |
| 3,000万円以上 | 13.1 |
| 無回答 | 26.2 |
| 平均 | 2,400万円 |
| 中央値 | 1,280万円 |
年収1,000〜1,200万円未満では非保有率が11.5%まで下がり、中央値は1,280万円と高水準です。高額資産層が急増し、金融資産3,000万円以上の割合も目立ちます。収入面の余裕から、教育費や住宅ローンを払いながらもまとまった資金を投資に回せる家庭が多く、複利効果による資産拡大が進みやすい状況です。
年収1,200万円以上:平均3,892万円・中央値1,500万円
| 金融資産額階級 | 割合(%) |
|---|---|
| 金融資産非保有 | 9.7 |
| 〜200万円未満 | 3.5 |
| 〜300万円未満 | 5.0 |
| 〜400万円未満 | 4.1 |
| 〜500万円未満 | 2.5 |
| 〜700万円未満 | 2.2 |
| 〜1,000万円未満 | 3.1 |
| 〜1,500万円未満 | 5.3 |
| 〜2,000万円未満 | 11.9 |
| 〜3,000万円未満 | 6.3 |
| 3,000万円以上 | 6.3 |
| 無回答 | 36.8 |
| 平均 | 3,892万円 |
| 中央値 | 1,500万円 |
年収1,200万円以上では非保有率が9.7%と最も低く、中央値1,500万円、平均は3,892万円と圧倒的な水準です。この層は全体の資産格差を押し上げる存在であり、高額資産3,000万円以上の割合も高いです。

4人家族の理想的な貯蓄率・毎月の貯金目安

家計管理の基本として、手取り収入の15〜20%を貯蓄に回すのが理想です。
手取り30万円なら毎月4.5〜6万円を積み立てれば、年間54〜72万円のペースになります。10年間続ければ500〜700万円近い資産が形成でき、教育費や老後資金の土台が整い、一般家庭でも無理なく資産形成が進みます。
手取り収入別に「15%を貯蓄した場合の月額と年間額」の内訳をまとめると以下のとおりです。
| 手取り年収 | 月の貯金目安 | 年間貯金額 |
|---|---|---|
| 300万円 | 3.75万円 | 45万円 |
| 500万円 | 6.25万円 | 75万円 |
| 700万円 | 8.75万円 | 105万円 |
| 1,000万円 | 12.5万円 | 150万円 |
自分の世帯年収に当てはめて目安を設定し、毎月の自動積立や定期預金で強制的に貯めることが大切です。

4人家族が貯金できない主な理由

ここからは、多くの家庭に見られる3つの典型的なパターンを紹介します。
家計簿をつけず支出が把握できていない
毎月の支出額を正確に把握できていない家庭では、無意識の浪費が積み重なりやすくなります。
感覚で「これくらい使っているはず」と思っていても、実際には外食やコンビニ利用、サブスク契約などで数万円単位の漏れが発生していることもあり得るでしょう。
固定費が生活費の半分以上を占めている
住居費、保険料、通信費、車の維持費などの固定費が高すぎると、生活費全体を圧迫し、貯蓄に回す余力がなくなります。
住宅ローンや家賃が手取りの3割を超えている場合、家計の圧迫度はかなり高くなるでしょう。まずは月々の固定費の見直しから始めましょう。
変動費の浪費が習慣化している
外食やレジャー、娯楽、日用品のまとめ買いなど、月によって増減する変動費はコントロールが難しく、油断するとすぐ膨らみます。
「セールだから」と必要以上に購入する癖や、日常的なコンビニ利用は典型例です。
改善するには、まず予算を決めて現金やプリペイドカードで管理すると効果的です。たとえば「週末の外食は月2回まで」といったルールを設定すれば、使いすぎを防げます。

4人家族が貯金額を増やすための現実的なポイント

ここからは、今日からでも始められる4つの実践策を紹介します。
固定費を見直して余力を作る
家計改善で最も効果が大きいのは固定費の削減です。通信費・保険料・サブスクリプションなどは一度見直せば節約効果が長く続きます。
たとえばスマホプランを家族全員で格安SIMに切り替えると、1人あたり月5,000円の節約になり、4人で年間24万円の削減が可能です。火災保険や生命保険も、必要保障額を見直すだけで数万円単位の負担減につながります。
教育費・住宅ローンとのバランスを取る
4人家族の家計では、教育費と住宅ローンが二大支出です。両方に全力で資金を注ぐと、貯蓄が停滞しやすくなります。
住宅ローンは返済負担率(年収に占める返済額の割合)を25%以内に抑えると、生活への圧迫度を減らせます。
ボーナス時の貯蓄率を高める
毎月の給与からの貯蓄が難しくても、ボーナスは資産を増やす絶好の機会です。最低でも3割を先取りで貯蓄に回すと、年2回の支給で数十万円単位の増加が見込めます。
生活レベルを下げずに資産形成が進み、ストレスも少なく続けやすいのが特徴です。習慣化すれば、数年後の資産額は大きく変わります。
つみたてNISA・iDeCoを始める
銀行預金だけでは利息がほとんど増えないため、長期的な資産形成には制度を活用した投資が最適です。つみたてNISAは年間360万円までの投資利益が非課税になり、低コストの投資信託で分散投資ができます。
iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となり、節税しながら老後資金を準備できます。

4人家族の貯金に関するよくある質問

最後に、4人家族の貯金に関するよくある質問と回答を紹介します。
4人家族の全財産はいくらあれば安心?
生活防衛資金としては生活費の半年〜1年分が目安です。加えて教育費や老後資金を合わせ、総額1,000万〜2,000万円(目安は年齢×10万)あれば長期的な安心につながり、総資産の安定的な増加が期待できます。
毎月いくら貯めれば年間100万円に届く?
年間100万円を貯めるには、毎月約8万4,000円の積立が必要です。ボーナスを活用すれば、毎月の負担を5〜6万円程度まで抑えられます。
貯蓄率は手取りの何割が目安?
家計管理の基準は手取りの15〜20%です。
まとめ:統計データと自分の家計を照らし合わせ、着実に資産形成を進めよう
この記事では、四人家族の平均・中央値の貯金額や年代別・年収(給料)別・世帯別の実態、さらに理想的な貯蓄率や増やし方について解説しました。
平均額は1,000万円超でも、中央値は650万円前後。つまり、数値だけで一喜一憂せず、自分の家計の位置を把握して行動に移すことが大切です。
手取りの15〜20%を目安に積立を続ければ、10年後には数百万円の資産形成も可能です。「うちも今から始めたい!」という方は、まず毎月の自動積立を設定し、可視化できる管理方法を整えてください。