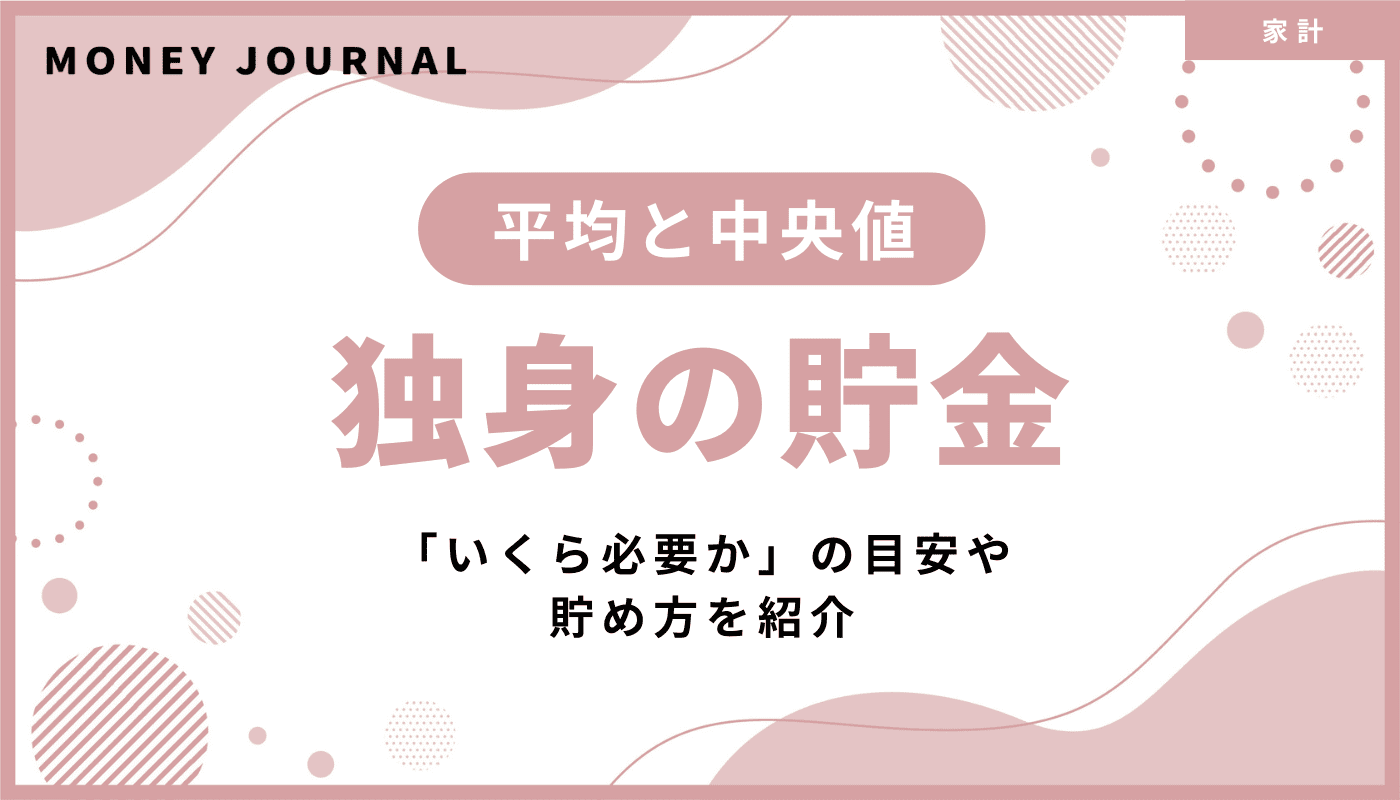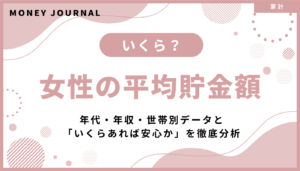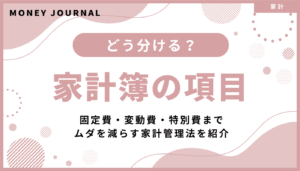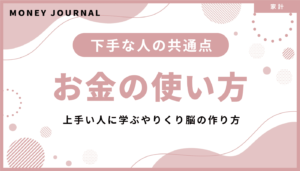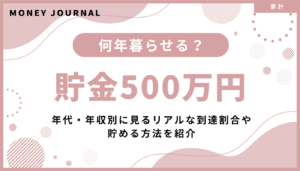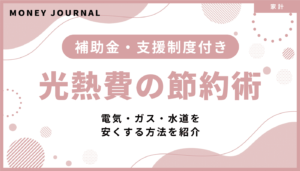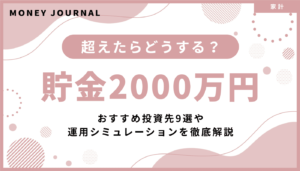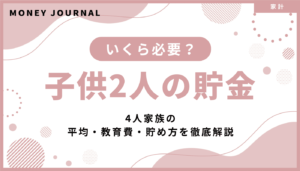- 「独身だとどのくらい貯金しておくべき?」
- 「周りの独身の人はどれくらい貯めているの?」
- 「老後のためにいくらあれば安心できるの?」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、独身の方が意識しておきたい目安は次のとおりです。
- 独身の平均貯金額は約941万円前後
- 老後に必要とされる資金は2,000万円程度
- 30代〜40代では年収の1〜2年分程度の貯金を持っておくと安心
本記事では、統計データをもとに独身の平均貯金や中央値を解説しつつ、老後資金の目安や効率的な貯め方までわかりやすくまとめています。
独身で将来のお金に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
- 年齢・年収・性別ごとの独身の平均貯金と中央値
- 独身が押さえておきたい老後資金の目安
- 貯金ができない原因と改善ステップ
- 新NISAやiDeCoを活用した資産形成の方法
- 理想的な貯金額を達成するための計画の立て方
独身の貯金事情総評

令和5年(2023年)の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査]」によると、単身世帯の金融資産保有額は以下の結果でした。
- 平均値:約941万円
- 中央値:100万円
平均値が高く見えるのは、一部の富裕層が全体を押し上げているためです。実際には、約8割の独身世帯が平均値を下回っており、中央値である100万円のほうが実態をよく反映しているといえます。
二人以上世帯との比較では、違いがさらに明確になります。二人以上世帯(夫婦世帯を含む)の平均貯蓄額は1,307万円と、単身世帯より約3割多くなっています。ただし、共働きによる収入増がある一方で、教育費や住宅費などの支出もかさむため、中央値は330万円と単身世帯との差は大きくありません。
つまり、独身世帯の貯金は「平均値と中央値の差が極端に大きい」ことが特徴です。平均額だけで判断して落ち込む必要はなく、むしろ中央値や年収とのバランスで考えるのが実態に近い見方といえるでしょう。

【項目別】独身の貯金平均と中央値

ここからは年代別、年収別、男女別の視点でデータを整理し、独身の貯金事情を解説していきます。
【年齢別】独身の貯金平均と中央値
金融広報中央委員会の最新調査をもとに、20代から60代までの平均と中央値をまとめました。まずは全体像を表で確認してみましょう。
| 年代 | 平均貯金額 | 中央値 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 約121万円 | 約9万円 | 初任給が低く貯金に回せる金額が少ない。金融資産保有者に限ると平均219万円、中央値103万円に増加 |
| 30代 | 約594万円 | 約100万円 | 収入が上がり貯蓄も増えるが、住宅購入や結婚などで支出も増えがち。資産保有者のみでは平均912万円、中央値300万円 |
| 40代 | 約559万円 | 約47万円 | 子育てや住宅ローンの負担が無い分貯めやすいが、三大支出(住宅・教育・老後)への備えが必要。資産保有者のみでは平均964万円、中央値500万円 |
| 50代 | 約1,391万円 | 約80万円 | 子の教育が終わり貯蓄に回せる金額が増えるが、老後資金の準備が急務。資産保有者のみでは平均2,288万円、中央値555万円 |
| 60代 | 約1,468万円 | 約210万円 | 年金受給前に退職金を受け取り一時的に貯蓄が増える。収入が減るため取り崩しに注意が必要 |
独身世帯(年代別)貯蓄内訳
| 独身 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融資産保有額 | 121万円 | 594万円 | 559万円 | 1,391万円 | 1,468万円 | 1,529万円 |
| 預貯金(定期性預金) | 65万円(14万円) | 289万円(145万円) | 275万円(102万円) | 510万円(177万円) | 637万円(310万円) | 676万円(378万円) |
| 金銭信託 | 3万円 | 1万円 | 7万円 | 6万円 | 11万円 | 9万円 |
| 生命保険 | 5万円 | 16万円 | 27万円 | 88万円 | 91万円 | 181万円 |
| 損害保険 | 1万円 | 1万円 | 7万円 | 9万円 | 11万円 | 23万円 |
| 個人年金保険 | 2万円 | 15万円 | 28万円 | 84万円 | 119万円 | 50万円 |
| 債券 | 2万円 | 6万円 | 9万円 | 35万円 | 81万円 | 97万円 |
| 株式 | 20万円 | 166万円 | 101万円 | 488万円 | 301万円 | 311万円 |
| 投資信託 | 21万円 | 73万円 | 81万円 | 126万円 | 171万円 | 166万円 |
| 財形貯蓄 | 2万円 | 7万円 | 10万円 | 17万円 | 19万円 | 2円 |
| その他金融商品 | 0万円 | 19万円 | 15万円 | 28万円 | 27万円 | 14万円 |
- 20代は中央値が極端に低い
中央値は9万円とほとんど貯められていない世帯が多いことを示しています。ただし、資産保有者だけを見ると中央値は103万円となり、貯金なしの層とコツコツ貯めている層に分かれているのが実情です。 - 30代は二極化が進む
平均594万円に対して中央値は100万円。資産を持っている人の中央値は300万円と差が大きく、早くから積立を始めている人との差が広がります。 - 40代以降はまとまった資産形成が進む
平均額は上がるものの、中央値は50万円前後と低めにとどまります。データからは「一部の高資産層」と「ほとんど貯められていない層」が明確に分かれていることが見てとれます。 - 50代以降は老後資金を意識
教育費の支出が落ち着き、退職までの間に貯蓄を増やしやすい時期です。特に資産保有者の平均額が2,000万円を超えている点は、老後資金を前倒しで準備している人が多いことを示しています。 - 60代は取り崩しが始まる
退職金で一時的に貯金額が膨らみますが、働き続けられるかどうかで老後の安定度は大きく変わります。年金受給までのブリッジ資金をどう用意するかがポイントです。
年代別データから、自分の貯蓄額が平均より少なくても慌てる必要はないことが分かります。平均値に惑わされず、将来のライフイベントやライフスタイルに合わせた目標金額を設定することが大切です。
【年収別】独身の貯金と貯蓄率
独身者であっても、年収によって貯蓄額には大きな差が生じます。金融広報中央委員会の調査結果をもとに、年収別の平均額と中央値を整理しました。
| 年収 | 平均貯金額 | 中央値 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 約663万円 | 約50万円 | 収入が少ないため貯蓄額も抑えられる傾向にあり、貯蓄ゼロ世帯の割合も高い |
| 300〜500万円 | 約1,019万円 | 約200万円 | 中堅所得層。貯蓄しやすい反面、30代では結婚や住宅購入などの支出が増える |
| 500〜750万円 | 約1,943万円 | 約600万円 | 高所得層。投資や資産運用に積極的な人が多く、平均額を大きく押し上げている |
- 20代:平均18%
- 30代:平均17%
- 40〜50代:平均14%前後
また、調査では20代の約30.8%、30代の約23.8%が「手取り収入からほとんど貯蓄できていない」と回答しており、貯蓄率の低さが若年層により顕著であることが分かります。
【男女別】独身の貯蓄格差
性別による貯蓄格差は年齢とともに変化します。総務省「全国消費実態調査(貯蓄・負債編)」では、男女別の貯蓄額と貯蓄年収比の違いが示されています。
以下は単身世帯全体のデータです。
男女別貯蓄現在高(全世帯)
統計によれば、若年層における貯蓄額は男女間で大きな差が見られません。
- 男性30歳未満:164万円
- 女性30歳未満:144万円
一方、高齢期に入ると格差が拡大します。
- 男性70歳以上:1,992万円
- 女性60歳代:1,586万円
- 女性70歳以上:1,378万円
さらに高齢の単身世帯では、男性平均1,816万円、女性1,422万円と男性のほうがやや多くなっています。
貯蓄年収比の違い
貯金額そのものよりも、「年収に対してどれだけ貯めているか」を見ると、男女の違いがより明確に表れます。
調査結果は以下のとおりです。
- 30歳未満:男性47.6%/女性51.5%
- 30代:男性105.9%/女性124.8%
- 40代:男性129.1%/女性206.9%
- 50代:男性280.0%/女性394.5%
- 60代:男性484.5%/女性637.2%
- 70歳以上:男性673.8%/女性612.4%
20〜30代では男女差はほとんどありませんが、40代以降になると女性の方が年収比で多く貯蓄しており、男性を大きく上回っています。女性が退職後の収入減に備え、手持ちの資産をできるだけ減らさず生活費に充てているためと考えられます。
若年単身世帯の貯蓄分布
若い独身世帯では、貯蓄の有無によって大きな格差が生じています。調査によると、約6割が平均額を下回っており、50万円未満しか保有していない世帯も少なくありません。
一方で高齢層になると状況は変わり、男女差が広がります。特に女性は平均寿命が長いにもかかわらず、年金額が少ないため、中央値が男性より低くなりやすいのです。
つまり、若い世代では「そもそも貯められていない人が多い」、高齢世代では「資産の厚みで男女差が出る」という二つの傾向が見えてきます。

独身者に必要な貯金額の目安と老後資金

独身で暮らしていると「生活費にいくら必要なのか」「老後までにどれくらい貯めておけば安心なのか」が気になるところです。平均や中央値のデータを確認しても、自分に当てはめると具体的にどの程度の準備が必要かイメージしにくい人も多いでしょう。
ここからは月々の生活費、老後にかかる資金の不足分、そして最終的な目標貯金額について整理していきます。
1か月の生活費の目安
一人暮らしの人の1ヶ月の支出額を見ていきましょう。総務省「家計調査(2022年」によれば、単身世帯の1か月当たりの支出は以下のとおりです。
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 食料 | 39,069円 |
| 住居 | 23,300円 |
| 光熱・水道 | 13,098円 |
| 家具・家事用品 | 5,487円 |
| 被服及び履物 | 5,047円 |
| 保健医療 | 7,384円 |
| 交通・通信 | 19,303円 |
| 教育 | 0円 |
| 教養娯楽 | 17,993円 |
| その他の消費支出 | 31,071円 |
| 消費支出計 | 161,753円 |
一人暮らしの生活費は平均して月16万円ほど。もちろん都心か地方か、持ち家か賃貸かなどによって金額は上下しますが、ひとつの目安として使えます。
「自分の生活費をよく把握していない」という方は、まずこのデータと比べて、自分の支出が多いのか少ないのかを確認してみるとよいでしょう。
必要な老後資金の計算例
次は、老後にかかるお金を具体的に見ていきましょう。総務省の調査によると、65歳以上の無職単身世帯は次のような状況です。
- 可処分所得:114,663円
- 消費支出:145,430円
- 毎月の赤字:約3万円
不足が20年間続くと約720万円、30年間では約1,080万円を、貯蓄や退職金から取り崩す必要があります。あくまで平均的なデータに基づく試算ではありますが、生活を維持するにはまとまった備えが必要だと分かります。
さらに、金融機関やシンクタンクの試算によれば、単身者が「ゆとりある老後」を送るためには合計2,300万〜4,500万円の資金が必要とされています。
貯金額の目安
これまでのデータを踏まえると、独身者が60歳までに準備しておきたい金融資産の目標額は、概ね2,000万〜3,000万円と考えられます。これはいわゆる「老後2,000万円問題」と整合し、現実的な目安といえます。
ただし、必要額には個人差が大きく、次のような要素によって変動します。
- 退職金や相続の有無
- 賃貸住宅か持ち家か
- 趣味や旅行などにどの程度支出するか
たとえば、生活費を月15.5万円に抑えて質素に暮らす場合と、趣味や旅行を楽しんで月20万円以上使う場合では、老後に必要な資金は2,000万円以上も差が出ます。

実家暮らしで貯金額を増やすための5つの方法

それでは、貯金ができない体質を変えるにはどうしたらよいのでしょうか。そのためには、貯金できない原因の対策を、ひとつずつ実行していくことが重要です。いきなり出費すべてを節約するのでは、気持ちが疲れてしまって長続きしません。少しずつお金に対する感覚を磨いていきましょう。
ここでは、実家暮らしで貯金を着実に増やしていく方法を5つご紹介します。
- 家計簿をつけて自分自身の収支を把握する
- 貯金の目的と目標額を明確に設定する
- 自動的に貯金できる方法で先取り貯金をする
- 買い物の際にきちんとポイントを貯める
- 貯金がある程度貯まったら投資に挑戦する
あなたが使っているのは、毎日働いて稼いでいる大切なお金です。5つの方法をどのように実践するか説明します。
①家計簿をつけて自分自身の収支を把握する
まず、最初にすべきことは、家計簿をつけることです。実家暮らしで無駄遣いしていないつもりなのに貯金ができないなら、無意識のうちに余分に使ってしまっています。
見えていない使い道を可視化して、自分自身の収支をきちんと把握することが貯金への第一歩です。この場合、家計簿は1円単位で合わせる必要はありません。あなたがどんなことで無駄遣いしてしまっているのかを分析しましょう。
②貯金の目的と目標額を明確に設定する
次に、貯金をする目的と目標額を、はっきりと具体的な数字で決めます。たとえば「2年後にカナダへ行くために100万円貯める」でもいいのです。
なんとなくではお金を貯めるモチベーションも高まりませんが、目的と金額が定まると日々の出費に意識が向くようになります。貯金するための行動を身につけるには、自分がやる気になる目標が必要です。
③自動的に貯金できる方法で先取り貯金をする
貯金の鉄則は、給与が入ったら先に差し引いておき、残りでやりくりすることです。給与支給日後すぐに定期預金に自動入金されるようにしておけば、なかったものとして生活するのも苦になりません。
その際に注意したいのは、先取り貯金を高額にしすぎないこと。金額が多すぎると結局貯金を崩すことになってしまい、先取りの意味がなくなってしまいます。無理のない金額から始めて、少しずつ増やしていくやり方でもいいのです。
④買い物の際にきちんとポイントを貯める
近年さかんに耳にするポイ活。買い物の料金を支払うことでポイントがもらえるため、使わない手はありません。コツは貯めるポイントを絞ること。種類が多すぎると分散してしまって貯まりにくくなるので、節約効果が得られにくくなります。
特に、クレジットカードやデビットカードはポイントを貯められるだけでなく、支払い履歴も管理できるためおすすめです。ポイント目当てにお金を使いすぎないよう、上手に使いこなしていきましょう。
⑤貯金がある程度貯まったら投資に挑戦する
ここまでの4つの方法を実践すれば、貯金をする第1の目的はある程度達成できるはずです。貯金がある程度貯まってきたら、次は積極的に増やすことを考えましょう。
投資というとリスキーなイメージがあるかもしれませんが、ハイリスクハイリターンな投資ばかりではありません。節税効果もあるおすすめの投資方法2つをご紹介します。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- NISA
この2つの制度は、国が用意した投資制度です。そのため、そこで扱う投資商品は国の基準に沿った比較的安全なものがセレクトされています。大きな利益を短期間で狙うのではなく、低リスク低リターンでじっくり増やすのに向いています。
また、運用や売却によって得た利益に所得税がかからないという大きなメリットもあるのです。どちらの制度も上手に利用し、あなたの貯金を増やしていきましょう。
独身で貯金できない原因と改善方法

独身は自由に使えるお金が多いように見えますが、実際には「気づけば貯金ができていない」と悩む人が少なくありません。収入があっても支出の管理が甘ければお金は貯まらず、将来の不安が増す一方です。
どこに落とし穴があるのかを理解することで、改善のきっかけがつかめます。ここからは貯金できない理由を整理しますので、具体的な改善方法へとつなげていきましょう。
貯金できない主な原因
貯金が思うように進まない背景には共通する理由があります。収入が少ないからではなく、使い方や考え方に課題があることが多いのです。
代表的な要因を順番に見ていきましょう。
- 固定費が高い
- 生活レベルの過剰な上昇
- 家計管理の不足
- 目標設定が曖昧
- 貯金方法が適切でない
固定費が高い
一人暮らしの家計において、最大の負担となるのは住居費です。収入の3割を超える家賃に加え、スマートフォン料金やインターネット回線、各種サブスクリプションなど、毎月必ず発生する固定的支出が積み重なると、貯蓄に回せる余地は限られてしまいます。
こうした固定費は「毎月必ず払うもの」だからこそ、見直しの効果が大きいポイントです。家賃の水準を下げたり、通信費やサブスクを整理するだけで、毎月の支出は驚くほど改善できます。
生活レベルの過剰な上昇
収入が増えると「少しくらいなら大丈夫」と思って外食や旅行にお金をかけすぎてしまうことがあります。さらにボーナスのたびに高額な買い物をしてしまうと、せっかくの昇給分が一瞬で消えてしまいます。
いわゆる「ご褒美消費」が習慣化すると、貯金に回すお金がなくなり、後で後悔することになってしまいます。
家計管理の不足
毎月の収支を記録しなければ、自身がどの程度の支出をしているかを正確に把握できません。気分でカードを使っていて、後になって「何に使ったんだっけ?」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。
家計管理をおろそかにすると、お金の流れが不透明になり、当然ながら貯金も計画的には進みません。貯める第一歩は、まずお金の出入りを見える化することです。
目標設定が曖昧
「貯金したいな」と思うだけでは、なかなか行動に移せません。たとえば「3年後までに100万円を貯める」といったように金額と期限を明確に設定しなければ、日常生活において支出を抑える意識を持ちにくいものです。
逆に目標がぼんやりしているとモチベーションが続かず、途中で挫折しやすくなります。貯金を習慣にするには、「いつまでに」「いくら」という明確なゴールを設定することが大切です。
貯金方法が適切でない
普通預金に資金を置いたままでは、利息はごくわずかであり、将来の資産形成にはつながりません。安全性のみを重視して投資や積立制度を利用しなければ、資産を効率的に増やす機会を逸することになります。
大切なのは「自分に合った方法を選ぶこと」。収入やライフスタイルに合わせて、定期預金・積立NISA・iDeCoなどを組み合わせれば、働いて得たお金をもっと活かせます。
改善のためのステップ
貯金が思うようにできないと悩む人は、やみくもに節約を意識するよりも「仕組みづくり」から始めたほうが効果が出やすいです。毎月の収支を把握し、固定費や変動費を整理したうえで、貯蓄の仕組みを先に作ることがポイントです。ここでは、実践しやすい5つのステップを紹介します。
- 家計の可視化
- 固定費の見直し
- 先取り貯蓄(自動積立)
- 変動費の抑制
- 無駄遣いの原因分析
家計の可視化
家計を健全に管理するためには、まず自身の収支を数値で正確に把握することが重要です。スマートフォン向けの家計簿アプリを活用すれば、入力の手間が軽減され、継続もしやすくなります。
支出は、家賃や通信費などの固定費、食費や交際費などの変動費に分けて整理すると、全体のバランスを一目で把握できます。固定費と変動費の割合を確認し、削減可能な項目を明確にするだけでも、改善への手がかりが得られるでしょう。
固定費の見直し
毎月かかる固定費を見直すと、節約の効果が長く続きます。たとえば、家賃が収入の3割を超えている場合には、思い切って住み替えを考えるのもアリです。スマホも格安SIMに変えるだけで、年間数万円は節約できます。
さらに、使っていない動画配信サービスやジムの会費を解約すれば、無理をせずに毎月の支出を減らせます。固定費は一度削ると効果が積み重なっていくので、最優先でチェックしたいポイントです。
先取り貯蓄(自動積立)
貯金を効率よく続けたいなら、コツは「先取り」にあります。給料が入ったらすぐに、振込口座から貯金専用の口座へ自動で移す仕組みを作りましょう。
たとえば毎月3万円を先に移してしまえば、残ったお金で生活するのが当たり前になります。意思の強さに頼らず「気づいたら貯まっている」仕組みを作ることが、長続きの最大のポイントです。
変動費の抑制
外食を控えて自炊を取り入れる、コンビニではなくスーパーでまとめ買いをするなど、日常の小さな工夫を積み重ねることで変動費は抑制できます。趣味や交際費も「月1万円まで」と上限を決めてしまえば、使いすぎ防止に効果的です。
変動費は固定費と違って、自分の工夫次第で柔軟に調整できるのがメリット。無理せず続けられる節約スタイルを探して、日常の習慣にしていきましょう。
無駄遣いの原因分析
無駄遣いには必ず理由があります。イライラしたときに衝動買いしてしまう、セールにつられて不要なものを買ってしまう…そんな経験は誰にでもあるはずです。
大事なのは「何がきっかけでお金を使ってしまうのか」を振り返ること。たとえば「欲しいと思ったら1週間は買わずに待つ」とルールを決めるだけでも、衝動買いはかなり減ります。原因を知って、代わりにできる行動を用意しておけば、無駄遣いは自然に減っていきます。

投資を活用した独身の資産形成

貯金だけではなかなか資産が増えず、将来の不安を解消するには限界があります。物価上昇や長寿リスクを考えると、効率的にお金を増やす仕組みを取り入れることが必要です。
ここからは代表的な制度である下記5つを紹介します。
新NISA
| 項目 | 新NISA(2024年〜) | 旧NISA(〜2023年) |
|---|---|---|
| 非課税期間 | 無期限 | 一般5年/つみたて20年 |
| 年間投資上限額 | 最大360万円(つみたて120万円+成長240万円) | 一般120万円/つみたて40万円 |
| 生涯非課税限度額 | 1,800万円(うち成長枠1,200万円) | 設定なし |
| 投資枠の併用 | 可能 | 不可 |
| 投資枠の再利用 | 可能(売却分を翌年以降再利用) | 不可 |
| 制度の期間 | 恒久化 | 期間限定 |
2024年からスタートした新NISAは、個人の資産づくりを後押しするために大きくパワーアップしました。投資で得た利益に税金がかからない仕組みはそのままに、これまでよりもずっと使いやすくなっています。
- 非課税期間の無期限化
旧制度では一般NISAが5年、つみたてNISAが20年に制限されていましたが、新制度では非課税期間の制限がなくなり、長期保有に適しています。 - 生涯非課税限度額の設定
一人当たり1,800万円までが非課税の対象となり、そのうち成長投資枠は1,200万円まで利用可能です。 - 投資枠の再利用が可能
投資商品を売却した場合でも、その分の非課税枠を翌年以降に再び利用できます。資金を効率的に回転させられる点が大きな利点です。 - 二つの投資枠を併用可能
つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)を同時に利用でき、合計で年間360万円まで投資可能です。 - 制度の恒久化
利用開始に期限がなく、いつでも制度を活用できます。
たとえば毎月5万円を投資信託に積み立てると、年間60万円の投資となります。これを20年間継続した場合、利回り3%でも1,600万円以上に増加します。非課税で利益を受け取れるため、課税口座に比べて効率的な資産形成が可能です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後のお金を自分で準備するための制度です。毎月の掛金を決めて、投資信託や定期預金、保険商品などを選んで運用し、60歳以降に年金や一時金として受け取ります。
- 税制優遇の手厚さ
掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。運用益は非課税で再投資可能です。受け取り時には、年金形式なら「公的年金等控除」、一時金形式なら「退職所得控除」が適用されます。 - 長期的な資産形成
公的年金に上乗せして、自ら老後資金を準備する仕組みです。 - 加入対象
原則20歳以上65歳未満の者が対象ですが、2025年からは70歳未満まで拡大される予定です。 - 運用は自己責任
選択した商品によって将来の受取額が変動します。 - 60歳まで引き出せない
老後資金を守るため、中途解約は原則できません。
運用次第では元本割れの可能性があるほか、手数料も発生します。運用商品を選ぶ際には、信託報酬などコスト面の確認をしましょう。
月2万円を30年間積み立て、年利3%で運用した場合:
- 積立総額:720万円
- 運用益:約370万円
- 合計:約1,090万円
上記に加え所得控除による節税効果が得られるため、実際のメリットはさらに大きくなります。
財形貯蓄制度
財形貯蓄制度は、会社員や公務員が使える「給与天引き型の貯金制度」です。給与から自動的に積み立てられるため、計画的かつ無理なく資産形成が可能です。住宅購入や老後資金の準備などに活用できます。
| 種類 | 主な目的 | 非課税措置 | 積立期間 |
|---|---|---|---|
| 一般財形貯蓄 | 使途自由(結婚・教育など) | なし | 3年以上(1年経過後は引き出し可能) |
| 財形住宅貯蓄 | 住宅購入・リフォーム | 住宅財形・年金財形合計で550万円まで利子非課税 | 5年以上 |
| 財形年金貯蓄 | 老後資金(60歳以降に受取) | 住宅財形・年金財形合計で550万円まで利子非課税 | 5年以上(年金形式で受取) |
- 給与天引きにより確実に貯蓄できる
- 財形残高の10倍(最大4,000万円)まで借入可能な「財形持家融資」を利用できる
- 住宅財形や年金財形は利子が非課税
毎月3万円を住宅財形で積み立てると、5年間で180万円以上を準備できます。これを住宅購入時の頭金とすれば、より現実的にマイホーム取得を検討できます。
利用には勤務先が制度を導入している必要があります。希望する場合は、会社の人事部門または金融機関窓口で手続きを行うとよいでしょう。
貯蓄型保険
貯蓄型保険は、保障と貯蓄の双方を兼ね備えた保険商品です。掛け捨て型と異なり、支払った保険料の一部が将来に向けて積み立てられ、満期または解約時に返戻金として受け取ることができます。保険で安心を得ながら、資産形成も進められるのが魅力です。
| 代表的な種類 | 詳細 |
|---|---|
| 終身保険 | 生涯にわたり死亡保障が継続し、解約時には返戻金を受け取れる |
| 養老保険 | 満期まで生存した場合は満期金、死亡した場合は死亡保険金が支払われる |
| 学資保険 | 子どもの教育資金を計画的に準備できる |
| 個人年金保険 | 老後に年金形式で受け取れる |
主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 満期保険金や解約返戻金が将来の資金になる 掛け捨て型と異なり、支払った保険料が無駄にならない安心感がある 保障と貯蓄を一つの商品で同時に確保できる 契約者貸付制度により、解約せずに一時的な資金を借りられる | 保険料は掛け捨て型より高額になりやすい 途中解約では元本割れのリスクがある インフレに弱く、実質的な資産価値が減少する可能性がある |
毎月2万円の終身保険を20年間続ければ、保障を受けながら数百万円単位の返戻金が貯まります。強制的に積み立てられるので、「自分ではなかなか貯められない」という人に向いています。
独身で投資を始める際のポイント

投資は「なんとなく始める」よりも、目的を定めてから取り組む方が成果につながります。そのため、生活資金と投資資金を分けて考えることが大切です。
ここでは、投資をスタートする際に意識しておきたい基礎的なポイントを整理します。
目標を明確にする
投資を始める前に、まず「何のために投資するのか」をはっきりさせましょう。目的があいまいだと、途中で投げ出したり、ちょっとした値動きに振り回されやすくなります。
- 投資の目的を決める(例:老後資金、住宅購入、教育費、旅行や趣味など)
- 期間と金額を具体的に設定する(例:10年後に500万円、20年後に2,000万円)
- 自身のリスク許容度と期待するリターンを整理する
- 生活防衛資金(生活費6か月分程度)を確保したうえで投資に回す
- 定期的に進捗を確認し、必要に応じて修正する
20代・30代の独身は「時間」という大きな武器があります。長期でコツコツ積み立てる戦略が最適です。また、独身者は生活費や老後費用を自ら賄う必要があるため、税金や医療費を考慮した長期的な資産設計が必要です。
リスク許容度を把握する
投資でうまくいくためには、「どこまでの損失に耐えられるか」である「リスク許容度」を知ることが大切です。
- 年齢:若いほど回復に時間をかけられる
- 収入や資産規模:余裕資金の大きさによって許容できるリスクは異なる
- 投資経験:初心者は少額から始める方が安心
- 性格・心理的要素:値動きに過度に影響されやすいかどうか
投資額の重みも重要です。たとえば月1万円の投資は、月収20万円の人と40万円の人では負担感が大きく異なります。月1万円の投資は、収入20万円の人には大きな負担ですが、40万円の人には比較的軽い額です。
リスク許容度を確認する方法としては、ロボアドバイザーの診断ツールが有効です。簡単な質問に答えるだけで、自身が「守り型」「中庸型」「攻め型」のいずれに近いかが把握できます。
▼タイプ別の資産配分イメージ
| タイプ | 株式 | 債券 | 現金 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 守り型 | 20% | 50% | 30% | 値動きに弱い人向け、安定重視 |
| 中庸型 | 50% | 30% | 20% | 値上がり益と安定性のバランス |
| 攻め型 | 70% | 20% | 10% | 長期目線で高リターンを狙う |
投資は「長期・積立・分散」が基本ですが、その前提となるのが自分のリスク許容度です。性格や資産状況に合わせた配分にすれば、無理なく投資を続けられるでしょう。
長期・積立・分散を意識する
投資を安定的に継続するための基本原則は「長期」「積立」「分散」の3点です。短期的な相場変動に惑わされることなく、資産を着実に形成しやすくなります。
- 長期
短期間で結果を求めると、相場の変動に心が揺さぶられがち。10年、20年と時間を味方にすれば、値動きが平均化されてリターンが積み上がります。 - 積立
毎月一定額を投資する「積立」は初心者にも安心の方法。ドルコスト平均法の効果で、価格が高いときは少なく、安いときは多く買う仕組みになり、結果的に買値が平準化されます。 - 分散
投資先を複数に分けることで、特定の資産が値下がりしても全体への影響を抑えられます。
分散の具体例をまとめると次のようになります。
| 投資対象 | 分散の方法 |
|---|---|
| 資産種類 | 株式・債券・現金・不動産投資信託など |
| 地域 | 国内株式+外国株式(米国・欧州・新興国など) |
| 業種 | IT・金融・医薬品・エネルギーなど |
さらに、定期的に資産配分を見直してリバランスすることも大切。株式の比率が上がりすぎたら、債券に一部を振り分けて全体のバランスを整えましょう。
税制優遇を利用する
独身で効率よく資産を増やすなら、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用しましょう。
代表的な制度を整理すると以下のようなものがあります。
| 制度 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 新NISA | 2024年スタート。非課税期間は無期限。 | 運用益が非課税。生涯で1,800万円まで非課税投資が可能(成長投資枠1,200万円含む)。 | 非課税枠をフル活用するには資金力が必要。 |
| iDeCo | 自分で積み立てる年金制度。 | 掛金が全額所得控除。運用益非課税。受け取り時も税制優遇あり。 | 60歳まで原則引き出せない。手数料がかかる。 |
| 企業型DC | 会社が導入する年金制度。 | 会社拠出分も含めて非課税で運用できる。 | 会社ごとに制度内容が違う。 |
どう選ぶかは目的次第です。
- 老後の資金づくり→iDeCoをメインに(強制的に積立できる)
- 中期の資産形成→NISAを活用(非課税でいつでも売却可能)
- 会社の制度あり→企業型DCも合わせて利用
たとえば「NISAに毎月3万円+iDeCoに1万円」というように組み合わせて使うことも可能です。制度は数年ごとに改正されるので、最新情報を確認しながら運用しましょう。
独身が理想的な貯金額を達成するための計画

計画を立てる際には「目標を定める」「逆算で積立額を算出する」「資産形成手段を選ぶ」「定期的に見直す」という流れを意識することが大切です。
ここでは、ライフイベントと年齢を踏まえた貯蓄計画の立て方を紹介します。
①年齢別の目標貯蓄額目安を確認する
「どのくらい貯めておけば安心か」は年齢やライフステージで変わってきます。まずは年代別の目安を知り、自分がどの位置にいるか確認してみましょう。
| 年代 | 目標貯蓄額(目安) | ポイント |
|---|---|---|
| 20代 | 50〜100万円 | 生活費3〜6か月分を緊急資金として確保。転職活動や車購入資金も念頭に置く |
| 30代 | 300〜500万円 | 結婚や住宅購入に備えるとともに、「結婚しない」選択をする独身継続の場合は老後資金の形成を開始 |
| 40代 | 500〜1,000万円 | 老後資金準備を本格化。投資と貯蓄のバランスを重視 |
| 50代 | 1,500〜2,500万円 | 老後まで残り10〜15年。退職金を見込みつつ、安定資産への移行を意識 |
| 60代 | 2,000〜3,000万円以上 | 年金支給開始までの生活費を補える資金を確保 |
もちろん、これはあくまで参考値。持ち家か賃貸か、どんな暮らしをしたいかで必要額は変わります。大事なのは「一生独身で暮らす場合も含め、自分が安心できる金額」を設定すること。
たとえば「旅行を楽しみたいから多めに貯めたい」「最低限の生活費だけで十分だから少なめでいい」など、自分の価値観に合わせた基準を持つことが長続きの秘訣です。
②貯蓄計画を立てる
目標を決めたら、あとは実行に移すだけ。ゴールを明確にし、そこから逆算して積立額を決め、どの方法で貯めるかを考え、定期的に見直す流れを作りましょう。
ゴール設定
将来に想定されるライフイベントを整理しましょう。結婚、住宅購入、車の買い替え、老後資金など、必要となり得る項目を具体的に挙げ、それぞれに目標金額を設定します。
- 住宅頭金:300万〜500万円
- 車購入:200万円前後
- 転職準備資金:生活費6か月分
- 老後資金:2,000万〜3,000万円
加えて、インフレや予備費を考えて少し余裕を見ておくとよいでしょう。
逆算で月々の貯蓄額を算出
次に、設定した目標を達成するために必要な毎月の積立額を逆算します。計算式は以下のとおりです。
たとえば500万円を10年(120か月)で貯めたいなら、毎月約4.2万円を積み立てればOKです。投資で運用するなら、複利の効果を含めてシミュレーションツールで試算すると、よりリアルな数字が出ます。
さらに、計画を確実に進めるためには以下の工夫が有効です。
- ボーナスから一定額を貯金に回す
- 臨時収入(副収入や祝い金など)をそのまま貯金へ
- 税金や手数料も見込んで、余裕を持った目標設定にする
資産形成手段を選ぶ
毎月の積立額が決まったら、次にどの方法で資産を形成するかを検討します。
代表的な選択肢は以下のとおりです。
- 普通預金・定期預金:元本保証で安全性は高い。ただし利息は低水準。
- 投資信託・ETF:少額から分散投資が可能。長期的な資産形成に適する。
- 株式・債券:高いリターンを期待できる一方、価格変動リスクを伴う。
- iDeCo・新NISA:非課税制度を活用でき、効率的な資産増加が可能。
- 不動産投資・副業:新たな収入源を確保する手段として検討の余地がある。
ポイントは「リスク許容度」と「ライフプラン」に合わせて組み合わせること。特に独身の方は、いざというときに使える流動性の高いお金(現金やすぐ換金できる資産)を残しておくことを意識してみてください。
定期的に見直す
貯蓄計画は立てただけで満足してしまいがちですが、生活環境は変わるもの。だからこそ年1回くらいは振り返りをするのがポイントです。
確認すべき主な項目は以下のとおりです。
- 収入や支出に変化はあった?
- 目標額や期限は現実に合っている?
- 投資の割合が偏っていない?
さらに、市場の動きや税制改正、結婚や転職といったライフイベントも考慮して調整していきましょう。

独身の貯金とライフイベント

結婚・出産・住宅購入といった節目では、数百万円単位の支出が発生するため、独身の方も準備が必要です。
必要な金額は家庭の事情やライフスタイルによって差が出るので、全国平均の目安を把握しながら自分に合った計画を立てましょう。
結婚資金
結婚にかかる費用は、規模によって大きく変動します。代表的な調査結果を整理すると、以下のとおりです。
| 項目 | 平均費用 |
|---|---|
| 婚約費用 | 約54万円 |
| 挙式・披露宴 | 約327〜355万円 |
| 新婚旅行 | 約61万円 |
| 新生活準備 | 約72万円 |
| 合計 | 約371〜542万円 |
婚約から新生活準備まで含めて平均400万〜500万円前後が相場。ただし、ご祝儀や親の援助を考慮すると、実際の自己負担は25万〜100万円程度に落ち着くケースも多いようです。
- 費用は式場、招待人数、演出内容によって大きく変動する
- 婚約・挙式・新居と段階的に資金を確保する
- 式まで数年ある場合は、安全性の高い運用を組み合わせる
最近では「小規模婚」や「フォト婚」を選んで費用を抑え、その分を旅行や将来の資産形成に回す人も増えています。
出産・育児費用
出産費用は病院や地域によって差がありますが、厚生労働省の調査によると平均は約463,000円です。現在は出産育児一時金として50万円が支給されるため、多くの場合は費用の大部分をまかなえます。
ただし、差額ベッド代や帝王切開などで追加費用が発生することもあるため、事前に余裕を持った準備が必要です。
- 入院・分娩費用(平均46万円前後、追加費用の可能性あり)
- 里帰り出産に伴う交通費・宿泊費
- 産休・育休による収入減少
- ベビー用品(ベッド、ベビーカー、ミルク、オムツ等)
- 保育料や医療費
子育て初期は月1〜3万円程度が目安といわれます。さらに教育費を考えると長期的に大きな負担になるため、貯金と資産運用の両立が必要です。
出典:厚生労働省「出産費用の見える化等ついて」
住宅購入・持ち家
マイホームの購入は、人生で最も大きな買い物のひとつ。住宅金融支援機構の調査による全国平均価格は以下のとおりです。
| 住宅タイプ | 平均価格 |
|---|---|
| 土地付注文住宅 | 4,903万円 |
| 建売住宅 | 3,603万円 |
| マンション(新築) | 5,245万円 |
| 中古マンション | 3,037万円 |
| 中古戸建て | 2,536万円 |
購入時には物件価格に加え、登記費用・不動産取得税・仲介手数料などが必要であり、総額の3〜9%程度が諸費用として発生します。マンションなら150万〜300万円程度の現金が追加で必要になるケースが多いです。
- 頭金の準備:購入価格の1〜2割を現金で用意する
- ローン返済計画:金利変動リスクを踏まえ、無理のない返済額を設定する
- 予備資金の確保:修繕費、固定資産税、家具・家電の更新費用に備える
- 資産配分の考慮:住宅に資金を集中させず、流動性のある資産を保持する
住宅価格には地域差が大きいため、希望するエリアの相場を事前に確認しましょう。
独身の貯金に関するよくある質問

独身の方からよく聞かれる疑問を整理しました。平均額や老後の必要額、月々の貯金目安などをデータとともに解説します。
独身の平均貯金額はどのくらい?
単身世帯全体では、銀行預金などの平均額が約408万円とされています。ただし株式や保険を含めた金融資産全体では平均941万円、中央値100万円というデータもあり、数字の見え方に大きな開きがあることが分かります。
年代別に見ると、30代独身の平均は約289万円。ただし中央値は100万円前後にとどまり、「貯金ゼロ」という人も単身世帯で36%にのぼるのが現状です。
平均値は高資産層に引っ張られるため、「本当の貯金額」を知りたいときは中央値を基準にした方がリアルです。結局のところ大事なのは「周りと比べてどうか」ではなく「自分にとってどれくらいあれば安心か」という視点。収入やライフスタイルに合わせて、自分なりの基準を持つことが必要です。
老後にいくら貯金すれば安心?
老後の最低生活費は月24万円ほど。ただし趣味や旅行を考えると30万円以上が必要です。しかし、医療費や介護費、さらにはインフレを考慮すると、この額でも十分とは言い切れません。
老後資金を見積もる手順としては、①年金見込み額の確認、②毎月の支出との差額の算出、③必要な貯蓄総額の逆算、④医療・介護費分の上乗せ、という流れが適切です。
安心できる金額は人それぞれ。大切なのは、平均やモデルケースに縛られず、自分の老後の暮らし方に合わせて見積もることです。
月々どれくらい貯めればいい?
一般的には「手取り収入の10〜15%」を貯金に回すのが良いとされます。たとえば手取り20万円なら2万〜3万円、30万円なら3万〜4.5万円ほどです。
もう一つの考え方は逆算です。たとえば10年で500万円を目標にするなら、月4.2万円が必要です。ボーナスや臨時収入を加えれば、毎月の負担を抑えつつ目標に近づけます。大切なのは、まず生活防衛資金を確保し、そのうえで「余裕分を先取りして貯める」習慣をつくることです。
貯金ゼロはやばい?
単身世帯の約36%は金融資産を持たず、20代では42%が「貯金ゼロ」という調査結果もあります。30代でも3人に1人は資産がないとされ、決して珍しい状況ではありません。
ただしリスクは高めです。病気や失業といった急な出費に対応できず、精神的にも不安が募ります。さらにゼロのまま長く過ごすと、投資で資産を増やすチャンスを逃す機会損失も大きくなってしまいます。
解決策は少しずつ積み上げること。まずは緊急資金として10万円を確保し、その次は100万円を目標に。生活に余裕が出てきたら資産運用を取り入れるのも有効です。
男性と女性で貯金に差はある?
調査によっては、男性の方が平均的に金融資産を多く持ち、女性は少なめという傾向が見られます。理由としては、収入格差や、出産・育児で収入が減る影響が考えられます。
ただし最近のデータでは、男女差がはっきり出ないケースも多く、一概に「男性の方が貯めている」とは言えません。実際のところ、貯金額を左右するのは性別よりも「収入水準」や「生活スタイル」の違いです。
まとめ:貯金しやすい環境を活かして貯金を増やそう
この記事では、独身の貯金平均や中央値の実態、老後資金の目安、そして効率的な貯め方について解説しました。
平均額だけを見ると不安になるかもしれませんが、中央値や自分の収入とのバランスを意識すれば正しい判断ができるものです。
年代別の目安を参考に、20代はまず生活費3〜6か月分を確保、30代からは老後を見据えた資産形成を始めましょう。たとえば「毎月3万円を積み立てて10年で360万円」というように、数字で目標を設定すると継続しやすくなります。
将来に備えるのは今の一歩からです。無理のない金額で仕組みを整え、コツコツ積み上げてください。