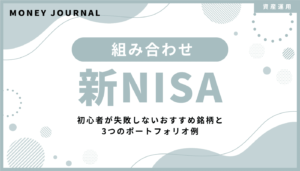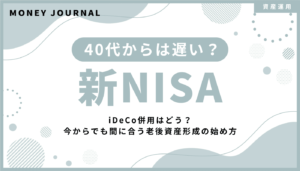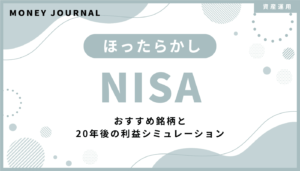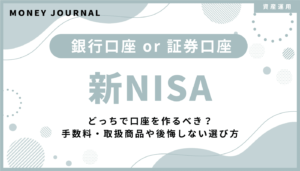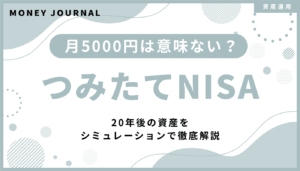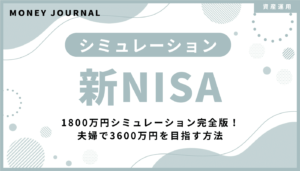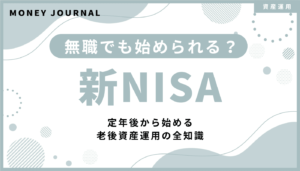- 「つみたてNISAの銘柄って、いくつ買うのが正解なの?」
- 「分散したほうが安心って聞くけど、本当に何本も必要?」
- 「1本だけに絞るのはなんとなく怖い…でも何を基準に選べばいいのか分からない…」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、つみたてNISAの銘柄は「1〜2本」で十分です。理由は以下の通りです。
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 過度な分散は意味がない | 同じような中身のファンドを複数持ってもリスクは減らない |
| 管理の手間が増える | リバランスや運用状況の確認に手間がかかる |
本記事では、つみたてNISAで複数銘柄を保有する際のメリット・デメリットから、投資スタイルに合わせたおすすめの組み合わせ方まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
「投資は難しそう…」と感じていた方も、ぜひ参考にしてください。
つみたてNISAの銘柄はいくつ買うべき?【結論】

まずは、つみたてNISAの銘柄をいくつ買うべきかの結論を以下の通り紹介します。
保有銘柄は1~2本で十分|何個でも良いわけではない
つみたてNISAでは1つ(あるいは多くても2つ)の銘柄を持つだけでも十分に分散投資が可能です。
過度に銘柄数を増やすと管理負担が増すため、無闇に「銘柄は多ければ多いほどいい」という考え方は禁物です。
「分散投資は安心」というのは半分嘘|銘柄の中身が重要
「複数銘柄を保有すれば絶対に安全!」なわけではありません。実際、似たような指数や資産に投資するファンドばかり増やしても分散効果は期待できません。
▼悪い例:重複投資のパターン(米国株中心)
| 銘柄名 | 主な投資対象 | 重複の可能性 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 米国大型株(500社) | 高い(S%P500全体) |
| 楽天・全米株式(VTI) | 米国株全体(大型~小型) | 高い(大型株部分がS&P500と重複) |
| iFree NEXT NASDAQ100 | 米国IT系大型株 | 高い(GAFAMなどがS&P500と重複) |
▼良い例:実質的な分散のパターン
| 銘柄名 | 主な投資対象 | 分散効果 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 世界中の株式 | 地域分散(米国・日本・新興国含む) |
| eMAXIS Slim 先進国債券 | 債券(低リスク資産) | 資産クラスの分散(株式と異なる値動き) |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 新興国の株式 | 地域・リスク分散(値動きが独立しやすい) |
このように、見た目の本数ではなく「中身」で分散されているかが重要です。つみたてNISAの銘柄選びでは地域・業種・資産クラスのバランスを意識して、「本当に分散になっている?」をチェックする習慣をつけましょう。
投資枠は将来の増額を見越して本数を決める
つみたてNISAは途中で積立額を変えたり銘柄を追加したりすることが簡単にできるため、最初から無理して複数の銘柄を買おうとしなくても問題ありません。
ライフステージに応じた投資スタイルの変化は以下を参考にしてください。
| ライフステージ | 状況 | 投資スタイルの変化 |
|---|---|---|
| 社会人なりたて | 収入が少なく余裕がない | 1本に絞って少額からスタート |
| 昇進・転職など | 手取りが増えてきた | 積立額アップ/既存銘柄への追加投資 |
| 結婚・出産 | 支出の増加で一時的に調整が必要 | 一時的な減額や一部取り崩し検討 |
| 子育て・教育費のピークを過ぎた後 | 再度投資に余裕が出る | 新しい銘柄の追加やポートフォリオの見直し |
現在は年間120万円の枠内で運用しますが、後々投資枠をフル活用したいなら最初は1本に絞って始め、慣れてきた段階で銘柄を追加するのも一つの方法です。
とはいえ、「自分にとって最適な投資スタイルが分からない」「家計に無理のない範囲でどれくらい積み立てるべきか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、プロのファイナンシャルプランナー(FP)による家計診断を活用してみるのもおすすめです。
- 何度相談しても無料
- スマホ・PCからすぐに予約可能
- カメラオフでもOKなので気軽に参加できる
「このままで老後資金は大丈夫?」「もっと貯金を増やしたい!」と少しでも感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
つみたてNISAで複数銘柄を保有するメリットとは?

つみたてNISAで複数銘柄を保有するメリットは次の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
複数に分けると投資許容度に合わせた運用がしやすくなる
人によってお金の使い方や投資に対して感じる「怖さ」はまったく違います。そのため、1つの銘柄に全額を投じるよりもいくつかの銘柄に分けて投資したほうが精神的・金銭的が少ないです。
例えば、つみたてNISA初心者の方には以下のような組み合わせを参考にしてみてください。
| 投資の目的 | 組み合わせ例 |
|---|---|
| 株価の上下が心配なのでリスクをおさえたい | 株式型ファンド+バランス型や債券型ファンド |
| 長期でしっかり資産を増やしていきたい | 全世界株式インデックス+先進国株式ファンド |
| 米国経済の成長に期待したい | 米国株式インデックス1本で集中運用 |
自分の投資許容度(どれくらいリスクを受け入れられるか)に合わせて、攻めと守りのバランスを自分で組めるのがNISAの魅力です。
「長期×分散」で複利の力を活かせる
つみたてNISAで長期投資&分散投資をすると、複利効果で資産増を見込めます。
長期で投資すると市場の上がり下がりが平均化されやすくなるため、複利の効果を活かしやすいのです。
仮に年利(1年あたりの利益率)6%で20年間、毎月3万円を積み立てた場合、最終的な資産は以下のようになります。
| 年数 | 20年 |
|---|---|
| 元本(つみたて合計) | 720万円 |
| 運用益 | 666万円 |
| 合計資産 | 1,386万円 |
複利は時間と組み合わせることで力を発揮するため、資産の元になる投資先が偏っていては効果が薄れてしまいます。
「長期×分散」の掛け算で、お金が自然にふくらむ環境をつくっていきましょう。
成長投資枠と積立投資枠を分けて使えば銘柄数に自由度が生まれる
2024年から始まった新NISAでは、「つみたて投資枠(年間120万円まで)」と「成長投資枠(年間240万円まで)」の2つを同時に使えるようになりました。
具体的にはこんな使い方ができます。
- つみたて投資枠では、全世界株式など長期に向いた投信をコツコツ積立
- 成長投資枠では、米国株やセクター別ファンド(特定の業界に投資するタイプ)でリターンを狙う
枠が分かれていることによって目的ごとに投資の軸を変えられるので「攻め」と「守り」のどちらも取り入れやすくなります。
銘柄数に縛られず、自分らしい運用を考えてみましょう。

つみたてNISAで複数銘柄を買うデメリット

複数の銘柄に分けて投資するのは良い面もありますが、むやみに数を増やせばいいわけではありません。
ここでは、つみたてNISAで複数銘柄を持つとき2つのデメリットを解説します。
同じ指数を追う銘柄同士では分散効果が薄れる
複数銘柄といっても、同一の指標や資産クラスに連動していれば意味がありません。
例えば「全世界株式ファンド」と「米国株式ファンド」を両方持っていても、後者に含まれる米国株は前者にも大きく組み込まれており、結果的に米国市場に偏る可能性があります。
以下のように、指数(指標)の重なりはリスク集中につながります。
| 保有ファンド例 | 中身の重複リスク |
|---|---|
| 全世界株式+米国株式 | 米国株がダブって構成比が高くなりすぎる |
| 先進国株式+米国株式 | 両方に米国株が多く含まれている |
| 日経225連動型+TOPIX連動型 | どちらも日本株なので地域的な分散ができない |
銘柄を選ぶときは「どの指数に連動しているか」を一度チェックするクセをつけましょう。同じような動きをするものをいくつも買っても、守りにはなりません。
銘柄数が増えると管理・リバランスの手間が跳ね上がる
銘柄を増やすほど面倒くささが増していきます。各ファンドの値動きや積立状況を把握する手間が増えるからです。
銘柄が少なければ数分でできる作業も、3本・4本と増えると一気に複雑になるのが懸念点です。
以下に、銘柄数と管理の負担感をわかりやすくまとめてみました。
| 銘柄数 | 管理の手間 | 難易度の目安 |
|---|---|---|
| 1本 | 確認が簡単。ほったらかしOK | ★☆☆(超初心者向け) |
| 2本 | 定期チェックが必要だが対応しやすい | ★★☆(慣れてきた人向け) |
| 3本以上 | リバランス・評価チェックが複雑になる | ★★★(経験者向け) |
投資は継続できるかが最も大切であるため、「気軽に続けられる仕組みかどうか」も銘柄選びのポイントになるといえるでしょう。
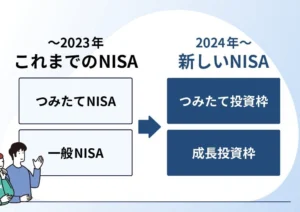
つみたてNISAの銘柄数は途中で変更しても大丈夫?

結論からお伝えすると、つみたてNISAの銘柄数はあとから変更してもまったく問題ありません。むしろ、ライフスタイルや考え方の変化にあわせて見直すのは自然なことです。
実際につみたてNISA銘柄を変更する方法は以下を参考にしてください。
- 証券会社のアプリorマイページにログイン
- 「NISA」⇒「積立設定」を開く
- 今までの銘柄を「積立停止」ボタンで一時ストップ(※売却ではない)
- 新たに積み立てたい銘柄を検索し「積立設定」を追加
- 毎月の積立額や日付、ボーナス設定などを入力して完了
「途中で銘柄を変えたら、それまでの積立がムダになるのでは…?」と思っている方が多いですが、これは完全な誤解です。積立を止める=過去の購入分が売られるわけではありません。
これまで買った分はそのまま非課税で保有されます。新たに買い足す銘柄と合わせて、1つのポートフォリオとして運用できるのです。
ただし、確かに変更は自由ですが、コロコロ変えすぎると長期運用の複利の力が弱まります。価格が下がった時に慌てて別の銘柄に変える行動は「安く売って高く買う」ことになり、資産形成がうまくいかなくなってしまいます。
「今決めきれない…」という方は、無料のFP(ファイナンシャルプランナー)相談を活用するのもおすすめです。
【投資スタイル別】つみたてNISAのおすすめ銘柄やファンドの種類

つみたてNISAのおすすめの銘柄やファンドの種類を紹介します。3パターンのケースを紹介するので、自分の投資目的がどのケースに近いかを考えながらご覧ください。
リスクがあってもお金を積極的に増やしたいケース
リスクがあっても資産を積極的に増やしたい方には、アクティブ型の投資信託がおすすめです。
なお、アクティブ型の投資信託はアナリストの分析や精査を必要とするため、一般的に信託報酬が高くなる傾向です。
このタイプの投資信託商品には、割安と考えられる銘柄を選定して運用益を出すことを目的とする「ひふみプラス」(レオス・キャピタルワークス)などがあります。
ミドルリスク・ミドルリターンで長期運用したいケース
リスクもリターンもほどほどに長期的に運用したいという人には、インデックス型の投資信託がおすすめです。
このタイプの投資信託商品には、日本株式指数に連動する「iFree 日経225インデックス」(大和アセットマネジメント)や、米国株式指数に連動する「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」(三菱UFJ国際投信)などがあります。
リスクを最低限に長期的に運用したいケース
大きなリターンは狙わずに、リスクを抑えて長期的に運用したいと考える方にはバランス型の投資信託をおすすめします。
商品にもよりますが、信託報酬はアクティブ型よりは比較的低め、インデックス型よりは比較的高めもしくは同程度の傾向です。
このタイプの投資信託商品には、「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」(三菱UFJ国際投信)や「野村6資産均等バランス」(野村アセットマネジメント)などがあります。
つみたてNISAの銘柄の買い方・選び方で失敗しないための6つの視点

まずは基本となる6つの視点をおさえるだけで、自分に合った銘柄を見つけやすくなります。
ここでは、初心者が「買ってよかった!」と思える投資信託を選ぶために押さえておきたいポイントを順番に解説していきます。
全世界株式インデックスとオールカントリーの違いに注意する
全世界株式インデックスと「オール・カントリー」の最大の違いは日本株を含むかどうかです。
それぞれの違いは以下の通りです。
| ファンド名の一例 | 日本株の有無 | 投資対象の範囲 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 含まれる | 日本・アメリカ・先進国・新興国すべてをカバー |
| SBI・Vシリーズ 全世界株式(日本除く) | 含まれない | アメリカ・ヨーロッパ・新興国など海外のみ |
同じオルカンでも連動している指標(ベンチマーク)が違えば、国ごとの配分やコストにも差が出ます。
選ぶときは以下のポイントを必ず確認しましょう。
- ベンチマークの違い(MSCI vs FTSEなど)
- 日本株を含むかどうか
- 信託報酬(年間の運用手数料)が低いか
「なんとなく全世界株」と選ぶよりも、自分の資産状況に合わせて中身を見比べてみてください。ちょっとした違いが、将来の資産に大きく影響することもあります。
高リターン狙いのアメリカ株はリスク許容度に応じて検討する
米国株式インデックスは長期で高い実績がありますが、価格変動リスクも大きい点に注意が必要です。
つまり「一時的に資産が減っても平気」と思える人には向いていますが、「下がったときに焦って売ってしまいそう」という方にはやや不向きかもしれません。
心構えができている場合は、低コストの米国株インデックス(S&P500や全米株式)で積極的にリターンを狙うのが一般的です。
投資目的を明確にする
つみたてNISAの銘柄を選ぶ際、投資目的を明確にする必要があります。
投資目的を明確にすることで、何年後にどのくらいの金額が必要かを考えることができます。目的が明確になったら、必要な時期と金額から銘柄を選びましょう。
リターンとリスクのバランス(ポートフォリオ)を考える
投資はリターンだけでなく、リスクも考える必要があります。
許容できるリスク内で、よりリターンの見込める銘柄を選定していきましょう。
手数料(信託報酬)をチェックする
つみたてNISAにおいて、手数料は非常に重要なポイントです。手数料率が0.1%違うといわれても、大したことないと思ってしまいがちですが、その0.1%が20年間続くと大きな額になるでしょう。
長期積立を考えている方は、手数料がかかる資産額が更に増え、手数料も毎年かさむ可能性があります。数十年単位で考えると、たった0.1%でも数十万以上の違いが発生するため注意が必要です。
純資産額と過去実績をチェックする
どの銘柄が信用できるのかを考えるために、銘柄の純資産額と過去実績をチェックすることも重要です。
また、過去の実績をチェックすることで、どのくらいのリターンを得られるか、リスクがあるのかを知ることができます。
純資産額と過去実績をチェックすることで、その銘柄が信用できる銘柄なのか確認することができます。
【銘柄本数別】つみたてNISAでおすすめのポートフォリオ例

ここでは、銘柄本数ごとのおすすめの組み合わせを紹介します。どのパターンも初心者でも無理なく始められる構成なので、迷っている方は参考にしてください。
【1本】全世界株式1本ならほったらかし投資に最適
投資にあまり時間をかけたくない方には、全世界株式インデックス1本にしぼった運用がおすすめです。
たった1本でも数百社に分散されているので「リスクが集中しないか心配…」という不安も不要です。
この投資法のいいところは、最初に決めたらあとは積み立てを続けるだけでOKという点です。忙しくて運用に時間を割けない人でも、ほったらかしで資産形成が進んでいきます。
【2本】先進国株式+バランス型で守りと攻めを両立
もう少し自分らしい運用を試してみたい方には、2本構成がちょうどいいバランスです。ここでのおすすめは「先進国株式」と「バランス型ファンド」を組み合わせること。
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(攻め)
- 楽天・インデックス・バランスファンド(守り)
配分例は以下の通りです。
| ファンド | 割合 | 役割 |
|---|---|---|
| 先進国株式ファンド | 70% | リターンを狙う |
| バランス型ファンド | 30% | リスクを抑える役目 |
バランス型ファンドは株と債券の比率を自動で調整してくれます。「少しリスクを取ってみたいけど、大きく減るのは怖い…」という方には2本構成はちょうどいいスタートラインといえるでしょう。
【3本】米国株+新興国株+債券型で高度な分散が可能に
投資に少し慣れてきた方や、より分散を意識したい方には3本構成がおすすめです。「攻め」「成長」「守り」の3つのバランスを取ると、どんな市況でも安定感のある運用が目指せます。
代表的な構成は以下の通りです。
| ファンドカテゴリ | 割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 米国株式ファンド | 50% | 安定的な成長を期待できる先進国の代表 |
| 新興国株式ファンド | 20% | 将来の成長に期待できるが変動もやや大きい |
| 債券型ファンド | 30% | 株の値下がり時に資産全体のブレーキ役を果たす |
複数の経済圏・資産タイプを組み合わせることで、どこかが下がってもどこかが支えるような仕組みができあがります。
「もう少し本格的に投資したい」「いろんな国に分散して育てていきたい」そんな気持ちが芽生えたら、ぜひこの3本構成を検討してみてください。
つみたてNISAで分散しすぎないための3つの工夫と複利効果を高める視点

分散とは、あくまで「意味のある分け方」をすること。自分の投資目的や資産状況に合った設計をすれば1本だけでもしっかり資産は育ちます。
ここでは、分散しすぎないための具体的な工夫と、複利効果を高めていくための考え方を紹介します。
地域・資産・業種の分散は「重複しない」ことが大前提
つみたてNISAで分散投資をするときは、ただ銘柄を分ければいいわけではありません。投資先がかぶってしまうと分散しているつもりでも実は「同じ場所に偏っていた」ということがよく起こります。
- 国内株式ファンドA(日本株中心)
- バランス型ファンドB(実は中身の3割が日本株)
⇒上記2つを同時に持っていると、日本株の比率が想定以上に高くなってしまう
かぶりがあると資産の影響を強く受けてしまい、分散の意味がなくなってしまいます。
分散する際に見ておくべき分類は以下の3つです。
- 地域:日本・米国・先進国・新興国など
- 資産:株式・債券・REIT(不動産投資信託)など
- 業種:ハイテク・医療・金融などの業界
つみたてNISAでは、分けることよりも「かぶらないこと」が大切です。
均等型ファンドでも投資先がかぶる場合は要注意
均等型ファンドは、8資産にそれぞれ12.5%ずつ分けるような商品です。一見バランスが良く見えますが、組み合わせ方を間違えると分散効果が薄れてしまいます。
たとえば、こんなケースがあります。
- 楽天・インデックス・バランスファンド(均等型:日本株含む)
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
⇒どちらも日本株を含んでいるため、合計で見ると日本株への投資割合が増えすぎてしまいます。
ファンドの中身をざっくり見るためには、証券会社の「投資比率」や「構成比」欄を確認すると分かりやすいです。
「均等型だから安心」と思い込まず、他のファンドとどう重なるかまで見るのがポイントです。
分散しない方が良い人もいる|目的と資金次第では1本が最適
「なんだかんだ言って、何本にすればいいの?」という疑問を持つ方も多いと思いますが、実は1本でOKな人もたくさんいます。
- 投資資金が少ない(月1〜2万円)
- 管理がめんどうだと感じる
- 投資のことはあまり考えず、放置したい
こんな方には、全世界株式1本での積立がシンプルで続けやすいかもしれません。
以下のような判断軸で考えてみましょう。
| 状況 | 最適な銘柄数 |
|---|---|
| 投資経験なし、時間もとれない | 1本でOK |
| 少しだけ勉強して試したい | 2本で様子を見る |
| 資産運用に慣れていて管理も苦じゃない | 3本以上も可 |
「続けやすさ」と「納得感」があれば、それがあなたにとっての正解です。無理せず、自分のペースで進めていきましょう。

よくある疑問をQ&Aで解決|つみたてNISAの複数銘柄運用に関するFAQ

最後に、つみたてNISAに関してよくある質問と回答を紹介します。
そもそもつみたてNISAとは?
つみたてNISAとは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できる税制優遇制度のことです。
つみたてNISAの概要は以下の通りです。
| 非課税保有期間 | 20年間 |
|---|---|
| 年間非課税枠 | 40万円 |
| 投資可能商品 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
| 途中換金・資金の引き出し | 可能 |
参考:日本証券業協会「NISA口座開設・利用状況調査結果 (2022年3月31日現在)について 」
通常の株式投資では運用益の約20%に対して税金が課せられますが、つみたてNISA口座では非課税となり税制上の優遇を受けることができます。非課税期間は一般NISAの4倍の20年間となっており、少額から長期の資産形成を始めることが可能です。
つみたてNISAで複数銘柄を持つと損しやすい?
銘柄が多いと損をする…というわけではありません。大事なのは中身がかぶっていないかどうかです。
数ではなく「組み合わせの質」が損しにくい投資のコツです。
途中でファンドを変更したいときの注意点は?
つみたてNISAでは、積立中の銘柄を変更することは可能です。ただし、乗り換えすぎると複利効果が弱まり、長期的な成長にマイナスになることもあります。
変更したいときは、現在の積立を止めて別の銘柄に切り替えるだけ。過去に買った分はそのまま運用されるので心配いりません。
何銘柄まで持てる?本数に上限はあるの?
法律で決まった銘柄数の上限はありません。1つの証券口座で何本でも保有できますが、現実的には3~4本までが管理しやすい範囲です。
複数銘柄に積立を分けることも可能で、1本に月1万円、もう1本に月2万円など設定できます。ただし、増やしすぎると内容把握やリバランスが面倒になるため、シンプルさも大切です。
ハイリターンを狙うならどのファンドが向いている?
大きな利益を狙いたい方には、成長が期待できるテーマのファンドが向いています。
- 米国株式インデックス(S&P500など)
- 全世界株式ファンド
- 新興国株式インデックス
ただし、ハイリターン=ハイリスクでもあるので、急な値下がりにも慌てない「覚悟」も必要です。投資額を調整しながら、リスクとのバランスをとって使いましょう。
つみたてNISAで得られる運用益はどのくらい期待できる?
期待できる利益は銘柄や相場によりますが、年3~7%程度を目安にするのが現実的です。
たとえば、年5%のリターンで20年間毎月3万円を積み立てると…
- 元本:約720万円
- 増えた分:約620万円
- 合計:約1,340万円
このように、長く積み立てるほど複利でお金がふくらんでいくのが特徴です。短期間で稼ごうとせず、コツコツ積み上げていくという心構えが大切です。
投資枠を増やすにはどうすればいい?
つみたてNISAの投資枠は年間120万円までと決まっています。ただし、新NISAでは成長投資枠(240万円)とあわせて最大360万円まで非課税枠を使えるようになりました。
もっと投資したい場合は、以下のような方法もあります。
- つみたてNISA+成長投資枠を両方活用
- 夫婦・家族でそれぞれの枠を使う
- NISA以外の投信やiDeCoを使う
家族で協力すれば、さらに投資の幅が広がります。
インデックス投資はなぜ初心者に向いているの?
インデックス投資は、市場全体に広く分散して投資する方法です。
たとえば「S&P500」や「全世界株式」のようなインデックスに連動するファンドを買えば、数百社に一気に投資できることになります。
さらに、以下のように初心者にとってメリットが多いです。
- 運用コストが安い
- 売買のタイミングを考えなくていい
- ほったらかしでも成果が出やすい
つみたてNISAでおすすめの割合・配分は?何対何で組めばいい?
投資の目的やリスクへの考え方によって、最適な配分は変わります。以下に初心者向けの組み合わせ例を紹介します。
| パターン | 配分例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1本型 | 全世界株式100% | 迷わず続けられる、ほったらかし向け |
| 2本型 | 先進国株式70%+バランス型30% | 攻めと守りのバランスを取りたい人向け |
| 3本型 | 米国株50%+新興国株20%+債券型30% | 高度な分散をしたい、管理できる人向け |
まとめ:初心者は1〜2本でOK!銘柄数より中身と続けやすさが重要
この記事では、つみたてNISAの基本や複数銘柄を持つ際の注意点、運用のコツや期待リターンなどを解説しました。
複数銘柄を組み合わせるからといって、必ずしも投資がうまくいくとは限りません。大切なのは「中身がかぶらないかどうか」を見極めることです。
資産タイプや投資地域が似ている銘柄を複数持ってしまうと、分散しているつもりが実は一点集中になっている、ということも少なくありません。
心から納得できる運用スタイルを見つけて、今日からつみたてNISAを始めましょう。
とはいえ、「本当に自分に合った銘柄の組み合わせが分からない」「家計的にいくらまで積み立てていいのか不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな方には、お金のプロによる家計診断サービス「マネーコーチ」の活用がおすすめです。
- 診断は無料&何度でもOK
- オンラインで全国どこからでも参加可能
- カメラオフもOKで安心
「このままで老後資金は足りるの?」「もっと効率よく貯めたい!」と感じた今こそ、家計改善のはじめ時です。