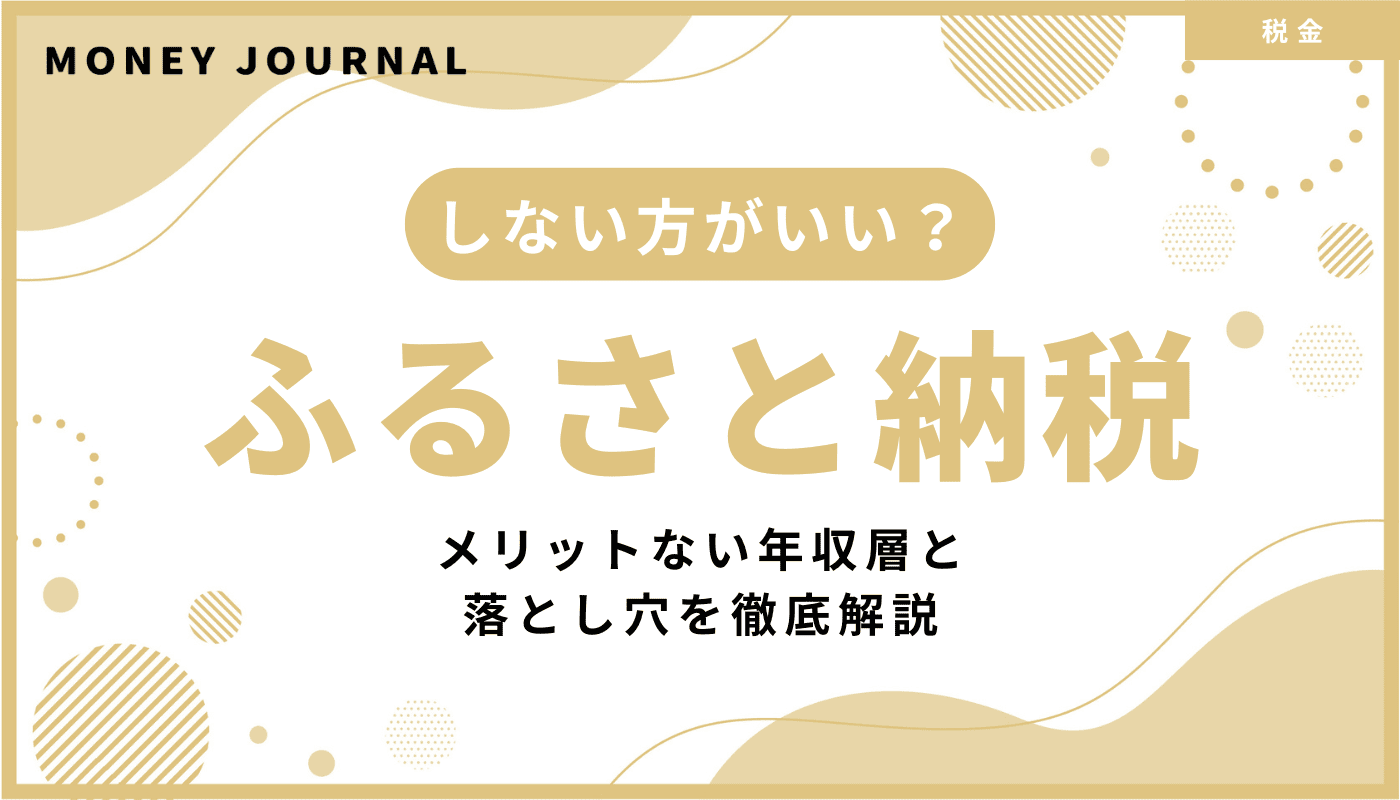- 「ふるさと納税って本当に得なのかな?」
- 「やらない方がいいって聞いたけど理由は何?」
- 「自分の年収でもメリットあるのか知りたい」
このように考えている方もいるでしょう。
結論、ふるさと納税はしない方がいいと言われる理由は次の2つです。
- 実質的に税金の前払いだから
- 無条件で得する制度ではないから
本記事では、なぜ「ふるさと納税はしない方がいい」と言われるのかを整理し、どんな人が損をしやすいのかを年収別にわかりやすく解説します。
「お得だと思って始めたのに逆に損してしまった…」と後悔したくない方は、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税はしない方がいいと言われる理由

ふるさと納税はしない方がいいと言われる理由は次の2つです。
実質的に税金の前払いだから
ふるさと納税は、寄付額から自己負担2,000円を除いた分が翌年の税金から控除・還付される制度です。つまり寄付をした瞬間に税金が軽くなるわけではなく、控除が反映されるのは翌年以降です。
生活費の支払いで家計が逼迫している家庭では、この「前払い」の性質が特に響きます。急な出費に備えたい人にとっては、ふるさと納税を無理に利用するのはリスクになる場合もあるのです。
無条件で得する制度ではないから
ふるさと納税は誰にでも必ず利益がある制度ではありません。控除できる上限額は年収や扶養家族の有無で変わるため、寄付額が多くても控除が追いつかない場合があります。
また寄付先によっては返礼品が届くまで数か月かかることがあり、場合によっては希望した品が手に入らないこともあります。さらに、確定申告やワンストップ特例の手続きを忘れれば控除は適用されず、単なる寄付で終わってしまいます。
こうした「うまく活用しなければ損をする可能性がある制度」は、ふるさと納税に限った話ではありません。住宅ローン控除や保険料控除なども同じです。
もし「自分にとってどの制度が有利なのか」「控除や節税の仕組みを正しく使えているのか」を整理したいと感じる方は、マネーコーチの無料オンライン家計診断を活用してみてください。

ふるさと納税をやらない方がいい人の条件

ふるさと納税をやらない方がいい人の条件は次の4つです。
控除額が少なく得にならない人
ふるさと納税の控除額は一律ではなく、人によって大きく差があります。年収や家族構成、障害者控除の有無などで上限が決まるため、低所得層や扶養が多い家庭では思ったほど得にならないのです。
独身で年収が200万円台なら、控除できるのは1万円前後。自己負担の2,000円を引くと実際のメリットは数千円程度で、返礼品を含めても大きな節約にはなりません。
生活費を切り詰めている家庭にとっては、この程度のプラスでは物足りなく感じるでしょう。しかも上限を超えて寄付してしまうと、その分はすべて自己負担です。
お得に見えても実際は期待できる範囲が小さいため、得にならない人は無理に利用する必要はないのです。
確定申告やワンストップ特例制度がめんどくさいと感じる人
ふるさと納税を利用するには、確定申告またはワンストップ特例の手続きが必要です。会社員でも寄付先が6自治体*を超えると確定申告をしなければなりません。
書類をそろえたり、申請書を書いて送ったりする作業は思った以上に手間がかかります。もし不備があれば手続きが無効になり、期限を忘れれば控除が受けられず全額自己負担です。
*参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「複数の自治体にふるさと納税を行えますか?」
寄付や返礼品に興味がなく無意味と考える人
ふるさと納税は、あくまで地方自治体への寄付を基盤とする制度です。地域を応援したいとか、名産品を楽しみにしたいという気持ちがある人には向いていますが、寄付に興味がなければ魅力を感じにくいでしょう。
返礼品の多くは食品や日用品ですが、「欲しいものがない」「もらっても使わない」という人もいます。控除による節税効果も限られるため、モチベーションがなければ単に支出が増えるだけです。
資金繰りが厳しくお金がない人
ふるさと納税は翌年の税金が軽くなる制度ですが、寄付金は一度自分で支払わなければなりません。控除が反映されるのは後になってからなので、その間はお金が減ったままです。
生活費で手一杯の家庭にとって、寄付金の支出は危険なレベルで家計をさらに圧迫します。急な出費に備えたい時期に5万円を寄付すると、数か月後に資金不足に直結しかねません。
返礼品が届いても家計が苦しくなれば喜びは薄れます。資金に余裕がない状態で利用すれば、制度のメリットより「やめておけばよかった」という後悔の方が残りやすいでしょう。

ふるさと納税を始めてもメリットない年収層

以下の表は、ふるさと納税で十分なメリットを得にくい年収層の目安です。
実際の控除上限額は、扶養の有無・社会保険料・住宅ローン控除などの条件で変動するため、あくまで参考としてご覧ください。
| 年収層 | メリットがない理由 | 損をする可能性 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 所得税・住民税とも非課税となる場合が多く、控除が発生しない | 非常に高い |
| 150万円未満 | 控除上限が数千円にとどまる。返礼品の実質的な得が少ない | 高い |
| 250万円未満 | 配偶者控除などで課税額が抑えられ、上限が極めて小さい | 比較的高い |
| 300万円前後 | 独身なら上限2〜3万円あるが、扶養や控除が多いと1万円未満に。条件次第でほぼ得にならない | 条件により高い |
ふるさと納税は「誰でも必ず得する制度」ではありません。年収が低い層や扶養控除が多い世帯では控除上限が小さく、実質的なメリットを得にくいのが実情です。
ふるさと納税の利用を検討する際は、必ずシミュレーションで控除上限を確認し、自分の条件に合っているかを判断することが大切です。

ふるさと納税の落とし穴とは?注意すべきデメリット

ふるさと納税の落とし穴や、注意すべきデメリットは以下の8つです。
控除限度額を超えるとすべて自己負担になる
ふるさと納税には、以下のとおり控除できる上限額があります。
| 給与収入 | 独身又は共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
| 450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| 500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
| 550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
| 650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
| 750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
| 850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
| 900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
| 1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
| 1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
| 2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
| 2500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
もし上限を超えて寄付すると、自己負担は2,000円どころか、超えた分がすべて自腹になります。
上限を知らずに寄付してしまい、思わぬ出費に悩む人も実際にいます。節税目的で利用するなら、必ずシミュレーションで控除可能額を確認しておくことが大切です。無駄な出費を避けるための最低限の準備といえるでしょう。
ワンストップ特例制度に制限がある
ふるさと納税には、確定申告をしなくても控除を受けられる「ワンストップ特例制度」があります。ただし、誰でも自由に使えるわけではなく条件が決まっています。
主な条件は次の2つです。
- 寄付先が年間で5自治体以内であること
- 会社員など、確定申告を行わない人であること
この条件を外れると制度は利用できません。制度を使えると思い込んで申請しても、要件を満たしていなければ無効です。
確定申告を忘れると寄付が無駄になる
ふるさと納税は、寄付するだけでは税金が安くなりません。確定申告かワンストップ特例の手続きを、必ず期限までに済ませる必要があります。
「返礼品は届いたのに控除を受けられなかった」という人も実際にいます。その場合、寄付金はすべて自己負担となり、節税どころか余計な出費になるだけです。寄付した後は、手続きを忘れず確実に済ませることが一番大切です。

寄付金を先に支払う必要がある
ふるさと納税は「寄付すればその場で税金が安くなる」と思われがちですが、実際には翌年の住民税から差し引かれる制度です。
まず自分でお金を出し、控除が反映されるのは後になります。返礼品は早ければ数週間で届きますが、税金の軽減が実感できるのは翌年です。つまり支払ったお金はすぐには戻ってきません。
家計に余裕がある人なら問題は小さいものの、日々のやりくりで精一杯の家庭にとっては負担になりやすいでしょう。
自分が住む自治体では返礼品がもらえない
ふるさと納税は「ほかの地域に寄付する」ことを前提にした制度です。そのため、自分が住んでいる自治体に寄付しても返礼品なしとなります。
返礼品を目当てにしている人にとっては「地元を支援しながら特産品をもらう」という形が取れないのは物足りなく感じるかもしれません。
クレジットカードの名義違いは控除対象外となる
ふるさと納税で控除を受けるには、寄付者本人の名義で支払うことが必須です。たとえば夫が寄付をするのに妻名義のクレジットカードを使ったり、親子で名義が異なるカードを利用したりすると、控除は受けられません。
安全に利用するには、自分名義のクレジットカードや銀行口座を使うことが基本です。寄付を始める前に決済方法を確認し、名義が一致しているか確かめるだけで防げるトラブルです。
寄付金受領証明書を紛失すると控除が受けられない
ふるさと納税をすると、寄付先の自治体から「寄付金受領証明書」が送られてきます。確定申告で控除を受けるために必要な大切な書類です。
紛失してしまうと寄付をしても税金の控除が受けられず、結果的に単なる寄付になります。自治体によっては再発行してくれない場合もあるので、届いたら封筒ごと保管しておきましょう。
最近は電子証明書に対応する自治体も増えており、マイナポータルやe-Taxで使える形式なら、紙をなくす心配も減らせます。
参考:国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」
手続き自体が手間で「めんどくさい」と感じやすい
ふるさと納税を利用するには、どうしても手続きが必要です。ワンストップ特例を選んでも、寄付するたびに申請書を書いて、マイナンバーカードのコピーを添えて自治体へ送らなければなりません。
「返礼品は欲しいけど、書類のやりとりが煩雑でやめた」という人も少なくありません。制度そのものは便利でも、利用者にとっては手続きのハードルが高くなる場面があるのです。

他の節税制度との比較で見えるふるさと納税の欠点

ふるさと納税は返礼品を受け取れますが、制度としての節税効果はその年限りで、長期的な資産形成にはつながりません
一方、iDeCoや新NISAは「資産を増やしながら節税できる」制度であり、将来にわたり効果が積み重なる点が違いです。
代表的な制度を整理すると以下のとおりです。
| 制度名 | 節税の仕組み | 節税効果 | デメリット |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | 住民税・所得税から控除(自己負担2,000円で返礼品) | 控除はその年限り(翌年の住民税に反映) | ・上限超過分は全額自己負担 ・資産形成につながらない |
| iDeCo | 掛金が全額所得控除/運用益も非課税 | 高い節税効果+老後資金形成 | ・流動性が低い ・口座管理手数料が必要 ・受取時に課税される場合あり |
| 新NISA(2024〜) | 投資利益が非課税/非課税投資枠が拡大 | 長期で大きな節税効果+資産形成 | ・投資リスクあり ・元本保証がない |
ふるさと納税は「節税」よりも「実質負担2,000円で特産品を得られる制度」と捉えた方が正確です。控除額は数万円規模にとどまることが多く、資産形成効果は期待できません。

ふるさと納税はやらないと損?損得をわかりやすく検証

ふるさと納税を始めるか迷っている方に向け、損か得かについて解説します。
全員にメリットがあるわけではない
ふるさと納税は「寄付すれば必ず得する」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。「税金を先に払って、翌年に控除される」というもので、納税額が少ない人には効果が小さいのです。
アルバイトやパートで収入が少ない人だと、控除の上限は数千円から1万円ほど。自己負担の2,000円を引けば、返礼品をもらっても思ったほどの得にはなりません。
自分の年収水準を確認したうえで利用を判断することが重要です。
損益分岐点は「控除額−自己負担2,000円」で判断できる
ふるさと納税で得か損かを見極める目安は「控除額から自己負担2,000円を引いた金額」です。この残りが実際の利益と考えるとわかりやすいでしょう。
たとえば控除の上限が5万円の人なら、5万円を寄付しても自己負担2,000円を引いた48,000円が返礼品の価値になります。食品や日用品が届けば、普段の生活費をカバーできるのでメリットを実感しやすくなります。

ふるさと納税をやらない方がいい具体的なケース集

ふるさと納税をやらない方がいい具体的なケースは以下のとおりです。
フリーター・ニート・無職は住民税が低く無意味
ふるさと納税は住民税や所得税を前提に控除が行われます。そのため、税金をほとんど納めていない人は控除を受けられる範囲がごくわずかです。
フリーターやニート、無職の人は収入が少なく、住民税が非課税になることもあります。この場合、寄付をしても控除は0円。返礼品は届きますが、支出だけが残ってしまいます。
各種控除の恩恵を最大限受けている
住宅ローン控除や医療費控除、扶養控除などをすでに使っている人は、ふるさと納税に回せる控除枠が残っていない可能性があります。
その状態で寄付をしても、税金から差し引かれることはなく、支払った分がまるごと自己負担です。返礼品は届きますが、実質的には割高な買い物をしたのと変わりません。

途中退職・退職予定で転勤予定がない
ふるさと納税の控除額は、その年の収入に応じて決まります。したがって退職などで収入が減れば、想定していたよりも控除枠が小さくなります。
たとえば「年収500万円の予定」で上限いっぱい寄付した人が、退職して実際は年収300万円になった場合、本来の控除額は大幅に減り、超えた分はすべて自己負担です。
翌年の住民税が減るケースも同じで、寄付額を高めに設定すると損をしやすくなります。転勤予定がなく住民税が下がる見込みのある人は特に注意が必要です。

ふるさと納税否定派の意見「ばかばかしい・廃止するべき」は正しいのか?

ふるさと納税には利用者から肯定的な声がある一方で、「ばかばかしい」「不公平だから廃止すべき」といった否定的な意見も根強く存在します。これらの主張は大きく二つの観点に整理できます。
第一に、自治体間の格差拡大です。返礼品競争の激化により、大都市圏など本来税収の多い自治体が収入を失い、地方の一部自治体に寄付が集中する現象が起きています。その結果、都市部の住民サービスに悪影響を与えかねないと批判されています。
第二に、「寄付というより実質的な買い物になっている」という点です。本来の趣旨は地域振興や応援ですが、実際には返礼品を目的に寄付先を選ぶ人が大半を占め、「制度として歪んでいる」という指摘があります。
否定派の意見には一定の合理性があるものの、制度そのものを不要と断じるのは早計といえるでしょう。
ふるさと納税に関するよくある質問

ふるさと納税に関するよくある質問は以下のとおりです。
ふるさと納税は会社にバレる?勤務先に影響はある?
ふるさと納税をしても、基本的に勤務先へ通知が届くことはありません。ワンストップ特例制度を使えば会社には一切知られずに済みます。
ただし確定申告を行う場合、住民税の控除額が変わるため、会社経由で天引きされる住民税額に差が出ます。その結果、間接的にふるさと納税をしていることが推測される可能性はありますが、業務や昇進に影響することはありません。
ふるさと納税をした翌年に引っ越しすると控除はどうなる?
控除は「寄付をした年の所得・住民税」に基づいて計算されるため、翌年に引っ越しても基本的に問題ありません。
ただしワンストップ特例制度を利用する場合は、住所変更を忘れると控除が適用されないリスクがあります。引っ越し後は速やかに寄付先自治体へ変更届を提出してください。
退職金を受け取った年もふるさと納税は使える?
退職金は「分離課税」の対象であり、住民税の控除に直結しません。そのため退職金そのものではふるさと納税の効果はありません。ただし同じ年に給与所得や事業所得がある場合には、その分の所得に応じて控除が使えます。
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?
併用は可能ですが注意が必要です。住宅ローン控除も住民税の減税効果を持つため、控除枠が住宅ローン控除で使い切られると、ふるさと納税の控除枠が残らず効果が薄れてしまうことがあります。
ふるさと納税は無職や専業主婦でもできる?
制度としては誰でも寄付できますが、住民税や所得税を納めていない人は控除を受けられません。つまり返礼品は受け取れても、自己負担2,000円以上の全額負担となり「メリットがない」状態です。
ワンストップ特例と確定申告を両方するとどうなる?
両方を行った場合は、確定申告の内容が優先されます。つまりワンストップ特例の申請は無効扱いとなります。二重に手続きしてしまってもペナルティはありませんが、不要な手間になるためどちらか一方に絞るのが正しい方法です。
自己負担2,000円は寄付ごとにかかるの?
いいえ。自己負担額は「1年間の合計寄付額」に対して2,000円のみです。複数の自治体に寄付したとしても、合計して自己負担は2,000円で変わりません。ただし控除限度額を超えた部分は全額自己負担になるため、上限額を超えないよう注意が必要です。
まとめ:まとめ:無理に利用せず、自分の年収・状況に合うか冷静に判断を
この記事では、ふるさと納税を「しない方がいい」と言われる理由や、損をしやすい年収層について解説しました。
制度は魅力的に見えますが、実際には以下の落とし穴があります。
- 税金の前払いで資金繰りが厳しくなる
- 控除上限を超えると全額自己負担
- 確定申告やワンストップ特例の手続きが手間
- 低所得層では控除効果が小さく得が少ない
だからこそ大切なのは、年収や家族構成をもとに控除上限をシミュレーションすることです。
無理に利用する必要はありません。自分の状況を冷静に把握し、本当に得になると判断できたときに取り入れてください。