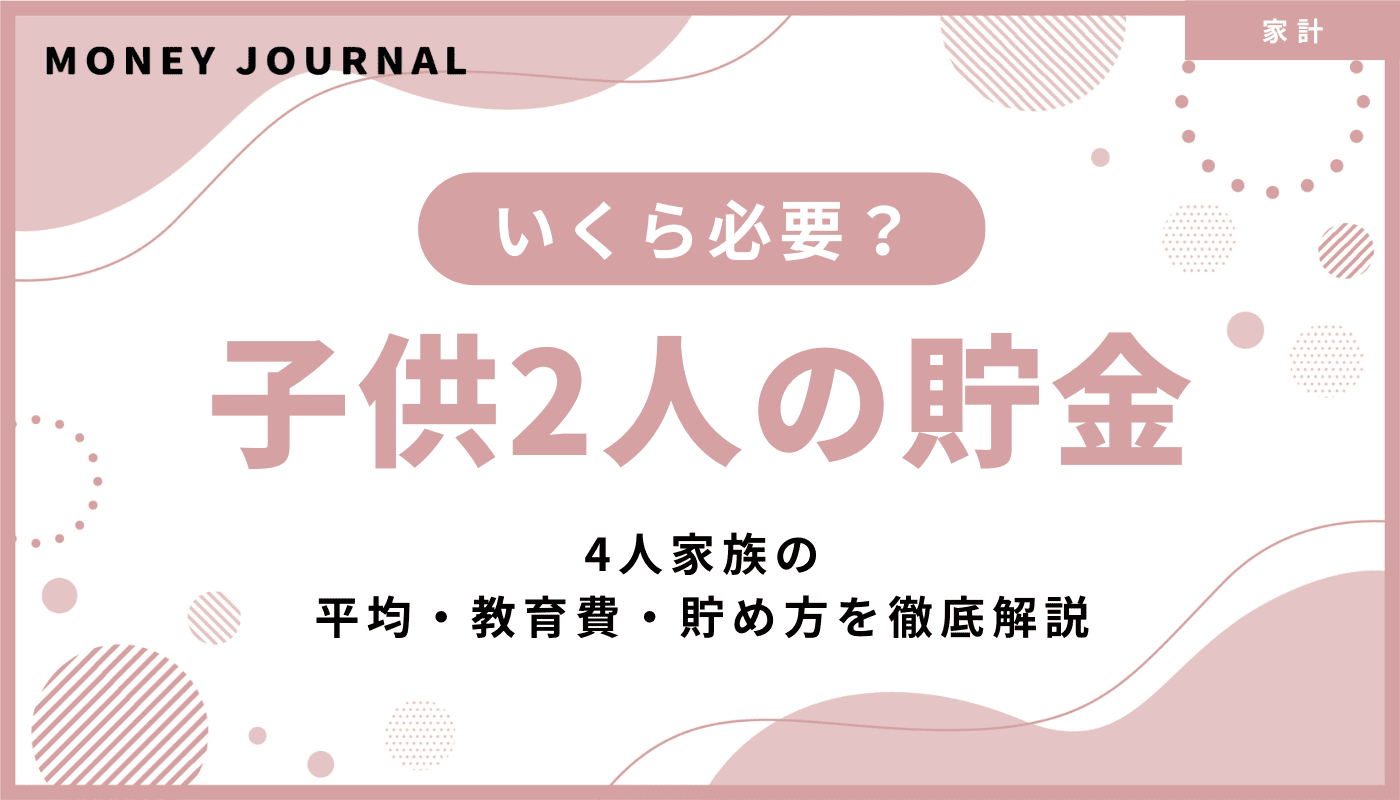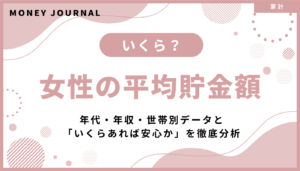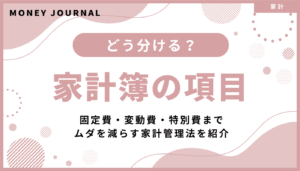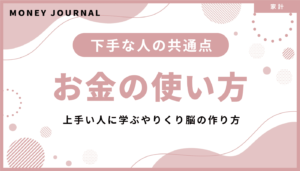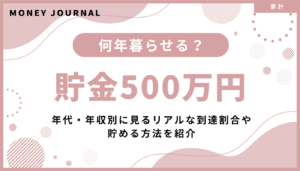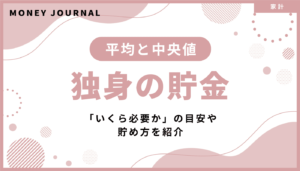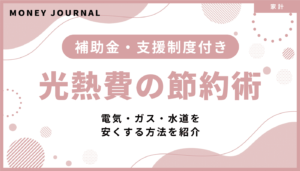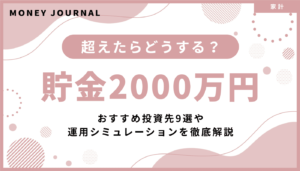- 「子供2人のためにどれくらい貯金が必要だろう」
- 「四人家族の平均貯金額はどのくらいなのか知りたい」
- 「100万しかないけど、今の貯金で足りるのか不安」
このように考えている方もいるでしょう。
本記事では、2人以上の世帯に焦点を当て、平均年収や中央値、貯金する方法、年収目安を徹底解説します。
子供の将来を考えて「貯金ないけどしっかり備えたい」「貯金なしで焦っている」という方は、ぜひ参考にしてください。
- 2人以上世帯の平均貯金額と中央値
- ライフステージ別の必要額の目安
- 定期預金や学資保険などの具体的な貯金方法
- NISA・iDeCoを活用した効率的な増やし方
- 貯金ができないときの現実的な対処法
- 子供2人を育てるための理想的な年収の目安
子供2人家庭のリアルな貯金額は?平均と中央値

「2人以上世帯」における、金融資産保有額*の平均と中央値は以下のとおりです。
| 年代 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 20代 | 249万円 | 30万円 |
| 30代 | 601万円 | 150万円 |
| 40代 | 889万円 | 220万円 |
| 50代 | 1,147万円 | 300万円 |
| 60代 | 2,026万円 | 700万円 |
| 70代 | 1,757万円 | 700万円 |
平均は一部の高額資産を持つ世帯に引っ張られやすいため、より生活実感に近いのは中央値です。
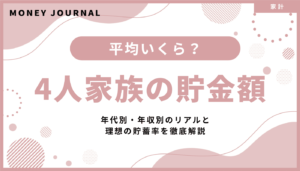
子供2人でいくら貯金があれば安心?ライフステージ別目安

一般的に「子供は小さいうちは手がかかるが、成長すると手はかからずお金がかかる」と言われるように、教育費は年齢が上がるほど負担が増えます。
ここでは、以下のライフステージ別に必要なお金を解説します。
幼稚園〜小学校
幼稚園から小学生までは、まだ教育費の負担が軽い時期です。
文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」によると、公立の幼稚園から小学校にかけてかかる学習費の合計はおよそ250万円です。私立に通わせると1,000万円を超えることもあります。
幼稚園から小学校の時期に必要な貯金の目安は300万円から500万円程度。余裕を持って教育費を払えるように、早めに積立を始めておくことが大切です。
参考:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果について」

中学校〜高校
中学・高校になると一気に教育費が膨らみます。公立の場合でも中学で約160万円、高校で約150万円かかり、合計で300万円を超えます。私立に進学すれば総額は1,000万円を大きく超えるのが一般的です。
中学校から高校のタイミングまでに用意しておきたい貯金の目安は700万円から1,200万円。部活動や塾、留学など追加費用も発生しやすいため、子供の進路を考えながら貯金を積み上げていきましょう。
参考:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果について」

大学
大学は最も費用がかかるライフステージです。日本政策金融公庫の調査によれば、国公立大学で約480万円、私立文系で約690万円、私立理系で820万円を超えます。さらに在学中に一人暮らしをすると、生活費だけで4年間で約600万円かかります。
つまり大学進学を見据えると、1,000万〜2,000万円の貯金が目安です。学費に加え、仕送りや生活費を含めてシミュレーションし、早い段階から準備を始めましょう。
参考:日本政策金融公庫|令和3年度「教育費負担の実態調査結果」

子供2人のために確実に貯金する方法

子育て費用は待ってくれないので、思いついたときに貯め始めることが大切です。ここからは代表的な貯金方法を紹介します。
定期預金・積立預金で強制的に貯める
もっとも取り入れやすいのが定期預金や積立預金です。普通預金より金利がやや高く、一定期間引き出せないので「つい使ってしまう」状況を防げます。
銀行には自動積立定期預金があり、毎月決まった日に普通預金から自動で振り替えられるため、意識せずに積立が進みます。元本割れの心配がない安心感も魅力です。
ただし、現在の低金利では利息がほとんど増えず、物価上昇には追いつきません。教育費を大きく増やす効果は期待できないため、緊急時の資金確保や確実な積立の手段として利用するのが現実的です。
財形貯蓄や社内預金で給与天引きにする
勤務先に制度があれば、財形貯蓄や社内預金を利用するのも有効です。給与やボーナスから天引きで積立できるため、先取り貯金の仕組みとして強力です。
社内預金は会社が用意する預金制度で、利率が高めに設定されていることもあります。ただし会社が導入していなければ使えず、倒産時のリスクも0ではありません。また転職すると継続できない場合もあるため、制度内容や解約ルールを事前に確認しておく必要があります。
学資保険で教育資金を計画的に積み立てる
教育費専用の積立として利用されるのが学資保険です。毎月保険料を支払うことで、満期時や進学の節目にまとまった保険金や祝い金を受け取れます。契約者に万一のことがあった場合でも、保険料の払込が免除され契約通りの給付が受けられるのが特徴です。
ただし途中解約では元本割れの可能性があり、利回りは低めです。純粋な増やす手段としては弱いものの、保障と積立を兼ねたものとしては有効です。
NISA・iDeCoを活用して効率的に貯金を増やす
教育費の準備をしながら資産を育てたい方は、NISAやiDeCoも有効です。NISAは投資信託や株式の運用益が非課税になる制度。iDeCoは掛金が全額所得控除の対象になり、運用益も非課税です。
老後資金向けの制度ですが、節税効果が大きいので家計に余裕を作り教育費に回すこともできます。
ただしiDeCoは60歳まで引き出せない制約があるため、教育資金そのものに充てるには不向きです。
預金や学資保険で流動性を確保しつつ、一部を投資に回すように役割を分けて組み合わせると効率的な資産形成につながります。

子供2人で貯金ができない家庭の解決策

思うように貯金できないと「うちだけなのでは」と焦る方も多いですが、工夫次第で改善は可能です。
教育費や生活費に加えて育児費用を少しずつでも確保するには、支出を減らす・収入を増やす・制度を使うという3つの視点が大切です。ここから具体的な方法を紹介します。
固定費を削減するなど支出を減らす
支出を減らすなら、まずは固定費の見直しから始めましょう。一度削れば継続的な節約効果が見込めます。
代表的な見直しポイントは以下のとおりです。
- 通信費:スマホを格安SIMに切り替え、不要なオプションを解約
- 保険料:保障内容を整理し、重複や過剰な特約を外す
- サブスク:利用していない定額サービスを解約
- 住居費:住宅ローンの借り換えや家賃の見直し
- 光熱費:電気・ガス契約を比較、使い方も工夫
見直す際は生活の質を大きく落とさないことが大切です。年に1度はチェックし、更新時期に合わせて調整すると効率よく改善できます。
児童手当を教育資金に全額充てる
国から支給される児童手当は、教育費の先取り貯金に適した制度です。
2024年10月から所得制限が撤廃され、0歳から18歳までの子どもが対象になりました。支給額は月1万円〜1万5千円、第3子以降は3万円です。偶数月に2か月分まとめて振り込まれます。
受給には市区町村への申請が必要なので、忘れずに手続きを済ませましょう。

高等学校等就学支援金で高校費用を軽減する
子育てで利用できる公的制度として高等学校等就学支援金があります。
主な受給資格は、日本国内在住の高校生であること、年収約910万円未満世帯の生徒であることの2点です。
支給期間や支給額の一部の例は、以下のとおりです。
| 定額授業料 | 支給限度額 |
|---|---|
| 公立高等学校全日制 | 9,900円/月 |
| 公立高等学校通信制 | 520円/月 |
奨学金や教育ローンで大学費用を一時的に補う
大学進学時はまとまった費用が必要になり、「お金がない」と感じる家庭も多いです。その際に活用できるのが奨学金や教育ローンです。
奨学金には返済不要の給付型と、無利子・有利子で借りる貸与型があります。
ただし支給は入学後が中心のため、入学金などの初期費用には使いにくい面があります。
教育ローンは保護者が借り入れ、入学前から利用できるため初期費用に充てられます。国の教育ローンは低金利で借入上限も明確ですが、民間ローンは金利が高めで審査も厳しめです。どちらを選ぶにしても、返済計画を立てたうえで利用しましょう。
共働きで収入を増やす
支出の見直しに加えて、収入を増やす方法も効果的です。専業主婦ではなく共働きにすると世帯収入が安定し、教育費や貯金に回せる余裕が生まれます。
夫婦で収入(月給やボーナス)と支出を見える化し、共通口座を設けて貯金目標を共有すると協力しやすくなります。給与から自動振替で貯金を行えば、無理なく積立が続くでしょう。
子供2人を育てるために必要な年収の目安

子供を育てるには、教育費をはじめ多くの費用がかかります。特に中学生や高校生になると学校教育費に加え、学校外の教育費用も多くかかってきます。
教育資金の形成を支援してくれる制度は多くありますが、余裕を持って子育てをするためにもある程度の年収が必要になるでしょう。
ここからは、子供を2人育てるために理想的な年収について紹介していきます。
教育費を考慮すると年間100万円以上の貯金が理想
幼稚園から大学まですべて国公立に進学すると仮定した場合でも1,000万円程度は必要です。私立の学校に進学する場合は、さらに費用がかかります。
単純計算で1年に100万円以上貯金するのが理想です。子供が2人いる場合は、倍の費用が必要になるため、年200万円以上は貯金しなくてはなりません。
また、子どもの学費貯金だけでなく、生活費や自分たちの将来に向けた積立などもかかってきます。そのため、生活費など諸々の費用とは別に年100万円以上貯金できるかが大切です。
世帯年収900万円ほどあれば余裕を持てる
厚生労働省の令和4年国民生活基礎調査によると、児童のいる世帯の平均総所得は785万円です。約790万円に対して税金と社会保険料の割合を25%と仮定すると約593万円です。
手取り額から年間100万円を貯金するには、手取りの約18%を貯金に回さなくてはなりません。子供が2人や3人いる場合は、さらに貯金が必要です。これらを踏まえて余裕を持って生活するためには、世帯年収が900万円ほどあるのが理想的でしょう。
また、国公立に通わせたり、奨学金制度を活用したりするなどの工夫も大切です。国の制度などを上手く活用するためにも、事前にリサーチしておくとよいでしょう。

子供が2人いる家庭の平均年収は約750万円

結論から言うと、子供が2人いる家庭の平均年収は約750万円です。
厚生労働省「2022年国民生活基礎調査の概況」によれば、児童のいる世帯の平均総所得は、以下のとおりです。
| 世帯の種類 | 平均総所得 |
|---|---|
| 全世帯 | 545.7万円 |
| 児童のいる世帯 | 785.0万円 |
児童のいる世帯という括りなので、子供が1人だけの場合や3人以上の場合もあります。児童のいる世帯の年収は、全世帯の年収と比べて約235万円多い計算になります。
子供2人を育てるときに考えたいポイント

子供を育てる時に考えたいポイントは様々なものがあります。地域によって子育て支援制度がちがったり、教育の方針だったりなど考えなくてはいけないことは沢山あります。
主に子供を育てる時に考えたいポイントとして、下記の3つを紹介します。
現状と照らし合わせながら将来について考えることが大切です。
住居の場所
1つ目は住居の場所です。地域によって子育てに関連の支援制度が異なり、家庭によって教育観や価値観によって理想とするものは様々です。夫婦ともに納得できる支援が提供されている地域に住むことで、金銭的な負担を抑えられます。
全国の中でも東京都は、0〜15歳の子どもの医療費が無料です。さらに千代田区では、高校生等医療費助成制度を導入しており、高校生も医療費がかかりません。次世代育成手当として月額5,000円の支援を受けられるため、子供にかかる費用の負担を軽減できます。
このような市区町村で行っている子育て支援は、自治体の公式HPやSNS、区報などから確認できます。
教育の方針
子供が幼稚園から大学まですべて公立に通えば金銭的な負担はさほど多くなりません。一方で、私立の学校に通うことになった場合は、想定よりも学費が多くかかってしまうこともあります。
もちろん家計をやりくりすれば私立に通わせることもできます。しかし、子どもの学費を優先することで、生活費が厳しくなったり、自分たちの貯金ができなくなったりすることも少なくありません。そのため、教育方針のなかで重視することを決めておくことが大切です。
公立学校と私立学校にはそれぞれ良さがあり、一概にどちらが良いとは判断できません。子どもの意思が一番ですが、夫婦同士の教育方針をすり合わせおくことで将来の計画がしやすくなるでしょう。
資産の作り方
今の時代は銀行にお金を預けていても増えません。子供が行きたい学校に通わせるためにも貯金だけでなく、投資や節税などマネーリテラシーを高めておくことが大切です。
投資と聞くとハードルが高く、なかなか手を出せない方も少なくありません。取り組みやすい資産運用の1つに「NISA」が挙げられます。金融機関によっては月額1,000円ではじめられるうえに、積立が厳しい月はお休みできたりなど初心者でもはじめやすい傾向にあります。
年金だけでは将来の生活資金に不安があるという方は、現金以外を貯める貯蓄を始めてみてはいかがでしょうか。現在は、勉強をするためのコンテンツも増えているので、知識がないという方でも安心して取り組むことができるでしょう。
また、節税対策も「ふるさと納税」や「生命保険控除」などが注目を集めています。取り組んでいる方も多いため、周囲に相談してみるのもおすすめです。
まとめ:子供2人の貯金は「平均額」と「教育費」を意識して計画的に
この記事では、子供2人を育てる家庭の平均貯金額や教育費の目安、さらに貯め方や制度活用について解説しました。
幼稚園から大学までの教育費は合計で1,000万〜2,000万円にも及ぶため、計画的に積み立てていく必要があります。
将来に向け準備を進める方法をおさらいすると、以下のとおりです。
- 固定費の見直しで支出を抑える
- 児童手当や就学支援金を先取り貯金に回す
- 学資保険や積立預金で強制力を持たせる
- NISAなどで資産を効率的に増やす
子供の進路や生活スタイルに合わせた計画を立て、今日から一歩ずつ積み上げてください。