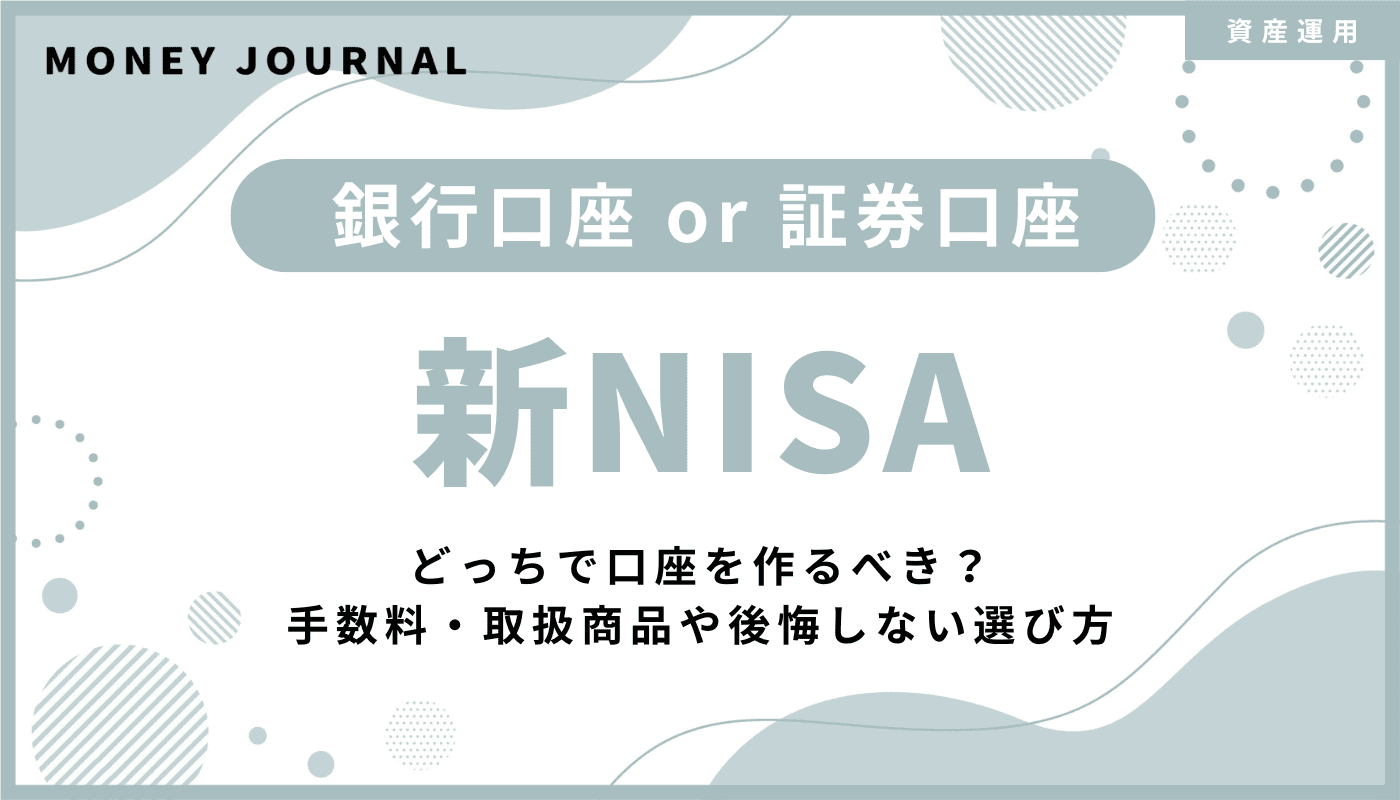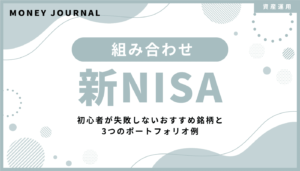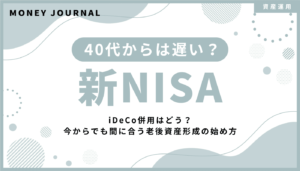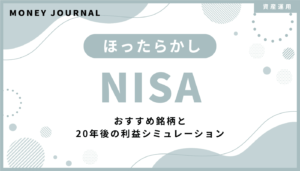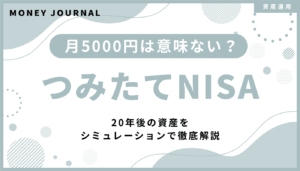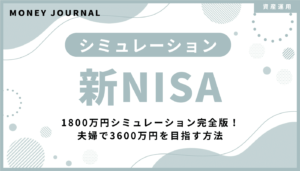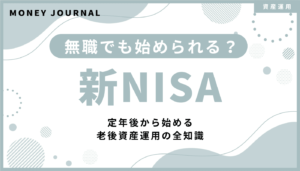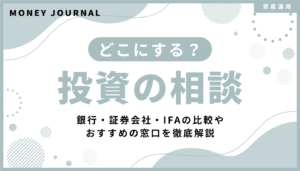- 「新NISAの口座って、銀行と証券会社どっちで作ればいいの?」
- 「銀行で始めてしまったけど、損してないか不安…」
- 「ネット証券が人気と聞くけど、何がそんなに違うの?」
このように考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、新NISAは「証券会社(特にネット証券)」での口座開設がおすすめです。理由はシンプルで、取扱商品の多さ・手数料の安さ・ポイント還元の充実度が圧倒的だからです。
主な違いを一覧でまとめました。
| 比較項目 | 銀行 | 証券会社・ネット証券 |
|---|---|---|
| 取扱商品数 | 限定的(投資信託が中心) | 豊富(投資信託+個別株など) |
| 取引手数料・信託報酬 | 高め | 低コスト中心 |
| サポート体制 | 対面で相談可能 | オンライン中心(チャット・電話対応あり) |
| 積立の柔軟性 | 制限あり(月1回など) | 高い(毎日・毎週積立も可) |
| ポイント還元・クレカ積立 | ほぼなし | 高還元でお得に積立可能 |
本記事では、銀行と証券会社それぞれのメリット・デメリットを中立的に比較し、「どんな人がどちらに向いているのか」まで解説します。
この記事を読めば、銀行・証券会社・ネット証券の違いが明確に分かるようになります。
- 新NISAの銀行・証券会社・ネット証券の違い
- 銀行で始めるメリット・デメリット
- 証券会社・ネット証券で始めるメリット・デメリット
- 後悔しない金融機関の選び方
- 新NISA口座の開設方法と必要書類
- 口座を変えたいときの対処法
新NISAの口座は銀行と証券会社どちらでも開設できる

新NISAの口座は、銀行でも証券会社でも開設できます。一見するとどちらでも同じように見えますが、実際は「できること」と「得られるメリット」が大きく異なります。
ここではまず、非課税枠とつみたて投資枠の基本、そして1人1口座のルールについて整理していきましょう。
新NISAの非課税枠とつみたて投資枠の基本
新NISAは、2024年から制度が大きくリニューアルされました。非課税期間は無期限となり、年間投資上限も合計360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)へと拡大しています。
以下に2つの枠の違いをまとめました。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
| 対象商品 | 投資信託(長期積立向け) | 株式・ETF・投資信託 |
| 投資スタイル | コツコツ積立 | 幅広く投資 |
| 向いている人 | 投資初心者・安定重視派 | 株にも挑戦したい人 |
銀行では投資信託のみ取り扱うことが多いため、株式やETFを買いたい場合は証券会社口座が必要です。自分の目的に合わせて、2つの枠を上手に使い分けましょう。
1人1口座のルール
新NISA口座は1人につき1つしか持てません。また、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で開くこともできません。たとえば「つみたて投資枠を銀行」「成長投資枠を証券会社」で運用することは制度上NGです。
変更時に気をつけたいポイントは次のとおりです。
- 同じ年のうちに2つの金融機関で買付すると制度違反になる
- 変更手続きは年末ではなく早めに行う
- 新しい金融機関での買付は翌年1月から可能
このルールを知らずに手続きを進めると、買付停止期間が発生して投資の機会を逃すおそれがあります。「どの金融機関にするか迷っている」「やっぱりネット証券に変えたい」という方は、手続きできる時期をしっかり確認しておきましょう。
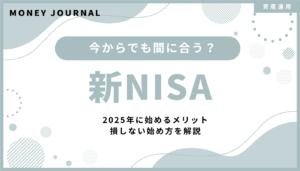
銀行・証券会社・ネット証券の違い|新NISAに最適なのは?

新NISAにおける銀行・証券会社・ネット証券の違いは以下のとおりです。
| 項目 | 銀行 | 証券会社(店舗型) | ネット証券 |
|---|---|---|---|
| 取扱商品 | 投資信託のみ | 個別株やETFなど幅広い | 国内外の株・投資信託・REITまで対応 |
| 手数料 | 高め | 高め | 無料〜安価 |
| サポート | 店頭で相談できる | 専任担当が対応 | オンラインツール中心 |
| 利便性 | 店舗への来店が必要 | 店舗への来店が必要 | 申し込みから運用まで全てWEBで完結 |
| 最低投資額 | 高め | 高め | 100円から可能 |
| ポイント制度 | なし | ほぼなし | クレカ積立でポイント還元あり |
ネット証券は、コストを抑えながら幅広い商品に投資したい人に向いています。少額から始めたい人や、クレジットカード積立でポイントを貯めたい人にも最適です。

銀行で新NISAを始めるメリット・デメリット
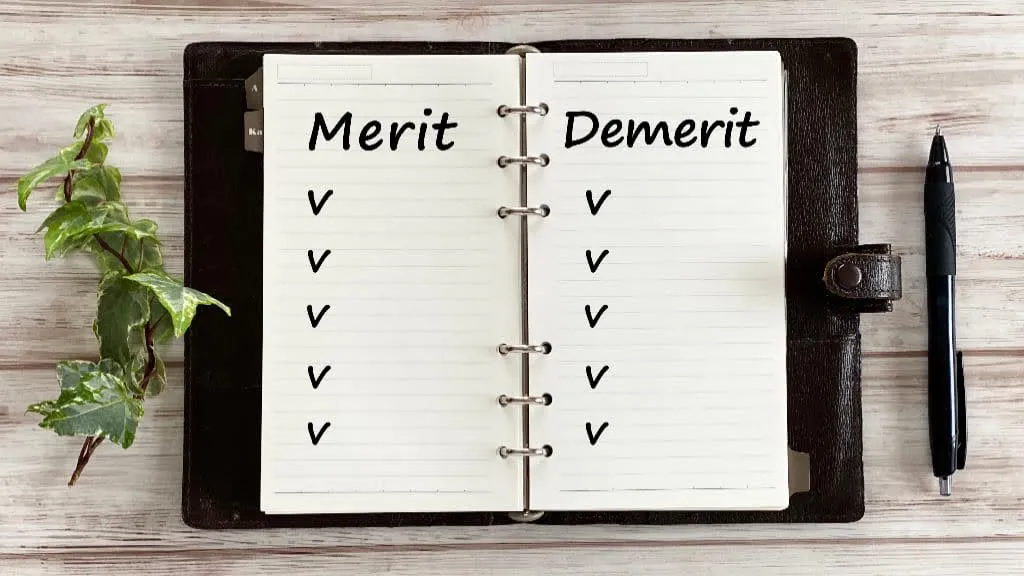
ここでは、銀行で新NISAを始める際のメリットとデメリットを順に見ていきましょう。
銀行で新NISAを始めるメリット
まずは、銀行で新NISAを始めるメリットを4つ解説します。
対面相談ができて安心感がある
銀行の大きな強みは、窓口で担当者に直接相談できることです。「インターネットの情報だけでは不安」「専門家に確認しながら決めたい」という人には、安心して始められる環境といえます。
口座開設や投資信託の選び方に迷ったときも、その場で質問できるため疑問をすぐに解消できます。
ローンや預金とまとめて管理できる
銀行では、預金・ローン・保険・NISAといった金融サービスをひとつの窓口で利用できます。同じ口座でお金の流れを確認できるため、資産全体を把握しやすく家計管理がしやすい点も特徴です。
また、教育資金や住宅ローンの相談とあわせて投資の話を進められるので、将来を見据えたライフプラン設計がしやすくなります。
投資初心者でも始めやすい
銀行で取り扱う新NISA用の投資信託は、種類が絞られており選びやすい構成です。
担当者が書類の確認を一緒に行いながら手続きを進めてくれるため、パソコンやスマートフォンの操作が苦手でも安心して始められます。
売却や積立額の相談も店舗でできるので、相場の変動に焦って判断してしまうリスクを抑えやすい点も安心です。
地方銀行なら地域密着で親身なサポート
地元に根ざした地方銀行は、メガバンクよりも利用者に寄り添った丁寧な対応が魅力です。小さな疑問にも親身に答えてくれる姿勢が評価されており、顔なじみの担当者に相談できる安心感があります。
ただし、全国展開している銀行に比べて投資信託の取扱数が少ない傾向があるため、希望する商品があるか事前に確認しておくと良いでしょう。
銀行で新NISAを始めるデメリット
続いては、銀行で新NISAを始めるデメリットを4つ解説します。
取扱商品が少なく株式投資ができない
銀行の新NISAでは、主につみたて投資枠に対応した投資信託のみを扱うケースが多く見られます。商品数は10〜20本ほどに限られ、個別株やETF(上場投資信託)などの成長投資枠で利用できる商品を扱っていないことが一般的です。
株式にも投資したい人は、証券会社で口座を開設する必要があります。また、取り扱う商品が少ないと、運用中に別の投資信託へ乗り換える選択肢が狭まり、分散投資もしにくくなる点にも注意しましょう。
手数料や信託報酬が高めでコストがかさむ
銀行で扱う投資信託は、信託報酬(運用中にかかる管理費)が証券会社より高い傾向があります。
信託報酬は毎年かかる費用のため、長期で積み重なると運用成績に大きな差が生まれる点に注意が必要です。
積立頻度と最低金額に制限が多い
銀行では、積立の頻度を毎月1回に限定しているケースが多く見られます。最低積立金額も1,000円〜1万円とやや高めに設定されており、少額から柔軟に投資したい人には使いにくい面があります。
一方、ネット証券では100円から毎日や毎週の積立が可能で、自分のペースに合わせた投資ができます。少額でコツコツ積み立てたい人や、生活リズムに合わせて資産を増やしたい人にとって、銀行の積立条件はやや不自由です。
ポイントサービスやクレカ積立が利用できない
銀行の新NISAでは、クレジットカード積立やポイント還元に対応していないケースがほとんどです。投資信託を購入してもポイントが貯まらないため、お得に資産を増やしたい人には魅力が少ないと感じられるでしょう。
一方、証券会社では、積立金額に応じて1〜3%のポイントを付与するサービスを導入している場合があります。この差は1回あたりは小さくても、年間を通して見ると無視できない金額になります。

証券会社・ネット証券で新NISAを始めるメリット・デメリット

ここからは、証券会社で新NISAを始める際のメリットとデメリットを整理していきます。
証券会社・ネット証券で新NISAを始めるメリット
証券会社・ネット証券で新NISAを始めるメリットは、次の4つです。
豊富なラインナップと個別株投資が可能
証券会社では、つみたて投資枠で購入できる投資信託の本数が200本以上そろっています。SBI証券では約271本、楽天証券では200本以上と、銀行の数十倍にあたる品ぞろえです。
さらに、成長投資枠では個別株やETF(上場投資信託)も購入できるため、分散投資・高配当株・インデックス連動型など幅広い運用が可能です。
参考:SBI証券「NISAで買える商品」
参考:楽天証券「つみたて投資枠」
低コスト・少額投資・積立頻度の自由度
ネット証券では、購入手数料が無料の投資信託が多く、信託報酬も銀行より低く設定されています。最低積立金額は100円から1円単位で設定可能で、毎日・毎週・毎月など積立のタイミングも自由に選べます。
たとえば、毎日100円ずつ積み立てることで相場の上下を平均化する「ドルコスト平均法」を自然に実践できます。
ポイント還元やクレカ積立でお得に積立
クレジットカード積立(クレカ積立)に対応している証券会社を利用すれば、投資と同時にポイントを貯められます。
SBI証券では三井住友カードで最大3%、楽天証券では楽天カードで最大1%のポイントが付与されます。
ネット証券の操作性と情報量の豊富さ
ネット証券は、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも取引できる手軽さが魅力です。アプリの操作性が高く、チャート分析・銘柄検索・自動積立設定など多くの機能を直感的に使えます。
さらに、初心者向けの動画セミナー・専門家によるレポート・最新のマーケットニュースなども無料で閲覧可能です。
証券会社・ネット証券で新NISAを始めるデメリット
証券会社・ネット証券で新NISAを始めるデメリットは、次の3つです。
商品数が多すぎて選べないこともある
対象商品の選択肢が多いことは利点ですが、投資対象やリスクの違いを理解して選ぶ必要がある点はデメリットです。
「どの投資信託を選べばよいかわからない」と悩む人は、金融庁や証券会社が公開している人気ランキング、または長期運用に向いたインデックス型ファンドを参考にすると選びやすくなります。
サポートがオンライン中心で対面相談ができない
ネット証券は店舗を持たないため、サポートはチャット・メール・電話が中心です。銀行のように、担当者と直接顔を合わせて相談することはできません。
そのため、操作に不慣れな人や投資判断を相談しながら決めたい人にとっては、不安を感じる場面もあります。
取引や情報管理は自己責任
証券会社での取引は、自分で情報を集め、判断し、行動することが前提です。株式やETF(上場投資信託)は値動きが大きく、元本を下回るリスクもあります。
さらに、注文内容の入力ミスや発注間違いも自己責任となるため、取引前の確認を徹底する意識が欠かせません。安心して取引を行うためには、NISAや投資信託の仕組みを学び、自分のリスク許容度を理解しておくことが大切です。
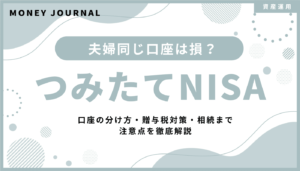
新NISAで後悔しない金融機関の選び方

新NISAを始める際に、最初に悩むのがどの金融機関で口座を開くかです。ここでは、金融機関を選ぶ際に確認すべき3つの視点を解説します。
コスト(手数料・信託報酬)を最優先にする
長期投資で成果を上げるために、最も大きな影響を与える要素がコストです。年率0.1%の違いでも、20年・30年と積み立てを続けると最終的なリターンに大きな差が生まれます。
NISAを含む投資で発生する主なコストは次のとおりです。
| コストの種類 | 内容 | 傾向 |
|---|---|---|
| 売買手数料 | 株式や投資信託の売買時にかかる費用 | ネット証券では新NISAの売買手数料が無料のところが多い |
| 信託報酬 | 投資信託を保有している間に発生する運用管理費 | 銀行などの対面型は高め、ネット証券は低水準が主流 |
| 購入時手数料 | 投資信託を購入するときにかかる費用 | 「ノーロード投信(購入手数料無料)」を選ぶと効率的 |
運用の自由度と取扱商品数をチェックする
新NISAは、利益が非課税になる貴重な投資制度です。せっかく始めるなら、自分の投資スタイルに合った商品を自由に選べる環境を整えることが大切です。
一方で、成長投資枠では金融機関によって取扱商品の幅に大きな違いがあります。
- 国内株・外国株
- 投資信託・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)
- 米国株や全世界株などの海外銘柄
ネット証券ならスマートフォンやパソコンから取引ができ、積立金額や頻度も自由に設定できます。「平日は忙しいけれど、週末に投資を見直したい」といったライフスタイルにも対応可能です。
将来の成長投資枠・株取引も見据えて選ぶ
新NISAを「つみたて投資だけの制度」と考えるのはもったいないことです。将来的に株式やETF(上場投資信託)へ投資したい人は、成長投資枠も利用できる金融機関を選んでおくことが大切です。
確認しておきたい主なポイントは次の3つです。
- 個別株やETFの取扱銘柄数
- 売買手数料の水準
- 海外株式の取扱有無
さらに、金融機関の変更は1年に1回しかできません。「別の証券会社に乗り換えたい」と思っても、すぐには移動できないためご注意ください。

新NISA口座の開設方法と必要書類

新NISAを始めるには、まず口座を開設する必要があります。手続きは思っているほど難しくなく、ネット上で完結できる金融機関も増えています。
ここでは、初めての方でも迷わず進められるように、口座開設の流れを順番に解説します。
金融機関を選ぶ
最初に、NISA口座を開設できる証券会社や銀行の中から1社を選びます。商品数・手数料・使いやすさを比較し、自分の投資スタイルに合う金融機関を見つけましょう。
口座開設の申し込みをする
金融機関を決めたら、公式サイトや店舗で口座開設の申し込みを行います。証券口座や投資信託口座を同時に開設し、その中で新NISA口座の利用申請を行います。
オンラインであれば、スマートフォンやパソコンから数分で申し込みを完了できます。
本人確認書類とマイナンバー確認書類を提出する
本人確認のために、身分証明書とマイナンバーの確認書類を提出します。提出方法は2通りあり、スマホで撮影してアップロードする方法と、郵送で書類を送る方法があります。
審査を受ける
申し込み後は、金融機関と税務署による審査が行われます。内容に問題がなければ、NISA口座の開設が完了します。
オンラインで手続きを行った場合は、数日で完了するケースもありますが、通常は1〜2週間ほどが目安です。審査の進捗状況は、マイページや登録したメールで確認できます。
取引開始
審査が終わると、いよいよ取引を始めることができます。積立設定や投資信託の購入を行い、自分のペースで運用をスタートしましょう。
新NISAの口座選びで後悔している人向けの対処法

新NISAでは、金融機関を1年に1回だけ変更できます。すぐに乗り換えることはできませんが、手続きの流れを知っておけば翌年から移行できます。
変更の手順は、現在利用している金融機関に「金融機関変更届出書」を提出し、税務署の確認を経て完了する流れです。すでに購入済みの投資信託や株式は旧口座で非課税のまま保有できるため、運用中の商品が無駄になる心配はありません。
新NISAの銀行・証券口座に関するよくある質問

新NISAの銀行・証券口座に関するよくある質問は以下のとおりです。
管理手数料はどれくらいかかる?
新NISA制度では、口座管理手数料はかかりません。購入時の手数料も原則として無料ですが、投資信託を保有している間は「信託報酬」と呼ばれる運用コストが発生します。信託報酬は商品によって異なり、銀行よりも証券会社の方が低く設定されています。
主な手数料の種類は以下のとおりです。
| 手数料の種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 売買手数料 | 投資信託や株式を購入・売却するときの費用 | 新NISAでは無料が一般的 |
| 信託報酬 | 運用管理にかかる費用 | 年率0.1%の差でも長期では大きな影響 |
| 管理手数料 | 口座の維持や管理にかかる費用 | NISAでは発生しない |
NISA口座を複数の金融機関で開設できる?
NISA口座は、1人につき1口座のみ開設可能です。「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を別々の金融機関で持つこともできません。
ただし、翌年に1回だけ金融機関を変更する手続きが認められています。変更を希望する場合は、現在の口座の取引を止めずに準備を進めることが可能です。
ただし、金融機関の変更手続きには1〜2ヶ月ほどかかるため、余裕を持って進めましょう。今の金融機関に不満がある場合は、変更時期や翌年の投資計画を含めて慎重に検討することが大切です。
結局どこがいいの?
金融機関の選び方は、何を重視するかによって変わります。相談のしやすさや安心感を求める人は銀行、コストや利便性を重視する人は証券会社を選ぶのがおすすめです。
金融機関選びで重視したいポイントは以下のとおりです。
| 重視したい点 | 向いている金融機関 | 理由 |
|---|---|---|
| 対面相談・サポート | 銀行 | 店舗で担当者の説明を受けながら進められる |
| 手数料・商品数 | ネット証券 | 低コストで幅広い銘柄を取り扱っている |
| ポイント還元 | ネット証券 | クレジットカード積立などでポイントが貯まる |
| 管理の一元化 | 銀行 | 預金やローンとまとめて資産を把握できる |
投資スタイルに合わせて、自分にとって使いやすい金融機関を選ぶことが大切です。迷ったときは、取扱商品数・信託報酬・ポイント制度の3点を比較することをおすすめします。
銀行と証券会社どっちが安全?
安全性に大きな差はないため、金融機関を選ぶときは手数料やサービス内容を基準に考えるのが現実的です。
また、NISA口座を扱う銀行や証券会社は、すべて金融庁の監督下にある金融機関です。NISAで保有する投資信託や株式などの資産は「信託保全制度」により分別管理されており、金融機関の財産とは切り離して保管されています。万が一金融機関が破綻しても、NISA口座の資産自体が失われることはありません。
ただし、投資商品の値動きによる損失は保護の対象外です。市場の変動で資産価値が下がる場合もあるため、投資判断は自己責任で行う必要があります。
ネット証券でもサポートはある?電話・チャット体制は?
ネット証券でも、しっかりしたサポート体制が整っています。SBI証券や楽天証券では、電話・チャット・メールでの問い合わせに対応しており、初心者向けのオンライン相談窓口も利用できます。
画面を共有しながら操作方法を説明してもらえる場合もあるため、店舗がないから安心できないというわけでは決してありません。
マイナンバー提出はオンラインで完結できる?
はい。スマートフォンやパソコンで撮影した画像をアップロードするだけで手続きが完結します。マイナンバーカードを持っていない場合でも、通知カードと本人確認書類(運転免許証など)の組み合わせで提出可能です。
オンライン提出は郵送よりも処理が早く、最短で申し込みから数日で口座開設が完了します。時間をかけずに始めたい人は、オンライン提出を選ぶとよいでしょう。
新NISAを銀行で始めたけど後から変えられる?
金融機関の変更は、年に1回だけ可能です。現在利用している銀行で「金融機関変更届出書」を提出し、翌年から新しい証券会社で新NISAを利用できます。
これまでに購入した投資信託は旧口座で非課税のまま保有できるため、運用を中断せずに切り替えられます。「銀行からネット証券へ移したい」と考えている方も、積立を止めずにスムーズな移行が可能です。
手続き中は投資できないって本当?切り替え期間とは?
金融機関の変更手続き中は、新しいNISA枠を使った投資が一時的に停止されます。税務署の承認を待つ期間にあたるもので、通常は1〜2ヶ月ほど要します。
ただし、すでに保有している投資信託の運用や売却は継続可能です。翌年の積立を滞りなく再開したい場合は、秋頃までに変更手続きを済ませておくとよいでしょう。
まとめ
この記事では、新NISAを銀行と証券会社のどちらで始めるべきかを整理しました。
取扱商品・コスト・ポイント制度を重視する人には証券会社(特にネット証券)が有利です。少額投資やクレジットカード積立など、自由度の高さが魅力といえるでしょう。
一方で、対面で相談したい人や操作に不安がある人には、銀行が向いています。
どちらを選ぶ場合でも、次の3つの比較ポイントを意識して確認することが大切です。
| 比較ポイント | チェック項目 | 目安 |
|---|---|---|
| 手数料・信託報酬 | コストを抑えられるか | 年率0.3%以下が理想 |
| 取扱商品数 | 成長投資枠に対応しているか | 株・ETF・海外銘柄の有無 |
| サポート体制 | 自分の性格や知識に合っているか | 対面 or オンライン中心 |
「銀行で始めたけれど、やはりネット証券に変えたい」と感じた場合は、翌年に金融機関を変更する手続きが可能です。まずは少額から始め、比較しながら自分に合った金融機関を見つけていきましょう。