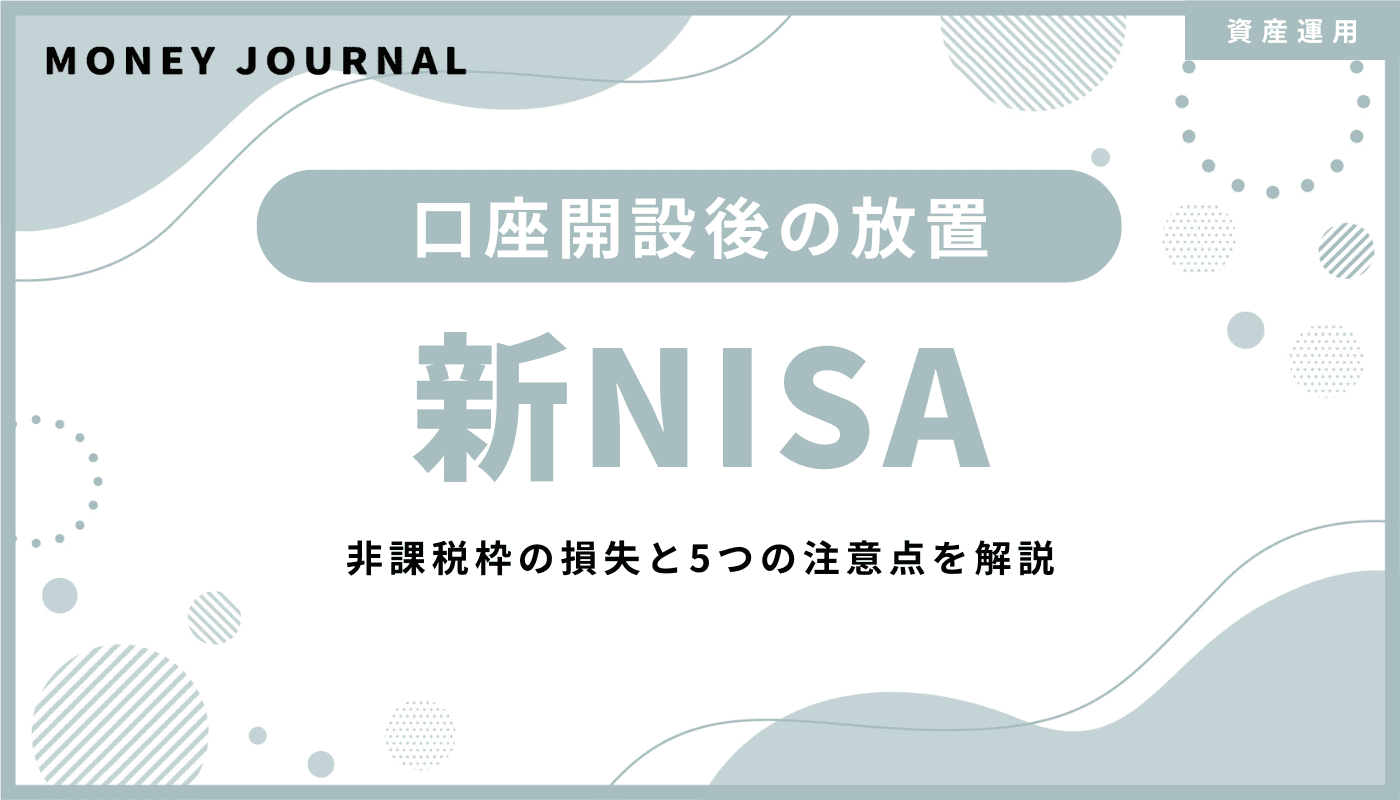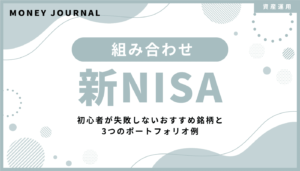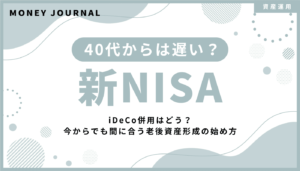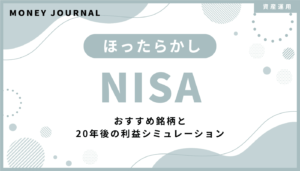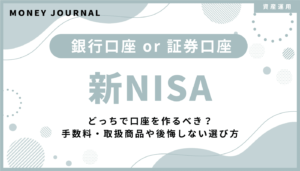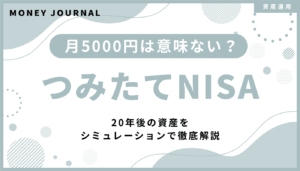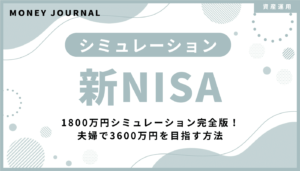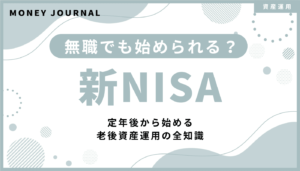- 「とりあえず新NISAを開設だけして放置している…」
- 「何に投資していいか決められずそのまま…」
- 「新NISAは“放置でも問題ない”と思い込んでいた…」
このように考えている方もいるでしょう。
新NISAは口座開設のみで何もせずに放置していると、次のような損が発生します。
- 非課税の年間投資枠が消滅
- 複利運用のスタートが遅れる
- インフレで資産が目減り
本記事では、新NISA口座を放置することで起こる具体的な損失をはじめ、なぜ多くの人が動けずに放置してしまうのか、そこから抜け出すための簡単なステップを投資初心者向けに解説します。
「何を買えばいいかわからず動けない…」という方は、ぜひ参考にしてください。
新NISAを口座開設後に放置するとどうなる?

新NISAを使わずに放置すると、実際には損が静かに進行している状態です。非課税枠を使わなかったら翌年に繰り越せず、投資をしなければ資産も増えません。
ここからは、新NISAをほっとくとどうなるのかを解説していきます。
放置しても手数料はかからないが何も得られない
新NISAを口座開設後に放置すると、費用はかかりませんが何も増えません。
SBI証券や楽天証券をはじめ、主要な証券会社では口座開設・維持に手数料は一切かかりません。そのため「損していないから問題ない」と思ってしまうものですが、それは大きな誤解です。
行動しなかったことで、「資産を育てられたかもしれない数年間」を失っていることが、新NISAを放置する最大の損です。
非課税枠は使わなければその年限りで消滅
新NISAは毎年360万円の非課税枠(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)が与えられますが、未使用分は翌年に繰り越せません。
つまり、2025年に成長投資枠を1円も使わずに放置してしまった場合、その240万円分の非課税投資枠は2025年末で失効します。翌年には新たな360万円分の枠が用意されますが、前年分の未使用分を翌年にまとめて使うといったことは制度上できません。
たとえ月1万円の少額投資であっても、非課税で積み上げた年数の差が、10年後には数十万円~100万円以上の違いになる可能性があるのが新NISAの特徴です。
制度改正を見逃し、損失リスクに気づけない
新NISAを放置していると、制度変更の通知や重要なお知らせを見逃すリスクがあります。
NISA制度はこれまでも内容が改正されており、旧制度では「ロールオーバー制度の廃止」など、非課税運用に直結する重要な改正が行われてきました。
通知は、証券会社の管理画面や登録メールアドレス宛に届くのが一般的です。
その結果、自分の資産がどのような扱いを受けているのか把握できず、制度改正の影響を受けていても気づけないというリスクが生じます。
実際、旧NISAでは非課税期間終了後に資産が自動的に課税口座へ移される仕組みがありました。このことに気づかず運用を続けた結果、想定していなかった課税(約20%)が発生してしまった、という事例も少なくありません。
大切なお金を守るためには、少なくとも通知が届く状態を維持し、定期的に口座の状況を確認することが大切でしょう。

新NISAの非課税枠を放置した場合の損失
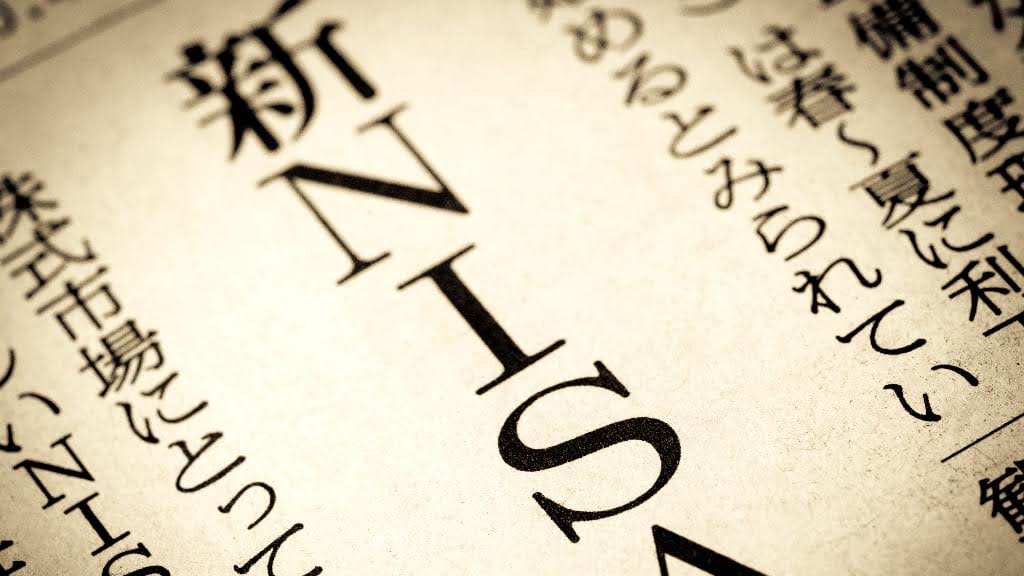
新NISAは「使ってこそ価値がある制度」です。口座を開設しても投資を始めなければ、非課税という強力なメリットは一切活かせません。
中でも怖いのは、金額的な損だけでなく「複利効果」や「インフレ対策」といった、時間を味方につける力を失ってしまうことです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
複利運用できないと老後資産の伸びが激減する
新NISAを口座開設後に放置すると、本来得られるはずだった運用期間と複利効果の両方を失います。
以下に、投資スタートの時期によってどれだけ差がつくかを具体的に示します。
▼想定利回り3%の新NISA運用シミュレーション
| 月1万円×20年 | 約328万円(運用益約88万円) |
|---|---|
| 月1万円×10年(開始が10年遅れ) | 約140万円(運用益約20万円) |
つまり、投資金額は変わらなくても、「始める時期の差」が最終的な差を大きく広げてしまうのが長期投資の世界です。
インフレで実質資産が目減りし続ける
新NISAを活用せずに資産を現金のまま置いておくと、インフレによってお金の価値が目減りする可能性があります。
仮に毎年2%のインフレが続いた場合、10年後には100万円の価値が実質で約82万円にまで下がります。これは何もしていないつもりでも「18万円分を失っている」のと同じ状態です。
一方、新NISAを活用して株式や投資信託といった「インフレに強い資産」で運用すれば、物価上昇に資産価値が追いつく、または上回る可能性があります。
つまり、新NISAはインフレ対策にもなる制度なのです。使わずに放置している間に、現金だけが静かに減っていく状況を避けるためにも、将来に向けて資産を守るための行動を検討することが大切です。
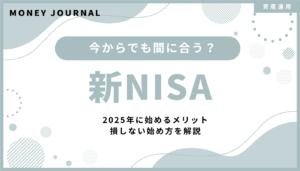
新NISAをなぜ放置してしまうのか?心理的ハードルを解説
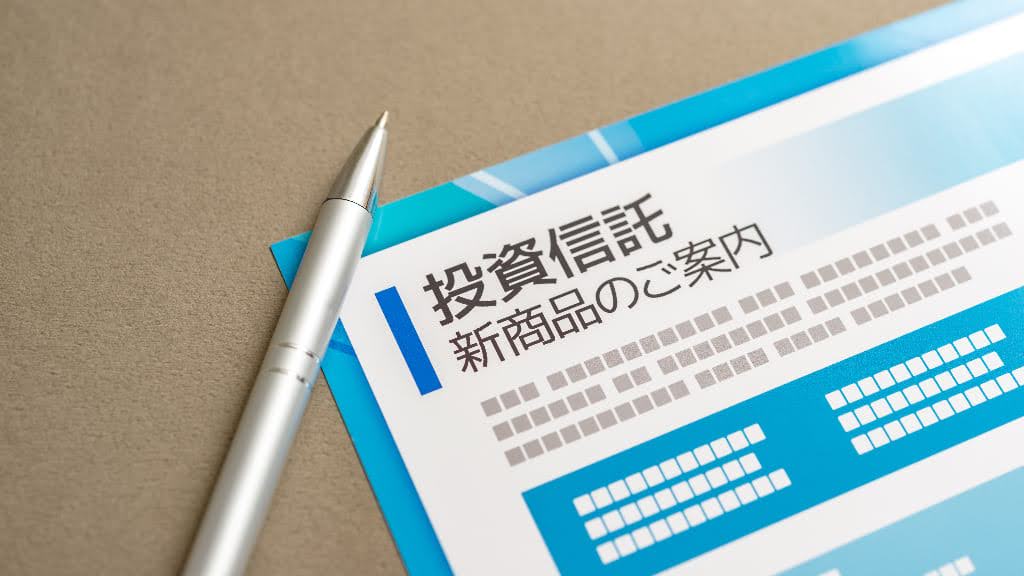
「新NISAを開設したものの、いつの間にか放置してしまっている…」という放置の背景には、次のような心理的な要因が隠れています。
投資に慣れていない人ほど、このような始めにくさに悩まされています。ここでは、よくある放置の原因とその乗り越え方を具体的に解説していきます。
「何を買えばいいかわからない」から行動が止まる
新NISAの口座を開設したあと、「さて何を買えばいいのか?」と迷ってしまい、そのまま放置してしまう人は少なくありません。
この選べない状態は、「損をしたくない」「間違いたくない」という心理からくるものです。結果として、最初の購入に踏み切れないまま数ヶ月〜数年が過ぎることになります。
最初から完璧な銘柄を選ぶ必要はありません。たとえば、以下のような導入が初心者にはおすすめです。
- 投資信託の人気ランキングを参考にする
- 自分のリスク許容度に合った商品ナビを使う
- 月1万円から投資信託を自動積立で始めてみる
SBI証券や楽天証券では初心者向けサポートが充実しているため、「わからないから止まる」状態から抜け出せることでしょう。
自動積立を設定しないと投資のリズムが作れない
投資は「始めること」も大事ですが、それ以上に「続ける仕組み」がないと意味がありません。そして放置されやすい理由のひとつが、自動積立の設定をしていないことです。
新NISA口座を開設しても、毎月の買付を手動で行うスタイルだと、次のような事態が起こりやすくなります。
- 「買うのを忘れた」と月末に気づく
- 相場の上下が気になって買えなくなる
- 手間がかかって、だんだん面倒になる
こうした心理的ブレーキをすべて取り除いてくれるのが「自動積立」です。月100円からの自動積立に対応している証券会社もあり、銀行口座だけでなくクレジットカードからの引き落とし設定も可能です。
自動化しておけば生活リズムに関係なく投資が継続され、心理的なブレーキを排除できます。
旧NISAの経験から「放置でもOK」と誤解しがち
旧NISA(2014〜2023年)を利用していた方の中には、「とりあえず買って放置しておけば大丈夫」という感覚が残っている方が多いでしょう。
たしかに旧制度では、5年間の非課税期間が終わった後でも「ロールオーバー」によって継続保有ができたため、深く管理しなくても制度面である程度カバーされていました。
しかし、新NISAは仕組みが大きく変わっています。非課税期間が無期限になった一方で、「使わなかった枠は翌年に繰り越せない」という重要なルールがあります。つまり、「今は投資しないけど、いつかまとめて使えばいい」という考えは通用しません。
さらに、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が併存しているため、自分がどちらを使っているのかを把握しないまま放置してしまうと、気づかないうちに非課税枠を失ってしまうこともあります。
もちろん、買った資産を長期で持ち続ける投資の放置自体は悪いことではありません。ただし、「制度の仕組みを理解せずに放置する」ことが損失につながるのです。

新NISAの放置を続けると起こる制度的なリスクとは?
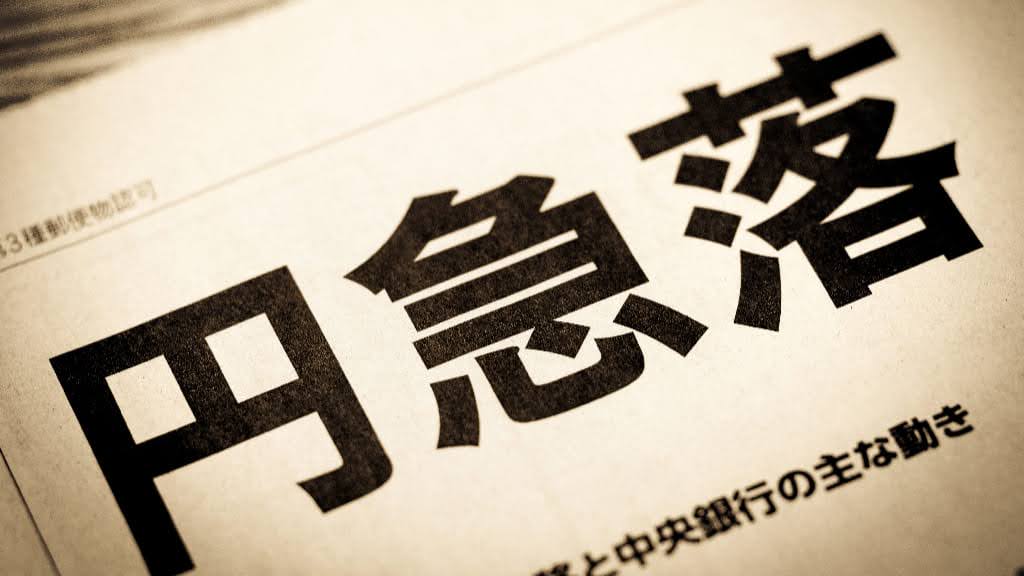
新NISAを口座開設したまま放置していると、以下のような不都合が起こる可能性があります。
証券会社によっては5年放置で利用制限されることも
新NISAを放置し続けると、証券会社の運用ルールによっては口座が「非アクティブ」とみなされ、ログイン制限や一時的な利用停止の対象になることがあります。
たとえば次のようなケースです。
- 5年以上取引やログインの履歴がない
- 登録した住所が変更されていて、郵便物が届かない
- マイナンバーの登録が完了していない、または更新が必要
このような状態が続くと、証券会社からの通知を見逃してしまい、再開時に再申請や書類の提出が必要になることも。制度自体は無料で使えますが、「使わずに放置しておけば安心」というわけではありません。
大切なお金を預けている口座です。年に数回でもログインし、登録情報に変更がないか確認する習慣を持つことをおすすめします。
資産管理を怠るとリスク許容度が崩れる
新NISAで何らかの金融商品を購入したあと、そのまま“買いっぱなし”で放置し続けていると、知らない間にリスクバランスが崩れてしまうことがあります。
投資信託や株式は常に価格が変動します。価格の変動によって知らないうちに配分が偏ってしまうのが特徴です。これにより、
自分ではリスクを抑えているつもりでも、知らないうちにハイリスクな運用になっていることがあるため、少なくとも年に1回は確認しておきましょう。
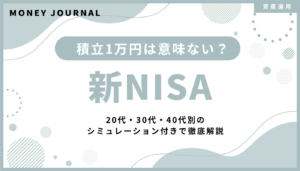
今からでも間に合う!放置状態からの脱出ステップ

新NISAを放置していた方でも、今からの行動で非課税の恩恵を取り戻すことは可能です。いつまで放置するか決められず迷っているなら、まずは「面倒に感じない仕組み」を先につくることが大切です。
投資において最も失いやすいのはやる気ですが、仕組みさえ整えておけば、気分に左右されずに資産形成を続けられます。
本章では、投資を習慣として生活の中に組み込められる方法を3つ紹介します。
少額×自動積立の設定だけでほったらかし運用が完成
新NISAを再開するなら、まず最初におすすめなのが「自動積立の設定」です。
一度仕組みを整えてしまえば、あとは毎月決まった金額が自動で投資に回されるため、手間をかけずに資産形成を続けられます。
「やる気が出たときだけ頑張る」のではなく、「やらなくても続く状態をつくる」。このスタンスが、投資を無理なく習慣にする大きなポイントといえるでしょう。
証券会社のロボアドや投信ランキングを活用する
口座開設後の始め方に迷う方は、証券会社が提供しているサポートツールを活用するのがおすすめです。
たとえば、以下のような便利なサービスが用意されています。相場の上下が気になって買えなくなる
| ツール | 内容 |
|---|---|
| 自動診断(ロボアドバイザー) | 簡単な質問に答えると、自分に合った運用プランを提案してくれる |
| 人気ランキング | つみたてNISAや一般の投資信託で、現在多く選ばれている商品が一覧で見られる |
多くの人がつい迷ってしまうのは、「この選択で本当にいいのか」と不安になるからです。ですが、自動診断や売れ筋の投資信託を参考にすることで、実績のある商品を選びやすくなります。
大切なのは、完璧を目指すことではなく、「続けられる仕組み」をつくること。選ぶ負担をツールに任せてみるだけで、投資の再スタートが気楽なものになるでしょう。
家計簿アプリと連携して資産管理を習慣化する
自動積立の設定が終わったら、次に意識したいのが「投資を忘れずに続ける仕組み」です。そのサポートとして便利なのが、家計簿アプリとの連携です。
スマホひとつで、日常生活の中に投資チェックの習慣を自然に取り入れられます。
代表的な家計簿アプリには、次のようなものがあります。
| アプリ名 | 特徴 |
|---|---|
| マネーフォワード ME | 複数の証券口座を一括管理でき、資産の推移グラフも見やすい |
| Zaim | 収支と資産残高をまとめて確認でき、通知機能も充実 |
さらに、連携しておくと以下のような通知も受け取れます。
- 保有ファンドが大きく値下がりしたとき
- 評価額が一定以上増えたとき
- 積立日が近づいたとき
投資を特別なものではなく、日常の一部として意識付けしていきましょう。
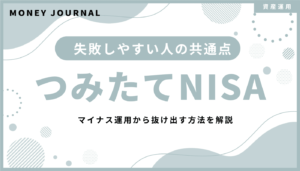
それでも使わないなら、口座を解約する選択肢も

投資は無理に続けるものではありません。もし、今後も使う予定がまったくないと感じているなら、いったん解約してしまうのも一つの方法です。
ここでは完全に使わない場合の最終対応として、解約の考え方や手続き方法を解説していきます。
「口座開設しただけ」のままなら影響は限定的
新NISA口座を作っただけで一度も取引していないなら、金銭的なデメリットは発生していません。一度も使わない場合でも非課税枠がその年限りで消滅するだけです。
つまり、実際の損失は「使わなかった非課税枠である機会損失」のみです。
以下に、未使用口座の影響をまとめました。
| 状態 | 実際の影響 |
|---|---|
| 取引なし | ペナルティなし/非課税枠だけ失効 |
| 管理費用 | 無料(請求なし) |
| 資産未保有 | 解約は簡単/再開時も比較的スムーズ |
「放置しているのがなんとなく気持ち悪い」「管理が面倒」という場合は、口座を閉じてスッキリさせるのも前向きな判断です。
正式な解約には手続き・書類が必要なので注意
新NISAの解約は、ワンクリックでは終わりません。正式に非課税口座を廃止するためには、証券会社に届け出書類を提出する必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①廃止届出書の提出 | 証券会社のマイページまたは郵送対応 |
| ②本人確認書類の提出 | 免許証・マイナンバーなどが必要なケースも |
| ③廃止通知書の受領 | 解約証明として今後の証券会社提出時に使用 |
「何も持っていないのに解約できない…」とならないように、事前に保有残高の確認もお忘れなく。
一度解約すると再開には時間と労力がかかる
新NISA口座を解約すると、再度口座を開設するには数週間〜1ヶ月ほどの手続きが必要になります。
再開時に必要なプロセスは以下のとおりです。
- 前の証券会社から「非課税口座廃止通知書」を取得
- 新しい証券会社に提出
- 書類審査を経て、新NISA口座が開設される(通常2〜4週間)
この期間は投資ができず、「始めたいのに始められない」状態に陥ります。年の後半など、非課税枠を急いで使いたいタイミングでは大きなロスになるでしょう。
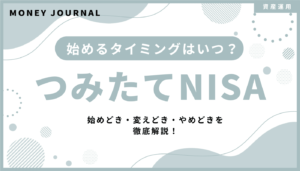
新NISAに関するよくある質問

最後に、新NISAに関するよくある質問と回答を紹介します。
新NISAは“ほったらかし投資”と何が違う?
「ほったらかし投資」とは、自動積立や長期運用によって、手間をかけずに資産を育てていく投資スタイルを指します。新NISAもその運用に適していますが、「口座を開設して放置しているだけ」では“ほったらかし投資”とは言えません。
ほったらかし投資は、最初に商品を選び、積立設定や分散投資を行ったうえで、あえて途中で触らずに運用を任せるのが前提です。
積立停止=口座停止ではないって本当?
はい、本当です。積立を一時的に止めても、新NISA口座そのものが停止・無効になることはありません。積立額を「0円」にしたり、買付設定を解除した状態でも、口座はそのまま有効に維持されます。
一度も使ってない口座は自動で解約される?
新NISAでは、基本的に一度も取引をしていない口座でも自動解約されることはありません。
ただし、次のような場合には解約または利用制限がかかる可能性があります。
- 5年以上取引やログインの履歴がない
- 登録した住所が変更されていて、郵便物が届かない
- マイナンバーの登録が完了していない、または更新が必要
もし解約された場合の対処法や解約方法が気になる場合は、以下の記事も参考にしてください。

利益だけ引き出すことはできる?
はい、できます。新NISA口座で保有している投資信託や株式を一部売却する際、「元本を維持しつつ利益分だけ売却」することが可能です。
放置するくらいならやめた方が良い?
一概には言えませんが、「ずっと使う気がない」「投資に興味が持てない」とはっきりしている場合は、放置せず正式に口座を解約するのも一つの方法です。
忘れていたNISA口座の確認方法は?
自分が過去に開設したNISA口座の有無を確認したい場合は、以下の方法を試してみてください。
- 過去に口座開設した可能性のある証券会社のマイページにログイン
- 「非課税口座」のステータスを確認(保有資産も表示される)
- ログイン情報がわからない場合は、証券会社のカスタマーサポートへ連絡
- 金融機関をまたぐ確認が必要な場合は、税務署に「非課税口座の開設届出状況」の開示請求が可能
他の証券会社に移す場合の注意点は?
新NISAでは、「年度ごとに金融機関を変更すること」はできません。一度その年に買付を行った証券会社からは、その年中は他社へ移れないルールとなっています。
また、翌年に乗り換えたい場合も、以下の手順が必要です。
- 現在の証券会社で「非課税口座廃止届出書」を提出
- 廃止通知書を受け取る
- 新しい証券会社に「非課税口座開設届出書」と併せて提出
- 審査通過後に新NISA口座が開設される(数週間かかる)
まとめ:新NISAは「放置=機会損失」今すぐ行動を
この記事では、新NISAを口座開設後に放置した場合の損失や注意点、今すぐ始められる対策について解説しました。
使わなかった非課税枠は翌年に繰り越せず、複利の効果もなし。制度の仕組みを知らずに放置していると、資産形成どころかリスクの温床になります。
放置による主な損失は以下のとおりです。
- 年間非課税枠の失効(最大360万円)
- 複利効果の損失(数十万~百万円以上の差)
- インフレによる実質的な目減り
- 5年放置で口座に制限がかかる恐れ
「何から始めていいか分からない…」という方こそ、まずは自動化で仕組みを整えて、NISAのメリットをしっかり活かしてください。