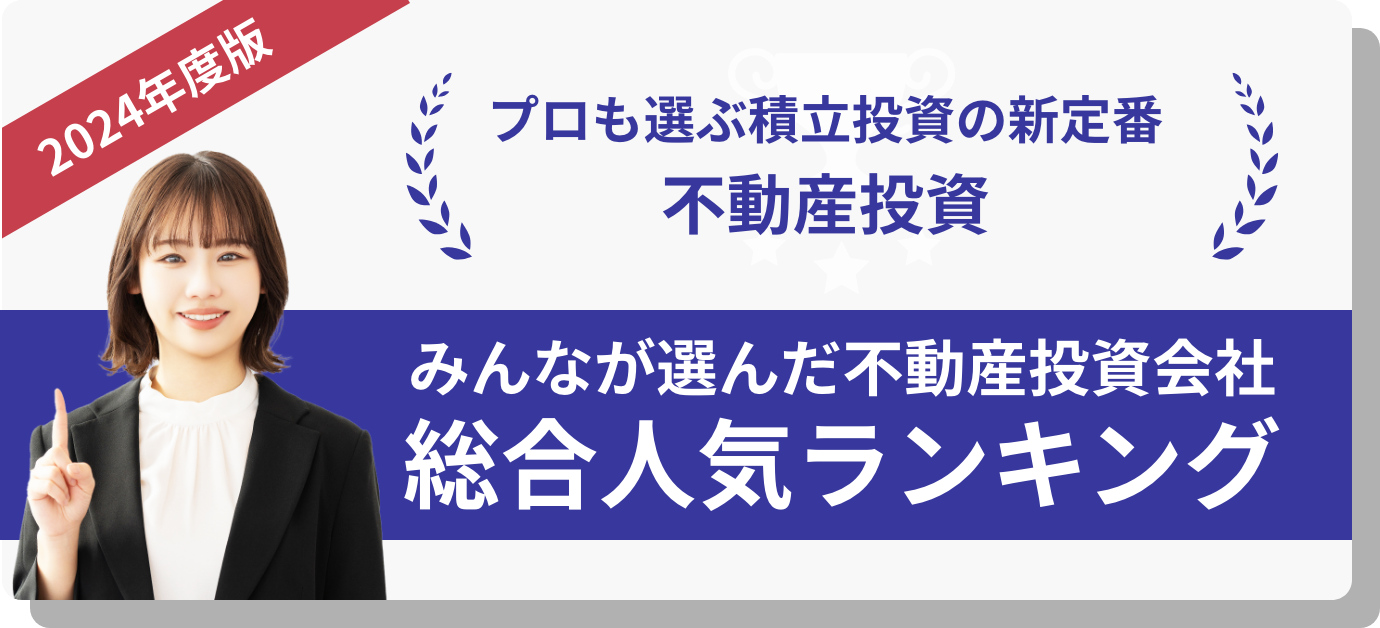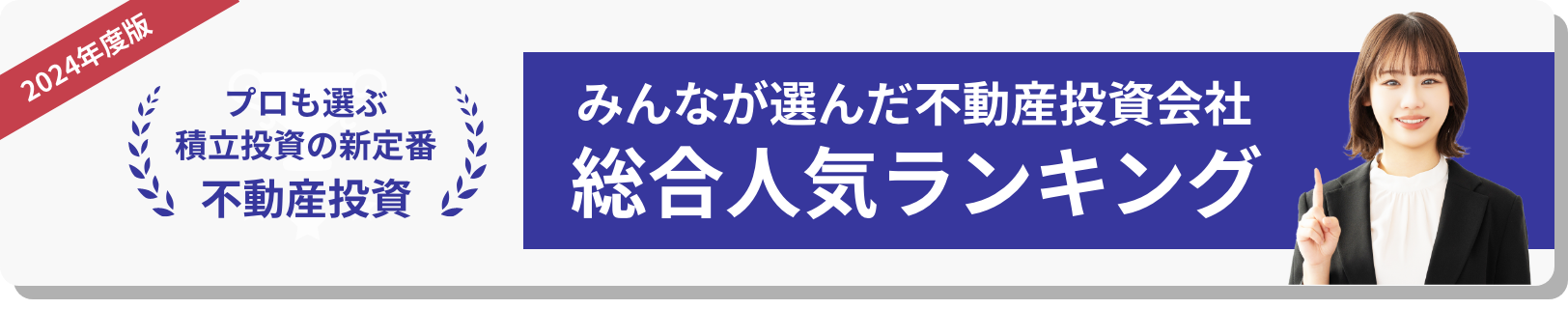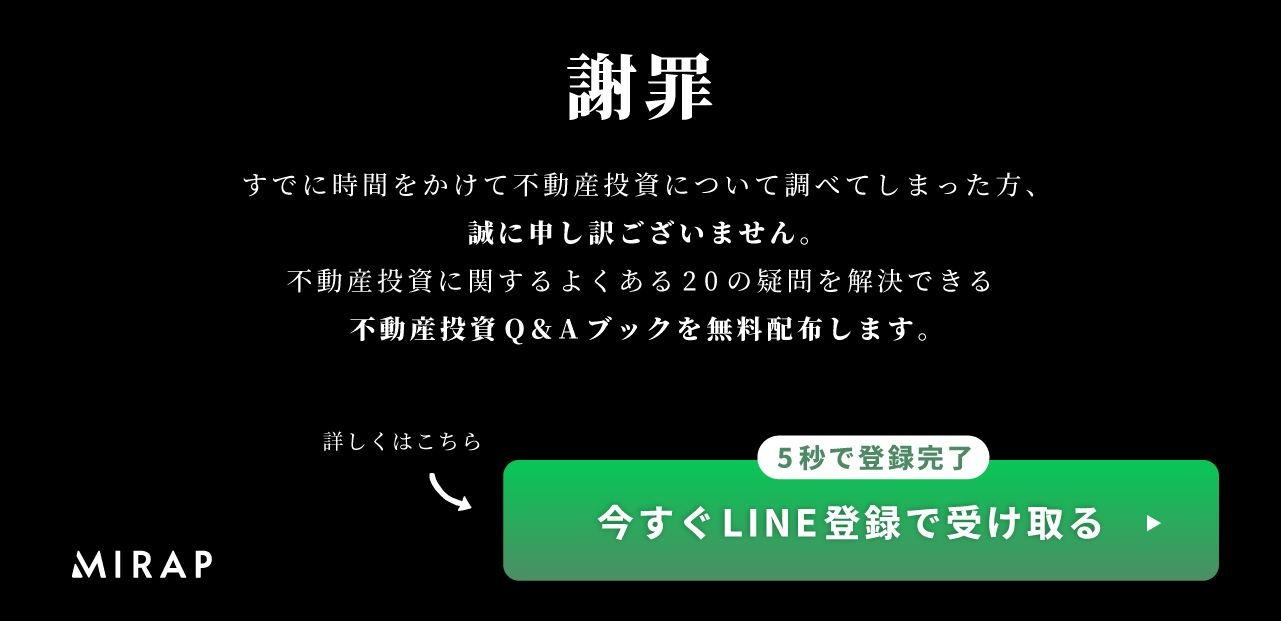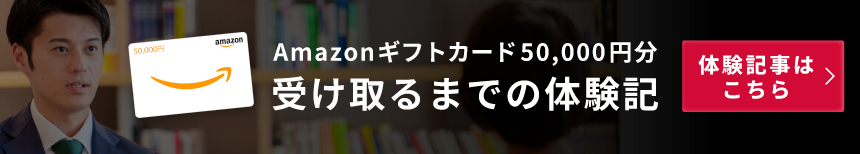近年、不動産投資を始める人の中で「サブリース契約」という言葉をよく耳にするようになりました。
「家賃が保証される」「手間がかからない」といった魅力的な宣伝が多い一方で、「サブリース契約はやばい」と警鐘を鳴らす声も増えています。
この記事では、実際にどんなトラブルが起きているのか、なぜ危険といわれるのか、そしてどうすれば安全に活用できるのかをわかりやすく解説します。


サブリース契約がやばいと言われる理由とは?
サブリース契約とは、不動産会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、入居者に再び貸し出す仕組みのことです。一見すると安心できるように見えますが、実際にはオーナーが不利になる落とし穴があるのです。
家賃が保証されると誤解されやすいから
サブリース契約の広告では「空室でも家賃保証」といった言葉が強調されることが多く、これを「家賃がずっと固定で支払われる」と勘違いしてしまうオーナーが多いのです。
実際には、不動産会社が支払う家賃(いわゆる「保証賃料」)は、契約の途中で減額される可能性があります。
これは、建物の老朽化やエリアの家賃相場の変動に合わせて調整される仕組みであり、オーナーが拒否することは難しいケースもあります。
つまり、「家賃保証」という言葉を鵜呑みにしてしまうと、結果的に想定よりも低い収益になってしまうリスクがあるのです。
契約更新時に家賃が下がることがあるから
サブリース契約では、契約期間が2年や5年などに設定されていることが多く、更新のタイミングで保証賃料が引き下げられることがあります。
これは、不動産会社側が「市場家賃の下落」や「建物の経年劣化」を理由に減額を要求するためです。
オーナーが減額を受け入れなければ、契約解除をちらつかされるケースもあり、実質的に交渉の余地がないというのが現実です。
このように、長期的には安定収入どころか、収益がどんどん減っていくことも珍しくありません。
中途解約が難しくオーナーに不利な契約が多いから
サブリース契約では、途中で契約を解除したいと思っても、オーナー側から一方的に解約できないことがほとんどです。
多くの契約書には、「契約解除は6ヶ月前の通知が必要」や「違約金を支払うこと」といった条項が入っています。
さらに、契約内容によっては、不動産会社が優位に立てるような条件が細かく設定されている場合もあります。
そのため、オーナーが不利な立場になりやすいのがサブリース契約の大きな問題点なのです。
サブリース契約がやばいと感じる人が増えている背景
なぜ近年になって「サブリース契約はやばい」という声が増えているのでしょうか?ここではその社会的背景を見ていきます。
アパート経営のブームで未経験者が増えたから
低金利が続く中で、不動産投資を始める人が急増しました。その結果、知識や経験が浅いままサブリース契約を結ぶオーナーが増加しています。
営業担当者の説明を鵜呑みにして契約してしまい、後から「思っていた話と違う」とトラブルになるケースも多いです。
「家賃保証」や「手間いらず」という言葉に惹かれて契約してしまう初心者が、被害にあうリスクが高いのです。
つまり、サブリースがやばいのではなく、仕組みを理解せずに契約してしまうことがやばいのです。
「30年家賃保証」という宣伝が誤解を招いたから
「30年家賃保証」と聞くと、30年間家賃が固定されて支払われるように感じますよね。しかし、実際には定期的に家賃が見直されるのが一般的です。
この「30年」というのはあくまで契約期間の目安であり、保証賃料がそのまま維持されるわけではありません。
不動産会社が途中で賃料を引き下げたり、契約内容を変更したりすることが可能なのです。
つまり、「30年保証」という宣伝は誇張表現になりがちで、実態とズレがあるということです。
有名な不動産会社のトラブル報道が影響したから
過去には、大手の不動産会社がサブリース契約をめぐって家賃減額トラブルや訴訟問題を起こしています。
オーナーが「契約時に聞いていた条件と違う」「家賃を一方的に下げられた」と主張するケースも多く、不信感を持つ人が増えたのです。
このような事例が広く知られるようになったことで、「サブリース契約は危険」というイメージが定着してしまいました。
サブリース契約は本当にやばい?仕組みをわかりやすく解説
「サブリース契約は危ない」という声は多いですが、仕組みを正しく理解すれば、必ずしも悪い制度ではありません。ここでは、その基本的な仕組みを簡単に解説します。
不動産会社が一括で借り上げて貸し出す仕組み
サブリース契約の基本は、不動産会社がオーナーから物件を一括で借り上げることです。
その後、不動産会社が入居者を募集し、入居者から家賃を受け取ります。
オーナーは、不動産会社に物件を貸している立場になるため、空室があっても一定の家賃(保証賃料)が支払われる仕組みです。
このため、空室の心配を減らせるというメリットがあります。
オーナーと不動産会社の間に賃貸借契約がある
多くの人が誤解していますが、サブリース契約ではオーナーと入居者の間に直接的な契約関係はありません。
オーナーは不動産会社と賃貸借契約を結び、不動産会社がさらに入居者と契約を結びます。
そのため、オーナーは入居者トラブルや管理の手間を負わなくて済むという利点があります。
しかし同時に、家賃の設定や更新条件を不動産会社に握られるというデメリットもあります。
空室リスクを減らせる一方で収益が制限される
サブリース契約は、空室リスクを軽減できる点で魅力的です。しかし、実際にはその分、収益が抑えられてしまうことが多いです。
なぜなら、不動産会社が管理や入居者募集などの手間を引き受ける代わりに、家賃の一部を差し引いてオーナーに支払うからです。
つまり、オーナーが直接貸し出すよりも、手取りの家賃収入は少なくなります。
「安定収入」と「高収益」は両立しにくいのがサブリース契約の現実なのです。
サブリース契約でやばいトラブルが実際に起きた事例
サブリース契約は表面上は安定して見えますが、実際には多くのオーナーがトラブルを経験しています。ここでは実際に報告された具体的な事例を紹介します。
家賃の減額通知が一方的に送られてきたケース
最も多いトラブルが、不動産会社から一方的に家賃の減額通知が届くケースです。
たとえば「周辺の家賃相場が下がったため」「建物が古くなったため」といった理由で、突然保証賃料を20〜30%減らすという通達が届くのです。
オーナーが納得できずに拒否した場合、「契約を更新できません」と告げられることもあります。
結果的に、オーナーは減額を受け入れるか、契約を失うかの二択を迫られてしまうのです。
契約解除を申し出ても違約金を請求されたケース
サブリース契約では、オーナー側からの中途解約が制限されているケースが多くあります。
あるオーナーは、家賃の引き下げに不満を持ち契約解除を申し出たところ、「契約残期間分の違約金を支払ってください」と言われました。
その額は数百万円にも及び、簡単に契約をやめられない現実を突きつけられたのです。
このように、契約書に記載された「解約条件」や「違約金条項」は非常に重要で、事前に確認しておかないと後悔することになります。
国民生活センターへの相談が年間200件以上寄せられた事例
国民生活センターの統計によると、サブリース契約に関する相談は年間200件以上にも上ります。
内容は「家賃を下げられた」「解約できない」「説明が不十分だった」などさまざまです。
中には、契約内容を十分に理解しないまま署名し、後から「言っていた話と違う」と気づいたケースも多いのです。
このように、トラブルの多さが「サブリース契約はやばい」と言われる最大の理由だといえます。
サブリース契約がやばいと言われる落とし穴と注意点
サブリース契約のトラブルを防ぐためには、どんな落とし穴があるのかを理解しておくことが大切です。ここでは特に注意すべき3つのポイントを紹介します。
「家賃保証=固定収入」とは限らないから
「家賃保証」という言葉に安心して契約するオーナーが多いですが、実際には保証されるのは“一定期間の賃料”であり、永続的な固定収入ではありません。
契約期間が過ぎると、家賃が見直されて減額されるケースが一般的です。
「30年保証」と書かれていても、途中で数回の見直しがある場合が多く、保証額が下がるリスクを想定しておく必要があります。
つまり、「家賃保証=一生安定」ではないことを理解しておきましょう。
契約書の中に不利な条項が隠れていることがあるから
サブリース契約のトラブルの多くは、契約書の細かい条項をよく読まなかったことが原因です。
例えば「家賃減額の合意があったものとみなす」「オーナー都合の解約には違約金を支払う」などの文言が小さく書かれている場合があります。
営業担当者が「安心です」「トラブルはありません」と言っても、契約書に書かれていればその内容が優先されます。
契約書を受け取ったら、時間をかけてすべての条文を確認し、理解できない部分は専門家に相談することが重要です。
修繕費や管理費がオーナー負担になる場合があるから
サブリース契約では、不動産会社が物件を管理するように見えますが、実際には修繕費や大規模修理費がオーナー負担になることもあります。
「管理を任せる代わりに安心」と思っていたのに、エアコンの交換や外壁の補修などを自費で行わなければならないケースもあるのです。
契約前に「どの範囲まで業者が負担してくれるのか」を明確にしておかないと、思わぬ出費につながります。
収益シミュレーションを行う際には、修繕コストを含めた計算をすることをおすすめします。
サブリース契約のやばいリスクを回避するための対策
サブリース契約が必ずしも悪いわけではありません。正しく知り、適切に比較・判断すれば、リスクを抑えながら活用することも可能です。
複数社に見積もり・契約内容を比較する
1社だけの説明で判断するのは危険です。必ず複数のサブリース業者に見積もりを依頼し、条件を比較しましょう。
家賃保証率、管理手数料、修繕費の負担範囲など、会社ごとに大きく違います。
比較することで、相場感がわかり、極端に不利な契約を避けることができるようになります。
特に「保証率が高い=安心」とは限らないので、契約内容全体を見て判断することが大切です。
契約前に弁護士や不動産鑑定士に相談する
契約書の内容が複雑で理解できない場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談するのが最善です。
専門家にチェックしてもらうことで、不利な条件やリスクを事前に指摘してもらえます。
費用は数万円程度かかる場合もありますが、数百万円の損失を防げる可能性があると考えれば安い投資です。
特に契約書の「解除条項」や「家賃改定条件」は重点的に確認してもらいましょう。
国土交通省の「サブリース業者登録制度」を確認する
2021年から、国土交通省による「サブリース業者登録制度」が始まりました。
これは、悪質な業者を排除し、健全な取引を促すための制度です。
契約前に業者がこの制度に登録されているかを確認することで、信頼性の高い会社かどうかを判断する指標になります。
国交省の公式サイトで簡単に検索できるので、必ずチェックしておきましょう。
サブリース契約がやばいと感じたときの相談先や対応方法
もしすでに契約していて「やばい」と感じた場合は、すぐに専門機関へ相談することが大切です。放置すると状況が悪化することもあります。
国民生活センターや消費生活センターに相談する
サブリース契約に関する相談は、まず国民生活センターや各地の消費生活センターで受け付けています。
無料で相談でき、トラブルの状況に応じて適切な対応方法をアドバイスしてもらえます。
契約書や書類を手元に用意して、事実関係を整理してから相談するとスムーズです。
消費者トラブルの初期対応として最も身近で頼れる機関といえるでしょう。
不動産トラブルに詳しい弁護士に依頼する
法的な対応が必要な場合は、不動産トラブルに強い弁護士に相談しましょう。
契約の解除や家賃減額交渉など、専門的な知識が必要なケースでは、弁護士の力が不可欠です。
弁護士に相談することで、法的な根拠をもとに交渉できるようになり、不利な立場を改善できる可能性もあります。
日本弁護士連合会や地元の弁護士会のサイトで、無料相談を受け付けている場合もあります。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の相談窓口を利用する
業界団体である公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(JPM)にも、オーナー向けの相談窓口があります。
サブリースに関する苦情や不明点を相談すると、第三者の立場から助言をもらうことができます。
また、悪質業者に関する情報提供や対応策についても教えてもらえるため、安心して相談できる機関です。
公的な機関と合わせて利用することで、より確実に問題解決へ近づけます。
まとめ
サブリース契約は、「家賃保証」「手間いらず」といった魅力的な宣伝文句がある一方で、実際には多くのトラブルが報告されているのが現実です。
家賃の減額、違約金請求、契約解除トラブルなど、油断して契約すると大きな損失を被る可能性もあります。
しかし、正しい知識を持ち、契約前に内容を比較・確認し、専門家に相談することでリスクは大幅に減らせます。
「サブリース契約=やばい」と決めつけるのではなく、仕組みを理解したうえで安全に活用することが大切です。
これからサブリース契約を検討する人は、焦らず、複数の情報を集めて慎重に判断してください。