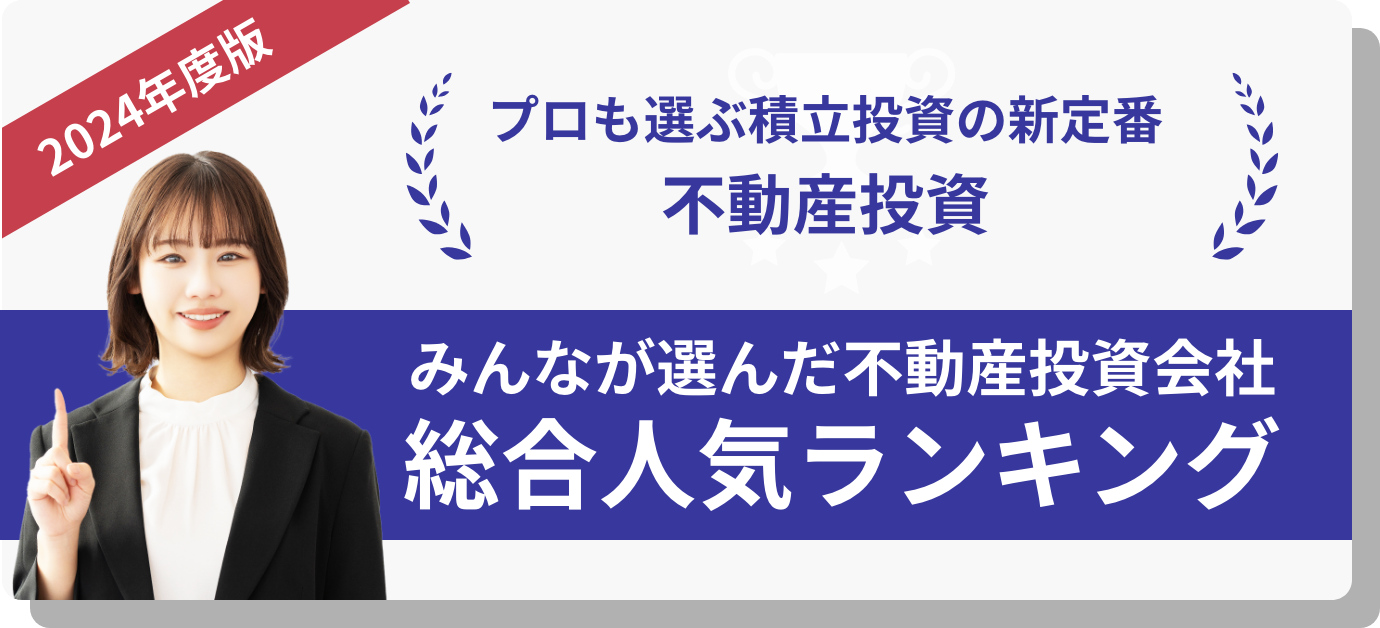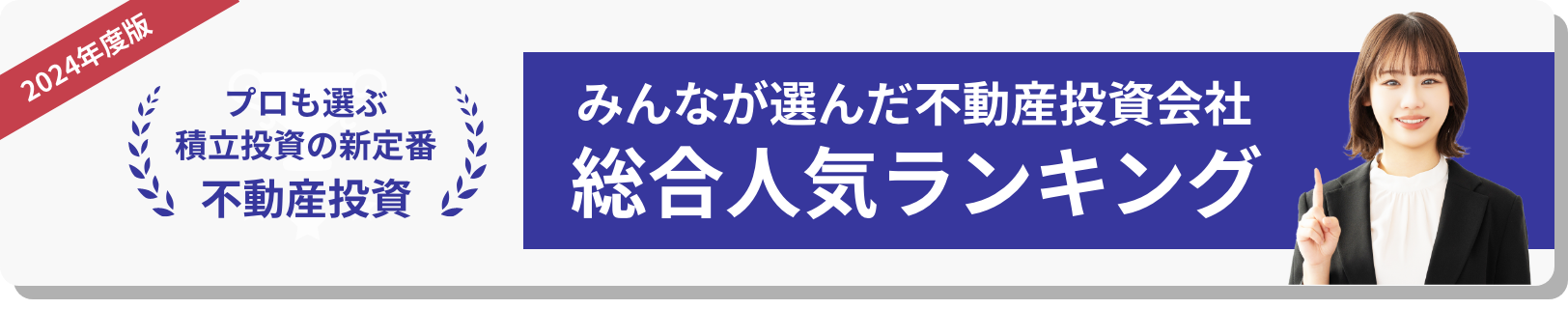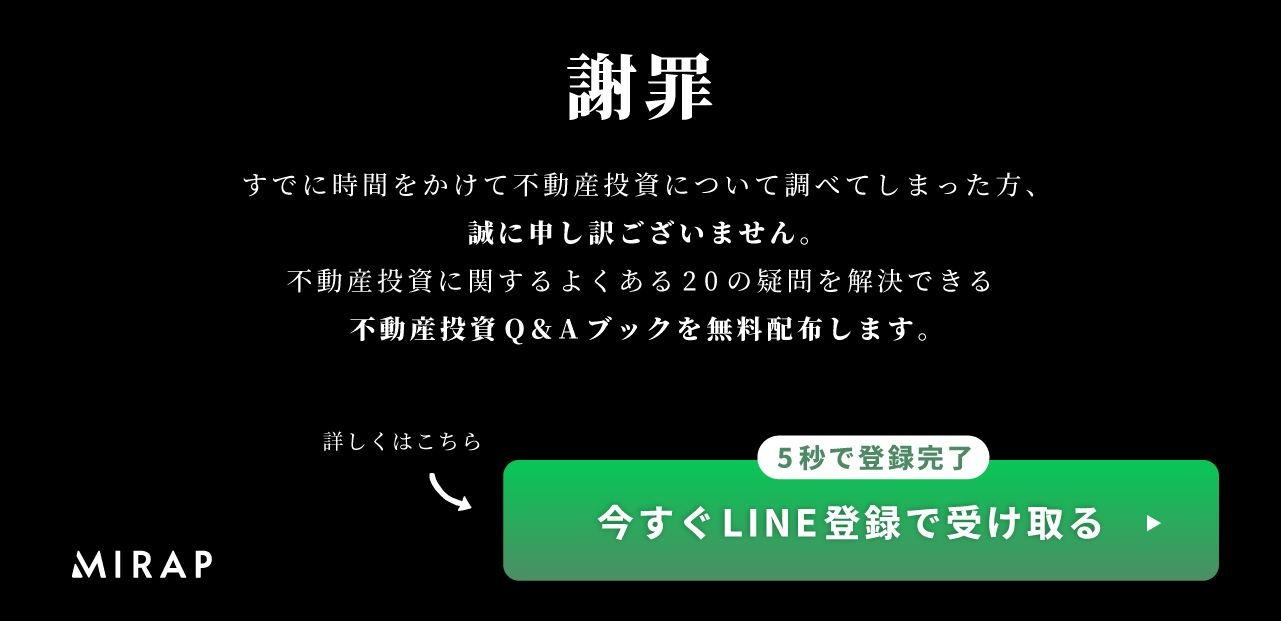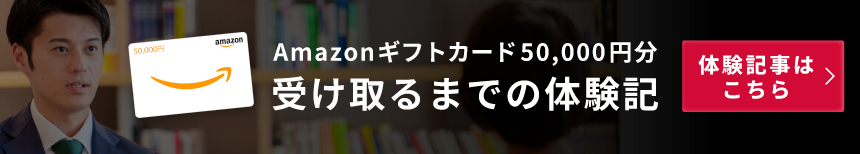「貯金が1,000万円を超えたら、何をすればいいの?」と迷っていませんか?
ただ銀行に預けているだけでは、お金の価値は時間とともに目減りしてしまいます。
この記事では、貯金1,000万円を超えた人がやるべきことや、今すぐ始めたい資産運用方法についてわかりやすく解説します。
※こちらのボタンをタップしてキャンペーンページが表示されたら、まだ開催中なので、締め切られる前にまずは確認してみましょう!


貯金1,000万円を超えている方の割合

まず最初に、日本で貯金1,000万円を超えている人がどれくらいいるのかを把握しましょう。実は、思っているよりも多くの人がこの金額を貯めています。
日本全体の貯蓄額の平均と中央値
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、全世帯の平均貯蓄額は約1,400万円です。
しかし平均には大きな資産を持つ富裕層も含まれているため、実態を知るには中央値を見るのがポイントです。
中央値は単身世帯で約500万円、2人以上世帯で約900万円程度となっており、1,000万円以上の貯金を持っている人は全体から見てもやや少数派であることがわかります。
このように、平均と中央値を理解しておくと、自分の貯蓄状況がどの位置にあるかが見えてきます。
年代別で1,000万円以上貯金している人の割合
年代別で見ると、40代後半から50代、そして60代以上で貯金1,000万円を超えている人の割合が増えます。
特に60代では、約4割が1,000万円以上の貯蓄を持っているという調査結果もあります。
一方、30代以下ではまだ1,000万円以上の貯金を持つ人は少なく、全体の1〜2割程度にとどまっています。
年齢とともに収入の増加や住宅ローンの完済などが影響し、貯蓄額は自然と増えていく傾向にあります。
単身世帯と二人以上世帯での違い
単身世帯と2人以上世帯では、当然ながら貯蓄額にも差があります。
二人以上世帯は生活費がかかる反面、共働き世帯も多く、合計収入が高いため貯蓄しやすい傾向があります。
単身世帯では生活費の節約がしやすいものの、収入源が一つしかないことが多く、大きく貯めるには時間がかかるケースが多いです。
貯金1,000万円のハードルは、世帯構成によっても異なるということを知っておきましょう。
貯金1,000万円を超えたらやるべきこと5つ
貯金が1,000万円を超えたら、「とりあえず預金」のままではもったいないです。以下の5つのステップで、資産を守りながら増やすことが可能になります。
生活防衛資金を確保する
まず最初にすべきことは「生活防衛資金」の確保です。
これは、急な病気やケガ、失業などの不測の事態に備えて持っておくお金のことです。
目安としては、生活費の6か月〜1年分を現金で確保しておくと安心です。
たとえ投資でお金を増やしたいと思っても、手元資金がないと安心して運用できません。まずは土台を固めましょう。
万一に備えて保険を見直す
次に、現在加入している保険内容を見直しましょう。
特に貯金が増えると、自分でリスクをカバーできる部分も出てくるため、不要な保険は見直して保険料を節約することが可能です。
また、医療保険やがん保険など、自分に合った保障内容になっているかも重要です。
お金があるからこそ、無駄な支出は減らしつつ、必要な備えはしっかり整えることが大切です。
余剰資金を投資に回す
生活防衛資金を確保したら、残りのお金は「余剰資金」となります。
この余剰資金を元に、投資を始めることでお金に働いてもらう仕組みが作れます。
初心者には、つみたてNISAやiDeCoなど税制優遇のある制度を活用した投資がオススメです。
長期的に運用すれば、複利効果で資産を効率よく増やすことが可能です。
相続や贈与の準備を考える
資産が増えると、相続や贈与についても早めに考えておく必要があります。
例えば、年間110万円までの贈与は非課税になる「暦年贈与」など、節税につながる方法もあります。
将来的に家族に資産を渡す予定があるなら、早いうちに準備をしておくと安心です。
税金対策を含めた相続・贈与の計画は、早ければ早いほど有利になるケースが多いです。
資産を見える化して管理する
1,000万円を超える資産があると、あちこちに分散してしまいがちです。
そこで、家計簿アプリや資産管理アプリなどを活用し、資産の全体像を把握しておくことが重要です。
どこにいくらあるのかを把握することで、無駄な支出を抑えたり、投資判断の材料になります。
見える化することで、「何にいくら使えるか」「どこに資金を回すべきか」が明確になります。
貯金1,000万円超えたら銀行に預けておくのは損
「とりあえず銀行に預けておけば安心」と考えがちですが、今の時代、それではお金の価値を守れません。以下の理由から、預金だけでは資産が目減りしてしまう可能性があります。
普通預金や定期預金は金利がほぼゼロだから
日本の銀行の普通預金金利は、現在0.001%ほど。1000万円預けても、1年間で得られる利息はわずか100円程度です。
定期預金でも金利は0.01%〜0.02%が相場で、利回りはほとんど期待できません。
つまり、銀行に預けていても、お金は「ほぼ増えない」のが現実なのです。
これではせっかくの貯金も、ただ寝かせているだけになってしまいます。
インフレで実質的に資産が目減りするから
インフレとは、物の値段が上がることを意味します。
もしインフレ率が2%であれば、1,000万円の価値は1年後に980万円程度の価値しか持たないことになります。
金利がほぼゼロの預金では、インフレにまったく対応できません。
「増えない」どころか「目減りする」というリスクを理解することが大切です。
銀行のペイオフ制度では1,000万円以上は保証されないから
日本にはペイオフ制度があり、万が一銀行が倒産しても、預金者一人あたり1,000万円とその利息までは保護されます。
しかし、それを超える預金については保護の対象外です。
つまり、1,000万円以上の資産を同じ銀行に預けていると、リスクにさらされている可能性があるということです。
複数の金融機関に分散したり、資産運用を活用してリスクを回避しましょう。
貯金1,000万円超えた方におすすめの資産運用5選
貯金が1,000万円を超えたら、「増やすこと」を真剣に考えるタイミングです。銀行預金だけで資産を眠らせるのではなく、自分に合った運用方法を選んで資産形成を加速させることが大切です。
投資信託
投資信託は、プロが選んだ株や債券に分散して投資してくれる仕組みです。少額から始められ、初心者にも向いています。
楽天証券やSBI証券など、ネット証券では多くの投資信託商品を取り扱っており、信託報酬(手数料)も低コストで人気です。
特に、インデックス型の投資信託は手数料が安く、長期保有にも向いているため、資産形成の土台になります。
自動積立設定も可能で、月々決まった額を積み立てる「つみたて投資」もオススメです。
株式投資
ある程度リスクを取れる方には、株式投資も有効な手段です。日本株だけでなく、成長性の高い米国株も選択肢に入れると、バランスのよいポートフォリオを組めます。
例えば、配当金が魅力の高配当株や、成長が期待できるテック銘柄など、目的に応じて戦略を立てましょう。
「日本株+米国株」のように、地域を分けて投資することでリスクの分散が可能になります。
長期保有による値上がり益や配当金を狙う「インカム+キャピタル」戦略も検討できます。
不動産投資
不動産投資は、家賃収入や物件の値上がりを狙える中・長期の資産運用法です。1,000万円あれば、現物不動産を頭金として購入することも可能です。
初心者には、少額から始められる「REIT(不動産投資信託)」もおすすめです。複数の物件に分散投資されており、リスクを抑えつつ安定的な配当が期待できます。
特に東京などの都市部のマンション投資は空室リスクが低く、資産価値も維持されやすい傾向にあります。
不動産投資は初期費用が高いですが、レバレッジ(借入)を活用することで効率的な運用も可能です。
iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を活用
1,000万円以上の貯蓄があるなら、税制優遇制度の活用は必須です。iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除になり、節税効果が非常に高い制度です。
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が非課税になるため、運用益を効率的に得ることができます。
2024年からは新NISA制度が始まり、年間投資上限額が拡大され、より柔軟な運用が可能になりました。
税金のかからない運用環境を最大限活用すれば、同じ運用でも手元に残る金額が大きく変わってきます。
外貨建て資産でリスク分散
資産の一部を外貨建てにすることで、為替リスクを取る代わりに、円安時に資産価値を高めることが可能です。
例えば米ドル建ての外貨預金や外貨MMF(マネー・マーケット・ファンド)などは、比較的安全に外貨投資ができます。
また、米国債などの債券商品を通じて、安定した利息収入も狙えます。
円だけに資産を集中させるのはリスクが高いため、「通貨の分散」も立派なリスクヘッジ手段です。
貯金1,000万円を超えた方からよくある質問
最後に、貯金1,000万円を達成した人から実際によく聞かれる質問をまとめました。どれも資産管理において重要な疑問なので、ぜひチェックしておきましょう。
貯金1000万円を超えたらゆうちょ銀行の場合どうすれば良い?
ゆうちょ銀行もペイオフ(預金保護制度)の対象ですが、保護されるのは1,000万円までです。
つまり、1,000万円を超えた金額は万が一破綻した場合には補償されないリスクがあります。
そのため、ゆうちょ銀行だけに資金を集中させず、他の金融機関に分散したり、一部を投資に回すなどの工夫が必要です。
特に資産が多くなると、分散管理と見える化が大切になります。
貯金1000万円を超えたら税金がかかるって本当?
貯金そのものに税金がかかることはありません。
ただし、預金に対して発生する利息や、投資による利益には課税されます。通常、預金利息には20.315%の税金がかかります。
また、贈与や相続によって得た資産には税金がかかる場合もあるため注意が必要です。
「貯金が増える=税金が増える」という誤解はありますが、基本的には利益が出てはじめて課税対象となります。
貯金1000万円を到達する年齢で最も割合が大きいのは?
一般的に、50代〜60代で貯金1,000万円を超える人が最も多いとされています。
これは住宅ローンの完済や、子どもの独立などで支出が減るタイミングと重なるためです。
また、退職金などの一時的な収入によって一気に貯金が増えるケースも見られます。
30代や40代で1,000万円を達成している人は、かなり堅実にお金を管理している層と言えるでしょう。
貯金1000万円はすごい?
はい、貯金1,000万円を達成するのは非常に立派なことです。
中央値で見ても、単身世帯では500万円未満が多数派であるため、1,000万円というのは少数派に入ります。
しっかりとした家計管理、節約、収入アップを継続しないと到達できない金額です。
今後の目標は「貯める」から「増やす」にシフトするタイミングです。
貯金1000万円を超えたら銀行から電話がくるって本当?
はい、場合によっては銀行から電話がくることもあります。
特に大きな預金がある場合、資産運用の提案や、新サービスの案内として営業電話を受けるケースがあります。
ただし、それが必ずしも悪いとは限りません。中には有益な情報や条件の良い商品の案内もあるかもしれません。
ただし、勧誘を鵜呑みにせず、自分で判断する目を養うことが大切です。
貯金1,000万円を超えたら投資するべき?
はい、余剰資金があるなら投資はぜひ検討するべきです。
特にインフレや低金利の時代には、現金の価値が目減りしていくため、資産を守る意味でも投資は重要です。
ただし、生活防衛資金を残したうえで、無理のない範囲で始めることが前提です。
自分のリスク許容度を把握しながら、段階的に投資を始めることで、着実に資産を育てることができます。
まとめ
貯金1,000万円を超えることは、非常に大きな節目であり、多くの人にとって自信となる金額です。
しかし、そのお金をただ銀行に眠らせておくだけでは、時間とともに価値が下がってしまう可能性があります。
生活防衛資金の確保・保険の見直し・分散投資・税制優遇の活用など、「守る」と「増やす」を両立させる戦略がこれからは重要です。
また、自分の資産状況を「見える化」することで、リスクを抑えながら無駄なくお金を活用することができます。
この記事で紹介した資産運用の選択肢を参考に、あなたに合った方法で大切なお金を未来につなげていきましょう。
貯金1,000万円は「ゴール」ではなく、「次のステージへのスタートライン」です。賢く管理し、将来の安心と豊かさを手に入れ
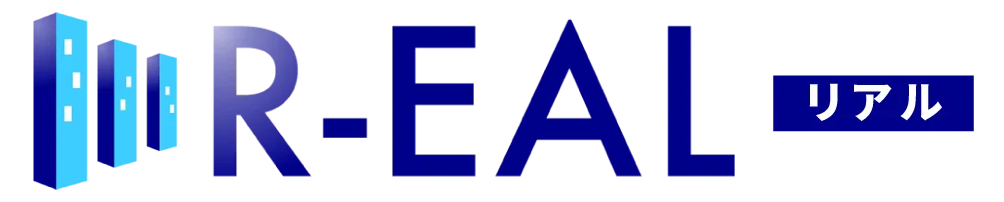

-150x150.jpeg)