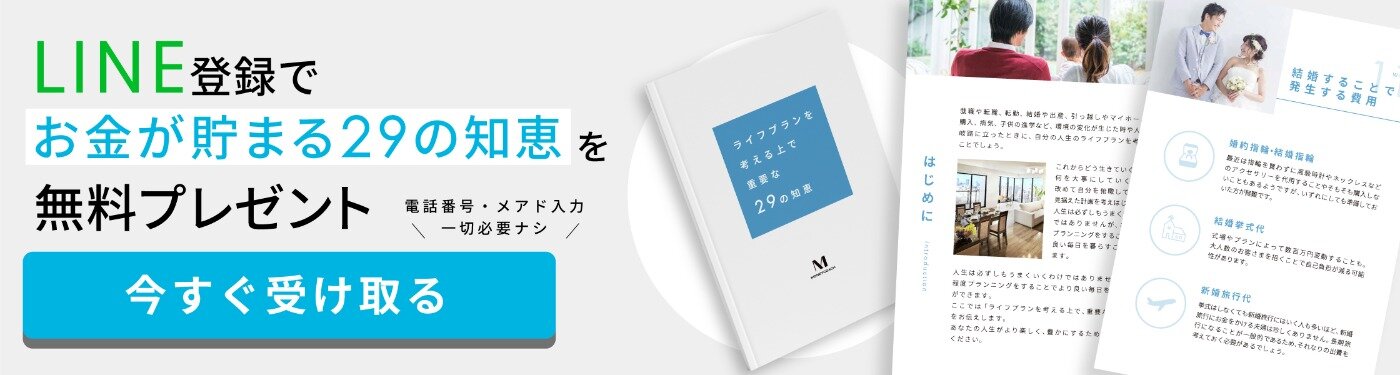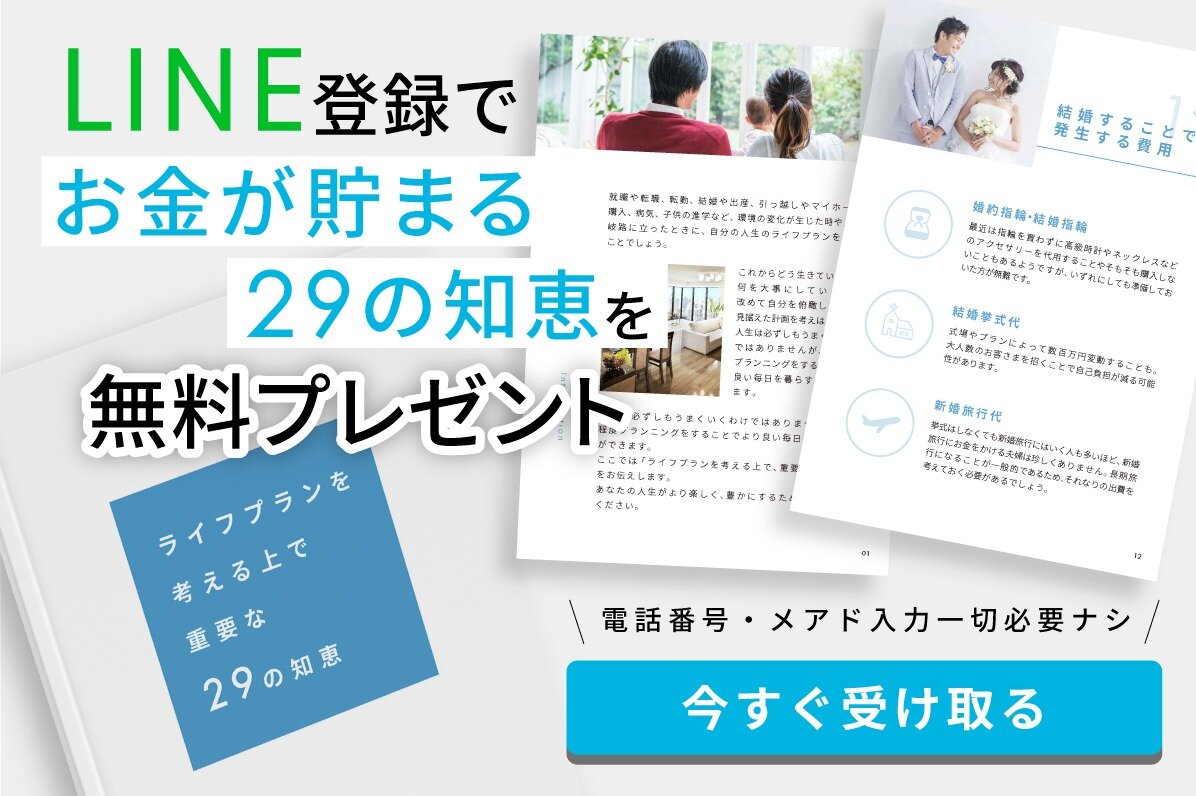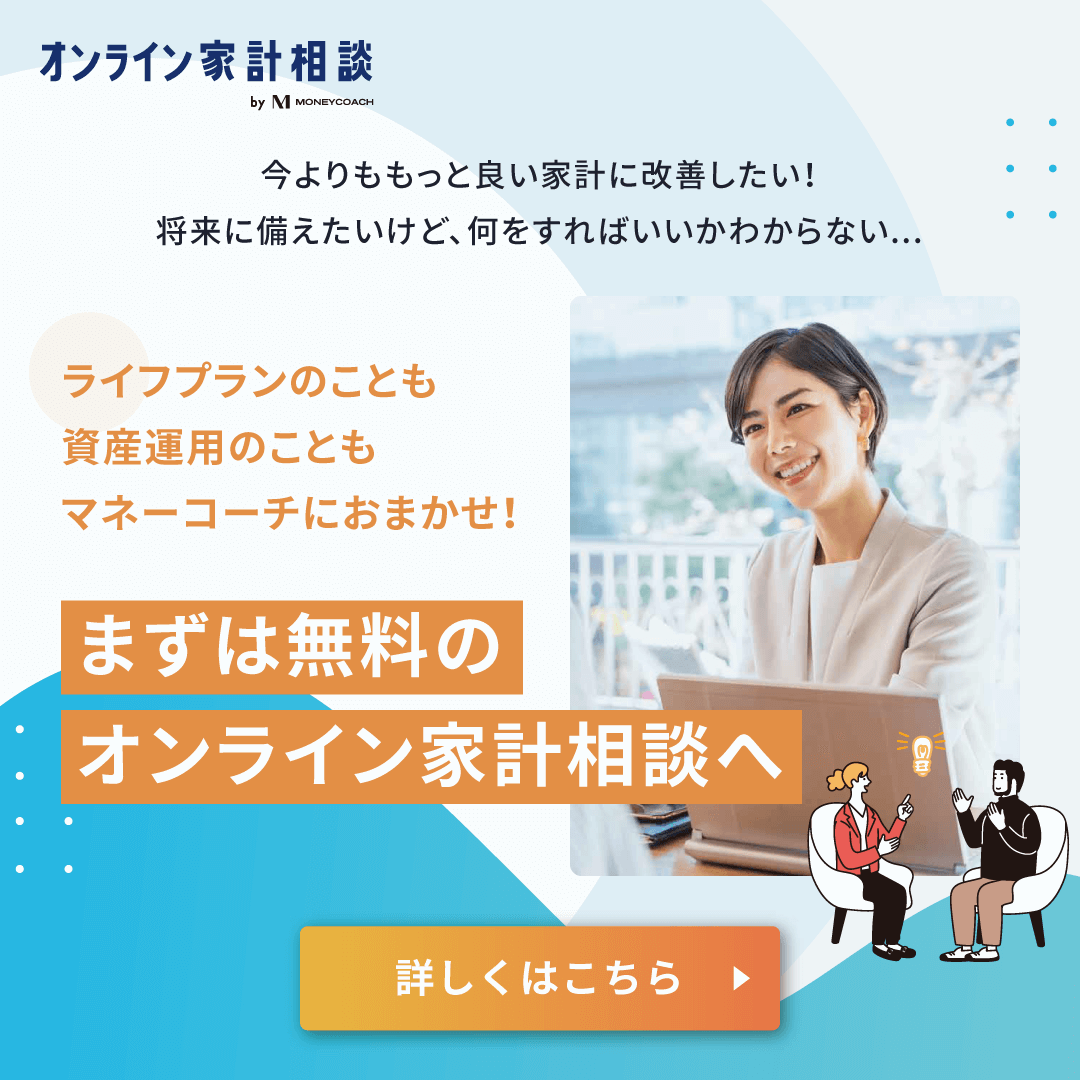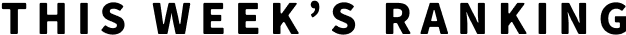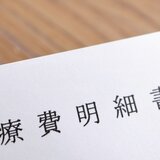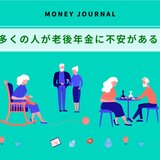老後の備えのために、年金について理解を深めておきたいと考えている人も多いのではないでしょうか。年金にはさまざまな種類があり、特徴も異なるため自分にあったものを選ぶことが大切です。この記事では、年金の基本的な知識、年金のなかでも注目を集めている個人年金保険について詳しく解説します。ぜひ、自身の老後の備えに役立ててください。
そもそも年金とは?
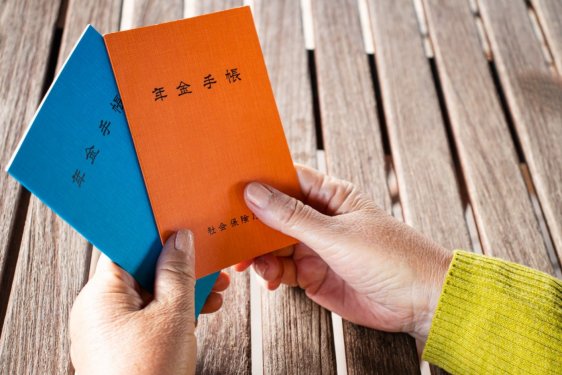
そもそも年金とは、主に老後に備えるもので、高齢を理由に働けなくなったときのために役立てられます。また、病気や怪我などで障害を負ったときや、一家の大黒柱を失ったときに、遺族の生活を支えるものとしても活用されています。
年金の種類や特徴はさまざまです。自分のライフスタイルや老後のプランに合わせて選ぶと良いでしょう。
「公的年金」と「私的年金」の三階建て
日本の年金制度は、家にたとえられており、3階建ての構造で成り立っています。1階・2階部分は国が運営している「公的年金」、3階部分は民間の企業や団体が運営する「私的年金」になります。この階層が多いほど、受け取れる年金は多くなります。また、加入者の働き方や加入目的によって、加入できる保険や受け取れる金額は変わります。
公的年金とは
公的年金は、国が運営している制度のひとつです。公的年金の1階部分にあたるのが国民年金で、基本的に20歳になると国民全員が加入する必要があります。2階部分には厚生年金があります。厚生年金とは、民間企業の従業員や公務員などを対象としており、国民年金に上乗せするものです。保険料は、所得に応じて決定されます。
このように、公的年金はその人の働き方によって国民年金と厚生年金にわけられます。
私的年金とは
私的年金は、民間の企業や団体が運営する年金制度です。年金制度の構造では、3階部分に該当し、加入は任意です。私的年金には、企業年金、iDeCo、国民年金基金、個人年金保険などがあります。自営業やフリーランスで厚生年金の対象にならない、公的年金だけでは老後が不安といった場合に役立ちます。
私的年金は、自分で運用方法を選び、掛金を運用するものもあります。運用の結果によっては将来、受け取る年金が増える可能性があります。
よくきく個人年金保険って?

個人年金とは、私的年金のうちのひとつです。保険契約時に決めた年数が経過すると、年金を受け取れるようになる貯蓄型の生命保険です。公的年金や企業年金では足りない部分を補うときに活用できます。もし、期間中に被保険者が亡くなった場合でも、遺族に年金が支払われるのが特徴です。個人年金保険に加入するには、保険会社と契約する必要があります。
iDeCoとの違い
iDeCoは証券会社が運営する制度です。積み立てた資金を自分で運用して年金を形成します。日本在住で20歳以上60歳未満であれば、原則誰でも取り組める制度で、月5000円から始められます。個人年金保険の場合は、運用を保険会社に任せますが、iDeCoは自分で運用する必要があるため手間がかかります。また、運用の掛金の上限が決められていることが特徴です。
受け取り方の違いによる個人年金保険の種類

個人年金の受け取り方法は、「終身年金」「確定年金」「有期年金」の3つの種類があります。ここでは、それぞれの特徴を解説します。
終身年金
終身年金は、年金の受け取り開始から一生涯受け取れるものです。例えば、年金の受取開始を65歳に決めておくと、65歳から被保険者が亡くなるまで年金を受け取れます。長生きするほど、コストパフォーマンスが良いのが特徴です。基本的に被保険者が死亡した場合、遺族は年金を受け取れませんが、保証期間内であれば遺族が残りの年金を受け取ることができます。
確定年金
確定年金は、5年・10年など予め設定した期間で年金を受け取れるもので商品のラインナップも豊富です。また、退職して公的年金の受け取りが始まる65歳までのつなぎとして、確定年金を利用する方法もあります。確定年金は被保険者が死亡した場合でも、遺族が残りの年金を受け取ることができます。
有期年金
有期年金は確定年金と同様に、設定した期間で年金を受け取れるものです。年金を満額受け取ることで、確定年金よりも年金額が多くなるのが特徴です。
保証期間付きの有期年金であれば、被保険者が死亡した場合でも遺族が年金を受け取ることができます。保証期間が付いていない場合は遺族への支払いはありません。そのため、早く亡くなると元本割れになる可能性もあります。
運用の違いによる個人年金保険の種類

個人年金は運用方法によっても種類が異なります。ここでは、「定額年金」「扁額年金」「外貨建て年金」について具体的に解説します。
定額年金
定額年金は、契約時に保険会社が設定した「予定利率」で運用します。契約したときに将来受け取れる年金額が確定することになりますが、契約時期によっては、設定する利率が低いこともあります。自分が受け取れる年金額をあらかじめ把握しておきたい、確実に年金を得たいという人に向いているでしょう。
変額年金
保険会社が運用する株や投資信託の運用実績によって、利率が変動するのが変額年金です。将来受け取れる年金額は運用次第なので、契約時にいくらもらえるかはわかりません。運用実績が良ければ、支払った保険料以上の年金を受け取れるでしょう。運用がうまくいかなかった場合は、元本割れすることもあります。
外貨建て年金
外貨建て年金は変額年金のひとつで、積立金をドルや豪ドル、ユーロといった外資で運用します。外資での運用は高い利回りが期待できる反面、為替レートの変動によっては大きな損失が発生することもあります。また、一般的な個人年金保険よりも、解約手数料や為替手数料などが高いのが特徴です。
この記事の内容の他にも、「お金が貯まる29の知恵」を1冊にまとめました。
今ならLINE登録するだけで、無料でプレゼントしています。
この機会に是非一度LINE登録して、特典を今スグ受け取ってください。
個人年金保険のメリット

個人年金には節税効果や貯金といったメリットがあります。ここでは、個人年金保険のメリットを3つ解説します。
所得控除による節税効果がある
課税対象となる所得から、個人年金保険に支払った保険料を差し引くことで「個人年金保険料控除」が受けられるようになります。これは、他の医療保険や死亡保険とは別枠で控除が受けられる場合もあります。なお、個人年金保険料控除を受けるには、支払期間が10年以上であることや、年金の受取人が被保険者と同じであることなど、いくつかの条件があります。
貯金が苦手でも続けやすい
個人年金保険の保険料は口座から自動で引き落とされます。このように強制力があるため、口座にお金があると、ついお金を引き出してしまう人や貯金が苦手な人でも続けやすいことがメリットです。一般的な貯蓄とは異なり、個人年金保険は解約のハードルが高い点も、積み立てを続けられる理由のひとつです。
死亡給付金が受け取れる
個人年金保険は、被保険者が年金を受け取る前に死亡した場合でも、代わりに遺族が年金を受けられます。「死亡給付金」と呼ばれる仕組みで、受け取れる年金額は死亡給付金の種類によっても異なります。死亡時点での払い込んだ保険料と同程度の生存保障重視型や、払い込んだ保険料を上回る一般型、保険料より下回る分、年金額を増やした長寿年金などがあります。
個人年金保険のデメリット

個人年金保険にはデメリットもあります。ここでは、元本割れや受取額の減額といったデメリットを3つ解説します。
途中解約は元本割れすることが多い
個人年金保険は途中解約すると元本割れすることが多く、解約したときに戻ってくる「解約返戻金」は、支払った保険料より下回る可能性が高いです。特に加入してから3年以内に解約すると、それまでに払った保険料より、半分以下になるケースもあります。また、振り込んだ保険料のうちどのくらい増えるのかを表す「返戻率」は、加入期間が短いほど低くなります。
保険会社の破綻で受取額が減る可能性がある
契約した保険会社が万が一破綻した場合、年金の受取額が減ってしまうケースがあります。破綻しても救済措置はとられますが、元本割れしてしまう可能性があります。ただし、実際に保険会社が破綻するリスクは小さいため、過度に気にする必要はありません。もしもこのようなことが起きたら、年金の受取額に影響があることは頭に入れておきましょう。
インフレに弱い
個人年金保険はインフレに弱いというデメリットがあります。定額年金は、契約時に決めた予定利率で運用されます。そのため、物価の上昇によって金利が上回った場合、受け取れる金額は契約通りでも、物価の値段が高まっていれば、お金の価値そのものが低下することになります。変額年金は金利も上がるので、インフレが起きても対応が取れます。
将来の備えには資産構築が重要
公的年金も私的年金も、種類や特徴、メリット・デメリットを踏まえて上手に活用しましょう。老後の蓄えに不安を抱く人は多く、年金以外でも将来の備えを準備することも大切です。