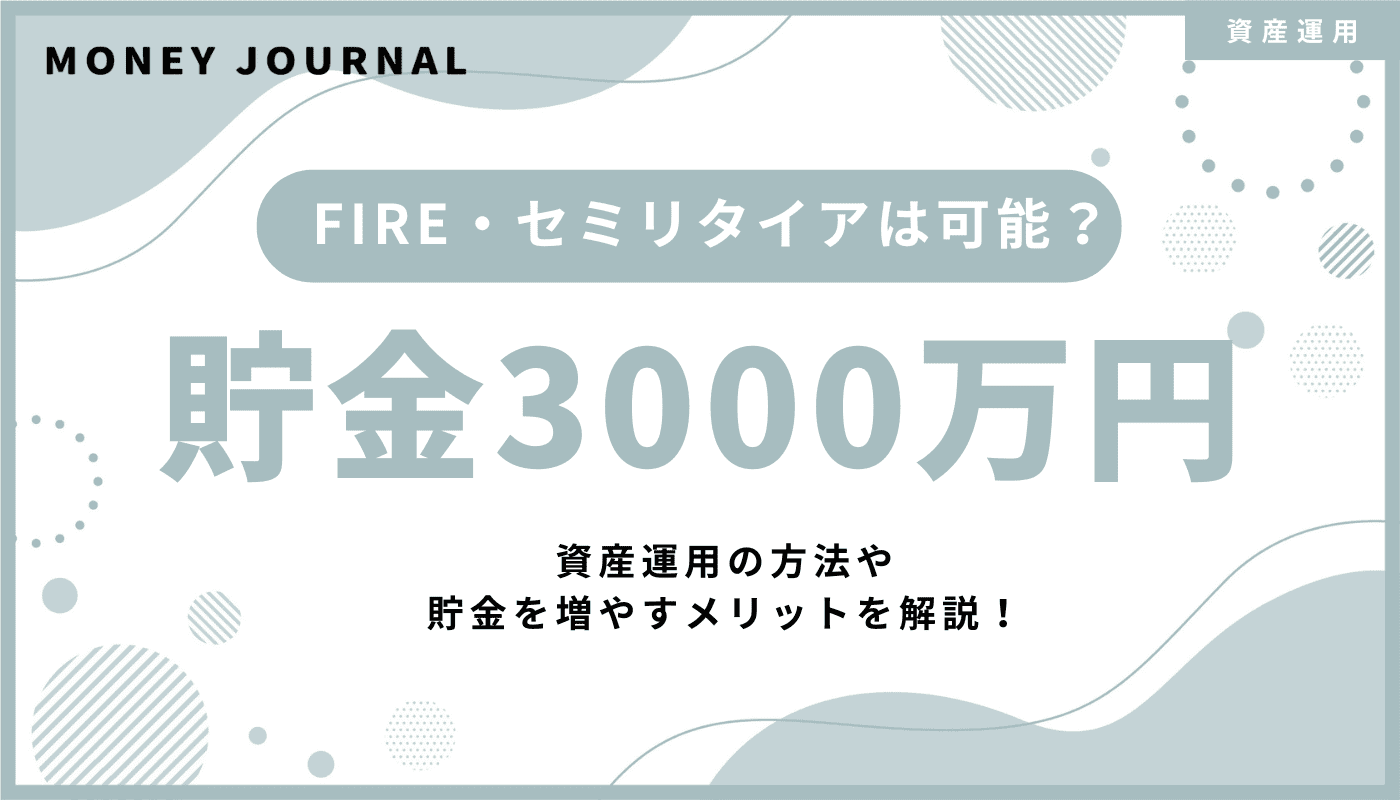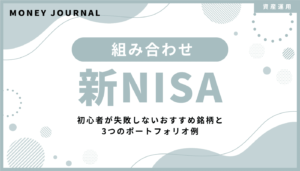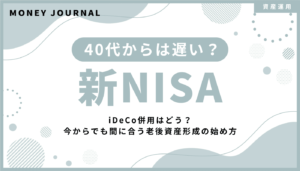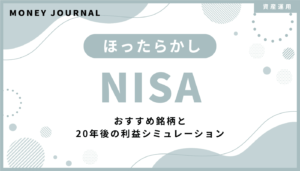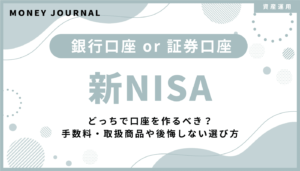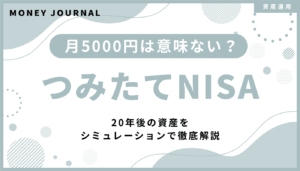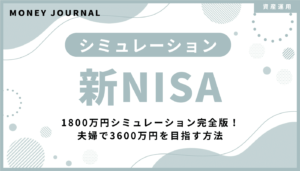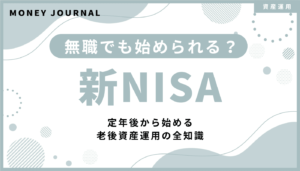FIREやセミリタイアという大きな目標を持って貯金をしている方のなかには、すでに貯金額が3000万円を超えた人もいると思います。
3000万円の貯金があれば実際にFIREやセミリタイアすることは可能なのでしょうか。結論から書いてしまうと、3000万円を超えたとしても、更に上を目指して資産運用することをおすすめします。
今回は3000万円を効率良く増やすためにおすすめの資産運用や、3000万円でもFIREやセミリタイアが難しい理由などについて解説します。
貯金3000万円を超えている人の割合はどれくらい?

貯金額が3000万円を超えているような人の割合は決して多くありません。
金融広報中央委員会が行った「令和5年(2023年)家計の金融行動に関する世論調査」によると、単身世帯と二人以上世帯で3000万円以上の金融資産を持っている人の割合は以下のとおりです。
単身世帯の割合
| 世帯主の年齢 | 金融資産3000万円以上の割合 |
|---|---|
| 20歳代 | 0.0% |
| 30歳代 | 4.0% |
| 40歳代 | 4.3% |
| 50歳代 | 9.3% |
| 60歳代 | 15.1% |
| 70歳代 | 17.3% |
独身の単身世帯は二人以上世帯と比較しても、全年代を通して3000万円以上の金融資産を持っている人の割合が少なくなっています。
原因は想像するしかありませんが、「働き手を増やせない」ということが大きな要因と言えるでしょう。
二人以上世帯の割合
| 世帯主の年齢 | 金融資産3000万円以上の割合 |
|---|---|
| 20歳代 | 0.6% |
| 30歳代 | 4.0% |
| 40歳代 | 6.5% |
| 50歳代 | 11.2% |
| 60歳代 | 20.5% |
| 70歳代 | 19.7% |
二人以上世帯は、ほとんどの年代を通じて単身世帯より3000万円以上の金融資産を持っている家庭が多い結果になりました。
特に60代の2人以上世帯では、20%以上が貯金3000万円の大台を超えています。「共働きで2人とも退職金が手に入る」「年金が2人分受け取れる」など、単身世帯よりは老後資金が手に入りやすい点が要因として考えられるのではないでしょうか。
いずれにしても、3000万円を超える貯金を持つ人は全体の一部しかいないことが分かります。

貯金3000万円で何年暮らせる?老後シミュレーション

ここでは、実際に貯金3000万円で何年暮らせるのかシミュレーションしていきます。
総務省データから見る生活年数の試算
総務省家計調査によると、「二人以上の世帯」「単身世帯」のそれぞれの支出額は以下のとおりです。
| 項目 | 消費支出 |
|---|---|
| 二人以上世帯 | 29万3,997円 |
| 単身世帯 | 16万7,620円 |
貯金が3000万円ある二人以上世帯では「3000万円÷29万3,997円=約102ヶ月(約8年)」、単身世帯では「3000万円÷16万7,620円=179ヶ月(約15年)」まで生活することが可能です。
FIREに必要な資産額
3000万円ではFIREには到底足りないだろうということはすでに解説した通りです。
では、いくらあればFIREが可能なのでしょうか。3000万円から更に資産を増やす際の目標にできるようにシミュレーションしてみましょう。
根拠は「4%ルール」です。資産を年4%で運用したうえで支出を資産の4%以内にすることで、資産が目減りしないという考え方があります。
仮に年間の生活費が400万円の場合、25倍の資産と言えば1億円です。1億円の4%=400万円ですから、資産を減らすことなく運用成果だけで生活することが(理論上は)可能になります。
年間の生活費が500万円の家庭であれば、預貯金3000万円を更に増やして1億円にするということが今後の目標になるのではないでしょうか。

貯金3000万円超えでも資産運用が必要な理由
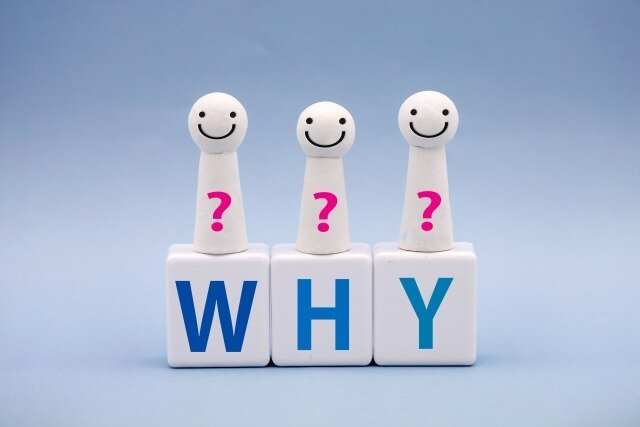
貯金3000万円もあればリスクをとって資産運用をしなくても、老後の生活に問題なさそうなイメージをお持ちの方はいませんか?
実際のところ、金融資産が3000万円あるご家庭でも、資産運用の必要性は高いです。ここでは、貯金が3000万円以上あっても資産運用が必要になる理由として、以下の3つを解説します。
- 老後生活費には足りない可能性がある
- インフレで実質価値が目減りする
- 年金だけでは生活が維持できない
老後生活費には足りない可能性がある
一般的には3000万円は大金であり、リタイアするには十分と考える人もいるでしょう。
ただ、実際には老後の生活をカバーするには十分な金額とはいえません。
生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」によれば、夫婦2人の老後生活に必要な費用は最低限の生活で1ヶ月23万2,000円です。老後が20年続くとすると「23.2万円×12ヶ月×20年=5,568万円」となり、最低限の生活をするにも3000万円では不足していることが分かります。
いったんリタイアすると以前のような収入を得られず、将来の厚生年金額が減少する可能性もあります。安易にリタイアせず、5,000万~1億と金融資産を積み重ねるまではリタイアはしないほうが良いでしょう。
インフレで実質価値が目減りする
インフレとは、物価が上昇することでお金の価値が目減りする状態です。例えば物価が現在の2倍になった場合、単純にいえば3000万円の価値は実質的に値上がり前の1,500万円分しかないということになります。
今は3000万円の貯金で十分に感じるかもしれませんが、将来的にインフレが進むと十分といえなくなる可能性があります。
年金だけでは生活が維持できない
令和6年現在、年金を受け取れる金額の平均は以下のとおりです。
| 種類 | 令和6年度の平均月額 |
|---|---|
| 国民年金 | 68,000円 |
| 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 230,483円 |
前述したように、老後に最低限の生活をするだけでも、23.2万円が必要という試算があります。あくまでも平均の話ですが、厚生年金(と、基礎年金)を受け取って、最低限の生活を何とか続けられるのが年金の水準です。
貯金が3000万円あったとしても、老後の生活を送るには十分とはいえないのが現状です。

貯金3000万円を超えた人が投資を始める4つのメリット

貯金3000万円以上ある人が投資を始めるメリットとして考えられるものは、以下のとおりです。
- お金を増やして更なる心の安心を得られる
- 大きなリターンが望める
- 分散投資を始めやすい
- 不動産投資ローンの審査に通りやすい
お金を増やして更なる心の安心を得られる
3000万円もあれば、さまざまな資産運用に挑戦することができます。
世の中には株式、債券、投資信託、不動産投資、仮想通貨など多くの投資があり、どれが大きく成長するかは分かりません。1本だけに絞るより、幅広く投資対象を検討したほうが利益を得るチャンスも向上します。
3000万円の金融資産の一部を幅広く投資することで効率良く資産形成を進めることができ、更なる安心感につながるでしょう。
大きなリターンが望める
貯金が3000万円もあれば、資産運用で効率的に資産形成を進めることが可能です。
AさんとBさんが同じ株式の銘柄に投資して、一定期間で株価が10%上昇したと仮定しましょう。
30万円を投資したAさんの利益は3万円ですが、3000万円を投資したBさんは300万円もの利益になります。
今のは資産を全て1社に投資する極端な例ですが、投資額が大きいほどより多くの利益を得やすいのは間違いありません。
分散投資を始めやすい
金融資産が多い人は、分散投資がやりやすいメリットがあります。
例えば1社に3000万円を全額投資して、その会社が不祥事で倒産したとしたらどうなるでしょう?3000万円分の株券が一気に紙くず同然になってしまうわけです。
倒産・株価の値下がりリスクを分散するためには「分散投資」を必ず行いましょう。1社の株価が急降下しても、別に保有している銘柄の株価が上がったりキープしたりすれば、資産へのダメージを抑えることが可能です。
不動産投資ローンの審査に通りやすい
不動産投資など、多額の初期費用がかかる投資の場合、初期費用を借りるためにローンを組むことになるのが一般的です。
金融資産が3000万円もあり、一部を頭金に回すことができれば、貯金が少なく頭金が出せない人よりも住宅ローンの審査で好影響につながることが考えられます。

貯金3000万円から1億円に増やすには?

3000万円の貯金を1億円にすることは可能です。
例えば3000万円を一括投資で1億円にするのに必要な運用期間と運用利回りは以下のとおりです。
| 運用期間 | 必要な年利回り |
|---|---|
| 5年 | 27.3% |
| 10年 | 12.8% |
| 15年 | 8.4% |
| 20年 | 6.3% |
| 25年 | 5.0% |
| 30年 | 4.1% |
長期で運用するほど必要な年利回りは小さくなっていきます。年4.0%の利回りを30年継続するというのが、一般投資家が実現できそうな現実的なラインでしょう。

貯金3000万円を超えたら検討したい資産運用ランキング6選

貯金が3000万円を超えれば将来安泰と思うかもしれませんが、「ゆとりある老後生活」のためには、さらに多くの貯金額を目指すことも検討しましょう。
元手が大きいほど効率的に資産運用ができるため、貯金が3000万円を超えた人こそ資産の一部を投資に振り向けることをおすすめします。資産運用を導入することで3,000万円の預貯金がさらに増え、4000万円や5000円万円といったように高額になっていくことも考えられます。
第1位:投資信託
3000万円を超える貯金ができる家庭は夫婦で共働きであったり、高年収な仕事をしていたりと、何かと多忙に過ごすことが多いのではないでしょうか。
数ある投資先の中から「どの投資先が効率良くリターンを得られるのか」を考えるには投資に関する勉強が不可欠ですが、多忙な家庭では学習時間の確保が難しい場合もあるでしょう。
そこで、おすすめしたいことが「プロに運用を任せる投資方法」です。
商品ごとに投資対象はさまざまですが、「日経平均株価」「TOPIX」「ダウ平均」といった指数に連動する値動きを目指すインデックスファンドであれば、指数を構成する数十~数千の銘柄全体に間接的に投資できます。
また、投資信託のなかには分配金を自動的に再投資する商品があり、複利で効率的に資産形成が可能です。
第2位:不動産投資
不動産投資は文字通り、マンションやアパートといった不動産を購入して、利用者に部屋を貸し出すことで家賃収入を得る投資方法です。
不動産を安く買って、土地などの価格が値上がりしたあとに売却することで売買差益(キャピタルゲイン)を得ることもできます。
第3位:株式投資
投資について勉強したり、投資先を厳選したりする時間的な余裕がある人なら、個別株式への投資もおすすめです。
株式投資は投資信託のようにプロに運用を任せることはせず、自分で投資先の株式や売買タイミングを判断することになります。
投資の対象は「トヨタ」「ソニー」など日本国内の銘柄だけでなく、米国・中国・ヨーロッパなど世界中の銘柄が投資対象になります。
たとえばiPhoneやiPadなどで有名なAppleは2020年3月20日時点で1株=57.31ドルだった株価が、2021年12月10日には179.45と、2年も経過しないうちに約3倍に株価が成長しています。
第4位:ヘッジファンド
ヘッジファンドは「私募ファンド」とも呼ばれており、投資信託と同様に運用を運用会社やファンドマネージャーといったプロに任せられます。
ヘッジファンドと投資信託の違いは、市場の値動きに惑わされない投資ができる点です。
一方のヘッジファンドは絶対収益の運用方針を掲げており、相場が上昇していても下落していても、利益を出すことを目指して投資をしていくことが特徴です。
たとえば、先物取引で売りから始めて「高く売って安く買い戻す」という取引をすることで、現物株価が値下がりしているタイミングでも利益を狙えます。
第5位:債券投資
「債券」と聞いて皆さんがイメージするのは、CMでも流れてくることがある「個人向け国債」ではないでしょうか。
日本の個人向け国債をはじめとした「債券」に投資する方法が債券投資です。債券は要するに国や企業が資金調達のために発行する借用証書であり、外貨建て債券なども選択肢に入ります。購入すると定期的に利子を受け取れて満期には元金が戻ってきます。安定した利子所得が得られるので、株価の高さに一喜一憂したくない人に向いているでしょう。
第6位:不動産投資信託(REIT)
不動産投資信託は、多くの投資家から集めた資金でオフィスビルやマンションなど複数の不動産を購入し、賃貸収入や売買益を投資家に分配する金融商品です。日本国内の不動産投資信託はJ-REITと呼ばれることもあります。
1口数万円~数十万円と株式と比較しても高めですが、現物の不動産を持つよりも必要資金ははるかに少ないです。管理運用はプロが代行してくれるので物件の分析や管理は必要なく、手軽に不動産投資にチャレンジしたい方におすすめです。
配当利回りが高い商品が多いため、配当収入を重視する投資家の方にもおすすめできます。

貯金3000万円を活かす資産運用成功のコツ
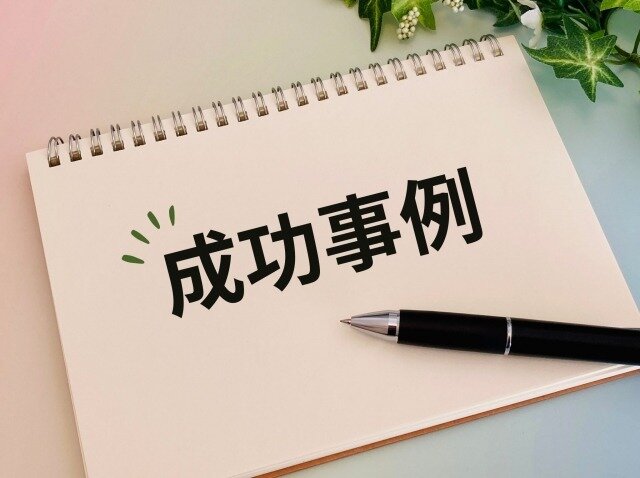
貯金が3000万円あれば幅広い投資にチャレンジできるものの、必ずしも成功するとは限りません。元本割れを起こしてせっかく3000万円まで貯めた貯金が目減りすることも考えられます。
投資を成功させるなら、事前の勉強は欠かさないことはもちろん、準備も念入りに進めていきましょう。
ここでは、投資を成功させるポイントとして、以下の3つを解説します。
- 幅広い商品に分散投資する
- 目標を立ててリスクを調整する
- 専門家に相談する習慣を持つ
幅広い商品に分散投資する
投資の世界には「卵は1つのカゴに盛るな」という有名な格言があります、
仮に1社(1つのカゴ)に投資できる全財産(卵)を入れてしまうと、籠を落とした(業績が悪化・倒産など)した場合に資産を全て失うという考え方です。
1つの銘柄に集中投資ではなく、できるだけ幅広い対象に分散投資しましょう。
目標を立ててリスクを調整する
資産運用でもっとも大事なのは「お金を貯める目的を明確にすること」です。
「いつまでに、いくらを用意したいか」が明確になれば、取るべきリスクとリターン期待値が分かり、適切なアセットアロケーション(投資資産の組み合わせ)が実現します。
逆に、目的がはっきりせず何となく投資をしていると、貯めたい金額やお金を使う期限、売却をするべきタイミングも判断ができません。
専門家に相談する習慣を持つ
これまで資産運用をした経験がない人は、自分だけでいきなり投資を始めないように注意が必要です。
ファイナンシャルプランナー(FP)などお金や資産運用に詳しいプロの方に相談することで、投資への考え方が大きく変わることもあります。資産運用をするうえでの基本的な知識や投資の考え方を知ることができ、一人で進めるよりも効率的に資産運用が可能になります。相談サービスにもよりますが、相談が終わったあとも無料でアフターフォローしてくれる業者もあります。

貯金3000万円でも資産運用を失敗する人の特徴

貯金3000万円を超えたら資産運用をしてさらなる資産形成を目指したいのは、すでに解説したとおりです。
ただ、金融商品によっては元本保証がなく、失敗して資産を減らしてしまう人もいるかもしれません。
ここでは資産運用を失敗しやすい人の特徴として、以下の3つを紹介します。
- SNSや知恵袋などの情報を鵜呑みにしている
- ハイリスクな商品ばかり選んでしまう
- 短期の値動きに惑わされる
SNSや知恵袋などの情報を鵜呑みにしている
資産運用を始める際、書店で本を購入して勉強するのがセオリーですが、最近ではネット検索やSNS検索でも情報を得ることができます。
金融商品が自分の目的や耐えられるリスクに見合った商品化を自分なりに良く分析し、納得してから申し込みすることをおすすめします。
ハイリスクな商品ばかり選んでしまう
ひとくちに「資産運用」といっても、金融商品によってリスクとリターンは大きく異なります。
リスクとリターンは比例して大きくなっていくのが通常で、リターンばかり追い求めてしまうと大きなリスクを背負うことになります。
例えば、某株式の成長率に目を付けて、生活費や子どもの教育費までつぎ込んでしまうと、もしその銘柄が暴落した際に資産が半減することも考えられます。
株式のような値動きが激しい金融商品は1点買いせず、できるだけ幅広く投資することを意識しましょう。
債権(債券)や金、不動産などの金融商品を織り交ぜてアセットアロケーションを作ることで、株式市場が下がっても他の資産が値上がりしたり、値下がり幅が小さかったりすることで資産全体の目減りを抑えることができます。
短期の値動きに惑わされる
資産運用は長期投資を前提に進めることが基本です。長期というのは半年~1年くらいのことではなく、10年~30年以上のことを指します、
しかし、短期的な値動きに惑わされていると、それ以上の損失を恐れて短期的に売却してしまうことが考えられます。短期的な値下がりのタイミングで売ってしまうことで含み損が確定し、「投資は儲からないから辞めよう」と感じてしまうことになります。
長期的に資産運用をする前提では、値下がりしているときは「バーゲンセール」の状態です。安いときに大量の銘柄を仕込むことで、次の市場の成長のときに大きく値上がりする可能性があります。

貯金3000万円を超えてから注意したいポイント

預貯金が3000万円もあれば、効率良く運用することで更に資産増を狙うこともできますが、間違った運用をしてしまうと資産を大きく減らしたり、全く増えなかったりする原因になる場合があります。
ここからは、預貯金3000万円を超えた人が資産運用で気を付けたいポイントを見ていきましょう。
高リスクの投資は避ける
これまで解説してきた「おすすめの投資方法」よりも、明らかにリスクが大きな投資・投機は避けるほうが無難です。
分かりやすいのは「暗号資産(仮想通貨)」でしょう。2017年頃に多くの「億り人」を生んだことで一気に有名になってニュースになったことを覚えている人もいるのではないでしょうか。
直近では2021年にも急成長しており、2020年12月11日には1BTC=約196万円のところ、2021年3月12日には約668万円と、3ヶ月で約3.4倍になりました。ただし、急成長のあとはいずれも急降下しており、2021年7月16日には約347万円と3月時点から半減しています。
このように暗号資産は乱高下が非常に激しく、買うポイントを間違えると急降下に巻き込まれて大きな含み損を抱えることになります。購入するなら、リスク許容度の範囲内で資産の一部に留めた方が良いでしょう。
元本保証商品だけの運用は非効率
あまりに高リスクの投資は避けるべき、とお伝えしましたが、逆に「元本保証の金融商品のみ」という資産運用もおすすめできません。
2023年4月現在、大手メガバンクの普通預金の金利は0.02%程度しかありません。
一方、IMFの「World Economic Outlook Databases」によれば、2022年1月~10月までの時点で日本のインフレ率は1.99%になっています。アメリカのインフレ率8.05%と比べればまだまだ低い水準であるものの、定期預金だけではインフレについていけずに実質的に資産が目減りすることが考えられるでしょう。
インフレに負けずに資産を増やすためには、リスク許容度に見合うレベルで資産の一部をリスク性投資に振り向けることが大切です。
3000万円は必ずしも十分な貯金額とは限らない
3000万円という貯金は一見すると高額ですが、「もう働かなくても生活できる」といえるほど十分な貯蓄額ではありません。
現役世代と同じような「ゆとりのある老後」を送りたい場合、1ヶ月で37.9万円が必要とされています。老後を20年としても9,096万円が必要と試算できてしまい、3000万円では全く足りていません。
質素な生活でも老後に5,000万円前後が必要と考えると、3000万円の貯金は決して十分とはいえません。
急な出費リスクを想定しておく
将来、どのような未来が待っているかは誰にも予想できません。
例えば親が要介護になってしまい、介護費用を子どもである自分が負担することになった場合。
生命保険文化センターによると、月々の介護費用は平均8.3万円、初期費用として平均74万円が必要です。介護の平均期間は5年1ヶ月と考えると、あくまでも平均ですが「581万円」がかかる計算です。
3000万円の貯金のうち6分の1以上を使う可能性があると考えると、3000万円で安心せずにさらに高額な貯金を目指して資産運用を頑張るべきでしょう。
投資詐欺など悪意ある人に騙されないようにする
貯金が3000万円もあることが分かると、さまざまな人が自分に近づいてきます。
お金を貸してほしいという人のほか、悪意を持った人物に騙されて貯金を失う可能性だってあります。
「短期間で必ず資産が2倍になる」
「利回り20%は確実」
このように「絶対」「確実」という言葉がついた投資は、ほぼ間違いなく詐欺・あるいは詐欺まがいの商品と想像できます。
上記はあくまで一例ですが、もっと巧妙に仕組まれた投資詐欺もあるかもしれません。
「自分は大丈夫」と過信せず、相手のほうから投資の話が出たときは詐欺に巻き込まれないように細心の注意を払いましょう。

貯金3000万円あればFIREやセミリタイアは可能?

結論からいってしまうと、3000万円の預貯金があったとしてもFIREはもちろん、セミリタイアも現実的ではありません。
リスク性商品の投資利回りは確実に決まってはいませんが、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用結果が参考になります。
ここではGPIFの収益率を参考に、年率3%の利益を得たと仮定してみましょう。3000万円を年率3%で運用すると1年で得られる利益は90万円であり、税引き後では約72万円しかありません。
毎月6万円で生活していくことはもちろん、子育て世帯の場合はセミリタイアも難しいことが分かります。だからこそ、資産運用を続けて更に多くの資産を狙う必要があるわけです。

貯金3000万円で実現できることと次の一手

3000万円では早期のFIREやセミリタイアはかなり難しいことは解説しました。しかし、ここまでの預貯金を持てる人がわずかであることも事実。悲観することなく、メリットに目を向けてみましょう。
3000万円もの貯金があれば、以下のようにさまざまなことを始められます。
将来的に1億円の資産形成が可能
前述の通り、FIREを目指すなら1億円前後が1つの目標になってきます。預貯金なしの状態から1億円を目指すことは相当難しいですが、初期費用が3000万円もあれば現実味のあるシミュレーションが可能です。
3000万円を元金として1年間で4%の利回りで運用した場合、資産を1億に増やすには「31年」かかる計算になります。
3000万円に加えて毎月5万円を追加投資した場合は「24年」まで短縮が可能です。
住宅を現金購入できる選択肢も
住宅の条件にもよりますが、3000万円の貯金があれば即金で住宅を購入することもできます。
老後資金とは使い方が全く異なりますが、賃貸物件の家賃を節約する目的なら選択肢に入るでしょう。
不労所得を得る仕組みづくりができる
3000万円を投資信託のように「配当金を再投資するタイプ」の投資に活用することで「複利」の効果が働き、効率良く資産形成を進められます。
一方、定期的に配当を得られるタイプの金融資産に投資することで不労所得を生み出すことも可能です。
3000万円を配当利回り3%の株式に投資した場合、年間90万円(税引き後は約72万円)の配当金を得られます。月にすると約6万円の不労所得が得られる計算になり、生活費の補填として十分に頼りになるでしょう。
銘柄によって配当金・分配金が入ってくるタイミング(配当月)が異なるため、配当月が異なる4~6銘柄を組み合わせることで毎月お金を得ることも可能です。

貯金3000万円からさらに増やす習慣づくりとは
預貯金が3000万円もあるのは日本全体でもごく一部であると考えられますが、なかにはもっと多くの貯金を目標にしている人もいるはずです。
ここでは3000万円から、さらに多くの貯金をしたい方に意識して欲しいポイントとして、以下の5つを解説します。
- 貯金の目的を明確にする
- 支出を減らすために家計簿をつける
- 固定費を見直す
- 貯蓄専用の口座を作る
- 人生で起きるイベントを先に考える
貯金の目的を明確にする
貯金を増やすためには、ただ漠然と「お金を貯めたい」と考えるだけなのはおすすめできません。
明確な目的があれば、期限から逆算して毎月の貯金額が分かり、貯金を達成することで目的のものにお金を使えるようになります。
例えば貯金の目的が老後資金で、「65歳から年金を受け取る前に60歳~65歳の生活費として1,000万円が欲しい」と考えた場合。
今が30歳なら「1,000万円÷12ヶ月÷30年=27,778円」となり、毎月3万円ずつ貯めれば目的を達成できることが分かります。
支出を減らすために家計簿をつける
貯金をするためには、収入を増やすか、支出を減らすかの2通りの方法があります。
毎月の収入を1万円増やすには、副業を始めるか、会社で昇進・昇給したり、残業や転職したりといった方法が考えられ、決して簡単ではありません。
一方、家計の無駄を洗いだして支出を1万円減らすことができれば、収入を1万円増やすのより簡単で同じ効果が得られます。
毎月支払っているお金に無駄がないか家計簿をつけてみて、無駄があれば早急に省きましょう。
固定費を見直す
家計簿をつけたあと、最初にするべきは「固定費の見直し」です。固定費は毎月固定金額を支払っている支出のことで、家賃やサブスク代やスマホ代金、Wi-Fiの料金、保険や水道光熱費などが該当します。
固定費に無駄があれば、積立保険の見直しなども含めて積極的に削減し、余ったお金を貯金に回せるように検討しましょう。固定費は毎月支払うことになる費用であり、一度見直すだけで長らく見直しの効果が続くことから費用対効果が大きいです。
ただし、生命保険に関しては安易に解約すると再契約できない場合があるため、解約するかは慎重に判断しましょう。判断できないときはFPへの相談も必要です。
貯蓄専用の口座を作る
貯金をするときは、生活費用の口座と貯金用の口座をわけるほか、会社の財形貯蓄制度を活用するのも有効です。2つを同じ口座に入れておくと、「いくらまでが生活費で、いくらまでが貯金なのか」が明確でなくなり、気が付くと貯金を使ってしまっている可能性もあります。
人生で起きるイベントを先に考える
お金を効率的に貯めるなら、人生で起こるライフイベントを先にイメージしておくことが大切です。
例えば「35歳までに結婚したい」という人生設計があれば、そこに向けて結婚費用を貯めるための具体的な計画を組むことができます。
貯金3000万円以上でも活用したい非課税制度

貯金3000万円を持っている方は、貯金額が少ない人よりも効率的に資産運用をすることができます。ただし、投資額が大きいと、納税する税金額も大きくなる点に注意が必要です。
例えば、同じ投資で10%の利益を得ているAさんとBさんがいます。
一方、Bさんの投資額は1000万円。同じく10%の利回りで100万円の利益を得られますが、税金は20万3,150円もあり、納税する金額は一気に跳ね上がります。
投資額が大きいほど利益が大きくなりやすい反面、税金も高くなるわけです。そこで利用を検討したいのが非課税で投資できる「NISA」「iDeCo」です。
少額投資非課税制度の愛称で、上限1800万円まで投資ができるNISA口座を開設できます。個別株などにも投資できる成長投資枠に年間240万円、特定の投資信託に積立投資できるつみたて投資枠に年間120万円を投資でき、運用しているあいだは利益がずっと非課税になります。
後述するiDeCoとは異なり、お金が必要になったらすぐに投資商品を売却して現金を引き出すことも可能です。
個人型確定拠出年金の愛称で、自分で掛金を拠出して自分で運用商品を選び、自分で運用することで将来に年金または一時金として受け取ることができます。
掛金の全額が所得控除になるため、所得税や住民税を節税しながら資産形成を進められるメリットがあります。
また、運用期間中の運用益が全て非課税で、受取時も税制メリットがあります。
ただし、あくまでも年金制度であり、最短でも60歳になるまで元金と利益を引き出すことができない点がデメリットです。

貯金3000万円を超えた人の相談先は?

資産運用に興味が出てくると「もっと詳しく知りたい」「知識をつけてから投資を始めたい」といった気持ちが湧いてくることがあります。
ここではお金や資産運用の相談先として、以下の2つを紹介します。
- 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
- ファイナンシャルプランナー(FP)
独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
独立系のファイナンシャルアドバイザーは特定の証券会社に属さず、投資や資産運用のアドバイスをする専門家のことです、
資産運用だけでなく税金や保険・相続などの知識も豊富であり、資産運用を中心にワンストップで相談できる強みがあります。
またIFAは投資に関する専門的な知識を有しており、クライアントの状況や希望に合わせた資産運用プランを立案してくれます。最適な金融商品の売買のサポートをしてくれる点もメリットです。
ファイナンシャルプランナー(FP)
IFAが資産運用の専門家とするなら、ファイナンシャルプランナー(FP)は「ライフプランニング」の専門家です。
収入・支出などの情報に加えて資産・負債、将来の目標のライフプランなどのデータをヒアリングし、今後のライフプラン(結婚・出産・マイホーム購入等)の希望を元に、家計を黒字化させたり目標のライフプランを達成させたりするためのアドバイスを得ることが可能です。

貯金3000万を超えた人に関するよくある質問

最後に、貯金3000万円を超えた人に関するよくある質問と回答を解説します。
30歳で貯金3000万円ある人の割合は?
金融広報中央委員会「令和5年(2023年)家計の金融行動に関する世論調査」によれば、60代の20%以上が貯金3000万円の大台を超えています。
一方、20代~40代の若い世代では3000万円を超える貯金を持っている人はほとんどいません。
貯金3000万円は何年で使い切れますか?
総務省統計局の「家計調査」のデータによれば、二人以上の世帯のうち「勤労者世帯」の消費支出と非消費支出の合計が43万2,269円です。
無職になって貯金3000万円を取り崩しながら生活すると仮定すると、「約69~70ヶ月分」と試算できます。無職になっても家族を4年~5年以上養うことができるので、次の働き方や貯金の方法など老後に向けてじっくりとプランニングすることができるでしょう。
20年で貯金3000万円は実現できますか?
3000万円を20年で貯めたい場合、毎月12万5,000円を貯金できれば達成できます。難しい目標ではありますが、決して不可能な金額でもありません。
ただし、定年退職したあとも現役世代と同様に貯金することはできません。65歳で定年退職をするイメージであれば、アラフォーのうちに預貯金をスタートさせたいところです。
30歳までにいくらくらい貯金しておけば良いですか?
20代のうちは30代以降と比較して給与が低いことが多く、東京など地価が高いところでは思ったように貯金が進められないこともあります。
明確に「30歳までに〇万円を貯めておくべき」という決まりはありませんが、300万円前後を目標にすると良いでしょう。300万円もあれば、資産運用を開始したあとに効率の良い資産形成を目指せます。
例えば300万円の元手と毎月3万円の追加投資分を年4%で運用(年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の過去20年以上の収益率4.36%を参考)すると仮定すると、30年後には元金1380万円が3000万円まで増える計算です。
参考:ファンドの海
貯金3000万あれば老後も安心ですか?
いいえ。
生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」によると、夫婦2人の老後生活に必要な費用は最低限の生活でも1ヶ月23万2,000円です。老後が20年続くと仮定すると「23.2万円×12ヶ月×20年=5,568万円」ものお金が必要になり、3000万円では不足していることが分かります。
貯金3000万円を超えたらセミリタイアも可能ですか?
3000万円の貯金があったとしても、セミリタイアするのは現実的ではありません。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用結果が参考を参考にすると、GPIFでは「国内株式」「国内債券」「外国株式」「外国債券」にそれぞれ25%ずつ分散投資して運用を行っていますが、2001年から2023年までの収益率が「4.36%」でした。
GPIFの収益率を参考に、少し利回りが下がったと仮定して年率3%の利益を得たと仮定してみましょう。3000万円を年率3%で運用すると1年で得られる利益は90万円、税引き後では約72万円しかありません。72万円ではセミリタイアにも十分とはいえません。
貯金3000万円を超えたらやるべきことはありますか?
貯金額が3000万円を超えたら、そこで安心するのではなく、資産運用を始めることをおすすめします。
例えば資産の一部の1,000万円を投資したとして、投資商品に年間5%の値上がりがあれば50万円の利益になります。投資額が100万円の人は同じ投資をしても5万円の利益にしかならないため、高額の資産がある人ほど資産形成には有利です。
貯金3000万円以上ある世帯はどれくらい?
貯金が3000万円ある世帯は、二人世帯では20歳代では0.6%、30歳代なら4.0%、40歳代なら6.5%とかなり低い水準です。貯金が3000万円もあれば、日本全体でもかなり勝ち組といえるでしょう。
資産運用で資産が減ることはありませんか?
株式や投資信託、仮想通貨などの投資商品は元本が保証されていません。短期的には、投資した元本を下回って実質的に資産が減ってしまう可能性もあります。
どうしても元本割れすることに耐えられないなら、「定期預金」「個人向け国債」などリスクが低くリターンが安定した方法をメインにして資産運用することもできます。特に定期預金はさまざまな銀行で扱っていて取り組みやすく、万が一、金融機関が倒産したときは預金保険制度によって元本1000万円とその利息が保護されます。
資産運用する際の注意点はありますか?
注意点としては、「あまりに高いリスクの投資は避ける」「元本保証のみの投資はしない」の2つです。
FXや仮想通貨など値動きが激しい投資商品は短期間で大きく資産を増やせる可能性がある一方、値動き次第では資産が急速に目減りすることが考えられます。最悪の場合は「ロスカット」になり、投資したお金の大半を失う可能性もあります。
また、リスクが怖いからといって低リスクかつ安定の定期預金や国債ばかりに投資することもおすすめできません。元本が保証されているタイプの商品は利回りが低く、20~30年つづけても資産が効率的に増えない可能性もあります。
その資産にどれくらいの金額を投資するかは、ご自身のリスク許容度とポートフォリオのバランスによって変わります。慎重になるあまり資産が増えないのは本末転倒であるため、ある程度の金額はリスク性商品に割り振ると良いでしょう。
貯金3000万あっても住宅ローンを組んだ方が良いですか?
住宅ローンを組んだ方が良いかは、個人の判断による部分があります。
すべて現金で自宅を購入すれば住宅ローンの審査は不要で、数百万円の利息を支払う必要はなくなります。一方でせっかく貯めたお金が一気になくなってしまうことや「住宅ローン控除」が受けられないなどのデメリットもあります。
独身の方が住宅を購入して貯金が尽きたときに大病を患って、入院するような可能性もあります。新居に住むなら当初は住宅ローンを組み、ローン控除がなくなったあとで完済をするために返済額を増やすことも可能です。
まとめ:3000万円の貯金があってもFIREやセミリタイアは難しい
本記事では貯金3000万円を持つことの難しさや、FIREの可能性などについて解説しました。
3000万円を超えるような金を貯金・投資をして多くの金融資産を持てる人はわずかです。
ただし、年率4%という現実的な数値で資産運用をするという前提で考えた場合、FIREするにはまだまだ足りない金額です。子どもがいる世帯の場合、セミリタイアも厳しい場合があります。
現実的にFIREするなら、年間生活費にもよりますが1億円前後の金額が目標になってくるでしょう。3000万円の元手を活かして投資信託やヘッジファンド等の資産運用を行うことで、更に貯金額を増やすことを目指しましょう。
どうしても3000万円の使い道が分からないときはプロのファイナンシャルプランナー(FP)への相談も視野に入れてみると良いでしょう。FPは無料相談も実施しているので、金銭的な負担をかけずに悩みを相談できます。